人道支援
緊急・人道支援
国際機関を通じた支援
近年、貧困、気候変動、テロ、大量破壊兵器の拡散、平和構築、感染症等、一国のみで解決することが困難な、国境を越える地球規模の諸課題が、外交における主要課題として顕在化しており、国際社会がこうした課題に対して一致して取り組む必要性が強調されています。我が国も、このような地球規模の諸問題の解決に向け、専門性を有する国際機関とも連携し取り組んでいます。特に人道支援の分野における国際機関を通じた支援は、二国間支援と相互に補いあう、有効な支援の手段であると考え、財政的、人的な協力を積極的に行っています。
人道支援をめぐる国際連合の取り組み
国際連合(国連/United Nations) では、様々な紛争や自然災害に対応するために、効率的な人道支援活動の体制作りに取り組んできました。1971年に、災害救済調整官事務所(UNDRO)を設立して、各国連機関・国際赤十字等により個別に実施されてきた災害救済活動の調整を行うことで救済活動を効率化させ、また、防災に関する研究活動の実施を目標としました(国連総会決議26/2816)。
では、様々な紛争や自然災害に対応するために、効率的な人道支援活動の体制作りに取り組んできました。1971年に、災害救済調整官事務所(UNDRO)を設立して、各国連機関・国際赤十字等により個別に実施されてきた災害救済活動の調整を行うことで救済活動を効率化させ、また、防災に関する研究活動の実施を目標としました(国連総会決議26/2816)。
1991年12月に採択された国連総会決議(46/182)に基づき、国連は緊急・人道支援の分野において以下のような改革を行いました。
- 緊急援助調整官(ERC(Emergency Relief Coordinator))の創設。
- 人道問題局(UNDHA(UN Department of Humanitarian Affairs))の創設(その後、1998年に国連人道問題調整事務所(UNOCHA)
 が発足。)
が発足。) - 複数の機関にまたがる人道支援にかかる諸事項・任務について、各機関が協議・調整を行うために機関間常設委員会(IASC)を設立。
- 「国連統一人道アピール・プロセス(CAP)」を導入。
(なお、UNOCHAは大規模自然災害等の発生を受けて「フラッシュ・アピール(Flash Appeal)」や「シチュエーション・レポート(Situation Report)」を発出しています。また、「ファイナンシャル・トラッキング・サービス(Financial Tracking Service(FTS))」を通じて、拠出状況をネット上で確認できる制度を創設しました。)
2004年末のスマトラ沖大地震・インド洋津波等を受けて、国連における人道支援システム改革の気運が高まり、2005年の国連総会で、資金メカニズム、人道支援の指導力強化、人道支援の能力・予見可能性の向上などの面で以下のような改革が行われました。
- 国連中央緊急対応基金(CERF)
 を設立して、資金メカニズムの改善を実施。
を設立して、資金メカニズムの改善を実施。 - クラスター・アプローチを採択し、人道支援機関間のパートナーシップを構築。
また、ドナー国の間の意見交換や協力体制を強化するため、人道作業部会(HLWG)、グッド・ヒューマニタリアン・ドナーシップ(GHD)、グローバル・ヒューマニタリアン・プラットフォーム(GHP)などが開催されています。
2010年のハイチ地震及びパキスタン洪水の際の課題を受けて、効率的・効果的かつ説明責任が確保された人道支援を行うための人道支援体制の改革(Transformative Agenda: TA)が、2011年12月、機関間常設委員会(IASC)機関長会合において合意されました。(参考:「国連を中心とした人道支援体制の改革(TA)の動きについて(PDF) 」)
」)
なお、8月19日は国連総会で定められた「世界人道デー(World Humanitarian Day)」となっております。
ここでは、各機関の特色や取り組みを紹介します。(アルファベット順)
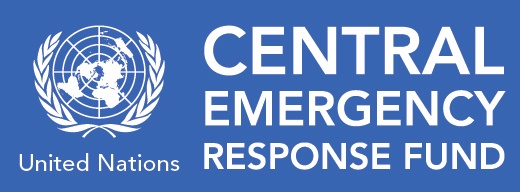 |
|
 |
|
 |
|
 (c)日本赤十字社 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
具体的な事業の紹介
要人往来等
- 超党派人道外交議員連盟による国光外務副大臣表敬(令和7年12月9日)
- 人道要員保護に関する宣言の発表イベント(第80回国連総会ハイレベルウィーク関連行事)(令和7年9月22日)
- 松本外務大臣政務官とカルボニエ赤十字国際委員会(ICRC)副総裁との会談(令和7年8月22日)
- 岩屋外務大臣とマケイン国連世界食糧計画(WFP)事務局長との会談(令和7年8月22日)
- 赤堀外務審議官とポープ国際移住機関(IOM)事務局長との意見交換(令和7年8月21日)
- 岩屋外務大臣とポープ国際移住機関(IOM)事務局長との会談(令和7年8月21日)
- バベ赤十字・赤新月常置委員会委員長の訪日(令和7年4月30日)
- 超党派人道外交議員連盟による岩屋外務大臣表敬(令和7年2月28日)
- 第3回日・IOM政策協議の開催(結果)(令和7年2月12日)
- ムスヤ人道問題担当国連事務次長補兼緊急援助副調整官による松本外務大臣政務官表敬(令和7年1月21日)
- 第2回日・OCHA政策協議の開催(結果)(令和7年1月21日)
- 赤堀外務審議官の「人道要員の保護に関する会合」出席(第79回国連総会ハイレベルウィーク関連行事)(令和6年9月24日)
- 第5回日・ICRC政策協議の開催(結果)(令和6年9月6日)
- 上川外務大臣とポープ国際移住機関(IOM)事務局長との会談(令和6年2月26日)
- 上川外務大臣とポープ国際移住機関(IOM)事務局長との会談(令和5年12月14日)
- クラメルト国連世界食糧計画(WFP)事務局次長による穂坂外務大臣政務官表敬(令和5年11月8日)
- スポリアリッチ赤十字国際委員会(ICRC)総裁による林外務大臣表敬(令和5年6月15日)
- 赤十字国際委員会(ICRC)ドナー・サポート・グループ年次会合の開催(結果)(令和5年6月14日)
- ムスヤ人道問題担当国連事務次長補兼緊急援助副調整官による武井外務副大臣表敬(令和5年6月7日)
- 第1回日・OCHA政策協議の開催(結果)(令和5年6月5日)
- 武井外務副大臣のグローバル難民フォーラム・シンポジウムへの出席(令和5年6月1日)
- 日・UNHCR政策協議の開催(結果)(令和5年5月30日)
- クレメンツ国連難民副高等弁務官(UNHCR)による武井外務副大臣表敬(令和5年5月29日)
- 林外務大臣とマケイン国連世界食糧計画(WFP)事務局長との会談(令和5年4月20日)
- チャパゲイン国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)事務総長による武井外務副大臣表敬(令和5年2月28日)
- 林外務大臣とグランディ国連難民高等弁務官との会談(令和4年11月9日)
- クラメルト国連世界食糧計画(WFP)副事務局長による吉川外務大臣政務官表敬(令和4年10月25日)
- 第16回日・WFP政策協議の開催(結果)(令和4年10月25日)
- 第2回日・IOM政策協議の開催(結果)(令和4年10月17日)
- ポープ国際移住機関(IOM)副事務局長による髙木外務大臣政務官表敬(令和4年10月14日)
- ラザリーニ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による木原内閣官房副長官表敬(令和4年10月7日)
- 林外務大臣とラザリーニ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長との会談(令和4年10月6日)
- 林外務大臣とビーズリー国連世界食糧計画(WFP)事務局長との会談(令和4年7月11日)
- 国際移住機関(IOM)総会ハイレベルセグメントにおける鈴木外務副大臣のビデオ・メッセージの発出(令和3年11月30日)
- 鈴木外務副大臣の「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に関する閣僚級国際会合」への出席(令和3年11月16日)
- 茂木外務大臣とグランディ国連難民高等弁務官との会談(令和3年7月31日)
- 宇都外務副大臣の「第3回国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に関する閣僚級戦略対話」への出席(令和2年10月16日)
- 鈴木外務副大臣の「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への資金調達に関する閣僚級会合」への出席(令和2年6月24日)
- 鈴木外務副大臣とマウラー赤十字国際委員会(ICRC)総裁とのテレビ会談の開催(令和2年4月20日)
- 鈴木外務副大臣の「第2回国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に関する閣僚級戦略対話」への出席(令和2年4月23日)
- 尾身外務大臣政務官のスイス訪問(結果)(令和2年2月27日)
- 鈴木外務副大臣のグローバル難民フォーラム出席(令和元年12月25日)
- ミュラー人道問題担当国連事務次長補兼緊急援助調整副官による中谷外務大臣政務官表敬(令和元年11月14日)
- 国際連合世界食糧計画(WFP)のノーベル平和賞受賞に際する菅総理大臣による祝意メッセージ(令和元年10月9日)
- 国際連合世界食糧計画(WFP)のノーベル平和賞の受賞について(外務大臣談話)(令和元年10月9日)
- マウラー赤十字国際委員会総裁による佐藤外務副大臣表敬(令和元年8月29日)
- ヴィトリーノ国際移住機関事務局長による河野外務大臣表敬(令和元年5月28日)
- 鈴木外務大臣政務官のマウラー赤十字国際委員会総裁訪日歓迎レセプション出席(平成30年11月21日)
- マウラー赤十字国際委員会総裁による佐藤外務副大臣表敬(平成30年11月21日)
- グランディ国連難民高等弁務官の訪日(結果)(平成30年10月28日)(PDF)

- 鈴木外務大臣政務官の国連難民高等弁務官事務所主催レセプション出席(平成30年10月25日)
- 阿部外務副大臣とグランディ国連難民高等弁務官との昼食会(平成30年10月25日)
- グランディ国連難民高等弁務官の訪日(平成30年10月23日)
- グランディ国連難民高等弁務官による河野外務大臣表敬(平成29年11月17日)
- グランディ国連難民高等弁務官の訪日(平成29年11月13日)
- ラスムーソン国連世界食糧計画(WFP)事務局次長による小田原外務大臣政務官表敬(平成28年12月13日)
- クレヘンビュール国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による岸外務副大臣表敬(平成28年10月25日)
- クレメンツ国連難民副高等弁務官による濵地外務大臣政務官表敬(平成28年7月6日)
- 木原外務副大臣とカズン国連世界食糧計画(WFP)事務局長との会談(平成28年6月15日)
- グランディ国連難民高等弁務官による安倍晋三内閣総理大臣表敬(平成28年3月1日)
- 濵地外務大臣政務官とグテーレス国連難民高等弁務官及び日本のNGO関係者との昼食会(平成27年11月27日)
- グテーレス国連難民高等弁務官による木原外務副大臣表敬(平成27年11月25日)
- クレヘンビュール国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による木原外務副大臣表敬(平成27年11月5日)
- クレヘンビュール国連パレスチナ難民救済事業機関事務局長及びガザの中学生による安倍総理大臣表敬(平成27年11月4日)
- クレヘンビュール国連パレスチナ難民救済事業機関事務局長による萩生田内閣官房副長官表敬(平成27年11月4日)
- ダ・シルバ国連世界食糧計画(WFP)事務局次長による濵地外務大臣政務官表敬(平成27年10月28日)
- シュティルハルト赤十字国際委員会(ICRC)事業総局長による濵地外務大臣政務官表敬(平成27年10月22日)
- 岸田外務大臣とカズン国連世界食糧計画事務局長との会談(平成27年3月15日)
- ウィリアム・スウィング国際移住機関(IOM)事務局長による中根外務大臣政務官表敬(平成27年2月27日)
- マウラー赤十字国際委員会(ICRC)総裁による城内外務副大臣表敬(平成27年2月13日)
- マウラー赤十字国際委員会(ICRC)総裁による安倍内閣総理大臣表敬(平成27年2月10日)
- グテーレス国連難民高等弁務官による中山外務副大臣表敬(平成26年11月14日)
- クレヘンビュール国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による城内外務副大臣表敬(概要)(平成26年10月22日)
- 近衞国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)会長及びシィIFRC事務総長による中根外務大臣政務官表敬(概要)(平成26年10月29日)
- カズン国連世界食糧計画(WFP)事務局長による安倍総理大臣表敬(概要)(平成26年6月6日)
- アレイニコフ国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)副高等弁務官による木原誠二外務大臣政務官表敬(平成26年5月29日)
- スウィング国際移住機関(IOM)事務局長による岸外務副大臣表敬(平成26年2月20日)
- エリザベス・ラスムーソン国連世界食糧計画(WFP)事務局次長による岸田外務大臣表敬(平成25年12月11日)
- アントニオ・グテーレス国連難民高等弁務官(UNHCR)による安倍総理表敬(平成25年12月4日)
- クレヘンビュール赤十字国際委員会(ICRC)事業総局長による木原外務大臣政務官表敬(平成25年11月22日)
- アレイニコフ国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)副高等弁務官による木原外務大臣政務官表敬(平成25年10月17日)
- フィリポ・グランディ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による岸田外務大臣表敬(平成25年9月12日)
- 安倍総理大臣とグテーレス国連難民高等弁務官(UNHCR)との会談(平成25年6月2日)
- 日・WFP栄養分野の協力(カズン国連世界食糧計画(WFP)事務局長の阿部外務大臣政務官表敬(平成25年5月31日)
- マウラー赤十字国際委員会(ICRC)総裁による安倍総理大臣表敬(平成25年5月17日)
- マウラー赤十字国際委員会(ICRC)総裁による松山外務副大臣表敬(平成25年5月16日)
- クレヘンビュール赤十字国際委員会(ICRC)事業総局長による阿部外務大臣政務官表敬(平成25年3月14日)
- グランディ国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)事務局長による松山外務副大臣表敬(平成25年2月15日)
- スウィング国際移住機関(IOM)事務局長による松山外務副大臣表敬(平成25年2月6日)
- グテーレス国連難民高等弁務官による岸田外務大臣表敬(平成25年2月5日)










