2 中東地域情勢
(1)中東和平
ア 中東和平をめぐる動き
2014年4月にイスラエル・パレスチナ間の交渉が頓挫して以降、中東和平プロセスの停滞は継続している。米国のバイデン政権発足後、当事者間の協力再開の動きが一時見られ、ハイレベルでの接触など前向きな動きもあったが、2022年12月末にイスラエルで極右政党を含む連立政権が発足し、それ以降、エルサレムを含め、イスラエル及びパレスチナにおいて暴力行為や衝突が断続的に発生し、多数の死傷者が出た。2023年5月にはガザのパレスチナ武装勢力とイスラエル国防軍(IDF)2の武力衝突、7月には西岸地区ジェニンでのIDFによる大規模な掃討作戦が行われるなど、暴力の応酬が続いた。
そうした中、10月7日にガザ地区からハマスなどパレスチナ武装勢力が、数千発のロケット弾を発射し、多数の戦闘員が、イスラエル側検問・境界を破り、IDF兵士のほか、外国人を含む市民を殺害・誘拐した。イスラエル側では、少なくとも1,200人が殺害され、4,500人以上が負傷した。さらに、外国人を含む200人以上がガザ地区に連れ去られ、人質になった。これを契機に、IDFがガザ地区への大規模な空爆を開始、その後ガザ地区内での地上作戦を開始した。国連及びパレスチナ保健省の発表によれば、2023年12月時点で、ガザ地区では、2万人以上の死者、5万人以上の負傷者が発生し、住民の85%に当たる約190万人が避難を余儀なくされた。
イスラエルの北部国境では、10月8日以降、レバノンのヒズボッラー(反政府勢力)が国境付近のIDF拠点及びイスラエル北部の主要都市を砲撃、イスラエル領内に侵入し、IDFが反撃するなどの武力衝突が続いた。10月19日以降、イエメンのホーシー派がイスラエルに対し、ミサイルや無人機などによる攻撃を断続的に実施し、11月19日にはイエメン沖において日本関係船舶が「拿(だ)捕」される事件が発生した。船舶に対する攻撃はその後も続き、世界経済の重要なシーレーンである紅海及びその周辺海域における船舶の自由な航行に重大な影響が生じている。
軍事衝突が続く中で、カタール、エジプト、米国による仲介で、11月22日、イスラエルとハマスは、人質解放をめぐる取引に合意し、11月24日から30日までにイスラエル人人質81人、外国人24人が解放され、イスラエルに収監されていたパレスチナ人240人が釈放された。この間に戦闘が休止され、燃料を含む人道支援物資のガザ地区への搬入が認められた。しかし、12月1日、戦闘が再開され、IDFはガザ地区南部への地上作戦を開始した。IDFは、ハマスなどが病院敷地内を含め地下トンネルを構築し、軍事利用していると主張し、ガザ地区各地の病院への作戦を実施した。
国連の場では、安全保障理事会(安保理)において4本の決議案が否決された後、11月15日に、ガザ地区における児童の保護に焦点を当て、人道的休止やハマスなどによる人質の即時・無条件の解放の要請などを含む決議第2712号が、12月22日に、ガザ地区に対する人道支援の拡大と監視に関する決議第2720号が採択された。日本は、安保理理事国の一員として、本決議の採択のため積極的に取り組んだ。また、国連総会においては、10月27日に人道的休戦などを求めるヨルダン提案の決議案、12月12日に人道的停戦などを求めるエジプト提案の決議案がそれぞれ賛成多数で採択された。さらに、同月29日、南アフリカがイスラエルを国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、イスラエルに対する暫定措置を要請したことを受け、2024年1月26日、ICJは、イスラエルに対し、ガザ地区のパレスチナ人との関係において、ジェノサイド及びその扇動を防ぐための措置をとること、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道支援を供給することを可能とする措置をとることなどを命じる暫定措置命令を発出した。
イ 日本の取組
日本は、国際社会と連携しながら、イスラエル及びパレスチナが平和的に共存する「二国家解決」の実現に向けて、関係者との政治対話、当事者間の信頼醸成、パレスチナ人への経済的支援の3本柱を通じて積極的に貢献してきている。
日本独自の取組としては、日本、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンの地域協力により、パレスチナの経済的自立を中長期的に促す「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。2023年末時点において、旗艦事業のジェリコ農産加工団地(JAIP)3ではパレスチナ民間企業14社が操業し、約200人の雇用を創出している。また、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)4」を通じて東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員し、パレスチナの国造りを支援している。
10月7日以降のイスラエルとハマスなどパレスチナ武装勢力の武力衝突を受けて、日本は、ハマスなどによるテロ攻撃を断固として非難し、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有することを確認した上で、人質の即時解放・一般市民の安全確保、全ての当事者が国際法に従って行動すること、事態の早期沈静化を一貫して求め、戦闘休止及び人道支援活動が可能な環境の確保に向けた積極的な外交努力を行ってきた。岸田総理大臣は、12月の国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)の機会にエジプト、イスラエル、カタール、ヨルダン、イラン、トルコとの間で首脳会談を行い(イランは電話会談)、事態の早期沈静化などに向けた連携・意思疎通を確認した。上川外務大臣は、10月21日、カイロ平和サミットに出席したほか、11月3日から4日にイスラエル、パレスチナ、ヨルダンを訪問し、各国・地域との間で外相会談などを行った。またG7の枠組みでも、11月のG7外相会合においてイスラエル・パレスチナ情勢について率直な議論を外相間で行い、11月29日には「イスラエル及びガザ情勢に関するG7外相声明」を発出した。国連においても、安全保障理事会がその責務を果たせるよう、安保理の一員として、ガザ地区に対する人道支援の拡大と監視に関する決議の採択に向けて精力的な働きかけを行った。さらには、日本は、ガザ地区における危機的な人道状況の改善に向け、10月以降、パレスチナに対する総額約7,500万ドルの人道支援や独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた物資支援などを表明し、実施してきている。また、2024年1月26日のICJによる暫定措置命令については、同月27日、外務省は、「国連の主要な国際司法機関であるICJの暫定措置命令は、当事国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきもの」である、「国際社会における法の支配を重視する我が国として、この機会に、ICJが果たしている役割に改めて支持を表明」する、などの日本の立場を表明する外務大臣談話を発表した。

(10月21日、エジプト・カイロ)
(2)イスラエル
高度な先端技術開発やイノベーションに優れているイスラエルは、日本の経済にとって重要な存在であると同時に、中東地域の安定にとっても重要な国となっている。
2022年11月の総選挙後、ビンヤミン・ネタニヤフ氏が組閣指名を受け、同年12月末にイスラエルで極右政党を含む連立政権が発足した。同政権の下では、これまで、司法制度改革をめぐり国論が二分され、国内で大規模なデモが継続的に発生したほか、ヨルダン川西岸地区では入植政策が推進され、パレスチナ人とイスラエル人入植者との間で繰り返し衝突が発生した。
10月7日に発生したハマスなどによるテロ攻撃を受け、ネタニヤフ首相は「戦争状態」を宣言、主要野党を含む形で挙国一致内閣を設置し、ガザ地区に対する軍事作戦を開始した。
日本との関係では、3月に両国間の定期直行便が運航開始したほか、2023年は「あり得べき日・イスラエル経済連携協定(EPA)に関する共同研究会合」が3回開催された。また、10月7日のテロ攻撃を受け、11月に上川外務大臣がイスラエルを訪問し、ヘルツォグ大統領やコーヘン外相と会談したほか、ハマスによるテロ攻撃で亡くなった方や誘拐された方の御家族と面会した。
(3)パレスチナ
パレスチナは、1993年のオスロ合意などに基づき、1995年からパレスチナ自治政府(PA)5がヨルダン川西岸及びガザで自治を開始し、2005年大統領選挙でアッバース首相が大統領に就任した。その後、大統領率いるファタハと、ハマスとの間で関係が悪化し、ハマスがガザを武力で掌握した。2017年、エジプトの仲介により、ガザにおけるパレスチナ自治政府への権限移譲が原則合意され、また2022年にはアルジェリアが仲介し、パレスチナ立法評議会選挙の1年以内の実施などを掲げる、パレスチナ諸派間の和解文書「アルジェ宣言」が署名されたが、依然としてファタハが西岸を、ハマスがガザを支配する分裂状態が継続している。
日本との関係では、9月、林外務大臣がカイロで日・アラブ政治対話の機会にマーリキー外務・移民長官と外相会談を行ったほか、10月7日のハマスなどによるイスラエルへのテロ攻撃を受け、11月には上川外務大臣がパレスチナを訪問し、同外務・移民庁長官と外相会談を行った。

(4)アフガニスタン
アフガニスタンは、中東、中央アジア、南アジアの連結点に位置し、歴史的に様々な宗教、文化、民族が交錯してきた、地政学的に重要な国である。
同国では、タリバーンが2021年8月に首都カブールを制圧し、翌月に「暫定政権」の樹立が発表されたが、民族・宗教的包摂性の欠如が指摘されている。また、女子中等・高等教育の停止、NGO・国連機関のアフガ二スタン人女性職員の勤務停止などの女性・女児の権利の大幅な制限に対し、国際社会は深刻な懸念を表明している。また、治安は改善したものの、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」系組織によるテロが各地で散発している。
こうした中、日本は、アフガニスタンが1990年代のように再び国際社会から孤立しテロの温床となることを避ける観点から、タリバーンに対し、女性や社会的少数者を含む全てのアフガニスタン国民の社会・政治参加や、各種制限の撤廃、及び、国際社会との建設的な関係構築を求める直接的な関与を継続している。2023年は、安保理非常任理事国として、また、アフガニスタン情勢に関するペンホルダー6として、UAEと共に関連決議の起草や調整を担い、国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)7に関する国連安保理決議第2678号の全会一致での採択、国際社会のアフガニスタンへの関与の指針を示す独立アセスメント8報告書による勧告の実施に向けた同決議第2721号の採択などに貢献した。
国連の発表によると、同国は、人口の約3分の2が人道支援を必要としており、日本は、タリバーンによるカブール制圧以降も国際機関などを経由し、人道支援やベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)に応える支援を継続してきた。2023年も、10月に発生した西部における大規模な地震被害に対して、JICAを通じた緊急援助物資の供与及び国際機関を通じた300万ドルの緊急無償資金協力を実施したほか、12月には、令和5年度補正予算において約5,840万ドルの追加的支援を決定した。これにより、2021年8月以降の日本による支援額は約4億7,000万ドル規模となった(2023年末時点)。
(5)イラン
イランは、約8,500万人の人口と豊富な天然資源を誇るシーア派の地域大国であり、日本とは90年以上にわたり伝統的な友好関係を発展させてきている。
同国は、米国のトランプ前政権によるイラン核合意(包括的共同作業計画(JCPOA)9)からの離脱を受け、2019年7月以降、核合意上のコミットメントを段階的に停止する対抗措置をとってきている。2023年末時点で、60%までの濃縮ウランの製造を行っており、保障措置問題の一部が未解決であるほか、国際原子力機関(IAEA)による抜き打ち査察を可能にしていた追加議定書の履行停止や、一部の特定の国籍のIAEA査察官の指名撤回などを行っている。日本は、イラン核合意を一貫して支持している立場から、2023年3月のイランとIAEAとの間の共同声明の完全かつ無条件の実施を含め、イランによる建設的な対応を求めている。バイデン政権下では、米国及びイラン双方による核合意への復帰に向けた様々な外交努力が行われてきたが、現時点で米国及びイランによる核合意上のコミットメント遵守への復帰は実現していない(2023年12月末時点)。また、10月18日には、イラン核合意の採択の日から8年が経過したことを受け、イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づく一部の対イラン措置に係る条項が期限を迎え、日本も同条項に基づく措置を解除した。一方、日本は、安保理決議の規定の有無にかかわらず、核兵器運搬手段に関連するモノ及び技術の移転について、外国為替及び外国貿易法に基づき厳格に対応している。
このような中、イラン正規軍海軍によるマーシャル諸島籍タンカー拿捕やイラン革命ガード海軍によるパナマ籍タンカー拿捕事案が発生したほか、10月以降のイスラエル・パレスチナ情勢を受け、イランに近いとされる勢力によるシリア及びイラク領内の米国権益への攻撃や紅海及びその周辺海域での船舶に対する攻撃が発生したほか、米国による報復攻撃、シリアにおけるイラン革命ガード上級軍事顧問の殺害、ソレイマニ元革命ガード司令官の追悼集会中の爆発事案、これらの事案に対するイランによる報復攻撃など、イランをめぐる情勢は高い緊張状態が継続している。日本は様々な機会を捉え、首脳・外相レベルを含め、イランに対し、イランが影響力を持つ勢力に対して自制を強く働きかけるよう求めている。
一方、イランをめぐる緊張緩和の動きも見られた。イランは、2016年以降外交関係を断絶していたサウジアラビアとの間で、イラクやオマーンによる仲介努力を経て、3月に中国が仲介する形で外交関係正常化に合意した。また、9月にはオマーンやカタールの仲介により、韓国にあるイラン凍結資産が解放され、米・イラン間の被拘束者の交換が実現した。
ロシアによるウクライナ侵略をめぐっては、イランによるロシアへの無人航空機(ドローン)の提供について、国際社会における非難を受けた議論が継続している。
日本は、米国と同盟関係にあると同時に、イランと長年良好な関係を維持してきており、保健・医療、環境、防災など、イラン国民が直接裨(ひ)益する分野での二国間協力を継続しているほか、イランにおけるアフガニスタン難民支援を実施している。また、岸田総理大臣は、前年に引き続き、9月に訪問中のニューヨーク(米国)においてライースィ大統領と会談を行い、12月には日・イラン首脳電話会談が行われた。アブドラヒアン外相との間では、8月の訪日時に林外務大臣が会談を行ったほか、上川外務大臣が10月に電話で、12月には対面で同外相と会談を行った。こうしたハイレベルの会談に加え、4月及び12月に日・イラン次官級協議、1月に日・イラン領事当局間協議、10月に日・イラン人権対話、11月に日・イラン軍縮・不拡散協議を行った。このように、日本は、イランとの様々なレベルでの重層的な対話を継続しつつ、あらゆる機会を捉えて、イランに対し、諸課題について懸念事項を直接伝達するなど、中東地域における緊張緩和と情勢の安定化に向けた独自の外交努力を行ってきている。
(6)トルコ
トルコは、地政学上も重要な地域大国であり、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として地域の安全保障において重要な役割を果たしており、欧米、ロシア、中東、アジア、アフリカへの多角的な外交を積極的に展開している。また、1890年のエルトゥールル号事件10に象徴されるように、伝統的な親日国である。
2023年2月、トルコ南東部を震源とする大地震が発生、多数の建物が倒壊し、犠牲者数が約5万人に達する未曽有と言える大災害となった。近年、高いインフレ率が市民の生活を圧迫してきたことや、同震災対応に関するトルコ政府への逆風もある中、5月、大統領選挙及び議会選挙が実施された。大統領選挙においては決選投票の末、エルドアン大統領が再選を果たし、また議会選挙においてもエルドアン大統領が率いる公正発展党(AKP)11などによる与党連合が勝利した。同選挙により、エルドアン大統領の任期は2028年までとなり、野党による統一候補が当選を果たせず、2024年の地方選挙を迎えることとなった。
外交面においては、深刻なインフレと経済危機に直面し、大統領選挙に向けて、実利的な面を優先して隣国との関係改善を図ってきた。NATO加盟国としては、フィンランドの加盟申請を容認した。一方、ハマスなどによるテロ攻撃発生以降、イスラエル・パレスチナ情勢が緊迫化したことを受け、関係改善中であったイスラエルを強く非難する姿勢を取っている。
日本との関係では、2月のトルコ南東部を震源とする大規模地震を受け、日本政府は発災当日に国際緊急援助隊・救助チーム、引き続いて医療チーム及び専門家チームを派遣したほか、自衛隊機を派遣して支援に必要な資機材などの輸送を行った。また、JICAを通じて緊急援助物資を供与したほか、国際機関及び日本のNGOを通じて計850万ドルの緊急人道支援を行った。加えて、復旧・復興に向け、がれき処理や医療機材・重機などの供与を目的とする総額50億円の無償資金協力の実施や被災地の復旧・復興を支援するための800億円の借款の供与などを表明した。また、9月のG20ニューデリー・サミット、12月のCOP28に際して、岸田総理大臣とエルドアン大統領との間で首脳会談を実施した。
(7)イラク
イラクは、2003年のイラク戦争後、2005年に新憲法を制定し、民主的な選挙を経て成立した政府が国家運営を担っている。
内政面では、2021年の国民議会選挙後に内閣を組閣できない混乱状態が続いていたが、2022年10月の新政府発足以降、広範な政治勢力による支持を背景に、スーダーニー首相による安定した政権運営が行われている。2023年6月には、2023年度から2025年度3か年予算法を施行し、予算の安定性と行政の継続性が実現することとなった。また、10年ぶりとなる県評議会選挙を12月に実施し、今後の地方行政の強化と行政サービスの拡充が期待されている。
スーダーニー政権発足後、イラクの国内治安は大きく改善した一方、10月以降、「イラクのイスラム抵抗」を名乗るイラク国内の親イラン民兵組織によるイラク国内の米軍関係施設への攻撃が相次ぎ、米軍による親イラン民兵組織への反撃も行われるなど、イスラエル・パレスチナ情勢がイラク国内情勢に影響を及ぼしている。
外交面では、イラン、サウジアラビア、トルコといった地域大国の間に位置し、近隣諸国との関係強化やバランス外交を志向している。3月に中国の仲介によって実現したイランとサウジアラビアの外交関係正常化に関する合意に至る過程においては、イラクもオマーンとともに仲介努力を行い貢献した。
日本は2003年以降、約138億ドル(2023年末時点)の経済協力を実施するなど、一貫して対イラク支援を継続している。
(8)ヨルダン
ヨルダンは、混乱が続く中東地域において比較的安定を維持しており、アブドッラー2世国王のリーダーシップの下で行われている過激主義対策、多数のシリア・パレスチナ難民の受入れ、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。
日本との関係では、両国の皇室及び王室は伝統的に友好な関係にあり、4月にはアブドッラー2世国王及びフセイン皇太子が訪日した。
首脳レベルでは、4月に岸田総理大臣が同国王と首脳会談を実施し、戦略的パートナーシップの下、協力関係を今後更に発展させることを確認した。10月には、ガザ地区をめぐる情勢について同国王と首脳電話会談を実施した。岸田総理大臣は12月にはCOP28に際して同国王と首脳会談を実施し、ガザをめぐる情勢を中心に協議を行い、地域の長期的な安定に向けて、緊密に連携していくことを確認した。
外相レベルでは、林外務大臣が、3月に訪日したサファディ副首相兼外相・移民相との間で第3回外相間戦略対話を実施したほか、5月にはシリアをめぐる情勢について電話会談を行った。また、林外務大臣が9月にヨルダンを訪問した際には、同国王及びハサーウネ首相を表敬したほか、同外相と第4回外相間戦略対話を行い、「二国家解決」に基づく中東和平実現及び難民支援の重要性を共有した。10月には上川外務大臣がガザをめぐる情勢について同外相との間で電話会談を行ったほか、11月にヨルダンを訪問した際に外相会談を実施し、同月サンフランシスコを訪問中にも外相電話会談を行った。また、12月にジュネーブを訪問中にも外相会談を行い、外相間で頻繁に会談を重ね、協力関係を深めていることを歓迎し、ガザ地区における人道状況の改善や事態の早期沈静化、及び二国間協力の更なる発展に向けて、連携して取り組んでいくことを確認した。
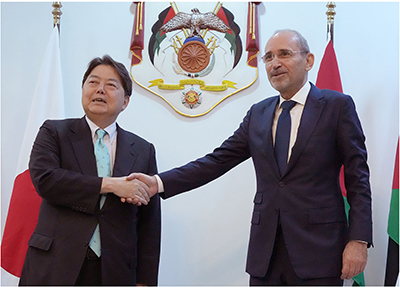
加えて、1月に西村康稔経済産業大臣、2月に山﨑統合幕僚長、7月に河野太郎デジタル大臣がヨルダンを訪問し、経済・安全保障面などでも協力を積み重ねてきている。
(9)湾岸諸国とイエメン
湾岸諸国は、近年、脱炭素化や産業多角化などを重要課題として社会経済改革に取り組んでいる。湾岸諸国は、日本にとってエネルギー安全保障などの観点から重要なパートナーであることに加え、こうした改革は中東地域の長期的な安定と繁栄に資するとの観点から、日本としても、サウジアラビアとの「日・サウジ・ビジョン2030」や、UAEとの「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)12」などの下で幅広い分野の協力を進めている。岸田総理大臣は7月にサウジアラビア、UAE、カタールを訪問して各国首脳と会談を行い、中東地域をクリーンエネルギーや重要鉱物のグローバルな供給ハブとする構想を提案し、従来の「産油国」と「消費国」という関係から、幅広い分野におけるパートナーの関係へと発展させると述べた。また、2009年以降交渉が中断していた日・GCC自由貿易協定(FTA)13について、2024年中に交渉を再開することでGCC側と一致した。9月には林外務大臣がサウジアラビアを訪問し、日・GCC外相会合に加え、サウジアラビア、オマーン、クウェート及びバーレーンの外相と会談を行った。また、日本はスーダン情勢やガザ情勢を受けて湾岸諸国と電話会談を行った。
サウジアラビアは石油輸出国機構(OPEC)14で主導的な役割を担っており、日本の原油輸入の約4割を供給するエネルギー安全保障上の重要なパートナーである。また、同国はアラブ諸国唯一のG20メンバーであり、イスラム教の二大聖地を擁するアラブ・イスラム諸国の盟主である。2023年には、イランとの外交関係正常化、イエメンのホーシー派との直接協議、シリアのアラブ連盟復帰の働きかけ、ガザ情勢を受けたアラブ連盟・イスラム協力機構(OIC)15緊急共同サミットの開催など、アラブ・イスラム諸国の外交政策の議論において主導的な役割を担った。また、同国は、「サウジ・ビジョン2030」を掲げ、包括的な社会経済改革を目指し、様々な分野で新たなイニシアティブを推進している。ムハンマド皇太子兼首相と岸田総理大臣との7月及び9月の2回の会談、10月の2回の電話会談、ファイサル外相と林外務大臣との4月の電話会談及び9月の会談、上川外務大臣との10月の電話会談、深澤陽一外務大臣政務官の12月の「日・サウジ・ビジョン2030」第7回閣僚会合への出席などを通じ、「日・サウジ・ビジョン2030」の枠組みの下での様々な分野での協力や「クリーンエネルギー協力のための日・サウジ・ライトハウス・イニシアティブ」の下での協力を一層推進し、両国の戦略的パートナーシップを強化させることを確認した。
UAEも日本の原油輸入の約4割を供給するエネルギー安全保障上の重要なパートナーである。また、2023年、同国はCOP28の議長国を務めたほか、安保理非常任理事国として、アフガニスタン問題では日本と共同で議論を主導し、またガザ情勢に関する決議案を提案するなど、国際場裡(り)において重要な役割を担った。日本は、岸田総理大臣とムハンマド大統領との7月の会談、10月及び12月の電話会談、林外務大臣による1月のサーイグ国務相、4月のジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使、4月(電話)及び6月のアブダッラー外相との会談、上川外務大臣の9月のジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使とのCSPI第1回閣僚級会合、10月のアブダッラー外相との電話会談などを通じ、「CSPI」の枠組みの下での様々な分野での協力や「日・UAEイノベーション・パートナーシップ」及び「グローバル・グリーン・エネルギー・ハブ」構想の下での協力を一層推進し、両国の戦略的パートナーシップを強化させることを確認した。また、防衛分野では、5月に署名した日・UAE防衛装備品・技術移転協定が2024年1月に発効した。

カタールは、世界最大級の産ガス国でありつつ、イラン、タリバーン、ハマスなどとの独自のチャンネルをいかし、米・タリバーン間の和平交渉、米・イラン間の被拘束者交換の交渉、イスラエル・ハマス間の人質解放をめぐる交渉などを仲介し、存在感を高めている。日本はカタールとの間で、7月の岸田総理大臣の同国訪問の際に、両国の包括的パートナーシップを戦略的パートナーシップへと格上げしたほか、岸田総理大臣がタミーム首長と10月に電話会談、12月に会談を行い、また、1月に林外務大臣とムハンマド副首相兼外相との間で第2回日・カタール外相間戦略対話を、10月には上川外務大臣とフライフィ外務省国務相との間で電話会談を行った。
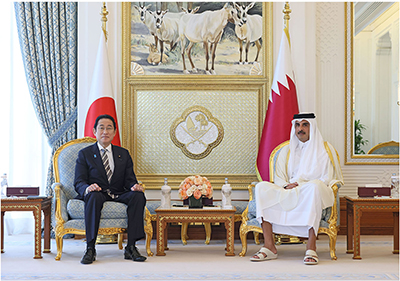
(7月18日、カタール・ドーハ 写真提供:内閣広報室)
オマーンは、イランやホーシー派との独自のチャンネルをいかし、サウジアラビア・イラン間の外交関係正常化の交渉、サウジアラビア・ホーシー派間の交渉、米・イラン間の被拘束者交換の交渉などを仲介した。日本は、バドル外相との間で、林外務大臣が3月及び9月に会談を行い、上川外務大臣が11月に電話会談を行った。
クウェートとは、1月の髙木啓外務大臣政務官の同国訪問、9月の林外務大臣とサーレム外相との会談のほか、12月にはナッワーフ首長の薨(こう)去を受け、森英介総理特使(衆議院議員)がクウェートを弔問し、ミシュアル新首長に弔意を伝達した。
バーレーンとの間では、9月に日・バーレーン投資協定が発効したほか、同月、林外務大臣とザヤーニ外相が会談を行った。
イエメンの安定は、中東地域全体の平和と安定のみならず、日本のエネルギー安全保障に直結するシーレーンの安全確保の観点からも重要である。イエメンでは、イエメン正統政府及びアラブ連合軍と、ホーシー派との間での衝突が継続していたが、2022年4月に全土での停戦が合意され、同年10月に同合意は失効したものの小康状態が継続している。2023年には、オマーンの仲介により、サウジアラビアとホーシー派との間での直接協議が複数回実施され、イエメンの恒久的和平に向けた前向きな動きが見られている。日本も、林外務省参与からホーシー派交渉団長への働きかけなどを通じ、イエメン人同士の対話の実施に向けた外交努力を継続している。ガザ地区をめぐる情勢を受け、11月、ハマスとの連帯を掲げるホーシー派は、イスラエル関係船舶に対する攻撃を行うことを宣言し、紅海のイエメン沖において日本関係船舶を「拿捕」するなど、紅海及びアデン湾などにおいて、船舶に対する攻撃を相次いで行っている。日本は、こうしたホーシー派の行動を断固非難し、船舶の自由かつ安全な航行を阻害する行為の自制を求め、日本関係船舶・乗組員の早期解放や周辺海域の安定化のため、関係国と連携しながら取り組んでいる。2024年1月には、日本が米国と共に提案した、紅海上の船舶に対するホーシー派のあらゆる攻撃の即時停止を求める安保理決議2722号が採択された。一方、紛争長期化により、イエメンは「世界最悪の人道危機」とされる深刻な状況に直面しており、日本は2015年以降、国際機関などと連携し、イエメンに対し、合計約4.3億ドル(2023年末時点)の人道支援を実施している。
(10)シリア
ア 情勢の推移
2011年3月に始まったシリア危機は、発生から12年が経過するも、なお情勢の安定化及び危機の政治的解決に向けた見通しは立っておらず、2019年に国連の仲介により設立され政権側及び反体制派側が一堂に会する「憲法委員会」も1年以上実施されていない。一方、2月6日に発生したトルコ南東部を震源とする大地震により、北部を中心にシリアでも甚大な被害が発生した(犠牲者は5,900人以上とされる。)。シリア国内で人道支援を必要とする人々の規模は2024年には1,670万人に上るとされており、国内避難民の数も2023年末時点で720万人を超えるなど、危機発生以降、人道支援ニーズが最も高い状況にあるとされている。
対外関係では、アサド政権を支持するロシアやイランとの協力関係は維持されつつ、近年に見られたアラブ諸国との関係改善の動きの一環として、5月7日にはアラブ連盟外相級臨時会合において同連盟への参加再開が決定された。また9月にはアサド大統領による、19年ぶりとなる訪中が実施された。なお、欧米諸国は、アサド政権による化学兵器使用や人権蹂躙(じゅうりん)16行為などを理由に、シリア政府との関係再開には依然として慎重な姿勢を維持している。
軍事・治安面では、首都ダマスカスの治安は総じて維持されている一方、北部などを中心に不安定な情勢が継続している。また10月7日に発生したハマスなどによるイスラエルに対するテロ攻撃発生以降、イスラエル・パレスチナ情勢が緊迫化したことを受け、シリア国内への空爆などの攻撃が増大するなど、シリア情勢にも影響を及ぼしている。
イ 日本の取組
日本は、一貫して、シリア危機の軍事的解決はあり得ず、政治的解決が不可欠であると同時に、人道状況の改善に向けて継続的な支援を行うことが重要との立場をとっている。6月に開催された「シリア及び地域の将来の支援に関する第7回ブリュッセル会合」には山田賢司外務副大臣が出席し、人道支援における日本の揺るぎない決意を表明した。日本は、2012年以降、総額約35億ドルの人道支援をシリア及び周辺国に対して実施してきている(2023年末時点)。
(11)レバノン
レバノンは、複合的危機による様々な課題に直面する中、2022年10月末のアウン前大統領の任期終了後、政治勢力間の対立などにより議会での協議は妥結に至らず、新たな大統領の選出も新内閣の組閣も実現しておらず、政治空白が続いている。国際通貨基金(IMF)17との事務レベル合意で提示された行財政改革は著しく遅れており、公共サービスの機能不全や高いインフレ率など、経済危機は長引いている。7月以降には、レバノン国内のパレスチナ難民キャンプで軍事衝突事案が発生した。さらに、10月7日以降のガザ情勢の影響を受け、イスラエルと接する南部ではイスラエルとヒズボッラーなどの間で軍事攻撃の応酬が継続しており、治安情勢や人道状況の更なる悪化が指摘されている。
日本は、2012年以降、合計2億9,090万ドル以上の支援(広域支援を含む。)を行っている(2023年末時点)。8月には山田外務副大臣がベイルートを訪問し、ミカーティ暫定首相やベッリ国会議長などとの会談を実施した。また、上川外務大臣は、12月にジュネーブを訪問中にブハビーブ外務・移民相との間で外相会談を行い、ガザ地区における人道状況の改善や事態の早期沈静化に向けて、両国が引き続き連携して取り組んでいくことを確認した。
2 IDF:Israel Defense Forces
3 JAIP:Jericho Agro-Industrial Park
4 CEAPAD:Conference on cooperation among East Asian countries for Palestinian Development
5 PA:Palestinian Authority
6 安保理において、特定の議題に関する議論を主導し、決議や議長声明などの文書を起草する理事国を指す。
7 UNAMA(United Nations Assistance Mission in Afghanistan):2002年、国連安保理決議1401号を根拠として設立され、アフガニスタン政府に対する和平プロセスのための政治的戦略的助言などを任務としている。2021年8月のタリバーンによるカブール制圧以降もアフガニスタンでの活動を継続し、タリバーンへの働きかけや人道支援の調整などを行っている。
8 アフガニスタンに関する「独立アセスメント」:2023年3月16日、国連安保理は、決議第2679号を通じ、アフガニスタンが直面する諸課題に対処するための方途などに関する「独立アセスメント」の実施を国連事務総長に対して要請した。これを受け、4月、国連事務総長は、同アセスメントの取りまとめ役としてシニルリオール特別調整官(トルコ人)を任命した上で、独立アセスメントに関する報告書を作成させ、11月8日付で安保理に提出した。同報告書は、国際社会とアフガニスタンとの間の信頼構築、主要課題に対処するための協力継続及びアフガニスタン人の間の対話追求などを求めるとともに、国連事務総長によるアフガニスタン特使の任命を始め、アフガニスタンへの関与を強化するためのメカニズム構築などを勧告している。
9 JCPOA:Joint Comprehensive Plan of Action
10 エルトゥールル号事件の詳細については、外務省ホームページ参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page22_001052.html

11 AKP:Adalet ve Kalkınma Partisi
12 CSPI:Comprehensive Strategic Partnership Initiative
13 FTA:Free Trade Agreement
14 OPEC:Organization of the Petroleum Exporting Countries
15 OIC:Organisation of Islamic Cooperation
16 国家権力が、憲法に保障された国民の基本的人権を侵犯すること
17 IMF:International Monetary Fund
