4 東南アジア
(1)インドネシア
インドネシアは、世界第4位の人口(2億6,800万人)を有する東南アジア地域の大国として、ASEANにおいて主導的な役割を担うほか、G20メンバー国として、国際社会の諸課題においてもイニシアティブを発揮している。
国内政治では、4月に大統領選挙が実施され、現職のジョコ大統領とマルフ・アミン副大統領候補の陣営と、プラボウォ・グリンドラ党党首とサンディアガ・ウノ副大統領候補の陣営が争ったが、55.5%の得票率でジョコ大統領陣営が勝利し、再選を果たした。同日に議会選挙(国会、地方代表議会、州議会、県/市議会)の投票も行われ、国会議員選挙においては、ジョコ大統領の擁立政党である闘争民主党が128議席(得票率の19.3%)を獲得し、与党第一党となった。10月20日にはジョコ大統領及びマルフ・アミン副大統領の就任式が実施され、日本政府を代表して中山展宏外務大臣政務官が出席した。また、同月23日には「前進内閣」が発表され、ジョコ政権の第2期目が始動した。
日本との関係では、ハイレベルでの交流が活発化した。首脳級では、6月のG20大阪サミットに際してジョコ大統領が、即位礼正殿の儀に際してマルフ・アミン副大統領が訪日したほか、11月のASEAN関連首脳会議(タイ・バンコク)に際して、安倍総理大臣とジョコ大統領との間で、ジョコ政権第2期目に入って初めての首脳会談が実施された。また、G20愛知・名古屋外務大臣会合に際して、ジョコ政権2期目において留任したルトノ外相が訪日し、茂木外務大臣との間で初めての外相会談を実施するなど、閣僚級の交流も活発に行われた。これらのハイレベル交流を通じて、政治・安全保障、経済・インフラ整備、海洋、防災、人的交流などの分野での協力関係や、南シナ海や北朝鮮などの地域的課題における連携を更に強化していくことを確認した。

(2)カンボジア
カンボジアは、メコン地域の連結性と東南アジア地域内の格差是正の鍵を握る国である。南部経済回廊の要衝に位置する地理的利点と年7%の経済成長率の下、2030年の高中所得国入りを目指し、ガバナンスの強化を中心とする開発政策を推進している。
日本は、1980年代後半のカンボジアの和平プロセスやその後の復興・開発に積極的に協力してきている。1992年から1993年にかけて、日本として初となるPKOを派遣した同国を「積極的平和主義」の原点として、近年様々な分野での関係を深めている。2013年に両国関係は「戦略的パートナーシップ」に格上げされた。2019年も要人往来が活発に行われ、ノロドム・シハモニ国王が10月の即位礼正殿の儀への参列のため訪日し安倍総理大臣と会談したほか、フン・セン首相も5月に訪日し首脳会談を実施した。また、8月と12月に外相会談を実施した。
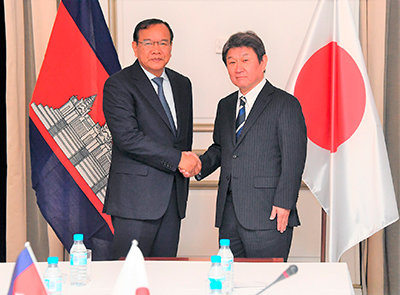
内政面では、2017年の最大野党・救国党に対する解党命令を含むカンボジア政府の野党、メディア、市民社会などに対する措置、及び2018年の国民議会選挙の結果を踏まえ、市民社会を含む国内外からの批判が継続した。一方で、カンボジア政府は、国内野党との対話や市民社会との定例会合を開催したほか、2017年以降捜査対象となっている旧救国党党首の国内移動の自由を認めるなどの措置を取った。日本は、カンボジアの民主的発展を後押しするという観点から、2018年10月の首脳間の合意に基づき、計3回の若手政治関係者の招へいのほか、市民社会を含む選挙関係者、市民社会担当政府高官の招へいなどを実施した。
日本が長年支援しているクメール・ルージュ裁判では、2018年に初級審が無期禁固刑を宣告した幹部2人のうち1人が死亡したが、残り1人の上訴手続を含む計4事案について司法プロセスが進んでいる(特集参照)。
~クメール・ルージュ特別法廷と同裁判文書センターへの支援~
長い混乱に苦しんだ時代を経て、現在急速に経済発展を遂げている国、カンボジア。しかし、クメール・ルージュ(KR)政権下の虐殺と内戦を経験した人々の心の傷が完全に癒(い)えることはなく、今なお社会に影響を与えています。一方で、内戦を経験していない若い世代が、今や人口の約半分を占めています。世代交代が少しずつ進み、社会の転換期を迎える同国では、過去の経験を次世代に継承し未来につなげるための取組の必要性が高まっています。今回はその取組の一つとして日本が支援しているクメール・ルージュ特別法廷と同裁判文書センターを紹介します。
KR政権は、過激な共産主義的思想の下、1975年から1979年の間に100万とも200万とも言われる自国民などを虐殺したとされています。1991年に和平が達成されましたが、KRは抗戦活動を続け、政権当時の責任は問われずに来ました。2006年にようやく同政権の罪を裁くためKR特別法廷が活動を開始し、これまでに当時の国家元首などを含む3人に対し終身刑の確定判決が下されました。うち1人については、別容疑での上訴審裁判が継続中で、軍・地方幹部3人についても裁判プロセスが続いています。
この法廷は、国連によって設立された旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所とは異なり、カンボジアと国連の間で2003年に締結された協定に基づき、犯罪が行われた国であるカンボジアの裁判所において、国連の支援を得て、関連するカンボジア国内法と国際法の双方を適用しながら裁判を行う点が特徴的です。これまで裁判を傍聴した者は延べ24万人、法廷視察などに参加した者を加えると延べ62万人に上ります。また、被害者参加制度を採用することで、人々がこれまでタブーとされた虐殺の経験について語り合えるようになりました。さらに、この法廷はカンボジアの司法改革のモデルとされ、国際標準の法廷管理の在り方が国内裁判所にも適用されたほか、国際水準のノウハウを学ぶ国内司法官の能力向上に貢献しています。


(11月27日、写真提供:クメール・ルージュ特別法廷(ECCC))
最近になって高校の歴史教育でもKR時代を扱うようになったものの、カンボジアの若者がKR時代を客観的に学べる機会は依然限られています。こうした中、2017年6月、クメール・ルージュ裁判文書センター(LDC)が首都プノンペンに開所しました。LDCでは、裁判文書の写しの保管・公開により教育・研究リソースを提供するとともに、法廷の活動に関する普及・啓発を行っています。2018年には延べ1,695人が同センターを訪問しました。今後、LDCを中心に過去の経験を次世代に継承する取組が更に進むことが期待されます。

日本は、KR裁判の迅速かつ成功裏の完結を「カンボジア和平の総仕上げ」と位置付け、国際支援全体の約3割に当たる約8,700万米ドルを拠出したほか、最高審判事などの日本人職員を派遣しました。また、LDCの建物及び内部設備の整備や活動費用の一部も支援しました。かつて同じ民族間で殺し合い、憎しみと不信を抱いた人々と社会が再び信頼を取り戻すことは、容易なことではありません。しかし、日本は、和平達成から現在まで一貫してカンボジアを支援してきた国として、過去に学び、対立を乗り越え、未来に向けて団結するためのカンボジアの人々の努力を、今後とも支えていきます。
※1 正式名は、Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
※2 正式名は、Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (LDC)
(3)シンガポール
シンガポールは、ASEANで最も経済が発展している国家であり、全方位外交の下、米国や中国を含む主要国と良好な関係を維持している。
国内では、リー・シェンロン首相率いる人民行動党(PAP)が議会での圧倒的多数を占めている。5月の内閣改造ではヘン・スイキャット財相が副首相兼財相に就任、次期首相候補とみられており、世代交代の準備が着々と進んでいる。
日本との関係では、2019年も引き続きハイレベルでの交流が実現した。5月、副首相就任直後のヘン・スイキャット副首相兼財相が来日し、安倍総理大臣を表敬した。また、6月にはリー・シェンロン首相がG20大阪サミットに参加するため、8月にはゴー・チョクトン名誉上級相(前首相)が第7回アフリカ開発会議(TICAD7)(横浜)に参加するため、10月にはハリマ・ヤコブ大統領が即位礼正殿の儀に参列するために来日し、首脳会談などが行われた。11月のASEAN関連首脳会合(タイ)の際、リー・シェンロン首相と安倍総理大臣が同年2度目の首脳会談を実施し、リー・シェンロン首相から、福島県産食品に対して残る輸入停止措置を解除する方針が表明された。加えて、11月にはバラクリシュナン外相がG20愛知・名古屋外務大臣会合参加のため来日した際、茂木外務大臣と会談を実施し、自由貿易の推進についての意見交換や東アジア地域包括的経済連携(RCEP24)の早期妥結に向けた連携を確認した。また、南シナ海問題や北朝鮮情勢などの地域情勢についても意見交換を行い、連携を確認した。
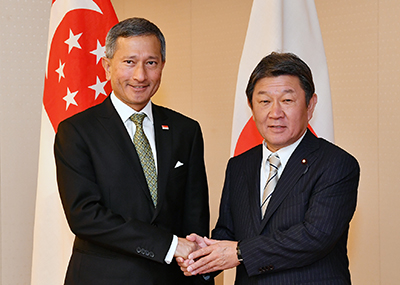
両国は1997年に署名した「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っており、これまでに約400の研修を実施、ASEAN諸国などから約6,900人が参加する実績を残している。日本文化情報の発信拠点としてシンガポールに開所された「ジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)」は2019年に10周年を迎え、文楽公演などの記念行事が行われるなど、文化交流も活発に行われている。
(4)タイ
タイは、メコン地域の中心に位置し地政学的に重要であるだけでなく、長年の投資の結果多くの日本企業の生産拠点となり、今日では地球規模でのサプライチェーンの一角として日本経済に欠くことのできない存在となっている。軍政によって設置された官選議会と暫定内閣の下、民政復帰のための下院総選挙が2019年3月24日に実施され、その結果を受けた連立交渉の末、7月16日、プラユット首相が続投する形で新政権が発足した。
日・タイ両国間では、皇室・王室の緊密な関係と「戦略的パートナーシップ」関係を礎に、政治面、経済面を含む様々なレベルで交流が行われている。日本がG20議長国であり、タイがASEAN議長国であった2019年も両国間では様々なレベルで活発な交流が継続した。5月にはタイ・フェスティバルに出席するためドーン外相が日本を訪問し、6月にはG20大阪サミット出席のためプラユット首相が日本を訪問した。また、7月にはASEAN関連外相会議出席のため河野外務大臣がタイを訪問し、10月には即位礼正殿の儀に参列するためプラユット首相が日本を訪問。さらに11月にはASEAN関連首脳会議への出席のため安倍総理大臣がタイを訪問した。
(5)東ティモール
東ティモールは、インド太平洋の要衝、オーストラリアとインドネシア間の重要なシーレーンに位置する、21世紀最初の独立国家(2002年)である。同国は、国際社会の支援を得つつ平和と安定を実現し、民主主義に基づく国造りを実践してきた。経済は天然資源(石油や天然ガス)への依存度が高く、国家の最優先課題として産業多角化に取り組んでいる。
外交面では、東ティモールの最重要外交課題であるASEANへの加盟に関して、2019年夏にバボ外務・協力相がASEAN各国を歴訪して要人と会談を行うなど、実現に向けて精力的に取り組んだ。
他方、国内では、2018年6月に第8次立憲政権を樹立させた政権与党とル・オロ大統領との間での対立により、国政は停滞の状況が続いている。
2019年は、東ティモールにおける独立回復の是非を問う住民投票や日本の対東ティモール支援開始から20周年を迎えたこともあり、活発なハイレベルの往訪が行われた。東ティモールからは、バボ外務・協力相(3月)が訪日、日本からは、薗浦健太郎総理大臣補佐官(4月)が東ティモールを訪問したのに加え、住民投票20周年式典に参列するために鈴木憲和外務大臣政務官(8月)が東ティモールを訪問した。一連のハイレベルの往来を通じ、教育・人材育成、人的交流、経済・インフラ、政治・安全保障などの分野における二国間協力や、日本・東ティモール・インドネシア三か国協力の枠組みにおける海洋分野などの協力、地域における連携を強化した。
(6)フィリピン
フィリピンは、南シナ海に位置する、7,000以上の島々からなる海洋国家で、海外出稼ぎ労働者からの送金や高い人口増加率に支えられた内需などを背景に、約6%の実質GDP成長を維持している。2019年は、2016年6月に就任したドゥテルテ大統領が、国民の高い支持と堅調な経済に支えられ、引き続き強い指導力を発揮した。2019年2月にはバンサモロ暫定自治政府が発足し、9月には武装解除活動が正式に開始されるなど、ミンダナオ和平プロセスは重要な進捗を見せた(54ページ 特集参照)。また、ドゥテルテ政権が重視している違法薬物対策、汚職撲滅、治安・テロ対策も引き続き推進され、経済面においては、包括的税制改革法が施行されるなど、税制改革が着実に実行されている。一連の改革は、国民から高い支持を得ており、5月に行われた中間選挙においても、大統領派が圧勝した。
「戦略的パートナー」である日・フィリピン関係を象徴するように、要人往来も活発に行われ、日本からは河野外務大臣(2月)、山下貴司法務大臣(7月)などがフィリピンを訪問した。フィリピンからはロクシン外相(5月)、ドミンゲス財相(2月、5月、12月)が訪日した。また、安倍総理大臣とドゥテルテ大統領の間で日・フィリピン首脳会談が2度(5月、11月)、日・フィリピン外相会談は3度(2月、5月、8月)行われた。
6月には、日・フィリピン外務・防衛当局間(PM)・防衛当局間(MM)協議及び海洋協議が行われ、安全保障分野で政策面での連携が強化された。経済面では、2017年1月に安倍総理大臣が表明した5年間で1兆円規模の支援を着実に実施するために立ち上げられた、日・フィリピン経済協力インフラ合同委員会を、2019年には3回(2月に第7回、6月に第8回、12月に第9回会合)開催するなど、日本はフィリピン政府が掲げる積極的なインフラ整備政策「Build, Build, Build」を強力に後押ししている。
3月には、諸外国に先駆けてフィリピンとの間で、日本の新しい在留資格「特定技能」に関する協力覚書が作成され、それに基づく介護分野などの試験が実施された。また、5月には、東日本大震災後、フィリピン政府が設けていた福島県水産物の輸入規制措置について、一部解除することが決定された。
ミンダナオは、フィリピン南部に位置するミンダナオ島やスールー諸島などで構成される地域のことを言います。緑豊かな山々と美しい海に恵まれ、多様な文化や宗教で溢(あふ)れるミンダナオは、土地が肥沃(ひよく)で、農業が盛んです。日本のスーパーで見かけるバナナやパイナップルの多くが、この地域の農園で栽培されています。また、ドゥテルテ大統領はフィリピン史上初のミンダナオ出身の大統領です。世界的に有名なプロボクサーで、フィリピン上院議員でもあるパッキャオ氏もミンダナオの出身です。
そのミンダナオでは、モロと呼ばれる先住民族とフィリピン政府との歴史的な対立に起因し、1969年以降、モロ民族解放戦線(MNLF)を始めとしたイスラム国家の樹立を目指す勢力による武力を伴う分離独立闘争が繰り広げられてきました。度重なる破綻を経ながらも、粘り強く和平交渉が続けられた結果、近年になり、バンサモロ基本法の成立(2018年7月)※1やバンサモロ自治政府設立のための住民投票を経て同暫定自治政府の発足(2019年2月)が実現するなど、和平プロセスは大きく進展しました。しかし、40年以上にも及んだ紛争の末、開発の波から大きく取り残された人々が平和の配当を実感できるようにすることが、現在の大きな課題となっています。

日本政府は、2002年の小泉総理大臣による「平和と安定のためのミンダナオ支援パッケージ」の表明以降、20年近くにわたり、フィリピン政府やモロ・イスラム解放戦線(MILF)などと連携して、和平プロセスの進展及び復興・開発を包括的に支援してきました。
その代表的な取組として、平和の象徴である鳩が羽ばたくような形をしているミンダナオになぞらえ、「日本・バンサモロ復興開発イニシアティブ(J-BIRD※2)」という名が付けられた、元紛争地域における集中的な開発協力プロジェクトの実施が挙げられます。J-BIRDは、2006年12月の安倍総理大臣のフィリピン訪問時に立ち上げられました。ミンダナオの持続可能な安定と発展の実現のためには、地元住民が和平による経済発展を感じられることが重要との認識に基づき、これまで、自治政府設立のための行政能力向上、生計向上支援や地域産業振興、インフラ整備、350以上の村落部における学校、農業施設の整備など、総額500億円以上に及ぶ支援を実施してきています(2019年12月時点)。最近では、地域の安定化を図ることを目的に、バンサモロ暫定自治政府に対する支援のほか、MILF兵士の退役・武装解除を行う独立退役・武装解除機関(IDB)や合同平和治安チーム(JSPT)に対し、車両や機材支援を実施しています。ほかにも、ミンダナオにおける停戦監視活動を行う国際監視団(IMT)に、在フィリピン日本国大使館員を派遣し、紛争影響地域におけるニーズの把握、支援案件の形成とモニタリングなどを行っています。


一連の日本政府による支援は、ミンダナオ住民の間で広く知られており、ドゥテルテ大統領を始めとしたフィリピン政府要人からも、感謝の意が繰り返し表明されています。ミンダナオ和平の深化は、フィリピンのみならず、インド太平洋地域の成長と繁栄、そしてテロの温床を残さないためにも極めて重要です。日本政府は今後も、ミンダナオ和平プロセスの進展に呼応する形で支援を強化していきます。
※1 バンサモロ(Bangsamoro)は、現地の言葉で「モロ(ミンダナオ先住民族)の土地」を意味します。
※2 J-BIRD:Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development
(7)ブルネイ
ブルネイは、豊富な天然資源を背景に、高い経済水準と充実した社会福祉を実現し、政治的にも経済的にも安定した国である。東南アジアの中心に位置し、ASEANの一体性、統合強化を柱とするバランス外交を行っている。
近年、経済面では、2014年以降、世界的な原油価格の大幅下落などにより、経済成長率が落ち込んでいた。石油・ガス価格の緩やかな回復などにより、2017年第2四半期から経済成長率はプラスに回復しているものの、ブルネイ政府はエネルギー資源への過度の依存から脱却すべく経済の多角化を目指している。
日本とブルネイは、1984年にブルネイが独立を果たした直後に外交関係を開設し、政治、防衛、経済、文化、人物交流など、様々な分野で良好な関係を発展させてきた。また、両国の皇室・王室関係も緊密である。ブルネイは日本へのエネルギー資源の安定供給の面からも重要な国であり、ブルネイの液化天然ガス(LNG)輸出総量の約6割が日本向けであり、ブルネイ産LNGは日本のLNG総輸入量の約5%を占めている。文化面では、「JENESYS2.0」25や内閣府「東南アジア青年の船」などの青少年交流事業のほか、バドミントンや柔道などのスポーツ交流も頻繁に行われている。
このような良好な両国関係を反映し、2019年も引き続き活発な要人往来が行われた。10月には、即位礼正殿の儀に参列するため、ボルキア国王が来日し、その際、安倍総理大臣との首脳会談が行われた。会談では、ボルキア国王から、東日本大震災に伴う日本産食品の輸入規制の撤廃が表明された。またボルキア国王に同行して訪日したエルワン第二外相と茂木外務大臣との外相会談も実施され、良好な二国間関係を更に活発化させ、地域の課題に対する連携を強化することが確認された。

(8)ベトナム
ベトナムは、南シナ海のシーレーンに面し、中国と長い国境線を有する地政学的に重要な国である。また、東南アジア第3位の人口を有し、中間所得層が急増していることから、有望な市場でもある。現在、インフレ抑制などのマクロ経済安定化、インフラ整備や投資環境改善を通じた外資誘致を通じ、安定的な経済成長の実現に取り組んでいる。また、行政改革や汚職対策にも積極的に取り組んでいる。
日本とベトナムは、「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」の下で、様々な分野で協力を進展させている。要人往来も活発に行われ、1月には阿部外務副大臣がベトナムを訪問し、ベトナムで最大級の両国交流イベントである第6回ジャパン・ベトナム・フェスティバルに参加した。5月にはミン副首相兼外相が国際交流会議「アジアの未来」に出席するため訪日し、日・ベトナム共同委員会や外相会談を実施した。6月にはフック首相がG20大阪サミットへ参加するため訪日し、安倍総理大臣との首脳会談が行われた。10月にはフック首相が即位礼正殿の儀に参列するため再び訪日した。
元来親日的なこともあり、ベトナム国民の訪日者数は2011年の約4万人から2018年には38万人を超え、日本に暮らすベトナムの人々は2011年の約4万人から2019年6月には約37万人に増えており、国別在留外国人数で中国、韓国に次いで3番目に多い数字となっている。
(9)マレーシア
マレーシアは、マレー半島の「半島マレーシア」とボルネオ島の「東マレーシア」から成る、インド洋と太平洋の結節点に位置し、南シナ海とマラッカ海峡に面した地政学的に重要な国である。また、13州及び3連邦直轄地から成る連邦国家で、マレー系、華人系、インド系などから構成される多民族国家である。
2018年5月に実施された第14回連邦下院総選挙において、マハティール元首相(第4代首相)率いる野党連合(希望連盟)が過半数を獲得し、1957年のマレーシア独立以来、初めて政権交代が行われた。第7代首相に就任したマハティール首相は、法の支配の回復、透明性、ガバナンスの改善、債務削減に取り組んでいる。2019年5月にマハティール首相は日本を訪問し、首脳会談で東方政策の再活性化を通じて、「戦略的パートナーシップ」の強化に取り組むことを確認し、「日本・マレーシア協力:新時代における東方政策再訪」のファクトシートを発出した。8月には、ASEAN関連外相会議(タイ)の際、河野外務大臣はサイフディン外相と外相会談を行い、10月には、アブドゥラ国王が即位礼正殿の儀に参列するため訪日し、安倍総理大臣と会談を行った。このほか、マレーシアの閣僚の訪日も相次いでおり、両国間の要人往来が活発に行われている。
両国間の具体的な協力については、3月にサムライ債が発行されたほか、9月には固形廃棄物分野における協力覚書が署名されるなど、様々な分野で協力が進展した。
マハティール首相が1981年に提唱した日・マレーシア間の友好関係の基盤である東方政策により、これまでに約1万7,000人のマレーシア人が日本で留学及び研修した。2011年9月に開校したマレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とするための協力が進められている。
経済面では、日本はマレーシアに対する最大の投資国であるほか、マレーシアへの進出日系企業数は約1,300社に上るなど、引き続き緊密な協力関係にある。
(10)ミャンマー
ミャンマーでは、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問率いる現政権が、民主化の定着、国民和解、経済発展に取り組んでいる。日本は、伝統的な友好国であり、経済発展への大きな潜在力及び地政学的重要性を有するミャンマーの安定が地域全体の安定と繁栄に直結するとの認識に立ち、同国の民主的国造りを官民挙げて全面的に支援している。2016年には、安倍総理大臣から2016年度から2020年度の5年間で、官民合わせて8,000億円の貢献を行うことを表明し、その後、都市開発、電力、運輸インフラを含む幅広い分野において協力を具体化している。2018年10月には、訪日したアウン・サン・スー・チー国家最高顧問に対し、安倍総理大臣から、ヤンゴン都市圏の市民生活向上のための新たな支援案件の実施を伝達した。2019年には、7月に河野外務大臣がミャンマーを訪問し、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問と会談したほか、10月に即位礼正殿の儀参列のため、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問が訪日した。
西部のラカイン州では、2012年に発生したコミュニティ間衝突以降、緊張状態が継続し、特に2017年8月の武装勢力による治安部隊拠点に対する襲撃、ミャンマー治安部隊による掃討作戦及びその後の情勢不安定化により、70万人以上の避難民がバングラデシュに流出した。日本は国際社会と共に、ミャンマー政府に対し、「安全、自発的かつ尊厳のある」避難民帰還の実現、国連の関与の下での帰還環境の整備を働きかけるとともに、バングラデシュ側の避難民、ホストコミュニティ及びラカイン州側の避難民・住民に対する人道支援を実施している。また、ラカイン州における人権侵害疑惑につき、ミャンマー政府に対し、国際社会の関与を得て透明性と信頼性のある調査を実施し、その結果を踏まえた適切な措置をとるよう促している。2019年1月、同国を訪問した阿部外務副大臣は、ミャンマー政府要人にラカイン州問題に関する日本の立場を伝えるとともに、日本や国連による支援の現場を視察した。

(1月15日、ミャンマー・北部マウンドー地区)
ミャンマー独立以来、国軍との戦闘を続けている少数民族武装勢力との和平実現も重要な課題である。2018年2月までに、カレン民族同盟(KNU)などの10の少数民族武装勢力が「全国規模停戦合意(NCA)」に署名した。日本からは、笹川陽平ミャンマー国民和解担当日本政府代表が、和平の当事者間の対話を促進しているほか、停戦が実現した地域の住民の生活向上のため、カレン州、モン州を始めとするミャンマー南東部において、日本のNGOと連携し、住居、学校、医療施設などのインフラ整備、農業技術指導、ソーラーパネルによる住居電化を含む復興開発支援を実施している。
(11)ラオス
ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接し、メコン連結性の鍵を握る内陸国である。2019年は内政面では、2016年の第10回人民革命党大会や第8期国民議会議員選挙を経て、人民革命党の一党支配体制の下、安定した政権運営が行われた。経済面では、最優先課題として財政安定化に取り組む一方、電力、鉱物資源に牽引される形で、経済成長率は前年度と同水準の約7%と、引き続き堅調な経済成長を維持している。日・ラオス間では2019年も要人往来が活発に行われ、5月にはトンルン首相及びサルムサイ外相がそろって訪日し首脳会談と外相会談が行われたほか、パンカム国家副主席が10月の即位礼正殿の儀参列と11月の大綬章等勲章親授式(旭日(きょくじつ)大綬章)への出席のため2度訪日した。また、日本からも6月に阿部外務副大臣が、10月に若宮外務副大臣がそれぞれラオスを訪問するなど、「戦略的パートナーシップ」の下、近年の緊密かつハイレベルな交流のモメンタムが維持されている。ラオス政府首脳から強い要望があった財政安定化支援については、専門家派遣や各種セミナーの実施など、官民が協力して重層的な協力が引き続き行われた。また、例年ラオス全土で発生する洪水などの自然災害に対しては、ラオス政府の要望を受け、日本政府は、防災・災害対策能力の向上に資する資機材などの供与に加え、国際機関を通じた復旧・復興支援を行った。6月には、メコン地域の連結性を強化する象徴的なプロジェクトである「国道9号線橋梁(きょうりょう)改修計画」が完了し、両国要人出席の下、引渡式が大々的に行われ、日本政府が「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて進める地域の連結性強化を印象付けた。このように、経済協力分野では、2019年も、2016年9月に両首脳から発表された「日ラオス開発協力共同計画」の着実な進展が見られた。文化交流では、2月にビエンチャンにおいて「ジャパン・フェスティバル」が、5月に東京において「ラオス・フェスティバル」がそれぞれ開催され、両国国民間の相互理解が深まった。
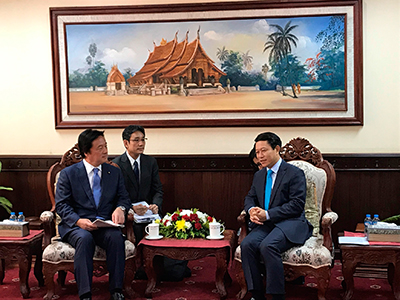
(10月5日、ラオス)
24 RCEP:Regional Comprehensive Economic Partnership
25 JENESYS:Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (21世紀東アジア青少年大交流計画)
