6 大洋州
(1)オーストラリア
ア 概要・総論
地域が様々な課題に直面する中、基本的価値と戦略的利益を共有する日本とオーストラリアが「特別な戦略的パートナーシップ」を確認してから10年が経過し、両国間の協力の重要性はこれまで以上に高まっている。インド太平洋地域における、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた両国の戦略的ビジョンは広い範囲で一致しており、首脳間や外相間の緊密な関係を基盤とし、国際社会の安定と繁栄に向けて、あらゆる分野での重層的な協力・連携を一層深化させている。さらに日豪は二国間だけでなく、日米豪、日米豪印といった多国間での連携も着実に強化してきている。
また、日豪両国は、発効後10年目を迎えた日豪経済連携協定(EPA)、2018年12月に発効した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を通じて相互補完的な経済関係を更に発展させており、日本にとってオーストラリアは第3の貿易パートナー、オーストラリアにとって日本は第2の貿易パートナーとなっている。
首脳間では、岸田総理大臣が9月にアルバニージー首相と首脳会談を実施し、安全保障分野を含む二国間協力や、地域・国際情勢について率直な意見交換を行い、両国の幅広い戦略認識の一致を改めて確認した。同時に、オーストラリアの核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)フレンズへの参加を歓迎した上で、「核兵器のない世界」の実現に向けて緊密に連携していくことを確認した。また、石破総理大臣就任直後の10月の首脳電話会談では、両国が、米国、韓国やインドなどの同志国との連携や日米豪印などの多国間連携を強化していくこと、また資源・エネルギー分野及び経済安全保障上の課題にも共に取り組むことで一致した。10月の首脳会談では、両首脳は、核・ミサイル問題及び拉致問題を含む北朝鮮への対応を始めとする東アジア情勢について意見交換を行い、こうした課題への対応における両国の協議と協力を更に強化していくことで一致した。
外相間では、上川外務大臣が、2月、ウォン外相と外相電話会談を実施し、両国が太平洋島嶼国との関係強化に向けて連携していくことで一致した。7月の外相会談では、上川外務大臣から、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて、両国の「特別な戦略的パートナーシップ」に基づく協力を一層強化していきたいと述べた。9月には、ワーキング・ディナーを実施し、グローバル・サウスとの連携強化を含む、地域・国際情勢について率直な意見交換を行った。また、岩屋外務大臣就任直後の10月の外相電話会談では、安全保障分野を始めとした幅広い分野で協力していくことで一致し、強固な日豪関係を下支えしている観光、ビジネス、留学を始めとした活発で重層的な両国間の人的交流を強化していくことで一致した。
日豪両国は、このような頻繁なハイレベルでの対話を通じて意思疎通を図り、以下に述べるような様々な分野において同志国連携の中核として貢献してきている。
イ 安全保障分野での協力
FOIPの実現に共に取り組むオーストラリアは、日本の安全保障に不可欠な存在であり、両国の安全保障協力は新たな次元に引き上げられている。2023年に発効した日豪部隊間協力円滑化協定の下、両国間の部隊間協力は強化されており、両国はインド太平洋地域の平和と安定に対する共同の関与を強めている。
9月には、第11回日豪外務・防衛閣僚協議(「2+2」)を実施し、2022年に発出した「安全保障協力に関する日豪共同宣言」(32)に沿って、日豪の戦略的協力・安全保障協力をたゆみなく深化させていくことで一致した。また、米国との協働を含め、共同で抑止力を強化し、相互運用性を高め、両国の安全保障政策をより緊密に連携させていくことで一致した。さらに、両国の安全保障協力は新たな分野にも広がっており、偽情報対策や、戦略的コミュニケーション分野での協力、日豪経済安全保障対話の活用を含めた経済安全保障分野における連携の強化についても一致した。10月の日豪首脳会談では、2022年の「安全保障協力に関する日豪共同宣言」で示された方向性の下、安全保障分野で日豪の相互運用性を向上させ、共同の抑止力を強化していくことを確認した。また、同会談では、サイバーや経済安全保障分野でも対話と協力を強化することで一致した。

ウ 経済関係
2018年12月に発効したCPTPPの交渉を日本とオーストラリアが主導したことに示されるように、両国は地域の自由貿易体制の推進や、法の支配に基づく自由で公正な経済秩序の構築について緊密に連携し、リーダーシップを発揮している。10月の日豪首脳会談では、CPTPPを含む経済分野での協力を一層強化していくことを確認した。
日本とオーストラリアの間では、日本が主に自動車などの工業品をオーストラリアに輸出し、また、オーストラリアが主に石炭や天然ガスなどのエネルギー資源や牛肉などの農産物を日本に輸出するという相互補完的な経済関係が、長年にわたり着実に発展してきている。特に近年では、水素関連の取組などの新しい協力も進んでいる。
7月の日豪外相会談では、上川外務大臣から、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想を通じて、経済成長、エネルギー安全保障に加えて、脱炭素化という共通課題への対応でも連携していきたいと述べた。
エ 文化・人的交流
オーストラリアには約41.5万人に上る日本語学習者(世界第4位)や100を超える姉妹州・都市提携があるなど、長年培われた親日的な土壌が存在する。青少年を含む人的交流事業であるJENESYS(対日理解促進交流プログラム)及び新コロンボ計画による日豪間の相互理解の促進、若手政治家交流など、両国関係の基盤強化のための各種取組が行われている。また、日豪ワーキングホリデー制度についても、引き続きその適切かつ着実な運用に取り組んでいる。
オ 国際社会における協力
両国は、国際社会の平和と安定に積極的に貢献するため、幅広い分野での協力を強化してきている。特に、海洋安全保障、北朝鮮の核・ミサイル開発といったインド太平洋地域が直面する諸課題に関する協力を深めてきている。オーストラリアは、日本周辺海域における警戒監視活動に駆逐艦「ホバート」を5月上旬から中旬に、駆逐艦「シドニー」を9月上旬から中旬にそれぞれ派遣し、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶との「瀬取り」(33)を含む違法な海上活動に対して、2018年以降11度目及び12度目の艦艇による警戒監視活動を行った。また、2月上旬から中旬の間及び11月上旬から中旬までの間、在日米軍嘉手納(かでな)飛行場を使用して、2018年以降13度目及び14度目となる航空機による警戒監視活動を行った。
(2)ニュージーランド
ア 概要・総論
日本とニュージーランドは、民主主義、市場経済などの基本的価値を共有し、長年良好な関係を維持している。近年、「戦略的協力パートナーシップ」の下、経済、安全保障・防衛協力、人物交流を含む二国間協力の強化に加え、地域や国際社会の課題についても協力関係を強化している。2023年に実施された議会総選挙の結果を受け、国民党(第1党)、ACT党及びNZファースト党の3党連立政権が成立した。
イ ハイレベル協議
地域情勢が複雑に推移する中、アジア太平洋地域に位置し、基本的価値を共有するニュージーランドと首相間や外相間で緊密な意見交換を行ってきている。6月、岸田総理大臣は、首相就任後初めて訪日したラクソン首相と首脳会談を実施し、インド太平洋地域の戦略環境が厳しさを増す中、FOIPの実現に向け、安全保障や経済を含む幅広い分野で、二国間の協力を一層強化することで一致した。両国間の安全保障・防衛協力については、情報共有の強化に寄与する日・ニュージーランド情報保護協定の交渉が実質合意に至ったことを歓迎した。また、北朝鮮や中国を含む東アジア情勢やロシア・ウクライナ情勢などの地域情勢について意見交換を行い、諸課題の解決に向けて連携していくことを確認した。さらに、太平洋島嶼国地域における両国の連携の重要性を確認し、太平洋島嶼国のニーズを踏まえた協力を進めていくことで一致した。7月には、日豪NZ韓(IP4)首脳会合を実施し、4か国の首脳は、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障はますます不可分となっているとの認識の下、インド太平洋地域の課題について欧州諸国とも引き続き意思疎通や協力を深めていくことを確認した。11月には、岩屋外務大臣がピーターズ副首相兼外相と短時間の懇談を行い、両国間の「戦略的協力パートナーシップ」を強化していくとともに、IP4やファイブアイズ諸国(34)との連携含め、多国間の協力を深めていくことで一致した。
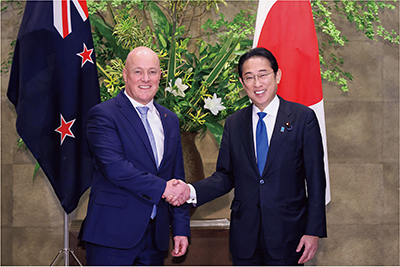
ウ 経済関係
両国は、相互補完的な経済関係を有しており、CPTPPやRCEP協定の着実な履行やWTO改革、インド太平洋経済枠組み(IPEF)など自由貿易体制の推進や法の支配に基づく自由で公正な経済秩序の構築について緊密に連携している。6月の日・ニュージーランド首脳会談では、CPTPPについて、戦略的な観点も踏まえて率直な議論を行い、同協定の発展に向けた取組の重要性について一致すると同時に、経済的威圧への対処や、サプライチェーン強靱化を含め経済安全保障分野において連携を強化していくことで一致した。
エ 文化・人的交流
日・ニュージーランド間の青少年などの人的交流は、人的交流事業であるJENESYSを通じ、2024年までの累計で1,100人以上が参加しており、外国青年招致事業「JETプログラム」については、2024年までに3,500人以上が参加(年平均換算で約100人)するなど活発な交流が続けられている。また、両国間には44の姉妹都市関係が構築されている。
オ 国際社会における協力
両国は、国連の場を含む国際場裡で国際社会の平和と安定のために緊密に協力している。例えば、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平洋経済協力(APEC)、太平洋・島サミット(PALM)などの地域協力枠組みにおける協力や、太平洋島嶼国地域における連携、IP4の枠組みにおける取組を強化するなど、地域の安定と発展のために積極的な役割を果たしている。ニュージーランドは、日本周辺海域における警戒監視活動に補給艦「アオテアロア」を8月中旬から9月中旬まで派遣し、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶との「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、初めてとなる艦艇による警戒監視活動を行った。また、4月中旬から5月中旬までの間、在日米軍嘉手納飛行場を使用して、2018年以降6度目となる航空機による警戒監視活動を行った。
(3)太平洋島嶼国(35)
ア 概要・総論
太平洋島嶼国は、美しく広大な海に囲まれ、海洋資源や自然に富んでいる。この地域は、それぞれの特色を持つ「ミクロネシア地域」、「ポリネシア地域」、「メラネシア地域」に分けられ、第二次世界大戦を経て1970年代以降に植民地・信託統治から独立した比較的若い国々から成り立っている。その一方、国土が小さな島々に散在している「隔絶性」、各国の人口が小さく規模の経済が働かない「狭小性」、主要な国際市場から遠く離れている「遠隔性」といった厳しい条件の下で、様々な脆弱性を抱える。中でも、気候変動は太平洋島嶼国の存在を脅かす「存続に関わる唯一最大の脅威」である。このような課題に直面する中で、太平洋島嶼国・地域の首脳が政治・経済・安全保障など、幅広い分野において地域の協力を推進するための対話の場として、1971年以降、太平洋諸島フォーラム(PIF:1999年に南太平洋フォーラムから改称)が発展してきた。
太平洋島嶼国は、日本と太平洋によって結ばれ、歴史的なつながりも深く、国際場裡での協力や水産資源・天然資源の供給においても重要なパートナーである。また、太平洋の中心に位置することからFOIPの要としてもその重要性が高まっている。日本は、二国間での協力に加え、PIFとの協力も進めている。PIFは、2022年の総会において、2050年の太平洋島嶼国地域における政治・経済などのあるべき姿と戦略的方策をまとめた「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」(「2050年戦略」)を発表した。日本はこの戦略に対する強い支持を一貫して表明してきている。
太平洋島嶼国地域の地政学的重要性が増す中、2022年に設立された「ブルーパシフィックにおけるパートナー」(PBP)の枠組みなど、域内・域外の関係国による協力強化が進展している。2023年5月の日米豪印首脳会合では、「海底ケーブルの連結性と強靱性のためのパートナーシップ」が発表された。2024年4月の日米首脳会談では、ツバル及びミクロネシア連邦に対する海底ケーブルシステムへの協力が発表された。
イ 太平洋・島サミット(PALM)
二国間協力に加え、日本の対太平洋島嶼国外交における主要な取組の一つは、太平洋・島サミット(PALM)である。1997年以降、3年に1度開催し、太平洋島嶼国との関係強化に取り組んできた。2024年は、7月に東京において、第10回太平洋・島サミット(PALM10)を開催し、太平洋島嶼国・地域との協力強化を確認した(4ページ 巻頭特集参照)。
PALM10に先立ち、2月には、PALM第5回中間閣僚会合をスバ(フィジー)において開催し、上川外務大臣が共同議長を務めた。同会合は太平洋島嶼国で開催された初めてのPALM中間閣僚会合となった。同会合では、2021年に行われたPALM9のフォローアップを行い、PIF加盟国・地域から、PALM9の全ての協力分野において日本がコミットメントを着実に実施し、協力を推進してきたことへの高い評価と日本政府・国民への謝意の表明があり、議長総括が採択された。また、上川外務大臣は、この機会に各国の参加者と会談を行い、二国間関係の強化にも努めた。

7月に東京で開催したPALM10では、岸田総理大臣がクック諸島のブラウン首相と共同議長を務め、「2050年戦略」への強い支持を表明し、地域・国際情勢について議論を行った。また、これまでに培われた「キズナ」を一層深め、日本と太平洋島嶼国・地域が共通の課題に取り組みながら、未来に向けて「共に歩む」関係を確認した。議論の成果としては、「PALM10首脳宣言」及び「PALM10共同行動計画」を採択し、日本は「太平洋気候強靱化イニシアティブ」を発表した。ALPS処理水の海洋放出に関し、岸田総理大臣から、IAEAと緊密に連携しつつ、継続的な情報共有を積み重ね、安心感を高めていくと説明し、太平洋島嶼国・地域から歓迎の意が示された。加えて、岸田総理大臣は、太平洋島嶼国・地域の首脳などとの間で17回の首脳会談などを行った。
ウ 国別の動き
(ア)キリバス
8月、大統領選挙・総選挙が行われ、10月25日、マーマウ大統領の再選が決定し、11月1日に大統領就任式が行われた。
(イ)クック諸島
2023年11月から2024年8月までPIFの議長国を務めた。日本は、2023年広島G7サミット・アウトリーチ会合に招待するなど、クック諸島との関係強化に努めた。7月のPALM10においては、ブラウン首相が共同議長を務めたほか、日・クック諸島首脳会談を行い、岸田総理大臣から、これまでの成果を積み上げながら、インフラ強靭化や気候変動への適応などクック諸島の重要課題に沿って、協力していく考えを表明した。
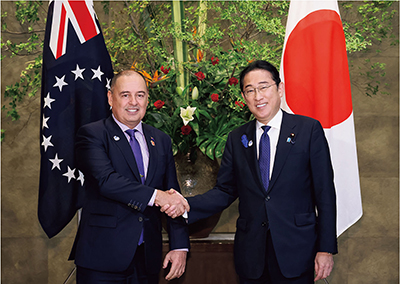
(ウ)サモア
2月、上川外務大臣は日本の外務大臣として初めてサモアを訪問し、トゥイマレアリイファノ国家元首やフィアメ首相などとの表敬・会談を行った。7月のPALM10においては、日・サモア首脳会談が行われ、太平洋気候変動センターへの協力を始めとする気候変動・防災分野での協力について議論した。
(エ)ソロモン諸島
4月、任期満了に伴う総選挙が行われ、ソガバレ首相に代わってマネレ首相が就任した。6月、石原宏高内閣総理大臣補佐官が総理特使としてソロモン諸島を訪問し、マネレ首相などとの会談を行った。7月のPALM10においては、日・ソロモン首脳会談が行われ、岸田総理大臣からソロモン諸島との信頼関係に基づいて協力していくと述べた。
(オ)ツバル
4月、高村正大外務大臣政務官が総理特使としてツバルを訪問し、テオ首相などとの表敬・会談を行った。7月のPALM10においては、日・ツバル首脳会談が行われ、岸田総理大臣は、ツバルが自ら気候変動の危機を訴え、国際社会を動かしてきたことに敬意を表明した。12月、同志国である日米豪などのドナーによる支援案件であるツバルの初の海底ケーブルの陸揚げ記念式典が開催された。
(カ)トンガ
2月、トゥポウトア・ウルカララ皇太子殿下が第2回日・太平洋島嶼国国防大臣会合出席のために訪日し、柘植芳文外務副大臣が懇談した。また5月、柘植外務副大臣は総理特使としてトンガを訪問し、同皇太子殿下への御接見を行った。7月のPALM10においては、日・トンガ首脳会談が行われ、岸田総理大臣からは、2022年のトンガ火山噴火からの復興や防衛協力の進展を歓迎した。8月、トンガはPIF議長国として首都ヌクアロファでPIF総会を開催し、域外パートナーである日本からは高村外務大臣政務官が総理特使として出席し、PALM10の成果に触れつつ、引き続き太平洋島嶼国のニーズに耳を傾けていくと述べた。
(キ)ナウル
5月、石原内閣総理大臣補佐官が総理特使としてナウルを訪問し、アデアン大統領などとの表敬・会談を行った。7月のPALM10においては、日・ナウル首脳会談が行われ、岸田総理大臣から、警備艇の供与を伝達し、これを通じて同国の違法漁業取締能力向上に協力すると述べた。
(ク)ニウエ
10月、ニウエは、憲法制定・自治権獲得50周年を迎えた。7月のPALM10においては、日・ニウエ首脳会談が行われ、岸田総理大臣から多くの課題に対応するニウエを力強く支えていきたいと述べた。また、同月にはニウエ初の名誉領事館が東京に開設された。
(ケ)バヌアツ
6月、松山政司参議院議員が総理特使としてバヌアツを訪問し、サルワイ首相などとの表敬・会談を行った。7月のPALM10においては、日・バヌアツ首脳会談が行われ、岸田総理大臣は、バヌアツの持続可能な水産業振興に貢献し、バヌアツの優先課題に共に取り組んでいきたいと述べた。
(コ)パプアニューギニア
4月から5月にかけて、エンガ州において地滑り被害が発生し、岸田総理大臣や上川外務大臣からお見舞いを述べるとともに、日本は、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて緊急援助物資を供与し、国連児童基金及び国際移住機関を通じた緊急無償資金協力の実施を決定した。5月、石原内閣総理大臣補佐官がパプアニューギニアを訪問し、マラペ首相などとの表敬・会談を行った。7月のPALM10においては、日・パプアニューギニア首脳会談が行われ、2025年の外交関係樹立50周年に向けて両国関係を強化していきたいと述べた。
(サ)パラオ
2024年は、日・パラオ外交関係樹立30周年を迎え、様々な交流を通じて両国関係の緊密化が図られた。2024年、ウィップス大統領は7月のPALM10出席のほか、6月にも訪日し、9月の国連総会の機会と合わせて計3回、ウィップス大統領の任期第1期目の4年間では計5回にわたり、岸田総理大臣との間での首脳会談が行われた。1月、上川外務大臣は、訪日したアイタロー外相と初めて会談を行い、日・パラオ外交関係樹立30周年(79ページ コラム参照)に当たり地域の平和と安定のために協力していくことを確認したほか、2月にもフィジーで会談した。5月、高村外務大臣政務官が総理特使としてパラオを訪問し、ウィップス大統領などとの表敬・会談を行った。10月、髙田稔(とし)久総理特使(前太平洋・島サミット担当大使)が日本政府を代表してパラオ独立30周年式典に出席した。11月、大統領選挙が行われ、ウィップス大統領の第2期目の再選が決定した。
2024年は、日・パラオ外交関係樹立30周年の年です。1994年10月にパラオが米国から独立し、同年11月に日本とパラオが外交関係を樹立して以来、両国の「キズナ」と「トクベツ」な関係は強固なものへと発展しています。

両国の歴史的な関係は外交関係樹立より前に遡ります。第1次世界大戦後、日本は約30年間にわたりパラオを含むミクロネシア(南洋群島)を委任統治していました。1922年にはコロールに南洋庁が置かれ、本格的な統治が開始され、最盛期には2.5万人を超える日本人がパラオに居住していたといわれています。その歴史的関係から、パラオの人口は約25%が日系人で構成され、パラオの初代大統領であったナカムラ大統領もその一人です。こうしたパラオにおける日系人の活躍から、パラオの人々は非常に親日的であり、言語においても、「トクベツ」、「ダイジョウブ」を始めとした多数の日本語が現地語化されるなど、両国間の歴史的・文化的な深いつながりが現在の良好な関係を支えています。
また、日本はパラオにとって不可欠な援助国であり、長年にわたり、環境や気候変動の分野を中心に、パラオの経済発展のための協力を行ってきました。2002年に開通したコロール島とバベルダオブ島を結ぶ「日本・パラオ友好の橋」は両国の友好的な関係の象徴となっています。
日・パラオ外交関係樹立30周年を迎えた2024年は、両国間の要人往来の機会が多く設けられました。岸田総理大臣とウィップス大統領は、6月のウィップス大統領訪日時、7月の第10回太平洋・島サミット(PALM10)開催時、9月の第79回国連総会出席時の計3回の首脳会談を実施し、個人的な信頼関係に基づき率直な意見交換を行いました。10月1日のパラオ独立30周年記念式典には、髙田稔久氏(前外務省参与、前太平洋・島サミット(PALM)担当大使)が総理特使として出席し、ウィップス大統領を表敬したほか、日・パラオ外交関係樹立30周年への祝辞も述べました。

両国間の人的交流は、草の根レベルでも行われており、地方自治体の訪問や学生の交流なども活発に行われています。7月の日・パラオ首脳会談で発表された2025年3月のチャーター便運航計画などにより、両国間の人的交流の更なる拡大が期待されています。
日本とパラオの関係は、このような歴史的・文化的関係、様々なレベルでの人的交流により、強化されています。2024年は、両国の今後の更なる関係の発展に向けて、両国の「キズナ」と「トクベツ」な関係を再確認する1年となりました。
(シ)フィジー
2月、PALM第5回中間閣僚会合がフィジーで開催され、上川外務大臣がフィジーを訪問し共同議長を務めた。4月には、高村外務大臣政務官が総理特使としてフィジーを訪問した。7月のPALM10においては、日・フィジー首脳会談が行われ、岸田総理大臣から、地域の中核であるフィジーとの協力関係を重視することを述べ、防災体制の構築支援やラグビーなどのスポーツ交流、ALPS処理水の海洋放出に対する信頼への謝意など、議論を深めた。
(ス)マーシャル諸島
1月、前年末の総選挙の結果を受け、ハイネ大統領が議会で選出され、大統領に就任し、田中和德(かずのり)衆議院議員が総理特使としてマーシャル諸島を訪問し、大統領就任式に出席した。2月、上川外務大臣はフィジーでカネコ外相との会談を行ったほか、3月に訪日したハイネ大統領と岸田総理大臣との間で首脳会談が行われた。7月のPALM10においては、日・マーシャル首脳会談が行われ、岸田総理大臣から、アマタ・カブア国際空港の旅客ターミナル建設に係る詳細設計などの協力決定に触れつつ、これらがマーシャル諸島の持続可能な発展に寄与することを期待すると述べた。
(セ)ミクロネシア連邦
2月、上川外務大臣はフィジーでロバート外務大臣との会談を行った。5月、高村外務大臣政務官が総理特使としてミクロネシア連邦を訪問し、シミナ大統領などとの表敬・会談を実施した。7月のPALM10においては、日・ミクロネシア首脳会談が行われ、岸田総理大臣から、ミクロネシア連邦国内の連結性強化のため、ポンペイ港の岸壁新設への協力を決定したと述べた。
(32) 2022年10月の日豪首脳会談で署名された日豪安全保障・防衛協力の今後10年の方向性を示す文書
(33) ここでの「瀬取り」は、2017年9月に採択された国連安保理決議第2375号が国連加盟国に関与などを禁止している、北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積替えのこと
(34) 米国・英国・オーストラリア・カナダ・ニュージーランドを指す
(35) 太平洋島嶼国:パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、ナウル、キリバス、ツバル、サモア、クック諸島、ニウエ、トンガ、フィジー、バヌアツ、ソロモン諸島、パプアニューギニア
