2 地球規模課題への取組
(1)持続可能な開発のための2030アジェンダ
「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)5の後継として2015年9月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた2030年までの国際開発目標である。
2030アジェンダは、先進国を含む国際社会全体の開発目標として相互に密接に関連した17の目標と169のターゲットから成る「持続可能な開発目標(SDGs)」6を掲げている。
日本は、2030アジェンダ採択後、まず、SDGs実施に向けた基盤整備として、総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部を設置し、SDGs達成に向けた中長期的戦略を定めたSDGs実施指針を策定し、日本が特に注力する八つの優先課題を掲げた。また、SDGs実施に向けた官民パートナーシップを重視するため、民間セクター、市民社会、有識者、国際機関などの広範な関係者が集まるSDGs推進円卓会議を開催し、SDGs推進に向けた地方やビジネス界の取組、次世代・女性のエンパワーメントの方策、国際社会との連携強化などについて意見交換を行っている。
2020年12月に行われた第9回SDGs推進本部会合では、関係府省庁のSDGs達成に向けた主要な取組を「SDGsアクションプラン2021」として決定した。同アクションプランでは、SDGsが達成された、しなやかで強靱な、経済と環境の好循環のあるウィズ・コロナ、ポスト・コロナの時代を実現するために、社会全体の行動変容をもたらすべく、①感染症対策と次なる危機への備え、②よりよい復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略、③SDGsを原動力とした地方創生、経済と環境の好循環の創出、④一人ひとりの可能性の発揮と絆(きずな)の強化を通じた行動の加速の四つの柱に沿って、国内実施・国際協力の両面においてSDGs達成に向けた取組を更に推進していくことを定めた。
同会合の機会には、SDGsに向けて優れた取組を行っている企業・団体を表彰する第4回「ジャパンSDGsアワード」表彰式も開催され、「顔の見える電力TM」をコンセプトに再生可能エネルギーを通じた地域間連携を推進する取組が評価された「みんな電力株式会社(東京都世田谷区)」が、SDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)を受賞した。
国際的な取組として、7月の国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)では、茂木外務大臣が、新型コロナの世界的拡大への対処における国際連携の重要性を強調した上で、日本として、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念、そして、脆弱な立場にある一人ひとりに焦点を当てる人間の安全保障の考えを踏まえつつ、二国間や国際機関を通じて数多くの開発途上国に対する新型コロナ対策支援を行ってきたことについて発言した。また、保健システムの強化を通じたユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向け、積極的に取り組んでいることを紹介しつつ、2020年はSDGs達成に向けた「行動の10年」のスタートであり、日本はSDGsの理念を踏まえ、国際社会と手を携えながら、今後ともSDGs達成に向けた取組を加速化していくと述べた。引き続き、様々な機会を活用し、SDGsを力強く推進する日本の姿を世界に発信していく。
一方、2030年までにSDGsを達成するためには、毎年約2兆5,000億米ドル(約280兆円)もの資金が不足しているとの推計7があり、資金ギャップの課題について議論するために設置された「SDGsの達成のための新たな資金を考える有識者懇談会」が7月に最終論点整理を茂木外務大臣に提出した。同最終論点整理を参考としつつ、今後も資金調達に関する課題について対応策を検討していく。
ア 人間の安全保障
人間の安全保障とは、個人の保護と能力強化により、恐怖と欠乏からの自由、そして、一人ひとりが幸福と尊厳を持って生存する権利を追求する考え方である。日本は、2015年に決定した開発協力大綱でも日本の開発協力の根本にある指導理念としてこれを位置付けている。国連においても関連する議論を主導し、日本のイニシアティブにより1999年に国連に設置された人間の安全保障基金に2019年末までに累計約478億円を拠出し、国連機関による人間の安全保障の普及と実践を支援してきた。また、二国間協力においても草の根・人間の安全保障無償資金協力などの支援を通じ、この概念の普及と実践に努めてきた。「人間中心」や「誰一人取り残さない」といった理念を掲げるSDGsも、人間の安全保障の考え方を中核に据えている。
新型コロナの感染拡大は、世界の人々の命・生活・尊厳を脅かしており、まさに人間の安全保障に対する危機を引き起こしている。これを乗り越えていくためには、人間の安全保障の考え方に基づいた取組が重要であり、9月の第75回国連総会一般討論演説において、菅総理大臣から、新たな時代の人間の安全保障の考え方に立って、様々な危機を乗り越え、SDGs達成を始めとした地球規模の課題への取組を加速することを表明し、そのために、世界の英知を集め、議論を深めていくことを提案した。
イ 防災分野の取組
毎年世界で2億人が被災し(犠牲者の9割が開発途上国の市民)、自然災害による経済的損失は、国連防災機関(UNDRR)の試算によれば、年平均約1,400億米ドルに及ぶ。防災の取組は、貧困撲滅と持続可能な開発の実現にとって不可欠である。
日本は、幾多の災害の経験により蓄積された防災・減災に関する知見をいかし、防災の様々な分野で国際協力を積極的に推進している。2015年3月に第3回国連防災世界会議を仙台で開催し、同年から15年間の国際社会の防災分野の取組を規定する「仙台防災枠組」の採択を主導した。また、日本独自の貢献として「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、2015年から2018年までの4年間で計40億米ドルの協力の実施や計4万人の人材育成を行うという目標を発表した。これが達成されたことを踏まえ、2019年6月に「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ2」を発表し、2019年から2022年の間に洪水対策などを通じ少なくとも500万人に対する支援を実施する予定である。
さらに、日本が提案して2015年12月に第70回国連総会で全会一致で制定された「世界津波の日(11月5日)」に合わせ、日本では2016年以降、世界各国の高校生を招へいし、日本の津波の歴史や、震災復興、南海トラフ地震への備えなどの実習を通じ、今後の課題や自国での展開等などの提案を行う「世界津波の日 高校生サミット」をこれまで4回実施している。2020年は、新型コロナの感染拡大をめぐる状況を踏まえて、UNDRRなどを通じて、「第3回世界津波博物館会議」のオンラインでの開催やアジア・大洋州の女性行政官などを対象とした津波に関する研修の実施、学校を対象とした津波避難計画の策定などを支援した。今後も災害で得た経験と教訓を世界と共有し、各国の政策に防災の観点を導入する「防災の主流化」を引き続き推進する考えである。
ウ 教育分野の取組
教育分野では、2030アジェンダ採択に合わせて日本が発表した「平和と成長のための学びの戦略」の下、世界各地で様々な教育支援を行っている。2019年3月の「国際女性会議WAW!」の際には、2020年までに少なくとも400万人の開発途上国の女子に対して質の高い教育・訓練の機会を提供すべく引き続き取り組んでいくことを発表した。また、同年6月のSDGs推進本部会合では、少なくとも約900万人の子供・若者にイノベーションのための教育とイノベーションによる教育を提供する「教育×イノベーション」イニシアティブを発表した。日本議長下のG20大阪サミットでは、教育に焦点を当てた「G20持続可能な開発のための人的資本投資イニシアティブ」に合意し、「人的資本に投資し、全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を推進する」とのコミットメントが盛り込まれた。
2020年の年初以降、新型コロナの感染拡大下での休校措置などにより、教育を受ける機会が奪われる子供たちが世界各地で急増したことも踏まえ、日本としては、遠隔教育や学校再開に向けた支援といった子供たちの学びの継続のための支援について、国際機関などと連携しながら実施してきている。
エ 農業分野の取組
日本はこれまでG7やG20などの関係各国や国際機関とも連携しながら、開発途上国などの農業・農村開発を支援している。2019年5月にはG20新潟農業大臣会合を開催し、人造り・新技術、フードバリューチェーン、SDGsなどに関する農業・食料の諸課題について、各国間で知見を共有することの重要性を確認し、「2019年G20新潟農業大臣宣言」を採択した。
2020年以降、新型コロナの感染拡大に伴う移動制限などを受けて、国際機関などを経由した支援を通じて、農産品などの流通の停滞による食料システムの機能低下などに対処している。
オ 水・衛生分野の取組
日本は、1990年代から継続して水・衛生分野での最大の支援国であり、日本の経験・知見・技術をいかした質の高い支援を実施している。国際社会での議論にも積極的に参加しており、日本のこれまでの貢献を基に、同分野のグローバルな課題に取り組んでいるほか、特に2020年の年初以降の新型コロナの感染拡大を受け、感染拡大を抑制する観点から、手洗いの励行といった取組について、国際機関などを活用しながら支援を行ってきている。2020年10月に、熊本において開催予定であった「第4回アジア・太平洋水サミット」は、新型コロナをめぐる状況を踏まえて延期され、2022年4月に、「持続可能な発展のための水~実践と継承~」(Water for Sustainable Development -Best Practices and the Next Generation-)をテーマに開催されることとなった。
(2)国際保健
人々の生命を脅かし、社会・文化・経済的活動を阻害する保健課題の克服は、人間の安全保障に直結する国際社会の共通の課題である。日本は人間の安全保障を提唱し、それを「開発協力大綱」の基礎とするとともに各種の取組を推進し、保健分野に係る協力を重点課題の中に位置付けている。日本は、2021年には国民皆保険制度創設60周年を迎え、世界で最も優れた健康長寿社会を達成しており、保健分野における日本の積極的な貢献に一層期待が高まっている。保健分野への投資は人々の活力を高め、国の経済発展に寄与し、社会の安定化につながるとの観点から、2015年に策定された開発協力大綱の課題別政策である「平和と健康のための基本方針」に基づき、日本は国際社会全体におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)8の達成に向けた取組を主導している。
日本はこれまで、G7やG20サミット、アフリカ開発会議(TICAD)などの国際会議の場で、UHCの達成や持続可能な保健財政の重要性などを積極的に提起してきた。2019年には、日本が国連総会UHCハイレベル会合の開催及び政治宣言の合意を主導するなど、国際保健に関する議論をリードしてきた。また、各国政府や、世界保健機関(WHO)、世界銀行、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)、Gaviワクチンアライアンス(Gavi)、国連人口基金(UNFPA)、国連児童基金(UNICEF)、グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)といった様々な国際機関と協力しながら、感染症や母子保健、栄養改善などの保健課題の克服に大きな成果を上げてきた。
2020年9月、菅総理大臣は就任後初めてとなる国連総会一般討論演説を行い、冒頭で新型コロナ対策を含む日本の国際保健政策について述べた。その中で、新型コロナの拡大は、人間の安全保障に対する危機を惹起(じゃっき)し、その対策を進めるに当たっては、「誰の健康も取り残さない」ことを目指し、UHCを達成することが重要であると指摘した。その上で、①治療薬・ワクチン・診断の開発及び開発途上国を含めた公平なアクセス確保への全面的な支援、②病院建設、機材整備、人材育成などを通じた各国の保健医療システムの強化支援、③水・衛生や栄養などの環境整備を含めた健康安全保障のための施策の実施といった分野を中心に、国際的な取組を積極的に主導することを表明した。また、国際社会におけるUHCの啓発を一層促進する観点から、10月に、茂木外務大臣はUHCフレンズ閣僚級会合を主催したほか、12月には、菅総理大臣が国連新型コロナ特別総会に出席し、UHCの達成の重要性などについて述べた。
さらに、日本は、分野横断的取組として「栄養」をSDGs達成に必要不可欠かつ人間の安全保障に関わる課題の一つと捉え、新型コロナの感染拡大によって2021年に延期となった「東京栄養サミット2021」の開催に向け、世界的な栄養改善に向けた取組強化に尽力してきている。
(3)労働・雇用
雇用を通じた所得の向上は、貧困層の人々の生活水準を高めるために重要である。また、世界的にサプライチェーンが拡大する中で、労働環境の整備などを図り、国際的に「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現に取り組んでいく必要がある。このディーセント・ワークの実現は、2019年に創設100周年を迎えた国際労働機関(ILO)でも、その活動の主目標に位置付けられている。
こうした中で、日本も労働分野での持続可能な開発に向けた協力に取り組んでいる。2020年には、ILOへの任意拠出金や国際的な労使団体のネットワークへの支援を通じ、東南アジア、南アジアなどのアジア太平洋地域及びアフリカ地域(モザンビーク)の開発途上国に対し、新型コロナ及び自然災害発生に伴う緊急雇用創出の支援や、労働法令の整備、労働安全衛生の実施体制の改善のための技術協力などを行った。
また、12月には、第3回日・ILO年次戦略協議(オンライン形式)を開催し、新型コロナに関する今日的課題への対応を含め、誰一人取り残さないためのより良い仕事の未来に向けた一層の連携強化について確認するとともに、労働分野での持続可能な開発に向けた協力支援における日本のこれまでの財政的・人的貢献及び一層のパートナーシップ強化、ILOにおける日本人職員の一層の増強などについてILOとの間で確認した。
(4)環境・気候変動
ア 地球環境問題
2030アジェンダにおいて環境分野の目標が記載されるなど、地球環境問題への取組の重要性が国際的により一層認識されている。日本は、多数国間環境条約や環境問題に関する国際機関などにおける交渉及び働きかけを通じ、自然環境の保全及び持続可能な開発の実現に向けて積極的に取り組んでいる。また、生物多様性・化学物質汚染などに関わる環境条約の資金メカニズムとして世界銀行に設置されている地球環境ファシリティ(Global Environment Facility)への最大のドナーとして地球規模の環境問題に対応するプロジェクトに貢献している。
(ア)海洋環境の保全
海洋プラスチックごみ問題は、不法投棄や不完全な廃棄物処理などにより生じ、海洋の生態系、観光、漁業及び人の健康に悪影響を及ぼしかねない喫緊の課題として、近年その対応の重要性が高まっている。2019年のG20大阪サミットにおいて打ち出した、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、日本は、国連環境計画(UNEP)などの国際機関とも協力し、海洋プラスチックごみの流出防止策に必要な科学的知見の蓄積支援及びモデル構築支援など、アジア地域における環境上適正なプラスチック廃棄物管理・処理支援などを行っている。
また、海洋環境の保全、漁業、海洋資源の利用などについて議論を行う「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル」(海洋国家の首脳で構成)は、12月2日、菅総理大臣を含む14か国の首脳の連名で「持続可能な海洋経済のための変革」と題する首脳文書を公表した。この中で、例えば、ハイレベル・パネル・メンバー国は、「2025年までに持続可能な海洋計画に沿って、国家管轄権内の海洋区域の100%を持続可能な形で管理することにコミット」し、また、「2030年までに国家管轄権内にある全ての海洋区域が持続可能な形で管理されるよう、全ての沿岸及び海洋国家に対してこのコミットメントに参加することを呼びかけ」ている。首脳文書を広報する目的で12月3日に外務省と海洋政策研究所は共催でウェビナー(オンライン形式のセミナー)を実施し、菅総理大臣は同ウェビナーに寄せたメッセージの中で、洋上風力発電などの海洋の力を活用することによる気候変動対策の重要性を強調し、海洋プラスチックごみ問題における日本の取組を紹介した。
(イ)生物多様性の保全
2月には、生物多様性条約の愛知目標に続くポスト2020生物多様性枠組に関する公開作業部会2回目(OEWG2)がローマ(イタリア)で開催され、同枠組みの要素などについて議論が行われた。また、生物多様性に係る行動を進める緊急性を最高レベルで強調し、当該枠組みの決定及び実施を後押しする目的で、9月に、国連生物多様性サミットがニューヨーク(米国)での会議にオンラインでの参加を組み合わせたハイブリッド形式で開催された。
近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つとなっているとして、国際社会で注目されている。日本は、2019年ウガンダ及びモザンビークにゾウ密猟対策のための監視施設を供与したのに引き続き、2020年にはザンビアにも供与を決定するなど、この問題に真摯に取り組んでいる。
日本は、持続可能な農業及び食料安全保障のための、食料・農業植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用の促進に係る世界的な議論にも貢献した。7月及び11月に開催された、食料・農業植物遺伝資源条約の第1回及び第2回資金戦略常設委員会において、日本は、遺伝資源へのアクセスと金銭的・非金銭的利益配分の支援やモニタリングなどを始めとする資金戦略全般を扱う資金戦略・資源動員に関し、地域を代表して助言した。
11月には、国際熱帯木材機関(ITTO)第56回理事会がオンラインで開催され、持続可能な森林経営や合法的に伐採された木材の貿易促進に資するプロジェクトを効率的に実行するための新しい枠組みなどについて、議論が行われた。
(ウ)化学物質・有害廃棄物の国際管理
11月、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」第12回締約国会議及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」第32回締約国会合がオンライン形式で開催された。同会合では、規制対象物質にハイドロフルオロカーボン(HFC)を追加した改正議定書の運用などに関する議論が行われた。
有害廃棄物の国境を越える移動などを規制するバーゼル条約において、日本は水銀廃棄物、有害な廃棄物などの陸上焼却・エネルギー回収及び廃プラスチックに関して、締約国が参考とするガイドラインの作成を主導している。
2017年に発効した「水銀に関する水俣条約」では、2021年第4回締約国会議に向け、附属書Aに掲げられた水銀添加物製品及び附属書Bに掲げられた水銀または水銀化合物を使用する製造工程の見直しに関する専門家会合、水銀の放出及び水銀廃棄物の閾値(いきち)に関する専門家会合において、日本は専門家として議論に積極的に参加している。
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、条約の義務を履行するために締約国が国内実施計画を策定し更新することとなっている。12月、第8回及び第9回締約国会議において新たに規制対象となった化学物質に関する日本の措置を国内実施計画に反映し、条約事務局に提出した。
イ 気候変動
(ア)2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目指した取組
10月、菅総理大臣は、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする、カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。また、世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環を作り出していくことを表明した。この日本の宣言に対しては、グテーレス国連事務総長を始め、国際社会から多くの歓迎の意が表明されている。(252ページ 特集参照)
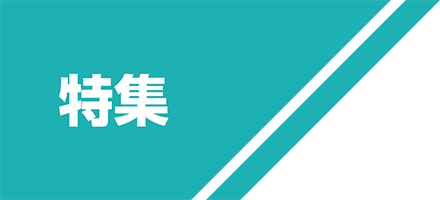
2020年は、日本の気候変動対策が大きな一歩を踏み出した、重要な1年となりました。
気候変動対策のための新たな国際的枠組みであるパリ協定は、2020年についに本格運用を開始しました。11月に予定されていた国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が1年延期されるなど、気候変動の国際的議論も新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、ポスト・コロナの復興をいかに持続可能なものとするかという観点から、気候変動対策に対する国際的な機運は、より一層の高まりを見せています。
そのような中、10月26日、菅総理大臣は所信表明演説で、グリーン社会の実現に最大限注力し、日本は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。また、長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換することも表明しました。これらの宣言は、一刻の猶予も許されない気候変動に対して積極的に対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換を促し、経済と環境の好循環を作り出すことで、世界のグリーン産業をけん引していくという強い決意を示すものでした。
この目標を実現する上で鍵となるのは、水素、次世代型蓄電技術、カーボンリサイクルを始めとした革新的なイノベーションです。このため、12月には、産業政策の観点から、2050年のカーボンニュートラルの実現に伴い、成長が期待される産業14分野ごとに、高い目標を掲げた上で、現状の課題と今後の取組を明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連携など、あらゆる政策を盛り込んだ実行計画である「グリーン成長戦略」を取りまとめました。
日本は、3月にパリ協定に基づいて日本のNDC※1(国が決定する貢献)を国連に提出し、2030年度削減目標の検討は、エネルギーミックスの改定※2と整合的に、更なる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指すことを表明しました。また、9月に地球温暖化対策計画の見直しに着手し、COP26開催前の追加情報の提出に向けて検討を進めています。10月にはエネルギーミックスの扱いを含むエネルギー基本計画の見直しに向けた議論も開始されました。
10月の菅総理大臣による所信表明演説での宣言に際しては、各国首脳や閣僚などから、歓迎の声が相次ぎました。また、菅総理大臣は、12月12日にパリ協定採択5周年を記念して開催された「気候野心サミット2020」において日本の取組について発信したほか、ASEANやG20、APECなど各種国際会議の機会にも説明を行っています。日本は、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現に向け、日本の取組を世界に発信するとともに、諸外国と連携・協力を深め、引き続き国際社会の取組をけん引していきます。
※1 Nationally Determined Contribution
※2 エネルギー政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すもの
(イ)国連気候変動枠組条約とパリ協定
気候変動の原因である温室効果ガスの排出削減には、世界全体での取組が不可欠であるが、1997年の同条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、先進国にのみ削減義務を課す枠組みであった。2015年12月、パリで開催されたCOP21で、先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みであるパリ協定が採択された。同協定は2016年11月に発効し、日本を含む180か国以上の国が締結している(2020年12月時点)。なお、2020年11月、米国はパリ協定から正式に脱退したが、2021年1月、パリ協定への復帰を表明し、2月に正式にパリ協定に復帰した。
パリ協定の採択後は、2020年以降のパリ協定の本格運用に向け、パリ協定の実施指針に関する交渉が開始され、2018年12月にカトヴィツェ(ポーランド)で開催されたCOP24において採択された。2020年11月に開催予定であったCOP26では、COP24及びCOP25で合意に至らなかった市場メカニズムの実施指針の採択が期待されていたが、新型コロナの感染拡大を受け、2021年11月に開催が延期となった。
こうした中、国際的には新型コロナ流行下でも気候変動への取組は重要であるとの気運が高まり、ジューン・モメンタム(6月)や気候対話(11月)など、各種国連会合がオンライン形式で実施された。また、12月12日には、パリ協定採択5周年を記念して、気候変動の更なる取組を国際社会に呼びかけることを目的として、英国・フランス・国連の共催により「気候野心サミット2020」がオンライン形式で開催された。日本からは菅総理大臣が出席し、日本の取組や国際貢献を発信した。
日本も、9月に新型コロナからの復興と気候変動・環境対策に関する「オンライン・プラットフォーム」閣僚級会合を国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局と共催するなど、気候変動に関する国際的機運の維持に貢献した。
(ウ)開発途上国支援に関する取組
開発途上国が十分な気候変動対策を実施できるよう、日本を含む先進国は開発途上国に対して、資金支援、能力構築(キャパシティ・ビルディング)、技術移転といった様々な支援を実施している。こうした観点から、開発途上国による気候変動対策を支援する多国間基金である「緑の気候基金(GCF)9」も重要な役割を果たしている。日本は、初期拠出(2015年から2018年)の15億米ドルに加え、2019年10月の第1次増資ハイレベル・プレッジング会合にて行った最大15億米ドルの拠出表明に基づき、2020年には第1回目の拠出を行った。また、GCFに理事を派遣し、基金の運営や政策作りに積極的に参画している。2020年12月までに159件の支援案件が承認されており、これにより12億トンのCO2排出削減と約4.1億人の裨益(ひえき)が見込まれている。
(エ)二国間クレジット制度(JCM)10
JCMは、開発途上国への優れた低炭素技術などの普及や対策の実施を通じ、地球規模での温暖化対策に貢献するとともに、温室効果ガス排出削減・吸収に対する日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する仕組みである。日本は、2020年11月時点で17か国とJCMを構築しており、180件以上の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを実施している。2020年も、インドネシア、カンボジア、サウジアラビア、タイのJCMプロジェクトからクレジット(排出枠)が発行されるなど、成果を着実に上げている。
(オ)日本による気候変動と脆弱性リスクに関する取組
2017年1月に外務省が開催した「気候変動と脆弱性の国際安全保障への影響」に関する円卓セミナーなどにおいて、「日本はアジア・大洋州に焦点を絞って気候変動と脆弱性について調査・議論していく」との示唆を得たことを受け、気候変動の脆弱性リスクに関する取組として、2018年、2019年に続き、2021年1月にも「アジア・大洋州における気候変動と脆弱性に関する国際会議」を開催した。2021年の会合では、「YOUTH気候変動政策コンペティション」との表題の下、高校生、大学生が、「脱炭素社会の実現に向けたあなたのまちの施策」をテーマとして、脱炭素社会実現のための具体的な施策に向けた自らの企画について論文及びプレゼンテーションを通じて競いあった。
(カ)非国家主体による気候変動分野の取組
気候変動対策においては、民間企業や自治体、NGOなどの非国家主体の取組も重要である。日本でも、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すと表明した自治体である「ゼロカーボンシティ」、気候変動対策に向けて積極的な行動を取ることを目的とした非国家主体のネットワークである「気候変動イニシアティブ(JCI)」、同様の目的を持った企業グループである「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)」、事業に必要な電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業のグループである「再エネ100宣言RE Action」などによる精力的な活動や、国際的なイニシアティブである「RE100」に参加する企業数及びTCFD11に賛同する企業数の増加など、非国家主体の取組は一層進展している。日本はこうした非国家主体のイニシアティブとも連携しながら、気候変動分野の外交を進めていく考えである。
(5)北極・南極
ア 北極
(ア)北極の現状
地球温暖化による北極環境の急速な変化は、先住民を始めとする北極圏の人々の生活や生態系に深刻で不可逆的な影響を与えるおそれがある。一方、海氷の減少に伴い利用可能な海域が拡大するとの見通しの下、北極海航路の利活用や資源開発を始めとする経済的な機会も広がりつつある。北極圏に最大の領土を有するロシアは、2020年3月に「2035年までの北極における国家政策の基礎」、10月に「2035年までの北極圏の発展及び国家安全保障の戦略」を公表し、軍事施設の整備、資源開発、北極海航路での貨物輸送量の拡大を進めている。また、2018年に北極政策に関する白書を発表し、自国を「北極問題の重要なステークホルダー」と位置付ける中国も、北極圏における資源開発、航路の商業利用、ガバナンス形成への参加に積極的な姿勢を見せており、2020年には、小型衛星BNU-1による北極観測や初の国産砕氷極地調査船「雪龍2号」による北極調査を開始するなど、科学調査分野における活動も本格化させている。このような中、米国も、北極域における情勢の変化を踏まえ関与を強める姿勢を示しており、4月に1,200万米ドル超の対グリーンランド(デンマーク)経済支援策を発表し、6月には在ヌーク領事館を約70年ぶりに再開させるなどの積極的な動きを見せている。
(イ)日本の北極政策と国際的取組
日本は、2015年10月、北極政策の基本方針として「我が国の北極政策」を総合海洋政策本部で決定し、また、2018年5月に閣議決定された「第3期海洋基本計画」では、北極政策について初めて独立の項目を設け、主要施策として日本の海洋政策の中に位置付けるなど研究開発、国際協力、持続的な利用の3本柱を中心に、積極的に取組を進めている。
国際的な取組として、日本は、2013年以来、北極担当大使を任命し、日本がオブザーバーとして参加する北極評議会12(AC)の高級北極実務者(SAO)会合を始め、北極関係の国際会議に出席し、北極をめぐる課題に対する日本の取組や考えを発信してきている。例えば、共にアイスランドで開催された2019年10月の第7回北極サークル13や11月のACSAO会合では、日本がAC現議長国のアイスランドとの共催により第3回北極科学大臣会合(ASM3)をアジアで初めて開催することを踏まえ、北極担当大使が日本の取組などについてスピーチを行った。なお、当初、2020年11月に東京で開催予定であったASM3は、新型コロナの感染拡大に鑑み、2021年5月に延期された。
加えて、日本は、北極において、北極圏国を始めとする関係国と国際協力を進めている。2015年度に立ち上げた北極域研究推進プロジェクト(ArCS)及び2020年度からはその後継の北極域研究加速プロジェクト(ArCS Ⅱ)を通じて、米国、カナダ、ロシア、ノルウェー、グリーンランド(デンマーク)などの研究・観測拠点で研究や人材育成のための国際連携を推進している。また、特定のテーマについて専門的に議論するACの作業部会に研究者を派遣し、日本の北極域研究の成果を発信し、議論に貢献している。2020年9月から10月にかけて、AC議長国であるアイスランドの主催でオンライン開催されたSAO海洋専門家会合(SAO Marine Mechanism)においては、「海洋問題に係る地域協力とグローバルな関与」をテーマとした分科会において、ArCS Ⅱの専門家が日本の北極政策や現地調査における国際協力や地元コミュニティとの協力について報告を行った。
イ 南極
(ア)南極と日本
日本は1957年に開設した昭和基地を拠点に南極観測事業を推進してきており、日本の高い技術力を生かした観測調査を通じて地球環境保全や科学技術の発展における国際貢献を行っている。また、南極条約の原署名国の一員として、南極の平和的利用に不可欠な南極条約体制の維持・強化に努めるとともに、南極における環境保護、国際協力の促進に貢献してきている。
(イ)南極条約
1959年に採択された南極条約は、基本原則として、①南極の平和利用、②科学的調査の自由と国際協力及び③領土主権・請求権の凍結を定めている。条約の締約国のうち、南極において実質的な活動を行う29か国が「協議国」として資格をもち、南極をめぐる課題について協議を行い、条約の目的を促進するための措置をとるなどしている。
(ウ)南極条約協議国会議と南極の環境保護
2019年7月にプラハ(チェコ)にて開催された第42回南極条約協議国会議(ATCM42)では、最近の課題として、南極海のマイクロプラスチック汚染問題や、観光などを目的とした南極地域への渡航が年々拡大していることを踏まえ、観光者数の増加に伴う南極の環境への影響などについて議論が行われた。2020年5月に開催予定であった第43回協議国会議(ATCM43)は、新型コロナの世界的流行の影響により中止となり、2021年6月にパリで開催される予定である。
(エ)日本の南極地域観測
日本の南極観測では、長期にわたり継続的に実施している基本的な観測に加え、2016年から開始した南極地域観測第Ⅸ期6か年計画に基づき、地球システムに南極域が果たす役割と影響の解明に取り組み、特に「地球温暖化」などの地球規模環境変動の実態やメカニズムの解明を目指し、南極唯一の大型大気レーダーによる大気精密観測を始めとした各種研究観測を実施している。
5 MDGs:Millennium Development Goals
6 SDGs:Sustainable Development Goals
7 出典:UNCTAD 「World Investment Report 2014」
8 UHC:Universal Health Coverage。全ての人が負担可能な費用で質の確保された保健サービスを受けられ、経済的リスクから保護されること
9 GCF:Green Climate Fund
10 JCM:Joint Crediting Mechanism
11 TCFDとは、金融安定理事会(FSB)によって設立された、民間主導による気候変動関連財務情報の開示に関するタスクフォース。最終報告書において、気候関連のリスク・機会に関する、企業の任意の情報開示のフレームワークを提示した。
12 北極圏に係る共通の課題(特に持続可能な開発、環境保護など)に関し、先住民社会などの関与を得つつ、北極圏8か国(カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン及び米国)間の協力・調和・交流を促進することを目的として、1996年に設立されたハイレベルの政府間協議体(なお、軍事・安全保障事項を扱わないことが明確に確認されている。)。日本は、2013年にオブザーバー資格を取得
13 グリムソン・アイスランド前大統領などにより2013年に設立され、政府関係者、研究者、ビジネス関係者など、約2,000人が参加する国際会議。日本は、第1回会合から北極担当大使などが参加しており、全体会合でスピーチを行っているほか、分科会において日本の研究者が科学研究の成果を発表している。
