気候変動
パリ協定実施のための様々な主体の取組:地方自治体
 相乗りくん発電所1号(長野県上田市内)
(写真提供:NPO法人 上田市民エネルギー)
相乗りくん発電所1号(長野県上田市内)
(写真提供:NPO法人 上田市民エネルギー)
 官民協働SUWACO Labo(長野県諏訪市)
(写真提供:自然エネルギー信州ネット)
官民協働SUWACO Labo(長野県諏訪市)
(写真提供:自然エネルギー信州ネット)
パリ協定実施のための様々な主体の取組:地方自治体
パリ協定を着実に実施するためには、民間企業、地方自治体、NGOや市民社会をはじめとする様々な担い手(非国家主体、non-state actors)の役割が重要であることが、パリ協定やCOP決定において言及されています。日本政府としては、パリ協定に定められている「2℃目標」をはじめとする目標の実現のために、そうした主体と連携し、一丸となって気候変動対策に取り組んでいくことが重要であると考えています。
日本においても、政府のみならず地方自治体がこうした理念の下、気候変動対策を推進するべく、積極的に具体的な目標を設定し、それぞれの取組を開始しています。以下にそういった取組の一部を紹介します。政府は、パリ協定の着実な実施に向け、今後一層様々な担い手と協力してまいります。
地方自治体によるネットワーク
イクレイ日本 |
イクレイは、持続可能な未来の実現に取り組む125か国2,500以上の都市や地域からなる国際的なネットワークです。日本では、21の自治体が加盟しており、人口の30%をカバーしています。国内外のネットワークを生かし、日本の自治体の取り組みを支援している他、情報提供、国際的な発信機会の提供等を行っています。 |
|---|
横浜市
温暖化対策統括本部 |
横浜市温暖化対策統括本部は、2050年までの脱炭素化を本市の温暖化対策の目指す姿とし、「Zero Carbon Yokohama」のスローガンのもと、省エネルギー、再生可能エネルギーの導入拡大といった取組を進めています。 その推進にあたっては、横浜の強みである市民力を活かした活動に取り組むとともに、企業、学術機関等との連携によるイノベーションを積極的に進め、目標の達成に向けて取り組んでいます。加えて、国内外の先進的な都市や団体、ネットワーク等と連携して「Zero Carbon Yokohama」の取組を広く世界に発信し、多くの人や企業を横浜に惹きつけます。
|
|---|---|
| 「SDGs未来都市」 (“SDGs FutureCity”) 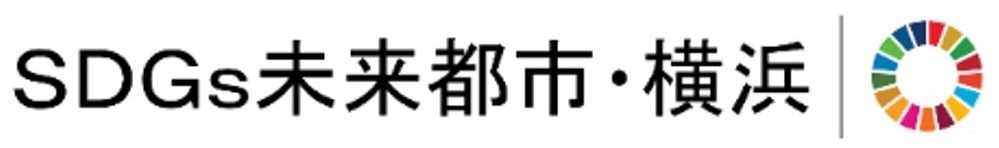 |
横浜市は平成23年に環境未来都市に選定され、環境負荷を抑えながら経済的にも発展し、市民生活の質を向上させるまちづくりの取組を積極的に進めてきました。
|
| 横浜スマートシティプロジェクト(YSCP) |
2010年から横浜スマートシティプロジェクト(YSCP)実証事業を推進し、家庭や業務ビルをはじめ、既成市街地でのエネルギー需給バランスの最適化に向けたシステムの導入などを、エネルギー関連事業者や電気メーカー、建設会社等34社と横浜市が連携して取り組んできました。実証事業を通じて培った知見や技術を実装展開していくため、2015年からは横浜スマートビジネス協議会(YSBA)を設立し、新たに策定したYSCP3.0マスタープランの実行など、更なるエネルギーマネジメントの取組を推進します。 |
長野県
G20環境エネルギー大臣会合・長野宣言 |
2019年6月に長野県軽井沢町で開催された「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」において、長野県はイクレイ日本とともに「持続可能な社会づくりのための協働に関する長野宣言」を発表しました。この宣言は、都市と地方等の協働による自立・分散・循環型社会を目指す「地域循環共生圏」の実現が必要との認識のもと、地方政府が協働する事項とG20 各国に呼びかける事項(地方政府への支援等)を掲げています。 この宣言には、国内96、海外35の自治体や研究機関の賛同を得ており(2020年7月末)、今後も国内外の地方政府や非政府組織とも一層の連携と協力を図りながら世界の脱炭素化にも貢献できるよう取り組んでいきます。 |
|---|---|
| 気候非常事態宣言・気候危機突破方針 |
2019年10月の台風で甚大な被害を受けた長野県は、同年12月、都道府県では初めてとなる「気候非常事態宣言」と、併せて「2050ゼロカーボン宣言」を行いました。 また、「気候非常事態宣言」の理念を具現化するための「気候危機突破方針」2020年4月に公表しました。 併せて、様々な主体と連携・協働し、まちづくりや新技術の開発などの敢えて難しい課題に挑戦する「気候危機突破プロジェクト」を始動させました。既存の制度や仕組みにこれらの「気候危機突破プロジェクト」を加え、ゼロカーボン実現に向けた取組を加速していきます。 |
自然エネルギー信州ネット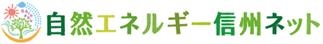 |
「自然エネルギー信州ネット」は、長野県の強みである豊かな自然エネルギー資源を活かした地域主導型の再生可能エネルギー普及モデルを創出することを目的に市民や企業等と行政がつながった協働ネットワークです。再生可能エネルギーに関する全県的なプラットフォームを提供し、再生可能エネルギーに関わる様々な主体の連携やネットワーク作りを行うほか、地域が主役のエネルギー事業の創出を目的として「計画する」「伝える」「育てる」の三つの軸を中心に地域間の情報交換やセミナーの開催、人材育成等の活動を長野県と連携しながら活動しています。
|
上田市民エネルギー |
日射量が多いという長野県の豊富な太陽エネルギーに着目し、陽光パネルの設置費用を出資した市民が売電収入を得ながら再生可能エネルギーの拡大を目指す「相乗りくん」という市民事業モデルを上田市において展開。相乗りくんは2012年3月に上田市内の住宅の屋根への設置からスタート。公共施設や企業の屋根や農地などに50か所の太陽光発電所を設置し、全国の約260名の出資者から合計1億4千万円以上の出資金(2020年8月)を得て事業を行っています。
|
さいたま市
| 電気自動車普及施策 「E-KIZUNA Project」  |
さいたま市では、運輸部門における二酸化炭素排出削減対策として、2009年から電気自動車普及施策「E-KIZUNA Project」を展開し、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車の普及に向けた取組を行っています。また、この取組を、自治体・企業等との広域的・多元的な連携へと広げ、ネットワークを構築するため、「E-KIZUNAサミット」を9回開催してきました。今後、これまで築き上げてきたネットワークを発展・拡充させ、海外の環境先進都市との交流・連携を通じて優れた知見を吸収するとともに、さいたま市がこれまで進めてきた取組を国内外に発信するため、「E-KIZUNAグローバルサミット」の開催を予定しています。
|
|---|---|
スマートシティさいたまモデルの構築 |
さいたま市では、国から総合特区として指定を受けた「次世代自動車・スマートエネルギー特区」の重点プロジェクトとして、水素をはじめとした多様なエネルギーを災害時にも継続して供給するエネルギーセキュリティの確保、パーソナルモビリティの社会実証、低炭素で災害に強く、コミュニティを形成する街区の整備など、環境・エネルギー分野、レジリエンス向上に向けた取組を推進してきました。 これらの取組を礎として、本市の副都心である美園地区において、本市が理想とするスマートシティのモデル構築に取り組んでおり、官民+学が連携して、IoT、AIといった技術とパーソナルデータを活用し、住民のQOLを向上させる生活支援サービスの提供に取り組んでいます。 |
京都市
2050京(きょう)からCO2ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)の推進 |
京都市は、全国の自治体に先駆けて「2050年CO2排出量正味ゼロ」を宣言し、2021年4月に、その実現を目指すことを明記した「2050京(きょう)からCO2ゼロ条例」を施行しました。併せて、脱炭素社会の実現に向けて重要な「行動の10年」の実行計画として、「京都市地球温暖化対策計画<2021-20330>」を策定し、4つの分野(ライフスタイル、ビジネス、エネルギー、モビリティ)の転換や、森林等の吸収源対策、適応策に取り組んでいます。 |
|---|---|
2050年CO2ゼロをめざす再エネ最大化アクション |
2050年CO2排出量正味ゼロの実現に向けて、徹底した省エネを推進するとともに、生活や事業活動に欠かせないエネルギーを、発電時にCO2を発生しない再生可能エネルギーへと転換していくことが重要です。「つくる(太陽光発電設備等の設置)」と「つかう(再エネ電気への切替え)」の両面から、再エネ導入を拡大する各種事業を実施しています。 再エネをつくる 再エネをつかう |


