1 欧州地域情勢
(1)欧州連合(EU)
EUは、総人口約5億1,000万人を擁する28加盟国から成る政治・経済統合体であり、日本と基本的価値・原則を共有し、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で重要なパートナーである。
2017年、EUは、英国のEU離脱交渉、移民・難民流入やテロ事件への対応といった諸課題に直面しつつも、主要国選挙での親EU政権の維持や欧州経済の好調を背景に、欧州の将来に関する議論を前進させようとした一年であった。
英国のEU離脱については、英国が3月29日に離脱通知を行い、その後、三つの主要課題(市民の権利、金銭上の義務、アイルランド国境問題)を中心に離脱の第一段階の交渉が計6回にわたり行われた。これらの交渉では議論が収斂(しゅうれん)しなかったが、12月の欧州理事会直前に首脳レベルで交渉が加速され、最終的に同理事会において第一段階の交渉における「十分な進展」が認定され、交渉は、移行期間や将来の英・EU関係に関して協議を行う第二段階に移行することとなった。
移民・難民の流入については、2016年3月のEU・トルコ合意を維持しつつ、アフリカからイタリアへ向かう地中海ルートへの対策を進めた結果、2017年夏以降にイタリアへの移民・難民の流入数が大きく減少し、欧州への流入数全体も減少した。一方、庇護(ひご)申請者の移転等EU域内における負担の分担を目的とした新たな移民政策の策定は難航している。また、2017年も、複数の欧州主要都市でテロ事件が頻発しており、引き続きテロ対策が課題となっている。さらにEU加盟国の一部においては、ポピュリズムの台頭等の動きが引き続き見られる。例えば、主要国の中で2017年最後の国政選挙が行われたドイツでは、ポピュリスト政党が大きく票を伸ばした。
一方、ユンカー欧州委員会委員長は、9月の欧州議会での一般教書演説において、主要国選挙で親EU政権が維持されたことや欧州経済の回復基調を背景に、欧州の更なる結束強化を訴えるなど、欧州統合の危機への対応から、再び欧州統合を深化させ、欧州の将来に関する議論を前進させようとする姿勢を見せた。
例えば、統合で先行する経済・社会分野だけではなく、安全保障面での協力強化を図る計画が目新しく、6月に防衛装備関連支出の効率化を目的とする欧州防衛基金が設立された。12月には、欧州連合条約上の防衛協力枠組みである常設の構造的協力(PESCO)が立ち上げられ、共同での防衛能力の向上、共同プロジェクトへの投資、作戦即応性と各国の貢献の強化が図られることとなる。引き続きNATOとの連携強化も進められている。
アジアについては、2016年に策定されたグローバル戦略に基づき、EUは引き続き関与を強める姿勢を見せた。北朝鮮をめぐっては、北朝鮮の累次にわたる核及びミサイル実験を受け、10月16日の外務理事会において対北朝鮮独自制裁を決定した。
経済面では、英国のEU離脱問題等の不透明感がある中、世界経済の緩やかな回復、個人消費の増加、失業率の低下等に支えられ、2017年のEU及びユーロ圏では緩やかな景気回復が続いた。
2017年は、日EU経済連携協定(EPA)の交渉妥結が確認されるなど、日・EU関係の包括的な強化に向けた大きな進展が見られた。まず、3月、ブリュッセル(ベルギー)を訪問した安倍総理大臣は、トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長との間で日・EU首脳会談を行った。また、5月、タオルミーナ(イタリア)で開催されたG7首脳会合の際にも、首脳会談が行われた。その上で、両首脳は、7月のブリュッセル(ベルギー)における第24回日・EU定期首脳協議において、日EU・EPA及び日・EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の大枠合意を確認するとともに、北朝鮮問題における連携を確認した。また、これらの会談において、安倍総理大臣は、英国のEU離脱プロセスが日本企業の活動等に影響を与えることを考慮し、プロセスの透明性と予見可能性の確保を一貫して求めた。2017年は外相間でも緊密な対話が行われ、岸田外務大臣が4月にルッカ(イタリア)で開催されたG7外相会合の機会に日・EU外相会合を行ったほか、河野外務大臣は、9月の国連総会の機会にモゲリーニ外務・安全保障政策上級代表と初会談を行った。
経済面では、7月の日EU・EPAの大枠合意の後も詰めの協議が精力的に行われ、12月8日、河野外務大臣とマルムストローム欧州委員(貿易担当)との間で電話会談が行われ、同日、安倍総理大臣とユンカー欧州委員会委員長との首脳電話会談において同EPAの交渉妥結を確認するに至った。

(2)英国
2016年6月に実施された国民投票の結果を受け、メイ首相はEUに対し、2017年3月29日にEU離脱通知を行った。メイ首相は下院を解散し、6月に下院総選挙が行われた結果、与党保守党は第一党を維持するも議席を減らし、単独過半数割れとなった。選挙後もメイ首相は続投を決意し、保守党は、北アイルランドの地域政党である民主ユニオニスト党との閣外連携で一致した。一方、労働党は、選挙により議席を増やし、これを受け、9月の党大会では極左派のコービン党首が党内の支持基盤を強化した。また、不祥事により、11月には、ファロン国防相及びパテル国際開発相、12月にはグリーン筆頭国務相と閣僚の辞任が相次ぐ事態となり、2018年1月には内閣改造が行われた。
日英両国は、首脳、外相を始め様々なレベルでの政策協調や交流を通じ、二国間関係を強化してきている。安倍総理大臣は、4月に英国を訪問し、英国首相公式別荘(チェッカーズ)でメイ首相と日英首脳会談を実施した。また、両首脳は、7月のG20ハンブルク・サミット(ドイツ)の際にも首脳会談を行った。8月にメイ首相が公賓として訪日した際に再び日英首脳会談を実施し、「日英共同ビジョン声明」、「安全保障協力に関する日英共同宣言」、「繁栄協力に関する日英共同宣言」及び「北朝鮮に関する共同声明」を発出し、安全保障、経済パートナーシップ、世界の繁栄・成長を柱に、日英協力を更なる高みに引き上げていくことで一致した。
また、岸田外務大臣とジョンソン外務・英連邦相は、2月のG20ボン外相会合(ドイツ)の際に日英外相会談を行い、4月にニューヨークで行われた北朝鮮非核化に関する国連安保理閣僚級会合の際にも外相会談を行った。加えて、7月にはジョンソン外務・英連邦相が来日し、第6回日英外相戦略対話を実施した。8月に就任した河野外務大臣も、9月の国連総会の際にジョンソン外務・英連邦相と日英外相会談を実施したほか、12月の訪英時にも日英外相会談を行った。
近年、日英間で安全保障・防衛協力が大きく進展している。8月のメイ首相訪日時に発出した「日英共同ビジョン声明」には、日本と英国は「アジア及び欧州において、互いの最も緊密な安全保障上のパートナー」であり、両首脳は、「我々のグローバルな安全保障上のパートナーシップを次の段階へと引き上げることにコミットした」と記載されている。これを踏まえ、12月にロンドンで開催された第3回外務・防衛閣僚会合(「2+2」)では、新たな段階を迎えるにふさわしい日英安全保障・防衛協力の在り方を確認し、共同声明を発出した。また、自由で開かれたインド太平洋の実現や、地域情勢について認識の共有と連携の強化、共同訓練、防衛装備・技術協力、テロ対策などの安全保障分野での幅広い協力の推進について議論を行った。防衛装備・技術協力の分野では3月から「将来戦闘機における英国との協力の可能性に係る日英共同スタディ」が開始され、5月には日本周辺海域及びグアム・テニアンで、初の日英仏米共同訓練を実施、さらに、8月には日・英物品役務相互提供協定(ACSA)が発効した。
(3)フランス
フランスでは、4月から5月まで大統領選挙が実施され、伝統的な二大政党の枠組みを超えた右派と左派の糾合を唱えて出馬したマクロン候補が、極右政党を率いるル・ペン候補を破り、第五共和制の第8代大統領として選出された。大統領選に続き6月に実施された国民議会選挙でも、マクロン大統領率いる中道政党「共和国前進」が過半数を超える議席を獲得し、フィリップ首相を首班とするフィリップ内閣が本格始動した。また、9月には上院選挙(半数改選)が実施された。
マクロン大統領は、内政面では、積年の課題である失業問題に対応するため労働市場改革に着手し、9月、労働法改正に関する行政命令(オルドナンス)を閣議決定した。また、テロ対策に関し、2015年11月のパリにおける連続テロ事件以降継続されていた緊急事態宣言を11月1日に解除するとともに、緊急事態宣言下で例外的に認められていた行政当局の一部権限を一般法化する法律を成立させ、テロの脅威に対応している。さらに、財政面では、ユーロ圏加盟国に求められている財政赤字のGDP比3%以内との基準を達成すべく、財政改革に取り組んでいる。外政面では、中東・アフリカの安定化や気候変動問題への対処を優先課題としており、12月にはパリで気候変動サミット(日本からは河野外務大臣が出席)を主催した。また、多極化する世界における多国間協力の枠組みを重視しており、EUについても、ユーロ圏共通予算の創設といったビジョンを発表するなど、欧州統合を牽引(けんいん)している。
日本との関係では、1月にパリで第3回外務・防衛閣僚会合(「2+2」)が開催され、物品役務相互提供協定(ACSA)の交渉を開始することで一致するとともに、2016年12月に発効した日仏防衛装備品・技術移転協定に基づく日仏間の初めての協力案件として機雷対処用水中無人航走体に関する協力を具体化していくことを確認した。また、4月から5月まで、日本周辺海域及びグアムにおいてフランスの練習艦隊「ジャンヌ・ダルク」による日仏英米の共同訓練が行われた。なお、3月には安倍総理大臣がフランスを訪問し、オランド大統領との間で首脳会談を実施したほか、5月に開催されたG7タオルミーナ・サミット(イタリア)の際に、新たに選出されたマクロン大統領との間で初の首脳会談を実施し、2018年にパリを中心に開催される「ジャポニスム2018」に向けた協力等を確認した。その後、9月の国連総会に際しても首脳会談を行い、また、河野外務大臣も、マクロン政権で新たに就任したル・ドリアン欧州・外務相との間で初となる外相会談を実施した。さらに、2018年1月、東京で開催された第4回日仏「2+2」及び第7回日仏外相戦略対話に河野外務大臣が出席し、日仏ACSAの大枠合意を歓迎したほか、仏海軍フリゲート艦「ヴァンデミエール」訪日に際し共同訓練を実施することで一致した。
(4)ドイツ
国際社会が引き続き、英国のEU離脱問題、ウクライナ問題、難民問題等様々な課題に直面する中で、ドイツは2017年のG20議長国として、7月にハンブルク・サミットを主催した。議長国として「テロ対策に関するハンブルクG20首脳声明」をまとめたほか、世界経済については、成長を強化し、下方リスクに対応するため、国際的な協力に対する各国のコミットメントを確保した。
経済面では、緩やかな回復基調を維持している。連邦政府は2017年の実質GDP成長率を2.0%と予測しており、11月の失業率は5.3%と1991年以来の低水準となった。
内政面では、2017年3月任期満了に伴い退任したガウク前大統領の後任として、シュタインマイヤー前外相が第12代連邦大統領に就任した。9月には4年に1度の連邦議会選挙が行われた。EU主要国を含む各国の首脳が交代する中、安定的な政権運営を行ってきたメルケル首相の続投に対する国内外からの期待は高まっていたが、与党キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)は第一党の座を維持したものの、得票率は戦後2番目に低い水準となり、大連立のパートナーである社会民主党(SPD)も史上最低の得票率に落ち込んだ。一方、反難民を掲げる「独のための選択肢(AfD)」は、既存政治への飽き、不満の受け皿の役割も果たし、二桁の得票率で第3党に躍進し、連邦議会で初めて議席を獲得した。また、自由民主党(FDP)が4年ぶりに議席を回復した。
選挙後、SPDが当初CDU/CSUとの大連立継続を拒否したため、CDU/CSUはFDP及び緑の党との連立政権樹立に向けた「事前協議」を開始したが、FDPが「事前協議」からの離脱を表明したため頓挫した。その後、シュタインマイヤー大統領による働きかけを経て、2018年1月CDU/CSUとSPDは連立交渉を開始し、2月に交渉を妥結した。
日本との間では、2016年に引き続き、ハイレベルの要人往来が行われた。岸田外務大臣は、2月にドイツで開催されたG20外相会合に出席するため、ドイツ・ボンを訪問した。3月には、日本がパートナー国となった情報通信見本市(CeBIT)に出席するために安倍総理大臣がドイツ・ハノーバーを訪問し、メルケル首相と共に情報通信分野の日独企業ブースなどを訪問したほか、首脳会談を行い、G7が従来以上に結束して安全保障及び経済面で揺るぎない連携とコミットメントを示すことが重要であるという点で一致した。また、2018年2月にはシュタインマイヤー大統領が訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を行った。
(5)イタリア
2017年、前年の日本に続いてG7サミット議長国を務めたイタリアは、G7タオルミーナ・サミット及び13の閣僚級会合を開催し、日本からも多くの要人がイタリアを訪問した。特に、安倍総理大臣は、3月にローマを訪問し、ジェンティローニ首相と首脳会談を行い、G7サミットの新旧議長としての緊密な協力を確認し、さらに5月にはG7サミット出席のためシチリアを訪問した。4月には岸田外務大臣がG7ルッカ外相会合出席のためにルッカ(イタリア中部トスカーナ)を訪問し、アルファーノ外務・国際協力相と外相会談を行った。
安全保障・防衛分野における両国の協力も着実に深化している。3月の首脳会談において、防衛装備品・技術移転協定の交渉開始に一致し、5月にピノッティ国防相が訪日した際に、岸田外務大臣との間で同協定に署名が行われた。
内政面では、2016年末に就任したジェンティローニ首相は堅実に政権を運営した。イタリアにおいて長年の課題であった選挙法についても、2017年10月に上下両院により改正案が可決され、11月に施行された。
(6)スペイン
2017年は、日・スペイン間で多くの要人往来が実現した。4月には、フェリペ6世国王王妃両陛下が国賓として訪日した。また、岸田外務大臣は国王王妃両陛下に同行して訪日したダスティス外務・協力相と外相会談を行い、ワーキング・ホリデー制度に関する協定の署名が行われた。7月には、滝沢求外務大臣政務官がバルセロナ及びマドリードを訪問し、現地日系企業関係者等との意見交換や、カストロ外務・協力省外交長官との会談を行った。10月には、スペインのマラガ市において、「第四次産業革命とグローバル化 日本とスペインの対話」と題して、第19回日本・スペイン・シンポジウムが開催された。
内政面では、スペイン憲法裁判所が、10月のカタルーニャ州の独立を問う「州民投票」を違憲とした。スペイン政府は、スペイン憲法に基づき、カタルーニャ州議会の解散を含む措置を執行した。
(7)ウクライナ
ウクライナ東部では、8月末や12月末の停戦合意により、一時的な情勢改善も見られたが、4月に欧州安全保障協力機構(OSCE)特別監視団員の死亡事案が発生する等、不安定な状況が継続した。1月以降、ウクライナ政府支配地域と被占領地域の物流が停止される事態が発生し、現在に至るまで被占領地域の経済封鎖の状況が続いている。また、ミンスク合意の履行に向けた関係国の協議についても、大きな進展は見られなかった。
外交面では、9月にEUとの間で深化した「包括的自由貿易協定(DCFTA)」を含む連合協定が発効した。ウクライナは、2度のノルマンディー・フォーマット首脳電話会談2を含め、欧米各国や近隣諸国との往来や協議、国連等のマルチ会合を活用した積極的な外交を展開した。
内政面では、2016年4月に発足したフロイスマン内閣の主導により、司法改革、保健改革、年金改革、選挙法改革等で一定の成果は見られるが、汚職対策等に関しては国内勢力に立場の違いが見られるなど、引き続き課題も残っている。
日本との関係では、2017年は外交関係樹立25周年に当たり、これを記念し「ウクライナにおける日本年」として、多数の日本関連事業がウクライナ各地で実施された。その一環として1,500本以上の桜の木をウクライナ各地に植樹した。2月末にはパルビー最高会議議長、6月にはイェメツ・ウクライナ日本友好議員連盟会長一行、10月にはエリセーエフ大統領府副長官が訪日し、また11月には中根外務副大臣がウクライナを訪問し、「ウクライナにおける日本年」関連行事に出席するなど、ハイレベルの交流は引き続き活発であった。
また、11月には第5回日・ウクライナ原発事故後協力合同委員会が首都のキエフで開催されたほか、2018年1月からウクライナ国民に対する査証緩和措置が導入されるなど、実務レベルでも二国間関係は着実に進展した。
対ウクライナ支援では、1月に約4億6,000万円(389万米ドル)の追加支援を決定した。
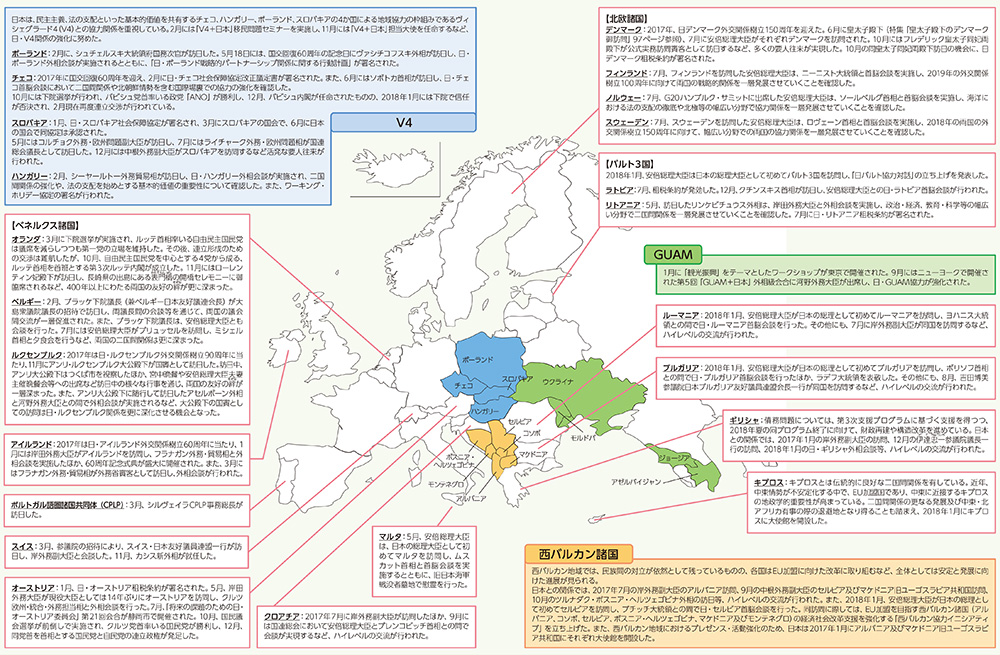
2 ウクライナ問題の解決を目的として、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナの4か国で構成される対話の枠組み
