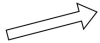ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第396号
第7回アフリカ開発会議(TICAD 7)を8月に横浜で開催
原稿執筆:TICAD事務局
 TICAD VI開会セッション及び全体会合1にて共同議長
TICAD VI開会セッション及び全体会合1にて共同議長を務める安倍総理大臣(2016年8月27日,28日)
© 2019 TICAD VI Nairobi
 第7回アフリカ開発会議
第7回アフリカ開発会議(TICAD7)公式ロゴ
本年8月28日から30日,パシフィコ横浜で第7回アフリカ開発会議(TICAD7:ティカッドセブン)が開催される予定です。今年7回目を迎えるTICAD首脳会合ですが,そもそもどのような会議かご存じでしょうか?
TICADとは,1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議(Tokyo International Conference on African Development:TICAD)です。TICAD Vまでは5年ごとに日本で開催され,その後のTICAD VIから3年ごとに日・アフリカで交互に開催されることとなりました。
TICAD7のテーマ:経済・社会・平和と安定
アフリカは2000年から2016年にかけて平均5%と順調な経済成長を続けています。単純に計算して15年で経済規模が2倍以上になったことになります。アフリカといえば飢餓や貧困、干ばつや自然災害、戦乱に悩まされている国々というイメージがあるかもしれません。そうした問題がすべて解決したわけではありませんが、実際に現地に行くと、高層ビルが立ち並ぶ大都会が、エネルギッシュな経済を象徴しています。
つまりアフリカは、もはや援助の対象だけではなく,日本にとって共に成長するパートナーともなったと言えます。1993年以降,25年以上にわたって,日本はTICADを通じてアフリカ開発支援を主導してきました。アフリカの豊富な天然資源や約12億人の市場は,日本企業にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。そうしたアフリカと友好的な関係を維持することは,日本外交の基盤強化につながります。
一方で,先ほども述べましたが、アフリカには紛争,感染症等も含めて,多くの課題を抱え、その解決に国際社会とともに引き続き取り組む必要があるのも事実です。
以上のようなアフリカの現状と、我が国との関係を踏まえて、今年のTICAD7のテーマは,経済、社会、そして平和と安定,という3つの柱を議論の中心とすることになりました。
TICADの特徴
アフリカから遠く離れた日本がなぜTICADを通じてアフリカ開発支援を主導してくることができたのでしょうか。4つの特徴を挙げることができます。
- アフリカ開発に係る先駆的存在
冷戦終結後,アフリカ支援に対する先進国の関心が低下した中,アフリカの重要性を論じ,日本が1993年に立ち上げたのがTICADです。アフリカ開発に関するフォーラムとして,TICADは先駆的存在なのです。 - 開かれたフォーラム
TICADは,アフリカ諸国のみならず,国際機関,ドナー諸国,民間企業,市民社会なども参加するマルチの枠組みです。TICAD7は,日本,国連,世界銀行,国連開発計画(UNDP),アフリカ連合委員会(AUC)が共催者となり,アフリカ諸国の首脳のみならず,多彩な参加者を迎えて開催する予定です。 - アフリカのオーナーシップと国際社会のパートナーシップの理念を具現化
TICADでは,アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」(自助努力)と,国際社会による「パートナーシップ」の重要性を提唱しており,この開発哲学は国際社会に共有され,アフリカ諸国にも浸透しています。 - 着実な公約実行・フォローアップ
首脳会合と首脳会合の間に開催する閣僚会合で取組の実施状況を確認し,TICAD報告書を発表するなど,公約をフォローアップする仕組みを構築しています。これはアフリカ諸国にも高く評価されています。
歌手のMISIAさんがTICAD7名誉大使に!


自らもアフリカを訪問し、10年以上にわたってアフリカ支援に携わってこられた歌手のMISIAさん。河野大臣から直接TICAD7名誉大使を委嘱させていただき、TICAD7を盛り上げるため,一緒に活動していただいています。
TICADに参加しよう!
また,TICAD7の会期中(8月28日~30日)には会場となるパシフィコ横浜において,国際機関,民間企業・団体,NGO等がさまざまなイベントを開催する予定です。たとえばTICAD7を日本国内の皆で盛り上げるために,アフリカ開発や日アフリカ関係強化に資する事業を,TICADパートナー事業として幅広く認定しています。横浜以外でもさまざまな応援イベントが企画されています。メルマガ読者の皆様の身近でも,TICAD7を盛り上げるイベントが開催されているかもしれません。外務省HPのTICAD7のページをチェックして,是非,足を運んでみてください。
「アフリカとの一校一国」
 第5回アフリカ開発会議の際、一校一国運動でマラウィ料理を学ぶ小学生
第5回アフリカ開発会議の際、一校一国運動でマラウィ料理を学ぶ小学生【Yokohama International Digestより】
「アフリカに一番近い都市」として、TICADが開催される横浜市内の各小中学校がアフリカの一国を交流国と定めて交流を行うことにより、アフリカ各国への理解を深め、交流を進めることを目的として、「アフリカとの一校一国」を実施しています。
また,TICAD7に向けて日本政府をはじめとする共催者は,公式SNS(Facebook,Twitter)で関連情報を発信しています。本番に向けて盛り上げていきますので,是非フォロー・いいね・シェアをお願いします!
(公式SNSはこちら)
- Twitter @ticad7

- Facebook TICAD7

JICA広報誌「mundi」2月号「教えて!外務省 知っておきたい国際協力」
2019年2月号「アフリカ開発会議(TICAD:ティカッド)」について掲載されています。是非ご覧ください。
コンゴの産業多様化を促進!ODAで漁業センターを建設

原稿執筆:コンゴ民主共和国日本国大使館(コンゴ共和国兼轄)三等書記官 高木勇歩
 日本のODAで建設されたCAPAP
日本のODAで建設されたCAPAP
 品質の良い氷を製造する製氷機も用意された
品質の良い氷を製造する製氷機も用意された
コンゴ共和国は,赤道直下,大西洋に面し,流域面積世界2位を誇るコンゴ川の北岸に位置する人口600万人に満たない小さい国です。この国は産油国で,国の歳入の約7割,輸出の約8割を石油産業が占めています。しかし,石油に依存した経済は,2014年の石油価格下落により深刻なダメージを受けました。そうした危機的状況を脱却するため,政府は「産業の多様化」を優先目標に掲げ,経済の立て直しを図っています。
日本は,ODAでこうした国の取組を後押しすべく,第二の都市である大西洋の港町ポワント・ノワールで,漁業振興支援として2018年6月に零細漁業センター(CAPAP)を建設しました。
 センターで魚が販売される様子
センターで魚が販売される様子
 日本で受けた研修をもとに
日本で受けた研修をもとに漁船管理の改善に取り組むセンター職員
日本の支援以前,この地域には,零細漁業に従事する漁民が衛生的な環境で鮮度の良い魚を販売するための施設がありませんでした。魚の鮮度を保つ方法として,水揚げされた魚に砂浜の砂をまぶす方法が昔から伝えられ,魚は炎天下の中でぞんざいに放置されたまま売られていました。
こうした状況を劇的に変えたのはCAPAPです。このセンターでは,日本で研修を受けた職員が中心となり,日本人の専門家のアドバイスを受けながら魚の保存や販売に関する積極的な啓発活動が行われています。今日では,毎日300人を超える漁民や仲買人がこのセンターを利用し,アジ、タイ、サメなどの魚が早朝から取引されています。
 氷を使って鮮度保持の研修を行う現地の人々
氷を使って鮮度保持の研修を行う現地の人々
また,センターで安価で販売される品質の良い氷を使って,魚の鮮度を保持する人が日に日に増えてきています。このセンターが価格や品質という,魚の流通にあたってとても重要な価値観を啓発することで,地元の漁民がポワント・ノワールの水産物流通を主体的に改善するきっかけとなっています。
 取材に答える日本人専門家
取材に答える日本人専門家
 センターを訪問した取材に
センターを訪問した取材に市場の哲学を語る品質管理責任者
今後,CAPAPの運営能力が強化されることにより,漁民の氷の調達コストが2割低減し,また漁業者の出漁回数が増えることにより,プロジェクト開始前に1日2ドルに満たなかった一部漁民の収入も改善される見込みです。CAPAPは魚食振興のイベントの開催や,漁民や仲買人への漁獲後処理の研修を行うことで,今後も地域の漁民とともに漁業の振興に取り組んでいきます。
CAPAPを建設し,漁業に携わる人々に日本のノウハウを伝える,まさに「魚を与えるのではなく,魚の釣り方(売り方)を教えよ」の哲学の体現とも言えるプロジェクトと言えます。
ODAの現代化 新たな計上方式により日本のドナー努力を正しく評価

 OECD/DAC統計作業部会(パリにて開催)の様子
OECD/DAC統計作業部会(パリにて開催)の様子ODAの計上方法に関するルールがここで議論されます
(左から2017年11月,2018年1月に撮影)
原稿執筆:開発協力企画室 統計資料班
4月10日,パリにある経済開発協力機構(OECD)が2018年の各国のODA実績(暫定値)を公表しました。日本の実績額は141億6,707万米ドル(1兆5,646億円)で,米国,ドイツ,英国に次ぐ第4位でした。みなさんは,このODA実績額をどのように計算しているかご存じでしょうか。
OECD開発援助委員会(DAC:ダック)は,どんな協力がODAに該当するか,それをどのように報告するかというルールを統計指示書(reporting directives)という文書にまとめています。
この統計指示書では,ODAの基本原則は(1)公的機関またはその実施機関によって供与される(2)開発途上国の経済開発を主目的とする(3)譲許的性格を有する(有償資金協力の場合、貸付条件(金利、償還期間等)が受取国にとって有利に設定されている),と定義されています。
DACでは,ODAを時代に合ったものに改善するいわゆる「ODAの現代化」に関する議論が行われており,我が国も積極的に議論に参加しています。このような議論の中で,有償資金協力(円借款等)の実績額の測り方について,これまでの「純額方式」に代えて,2018年実績から「贈与相当額計上方式」に変更することが決まりました。
「純額方式」とは,有償資金協力について,その年に新たに供与した額をプラス計上するとともに,同じ年に返済された額をマイナス計上して実績額を計算するものです。この方式の場合,円借款を供与しても,最終的に返済が完了すれば,トータルではプラス・マイナスがゼロになってしまうことになります。
これに対して,新たに導入された「贈与相当額計上方式」は,有償資金協力がどれだけ緩やかな条件で供与されているのかに着目し,供与額,利率,償還期間などの供与条件を考慮して贈与に相当する額を算出するものです。供与条件が緩やかであればあるほど,実績額が大きくなるため,ドナー努力がより正確に反映される方式と言えます。
日本の場合,開発途上国に有利な条件で多額の有償資金協力を行っているので,2018年の実績額では,従来の「純額方式」に比べ,約4割大きく計上されることとなりました。
贈与相当額計上方式と純額方式の比較
(2018年ODA実績(暫定値)DACメンバー上位10か国)
(2019年4月10日OECD公表)
| 【旧】純額方式 | ||
|---|---|---|
| (単位:億ドル) | ||
| 順位 | 国名 | 実績額 |
| 1 | 米国 | 337.4 |
| 2 | ドイツ | 258.9 |
| 3 | 英国 | 194.5 |
| 4 | フランス | 125.0 |
| 5 | 日本 | 100.6 |
| 6 | スウェーデン | 58.4 |
| 7 | オランダ | 56.2 |
| 8 | イタリア | 49.0 |
| 9 | カナダ | 46.2 |
| 10 | ノルウェー | 42.6 |
| DACメンバー国計 | 1,493.2 | |
順位が上がった!
| 【新】贈与相当額計上方式 | ||
|---|---|---|
| (単位:億ドル) | ||
| 順位 | 国名 | 実績額 |
| 1 | 米国 | 342.6 |
| 2 | ドイツ | 249.9 |
| 3 | 英国 | 194.0 |
| 4 | 日本 | 141.7 |
| 5 | フランス | 121.5 |
| 6 | スウェーデン | 58.4 |
| 7 | オランダ | 56.2 |
| 8 | イタリア | 50.1 |
| 9 | カナダ | 46.5 |
| 10 | ノルウェー | 42.6 |
| DACメンバー国計 | 1,530.2 | |
ODA短信
最新のODA関連情報をお届けするコーナーです。
- 「次世代のSDGs推進プラットフォーム」による「SDGs達成に向けた若者の参画」が開催されました。これは,2030年以降にSDGs推進の主役となる次世代によるSDGsへの関与を深め,諸外国の若者同士のネットワークを強化することを目的とするものです。
次回予告!特集「開発コンサルタントに聞く,日本の開発協力」
第397号は5月10日配信予定です。開発コンサルタントの仕事内容の紹介や,これまでのキャリアや仕事の上での困難,やりがいについて,開発コンサルタントにインタビューします。途上国のニーズに寄り添う姿はまさに開発援助のプロフェッショナル。
次回,お楽しみに!
編集・発行:外務省国際協力局政策課広報班
 外務省 ODA広報キャラクター ODAマン
外務省 ODA広報キャラクター ODAマン