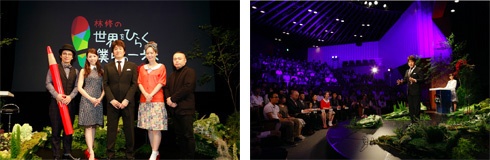ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第309号
ODAメールマガジン第309号は,コスタリカ共和国からの「コスタリカと日本:「共に」(Juntos:フントス)発展しあうパートナーシップ」,「住民と共に学び合いながらコスタリカの自然を守る」と「平成27年度 開発協力特集番組『林修の「世界をひらく僕らの一歩」』」をお届けします。
コスタリカと日本:「共に」(Juntos:フントス)発展しあうパートナーシップ
原稿執筆:在コスタリカ日本国大使館 木村 泰次郎 参事官
コスタリカは,日本語で「豊かな海岸」を意味します。人口480万人,九州と四国を合わせたくらいの面積の小さい国ですが,豊かな個性に溢れた国です。国土の約4分の1が自然保護区に指定されており,そこは珍しい蝶や鳥などの動植物が共生する生物多様性の楽園です。手塚治虫の「火の鳥」のモデルとなったケツァールやウミガメの産卵等を観賞するためのエコツアーに世界から毎年240万人もの観光客が訪れています。
 コスタリカの珍しい動物類
コスタリカの珍しい動物類
 豊富なフルーツが店頭に並ぶ朝市の様子
豊富なフルーツが店頭に並ぶ朝市の様子
 コスタリカ市民が誇りとする国立劇場
コスタリカ市民が誇りとする国立劇場
コスタリカは,政治もユニークです。1948年の内戦終結以来60年を越えますが,その間,政権交代は全て選挙で行われており,中南米で最も政治的に安定した国の一つです。
また,1949年に憲法で常備軍の保持を禁止し,軍事支出がない分,教育や社会福祉に力を入れてきました。長年の取組により,国民の教育水準は高く,社会保障制度も整備されています。
しかし,近年の政府による自由主義的経済政策の実施を背景に,首都圏と地方の経済格差や国民各層の社会格差が広がっているのも事実です。公共インフラの老朽化,都市環境の悪化も深刻です。これらの課題に直面するコスタリカに対して,共通の価値観を有するパートナーである日本は,その経験と技術を活かして以下の重点分野を中心に支援を行っています。
(1)環境問題への支援
コスタリカは,2021年までに温室効果ガスの排出と吸収を相殺する「カーボン・ニュートラル」の実現を目指しています。日本は,再生可能なエネルギーの開発に向けたコスタリカの取組を支援してきました。2013年11月には,グアナカステ県に地熱発電所を建設するための円借款に関する交換公文が締結されました。また,その他の環境保全分野の支援として,参加型生物多様性保全の推進や下水処理施設の整備による首都圏環境改善にも取り組んでいます。本年4月,訪日したグティエレス環境エネルギー大臣は,コスタリカと日本が持続可能な発展を目指すパートナーとして引き続き協力を深めていくことへの期待を示しました。
 我が国が支援した下水道処理施設を視察するソリス大統領と篠原大使
我が国が支援した下水道処理施設を視察するソリス大統領と篠原大使
(2)産業振興への支援
日本は,長年,コスタリカ国内で中小企業の生産性向上・品質管理のための人材育成に力を入れてきました。今やこの協力により育成されたコスタリカの専門家が,他の中米諸国における人材育成に日本の専門家と一緒に取り組む時代になりました。コスタリカと日本の人材が一緒になって他の中米諸国を援助するいわゆる三角協力の姿は,昨年8月に安倍総理が示された対中南米外交の指導理念である「共に」(フントス)を体現したものと言えましょう。
(3)社会的弱者への支援
人間の安全保障の観点からの貧困地域の住民や障がい者に対する支援も重点分野です。例えば,障がい者の自立をはかることで地域社会全体を変えるための取組を行っています。
本年は,日本とコスタリカが外交関係を樹立してから80周年の佳節を刻みます。コスタリカとの着実な経済協力を通じて,両国の絆が一層深まるように取り組んでまいります。
 我が国が支援している障がい者団体と交流する篠原大使
我が国が支援している障がい者団体と交流する篠原大使
 リハビリを指導する青年海外協力隊員
リハビリを指導する青年海外協力隊員
住民と共に学び合いながらコスタリカの自然を守る
原稿執筆:コスタリカ参加型生物多様性保全推進プロジェクト・チーフアドバイザー 大澤 正喜
コスタリカには地球上の全陸地面積の5%の生物が存在すると言われています。そのコスタリカの豊富な自然を保全していくために,日本が行っている協力の一つが「参加型生物多様性保全推進プロジェクト」です。
プロジェクトの目的は,自然豊かな地域に住んでいる人たちが生活を犠牲にすることなく,身の回りの豊かな自然の保護にも参加してもらえる方法を考え,実践していくことです。
例えば,国の北東部にあるバラ・デル・コロラド野生生物保護区で行っている活動があります。保護区の中にあるリンダ・ビスタ村の方たちと,今ある農牧畜を軸にし,村の豊富な自然を活用した村落ツーリズムを発展させることを一緒に考えています。押しつけの活動にならないように,一緒に考えると言うことが大切です。自然保護に関しては,私たち専門家が村の人たちから学ぶことの方が多いからです。
 植生調査のために保護区内の水路を移動する。
植生調査のために保護区内の水路を移動する。
万が一の安全確保のために,警察官が同行してくれた。
マリア・ルイサさんは,リンダ・ビスタ村の森を守るリーダー的存在です。電気もない村の外れの森の中で,コショウを栽培したりして,一人で生活しています。人生経験豊富な彼女から,学ぶものは多くあります。先日も,次のような話をしてくれました。ある日息子が仕事で汚れた服を着て家に帰ってきた。「お帰りなさい」と言ってハグしようとしたら,息子は「仕事で服が汚れていて,お母さんの服を汚したくないから,後でいいよ」と言ったそうです。でも彼女は「自分の息子が一生懸命働いているのは私の誇りだよ。」といってギュッと抱きしめたそうです。
その息子さんは今年,交通事故で亡くなってしまいました。それでも彼女は,森の中で一人,大好きなリンダ・ビスタ村の自然と一緒に住んでいます。
今でも年間850万ヘクタールの熱帯林が世界で失われていると言われています。一方で,マリア・ルイサさんのように,シンプルな生活をし,自分の大好きな森を保全しようとしている人もいます。そのような人に接すると,私が自然保護を語ることの傲慢さを感じます。自分にできないことを普通にできる人への畏敬の念を持ちながら,毎日の活動を行っています。
 マリア・ルイサさんの入れてくれるコーヒーの味は,格別です。
マリア・ルイサさんの入れてくれるコーヒーの味は,格別です。
 村の青年たちに鳥の観察についての研修を行っている。
村の青年たちに鳥の観察についての研修を行っている。
身の回りの鳥を覚えることで,少しでも鳥への興味が湧き,また,保護区管理に必要なデータを蓄積してくれること,そして,バードウォッチングのガイドとして働くことができるようになることを期待している。
平成27年度 開発協力特集番組『林修の「世界をひらく僕らの一歩」』
原稿執筆:国際協力局政策課広報班
世界各地で展開されている日本の「開発協力(ODA)」。
具体的にどこでどんなことを行っているのか,知っているようだけど,知らない方も多いと思います。そこで,今回,林修先生が普段とは違う白熱した講義スタイルで,「開発協力」について,わかりやすくプレゼンする番組『林修の「世界をひらく僕らの一歩」』をテレビ東京系列6局ネットで,全3回にわたって放送いたします。
番組では,世界各地で行われている様々な開発協力を,現地のロケ映像を交えながら紹介し,開発協力の現状について,林先生ならではの興味深く,わかりやすい形でプレゼンテーションします。
皆様是非御覧ください。
<番組概要>
タイトル:『林修の「世界をひらく僕らの一歩」』
放送局:テレビ東京系列6局ネット
(第1回目(9月20日放送)はBSジャパンにて再放送)
放送日予定日:
第1回「人間の安全保障 世界の人々の“ヘルプ”に耳を傾けよう」
平成27年9月26日(土曜日)11時45分~13時00分 ((注)再放送:BSジャパン)
第2回「パートナーシップ あなたにもできる国際協力」
平成27年10月25日(日曜日)16時00分~17時15分(予定)(テレビ東京系列6局ネット)
第3回「質の高い成長 世界とともに歩む日本の技術」
平成27年11月15日(日曜日)16時00分~17時15分(予定)(テレビ東京系列6局ネット)
関連ページ: