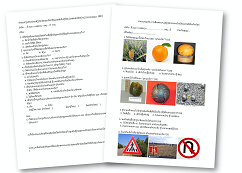ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第468号
2023(令和5年)年8月28日発行
不発弾のないラオスを目指してオールジャパンで取り組む支援
在ラオス大 経済・経済協力班
皆さんは「ラオス」と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。東南アジアの一国であることは御存じの方もおられるかもしれませんが、その東南アジアの中でも海に面していない内陸国であり、カンボジア、ミャンマー、東ティモールと同じ後発開発途上国(LDC)に分類されていることも御存じでしょうか。その一方で、古都・ルアンパバーンの町、チャンパサック県のワット・プー、シェンクワン県のジャール平原が世界遺産に登録されており、ニューヨーク・タイムズの「世界で一番行きたい国」の1位に選ばれるなど、注目を浴び続けている国の一つでもあります。
(写真左:ルアンパバーンの町、中央:ジャール平原、右:ワット・プー)
日本とラオスの意外なつながり
日本とラオスのつながりは意外と古く、室町時代にラオスの地酒・ラオラーオ(もち米から作られる蒸留酒)が沖縄に伝わり、泡盛の起源になったと言われています。既に江戸時代の朱印船制度の頃には、象牙、毛皮、香料等の交易が行われていたと言われており、キセルの吸い口と火皿を接続する竹管を「羅宇(ラオ)」と称するのは、江戸時代にラオスから渡来した竹を用いたからであるという説もあります。
こうした日本とラオスの関係は様々な面で現代につながっています。日本とラオスの外交関係は1955年に樹立され、外交関係樹立60周年にあたる2015年に、両国関係は包括的パートナーシップから戦略的パートナーシップに格上げされました。これを記念してラオスからはゾウが(ラオスはかつて「100万頭のゾウ」という意味を持つ「ランサーン王国」と呼ばれており、現在でも、ラオス人にとってゾウは非常に身近な存在)、日本からは桜が寄贈されました。両国の関係は伝統的に良好であり、2025年には外交関係樹立70周年を迎えます。
(写真左:ラオラーオ、中央:ラオラーオと泡盛が融合した日本向け蒸留酒「美らラオ」、右:京都市動物園に寄贈されたゾウ)
ラオスが抱える根深い課題


先ほど、ラオスは「世界で一番行きたい国」の1位とお話ししましたが、もう一つ、ラオスが世界で1位となっていることがあります。それは、国内に残っている不発弾の数です。1964年から1973年まで続いたベトナム戦争中、ラオスは、共産主義勢力の拠点であった北部や南部を通っていたホーチミン・ルート(ベトナム戦争時の重要な補給路)を中心として激しい爆撃を受けました。このときに投下された爆弾は少なくとも200万トン以上と言われており、これは、ラオスの人口(2021年時点で733万人)の一人当たりに換算すると世界一です。この中には2億7,000万個のクラスター子弾(クラスター爆弾に含まれている小さな爆弾)が含まれています。このうちの少なくとも3割は爆発しなかったとみられ、推定8,000万個が戦争終結後も不発弾として残され、今に至っていると言われています。こうした不発弾の被害は深刻であり、ベトナム戦争が始まった1964年以降、現在までに不発弾で死傷した住民は5万人以上にのぼります(約150人に一人が何らかの被害に遭っている計算になります)。このように、不発弾の存在は現在も人々の生活の安全を脅かすのみならず、国内の農地拡大やインフラ開発をはじめとした社会経済発展の阻害要因となっています。
(写真左:クラスター子弾、右:不発弾被害によって両目・両腕を負傷した男性)
ODAでの不発弾除去機材等の供与と技術支援、国家主席からの感謝


こうした状況の中で、日本は1998年から20年以上にわたって8,000万米ドル(約82億円)を投じて、不発弾除去に必要な機材の供与、不発弾除去に取り組む組織の能力強化、不発弾被害を回避するための啓発活動、不発弾被害者の社会復帰支援など、包括的な取組を実施してきました。2023年4月には、不発弾除去に必要な活動費、日本製の不発弾検知センサー機材をはじめとした機材供与、不発弾除去に取り組む組織の施設整備等を支援する新たな取組に関する書簡が交換されました。2023年5月に来日したトンルン・シースリット国家主席からは、岸田総理との首脳会談の場において、こうした長年にわたる日本の協力に対して深い感謝の意が示されています。日本の協力は、JICAを通じた技術協力プロジェクトとしても実施されています。現在実施されているプロジェクトでは、限られた予算と人員の中でも効果的な除去活動が可能となるよう、ITを活用した年間計画の策定を支援しています。また、南南協力の一つとしてカンボジアの地雷除去実施組織であるカンボジア地雷対策センターへの政府職員の派遣を通じて、不発弾除去活動や機材操作をはじめとした知見やノウハウの技術移転も実施しています。
(写真左:2023年4月に開催された署名式の様子、右:技術指導を行うJICA技術協力プロジェクト専門家)
オールジャパンとしての様々な取組
日本の取組は、日本NGO等の民間セクターからの協力も得て実施されています。ラオス北部のシェンクワン県では、日本NGOが日本企業からの協力を得て、不発弾処理機械を導入し、実際の運用や整備作業等の技術移転を実施しています。従来、不発弾が発見された場合には爆破処理することが基本でしたが、その処理のためには大量の火薬が必要であり、その分、費用がかかるという問題点がありました。一方、新たに導入される機械で不発弾を処理する場合には、こうした多額の費用は必要なく、限られた予算の中でも効果的な除去活動が可能になるという大きなメリットがあります。
また、同じくシェンクワン県では、主に子供を対象とした不発弾回避教育(MRE:Mine Risk Education)が実施されています。クラスター爆弾は、コンテナー(入れ物)の中に数個から数百個の子弾を含んでいて、投下されると、サッカー場の何面分もの面積にわたる広大な範囲に子弾をばらまきます。そのため、投下された地域にいる人は、軍人であれ民間人であれ、無差別に被害に遭ってしまいます(一般的に、被害者の98%が民間人であるとも言われています)。その中でも、特に被害に遭いやすいのが子供です。クラスター子弾は丸く小さい金属でできており、その見た目から子供が拾って投げたりすることによって爆発し、被害を受けるケースがあります。そこで、子供たちに不発弾の危険性を知ってもらい、不発弾を発見した場合の正しい対処法を教えることによって、こうした被害の軽減が期待されています。
(写真左:除去現場で活躍する不発弾処理機、中央:小学生に対する不発弾回避教育、右:不発弾回避教育のために開発された教材)
不発弾のないラオスを目指して

こうした厳しい課題を抱えるラオスですが、その中でも世界の不発弾や地雷除去をけん引する役割を果たしています。皆さんもSDGs(持続可能な開発目標)の存在を御存じだと思いますが、その目標はいくつあるか御存じでしょうか。正解は17ですが、実は、ラオスは独自に18番目の目標を設定しています。それが、「不発弾被害者の大幅な削減」です。
日本をはじめとした各国による取組によって、ラオス国内の不発弾除去活動は着実に進められており、その結果、不発弾被害者の数は、最も多かった2008年(事故発生件数186件、死者99名、負傷者203名)から、現在(2022年時点)では事故発生件数16件、死者5名、負傷者15名と、大幅に減少しています。その一方で、これまでに除去された不発弾の数は約170万個(8,000万個中の約2.1%)に過ぎません。LDCからの卒業を目指すとともに、クラスター弾禁止条約(オスロ条約:クラスター弾の生産、貯蔵、使用、移譲を禁止するとともに、締約国内に残存しているクラスター弾等を除去・廃棄することを義務づけ)の締結国であるラオスにとって、国内の不発弾を除去し、社会経済の発展につなげていくための取組は、今後も必要とされています。日本の取組が、ラオスにおける不発弾被害の予防、不発弾被害者の社会復帰、効果的な不発弾除去活動を通じた社会経済の発展につながっていくことを心から願っています。
(写真:SDGsゴール18)