ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第443号
海洋プラスチックごみ削減を目指す
アジアでの日本の国際協力について
世界的な関心の高まりを受け、日本は議長国を務めた2019年G20大阪サミットの際に、海洋プラスチックごみの追加的な汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を首脳間で共有し、国際的な議論を主導しました。世界の海洋プラスチックごみ問題の解決にあたっては、成長著しいアジア諸国からの排出をいかに食い止めるかが大きな課題であり、日本の経験や最新技術を伝え、現地の課題に沿った流出防止や廃棄物の収集・処分を手助けしていく必要があります。
そこで今回は、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)の上席主任調査研究員であり、JICAが途上国向けに実施する研修でも講師を務める小島道一さんに、アジア地域における廃棄物処理やリサイクルの状況と、この地域における海洋プラスチック削減対策における日本の取組や貢献について概説いただきます。また、日本が国連環境計画(UNEP)と連携して行う、アジア地域における海洋プラスチックごみ流出防止対策支援(CounterMEASURE)の現場から、最新技術を駆使してごみの流出実態の調査に貢献し、支援国への政策提言や対策の実施など問題の解決に繋げるべく尽力する、日本企業ピリカの取組について紹介します。
海洋プラスチック問題解決に重要な意味を持つ
アジアの発展途上国への協力
アジア経済研究所新領域研究センター 上席主任調査研究員 小島 道一
近年、海洋プラスチックごみの問題への関心が高まってきた。海に流出しているプラスチックが海洋の生態系に影響を与えていることが明らかになってきたからである。2019年に開催されたG20大阪サミットでは、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が首脳間で共有された。2020年7月から始まったレジ袋の有料化の背景にも、海洋プラスチックごみの問題がある。
プラスチックの海洋生態系への影響が、地球環境問題の一つとして認識され国際的に注目されるようになったのは、2012年以降である。きっかけの一つとして、地球環境ファシリティー(注1)の科学技術委員会が2011年11月にまとめた『地球環境問題としての海洋ゴミ:プラスチックに焦点をあてた問題解決のためのフレームワーク』(STAP 2011)という報告書がある。この報告書は、生物多様性条約の第11回締約国会議(2012年)に提出された。同締約国会議では、海洋ゴミの生態系への影響についての情報収集を事務局に求め、各国の取組を促す決議が採択されている。2014年から約2年おきに開催されている国連環境総会でも、毎回、海洋プラスチックごみの問題が主要議題の一つとなっている。
海プラを多く排出している、アジアの発展途上国の現状は?
 タイ・バンコク近郊にあるマングローブ林に溜まっているプラスチック類。2019年7月、筆者撮影。
タイ・バンコク近郊にあるマングローブ林に溜まっているプラスチック類。2019年7月、筆者撮影。
 フィリピン・マニラ湾の堤防わきに溜まっているゴミ。写真の右手に住宅地があり、そこからゴミを捨てに来る人もいた。
フィリピン・マニラ湾の堤防わきに溜まっているゴミ。写真の右手に住宅地があり、そこからゴミを捨てに来る人もいた。2020年1月、筆者撮影。
海洋プラスチックの主な排出源とみなされているのは、アジアの発展途上国である。
2015年にScience誌に発表された米国ジョージア大学のJambeck教授らによる論文では、海岸からの50キロメートル以内の人口、一人当たりの廃棄物発生量、廃棄物中のプラスチックの割合、不適切な処理がされている廃棄物の割合などを用いて、海洋へのプラスチックの流出量を推計したものである。1位中国、2位インドネシア、3位フィリピンなど、人口が多く、所得が上昇し、プラスチックの使用量が多くなってきた一方、廃棄物の収集や処分が十分にできていないアジアの発展途上国からの流出量が多いと推計されている。
2021年4月、Science Advances誌に発表されたMeijer et al.(2021)の論文では、河川ごとの流域人口、一人当たりの廃棄物発生量、廃棄物中のプラスチックの割合、不適切な処理がされている廃棄物の割合に加え、川の斜度や降水量をもとに、河川ごとの流出量を計算し、各国からのプラスチックの流出量を推計している。Jambeckらの研究と比較すると、流出量は、おおよそ1桁低い推計となっているが、1位フィリピン、2位インド、3位マレーシア、4位中国、5位インドネシアとなっている。どちらの推計もアジアの発展途上国が上位10か国中、8か国を占めている。
海洋プラスチックの流出量については、推計方法により幅があるが、海洋プラスチックが海洋生物に影響を与えていることが明らかとなってきている。例えば、2019年3月には、フィリピンのミンダナオ島で死亡したクジラを解剖したところ、胃の中から約40キログラムのプラスチックの袋が見つかり、栄養がとれず、餓死したと考えられている(文末関連サイト1参照)。また、2019年4月に、母親とはぐれていたジュゴンの赤ちゃんが保護されたが、8月に死亡し、解剖したところ、胃からプラスチックの袋や破片がみつかり、プラスチックの誤飲が死因となった可能性が高いという(文末関連サイト2参照)。
実際に、海岸沿いや川沿いを歩くと、プラスチックが海面や表面に浮いていたり、ポイ捨てされたりしている光景を目にすることが少なくない。
アジアの発展途上国の取組と日本の支援
 葉を使って、野菜を束にしている。ベトナム・ホーチミンのスーパーにて。2019年4月、筆者撮影。
葉を使って、野菜を束にしている。ベトナム・ホーチミンのスーパーにて。2019年4月、筆者撮影。
 紙製のストローとサトウキビで作られたマドラー。2019年4月、インドネシア、ジャカルタのレストランにて、筆者撮影。
紙製のストローとサトウキビで作られたマドラー。2019年4月、インドネシア、ジャカルタのレストランにて、筆者撮影。
海洋プラスチックの主たる排出源とみなされた国でも、廃プラスチックの海への流出を減少させようと、さまざまな取組が始まっている。日本と同様に、レジ袋の無償配布を禁止したり、生産者にプラスチック容器の回収やリサイクルの責任を負わせる拡大生産者責任の考え方を取り入れた法律を導入したりしている。また、自主的な取組も進んできており、スーパーが、レジ袋に生分解性のプラスチックを使っていたり、プラスチックの代わりにバナナの葉などを使って包装するといった取組が始まったりしている。
また、レストランでも、プラスチック製のストローやマドラー(英語では、stirrer)を植物由来のものに替えるといった取組も拡がってきている。
日本政府は、排出源とみなされているアジアの発展途上国、特に、東南アジア諸国への国際協力を進めている。インドネシア・ジャカルタにある国際機関である東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)に、ASEAN+3諸国(注2)海洋プラスチック対策に関するグット・プラクティスを集約・共有する「海洋プラスチックごみ地域ナレッジ・センター(Regional Knowledge Center for Marine Plastic Debris:略称RKC-MPD)」が2019年10月に開設された。各国の関連法令や計画、民間企業の取組などを紹介するウェブサイトが開設されている。
また、日・ASEAN統合基金(JAIF)の予算で、ASEAN諸国における海洋プラスチックに関する国家計画の策定支援に向けた調査が行われ、報告書が2020年にまとめられた。さらに、2021年には、国際協力機構(JICA)が、シンガポール政府と協力して、アジアの発展途上国および太平洋島嶼国を対象とした研修事業を立ち上げている。また、日本政府は、国連環境計画(UNEP)やアジア開発銀行などが実施しているアジア地域の海洋プラスチック対策関連事業にも資金面の支援などを実施してきている。
日本の責任と今後の貢献
 2019年7月21日にインドネシア・ジャカルタで48の市民団体が開催した海洋プラスチック問題への対応の必要性を訴えるイベントでの筆者。プラスチックごみなどを用いて作られたクジラのモニュメントの前で撮影。
2019年7月21日にインドネシア・ジャカルタで48の市民団体が開催した海洋プラスチック問題への対応の必要性を訴えるイベントでの筆者。プラスチックごみなどを用いて作られたクジラのモニュメントの前で撮影。
筆者は、日本貿易振興機構アジア経済研究所で、アジア地域の廃棄物・リサイクル分野について、政策や制度面から研究を行ってきた社会科学系の研究者である。2018年3月末からERIAに出向し、RKC-MPDの立ち上げに尽力した。また、海洋プラスチックに関するUNEPのCounterMEASUREプロジェクトの会合やASEANの海洋プラに関する行動フレームワークを策定する会議などにも参加し、情報提供、意見交換を行ってきた。2020年10月にアジア経済研究所に帰任したが、引き続き、RKC-MPDの事業にも携わっている。
海洋プラスチック問題については、マイクロプラスチックのモニタリング、プラスチックの生態系への影響、廃棄物の適正処理、リサイクル技術、プラスチックを代替する素材の開発など、理科系の分野での研究開発や技術移転が求められている。その一方で、海洋プラスチック問題の解決につながる技術や製品が使われるための、制度的な条件を整えていくうえで、社会科学分野の貢献も重要である。
例えば、多くの東南アジア諸国では、廃棄物の収集は、中小都市や農村にまで行き届いておらず、処理・処分が適切に実施できていない。日本では、1960年代後半から1970年代にかけて、複数の市町村が一部事務組合を作り、共同で廃棄物処理を行うことで、処理コストを抑え(注3)、人材を確保するといった取組が行われてきた。ERIAの事業として、日本、タイ、フィリピンなどの地方政府が共同で処理を行っている事例等を2020年にまとめた(Kojima(ed.)2020)。海洋プラスチック対策として、レジ袋などの使い捨てプラスチックの無償配布の禁止や生分解性のプラスチックの利用、リサイクルの促進などが進められようとしているが、農村にまでどのように廃棄物の収集、適正処分を拡げるかについては、あまり議論されていない。広域処理により、埋立処分場などの建設コストを抑えつつ、農村にまで廃棄物の収集サービスを拡げていく必要があることを、JICAの研修コースや国際会議での発表を通して伝えている。
国内での海洋プラスチック対策も重要であるが、日本は、協力対象国の課題を理解し、現地の課題にあった対策について、日本の経験を伝え、技術移転を進め、地球規模の課題である海洋プラスチック問題を一緒に解決していく必要がある。
- 著者略歴:
- 1990年慶応義塾大学経済学部卒業。アジア経済研究所入所。1997年カリフォルニア大学バークレー校農業資源経済学科修士。2018年3月~2020年9月、東アジア・アセアン経済研究センターへ出向。現在、日本貿易振興機構アジア経済研究所上席主任研究員。アジアにおけるリサイクル、海洋プラスチック問題等を研究。
- (注1)開発途上国及び市場経済移行国が、地球規模の環境問題に対応するための資金メカニズム。日本は主たる出資国の一つ。
- (注2)ASEAN+3:ASEANの10か国および中国・日本・韓国。
- (注3)廃棄物の埋立処分場や廃棄物の焼却発電施設の建設については、規模の経済が働くことが知られている。
- <参考文献>
- Jambeck, J.R. , R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, and K. L. Law, (2015) “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean,” Science, Vol. 347, No. 6223, pp. 768–771
STAP (2011). Marine Debris as a Global Environmental Problem: Introducing a Solutions Based Framework Focused on Plastic, Global Environment Facility, Washington, DC.
Meijer, Lourens J. J., Tim van Emmerik, Ruud van der Ent, Christian Schmidt, and Laurent Lebreton “More than 1000 Rivers Account for 80% of Global Riverine Plastic Emissions into the Ocean” Science Advances, Vol. 7, April 30, 2021.
Kojima, M. (ed.) (Regional Waste Management – Inter-municipal Cooperation and Public and Private Partnership)
アジアのマイクロプラスチックを集めて分析!
海洋プラスチックごみ流出防止に貢献する日本企業の最新技術
一般社団法人/株式会社ピリカ 杉浦菜月・井上慎也
現在、非常に意識が高まりつつある「マイクロプラスチック」(直径5ミリメートル未満のプラスチック)問題。これに取り組むべく、我々ピリカは、独自の技術「アルバトロス7」を用いて海洋プラスチック流出経路の特定・追跡に取り組んでいます。この技術は現在、日本政府と国連環境計画(UNEP)による連携プロジェクト「CounterMEASURE」におけるプラスチックごみ流出実態調査のために使われています。
CounterMEASUREとは、アジア(特にメコン川ならびにガンジス川)におけるプラスチック流出の経路/実態を調査するため立ち上げられた、日本政府とUNEPの連携プロジェクトです。GIS(地理情報システム)/機械学習/ドローンなどのテクノロジーを用い、アジア6か国におけるプラスチック流出モデルの構築に取り組んでいます。
2020年にはCounterMEASURE 1が実施され、得られた成果は各国政府への政策提言として活用されました。今年2021年のCounterMEASURE 2では、1で行った試みの規模を拡大し、河川域でのプラスチック流出対策の成功例として他の河川域でも展開することを目指しています。この中で「アルバトロス7」は、流出実態を調査するためマイクロプラスチックのサンプリング手法として採用されています(CounterMEASUREの公式サイト )。
)。
マイクロプラスチック調査を強力に推進
日本の技術を集約した「アルバトロス7」
 マイクロプラスチック採取装置「アルバトロス7」の仕組み
マイクロプラスチック採取装置「アルバトロス7」の仕組み
 採取されたサンプルを顕微鏡で画像撮影
採取されたサンプルを顕微鏡で画像撮影
従来、マイクロプラスチックの調査のためには、船の後ろに網をくくりつけて牽引するという手法が主流でしたが、高コストな上、浅く狭い川では調査ができない等の難点がありました。そこでピリカは、安価かつ手に入れやすい素材で作られた、ピリカ独自のマイクロプラスチック採取装置「アルバトロス7」を開発しました。
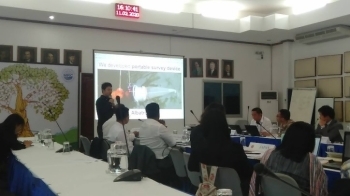 2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1ワークショップで、ピリカ代表の小嶌によるマイクロプラスチック調査に関するプレゼンテーションが行われた。
2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1ワークショップで、ピリカ代表の小嶌によるマイクロプラスチック調査に関するプレゼンテーションが行われた。
 2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1の報道機関関係者を招いてのメディアツアーにて。ピリカ代表小嶌がアルバトロスを使用してサンプリングを行っている。
2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1の報道機関関係者を招いてのメディアツアーにて。ピリカ代表小嶌がアルバトロスを使用してサンプリングを行っている。
調査したい河川・水路の水面付近にアルバトロス7を浮かべ、3分間採取を行います。バッテリー駆動のスクリューで水をネットに流し込み、水中のプラスチック粒子を採取、集められたサンプルは後ほど分析にかけられます(ピリカ独自技術「アルバトロス7」の仕組み(流出抑止のためのマイクロプラスチック調査サービス) )。
)。
これにより、調査が低コストになり、かつトレーニングを受けた人なら誰でもプラスチック粒子の採取ができるようになりました。CounterMEASUREでも、実際に現地パートナー(タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム)が使って調査を実施しています。
 2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1でアルバトロスを使用しての調査風景。ラオス国立大学スタッフとピリカのスタッフが調査を実施している。
2020年ラオス・ビエンチャンにおけるCounterMEASURE 1でアルバトロスを使用しての調査風景。ラオス国立大学スタッフとピリカのスタッフが調査を実施している。
 東はラオス、南はカンボジアに接するムーン川に沿ったタイ最東部の都市ウボンラチャタニでの調査風景。トレーニングを受けた現地パートナーによってアルバトロスが活用されている。
東はラオス、南はカンボジアに接するムーン川に沿ったタイ最東部の都市ウボンラチャタニでの調査風景。トレーニングを受けた現地パートナーによってアルバトロスが活用されている。
CounterMeasure 1に参加したピリカ隊員が
現地にて思うこと
 ビルやモダンな建物が立ち並ぶプノンペンの光景
ビルやモダンな建物が立ち並ぶプノンペンの光景
CounterMEASURE 1ではタイ、ベトナム、ラオス、カンボジアを訪問し、現地の人々と共にアルバトロスを使用してマイクロプラスチック調査を行いました。プラスチック流出問題は、特に東南アジアにおいて今後優先的に取り組まれるべき問題であり、日本はそこに数多くの貢献ができると確信しています。
現地では東南アジアの急速な発展を実感しました。カンボジアのプノンペンを訪問した際、現地パートナーの一人が夕食に誘ってくれ、日本にあるものより巨大で、綺麗なショッピングモールへ足を運びました。そこには日本発の飲食店や海外チェーン店が立ち並んでおり、高層ビルや綺麗なカフェなどの夜景が見え、日本とあまり変わりありませんでした。その晩は、「近年の東南アジアの発展を考えると、あと数十年すれば東京よりも大都会が広がっているのかもしれない」と思いを巡らせていました。
 河川沿いに投棄されたプラスチックごみ
河川沿いに投棄されたプラスチックごみ
 街中の用水路に溢れたプラスチックごみ
街中の用水路に溢れたプラスチックごみ
しかし翌日、街中を散策していた際、大量のプラスチックごみを目の当たりにし、今後都市が発展するに伴いプラスチック問題はより深刻になると感じました。日本は、技術や知見の観点から活かせることは数多くあります。既存の技術はもちろんのこと、近年発展している新しいテクノロジーなどを使い、現地に即した新しい問題解決の方法を見つけていくことが必要だと活動を通じて考えるようになりました。
ピリカの目指す、プラスチックごみ解決への道すじとは?
弊団体は、様々な環境問題の中でも一歩目としてごみ(特にプラスチック)の自然界流出問題に注力しています。ごみ拾いSNS「ピリカ」、画像解析技術による広範囲のポイ捨て状況調査サービス「タカノメ」、マイクロプラスチック調査サービス「アルバトロス」を通じて、海洋・陸のごみの流出状況をオープンデータで発表し、課題発見と解決に向けた協業・連携を展開しています。2021年には環境スタートアップ大臣賞を受賞しました。
CounterMEASUREではマイクロプラスチック調査から得られた結果をもとに水域へのプラスチック流出源の推定を目指しています。今回、乾季におけるサンプリングを実施しましたが次は雨季に実施する予定です。その他にもマクロプラスチックごみの調査も実施しており、それらの結果を組み合わせ、流出源を推定していく計画です。
今後、海洋プラスチック問題やマイクロプラスチック問題の解決に向けて、世界各地で今まで以上の調査が行われていくと考えられます。ピリカも多くのパートナーと協力し世界中で調査の実施やデータの蓄積を行なっていきたいと考えています。その結果を用いて政策提言や対策の実施など問題の解決に貢献していきたいと考えています。

