ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第406号
対アフリカ民間投資促進へ
前回の2倍を超える日本企業の参加を集めたTICAD7
外務省 TICAD事務局
2019年8月28から30日,横浜で第7回アフリカ開発会議(TICAD7:ティカッドセブン)が開催され,今後更なる対アフリカ民間投資の促進に取り組むことを表明し,安定した貿易・投資環境実現に向けて努力することを盛り込んだ「横浜宣言2019」が採択されました。TICAD7では,TICADVIの2倍を超える企業が参加し,TICAD史上初めて民間企業を公式なパートナーとして位置づけました。
 開会式にてあいさつをする安倍総理
開会式にてあいさつをする安倍総理
 官民ビジネスセッションの様子
官民ビジネスセッションの様子 共同記者会見後,エルシーシ・エジプト大統領(AU議長)
共同記者会見後,エルシーシ・エジプト大統領(AU議長)
と握手する安倍総理
7回目の開催となる今回のTICAD(Tokyo International Conference on African Development)には,42名の首脳級を含むアフリカ53か国,52か国の開発パートナー諸国,108の国際機関および地域機関の代表,並びに民間セクターやNGO等市民社会の代表等,10,000名以上が参加しました。安倍総理大臣は,エルシーシ・エジプト大統領(AU議長)と共に共同議長を務めました。
今回テーマの「アフリカに躍進を!ひと,技術,イノベーションで。」のもと,民間投資促進,アフリカ各国における雇用の創出や技術移転等の促進にスポットを当て,本会議においては,ビジネス促進が議論の中心になりました。
安倍総理は過去3年間で200億ドル規模だった対アフリカ民間投資が今後更に大きくなるよう,日本政府として全力を尽す旨表明しました。日本の民間からは前回の2倍を超える企業が参加し,TICAD史上初めて,民間企業を公式なパートナーと位置づけ,本会合にて日アフリカ官民の直接対話を実施しました。また,安倍総理は,31日までの間に,42か国の首脳級参加者及びAU委員長,3つの国際機関の代表並びに1名の個人招待者と47回,河野外務大臣は,アフリカ諸国の閣僚や国際機関代表等と25回の二国間会談を実施しました。
会議の閉会式では,「横浜宣言2019」を採択し,「横浜行動計画2019」をその付属文書として発表しています。TICAD7の概要,日本の取り組み,横浜宣言の概要については,以下のURLをご参照ください。
【ホストシティの取組】
TICAD7の開催都市の横浜市では,総理・横浜市長共催歓迎レセプションを始め,会期中にも多くのイベント等が開催されました。
 総理・横浜市長共催歓迎レセプション
総理・横浜市長共催歓迎レセプション
 横浜市内の小学生によるアフリカ各国首脳お迎え
横浜市内の小学生によるアフリカ各国首脳お迎え
(写真提供:横浜市) コートジボワール共和国アマドゥ・ゴン・クリバリ首相
コートジボワール共和国アマドゥ・ゴン・クリバリ首相
による横浜市会本会議場での演説
(写真提供:横浜市)
多くのアフリカの首脳,開発パートナー諸国,国際機関及び地域機関の代表,また民間セクターやNGO等市民社会の代表等,10,000名以上が参加し,大成功に終わったTICAD7。読者の皆様もぜひTICAD7以降の日アフリカ関係にご注目いただけると幸いです。次回TICAD8は,2022年アフリカで開催の予定です。
(外務省ホームページのTICAD7関連はこちら)
ケニアの難民キャンプから平和共生を目指して
原稿執筆:ピースウィンズ・ジャパン ケニア事業担当者一同
ケニアはサファリツアーが人気で外国から多くの観光客が訪れる国です。その一方,周辺国のソマリア,南スーダンなどからの難民を30年程前から受け入れている国でもあります。ケニア東部のソマリアとの国境に近いダダーブ難民キャンプでは,今もなお約20万人もの難民たちが祖国を離れて暮らしています。
国際協力NGOのピースウィンズ・ジャパンがダダーブに事務所を開設したのは2012年2月。当時は60年に一度といわれるほどの深刻な干ばつの影響で,主に隣国のソマリアから45万人を超す難民が押し寄せていた時期でした。難民キャンプ内の家は,屋根がプラスティックシートで雨漏りする,強盗・動物に襲われる危険性もある,子どもが風邪や伝染病にかかりやすいなど,多くの問題を抱えていました。
 難民の人たちが住んでいる一般的な家
難民の人たちが住んでいる一般的な家
私たちは難民の住環境を改善するために日本政府のNGO連携無償資金等を活用し,2018年12月までに約14,000軒の仮設住宅を建設しました。この成果が認められたのか,難民の人たちから「日本の支援は公平で迅速」,「日本の皆さんに感謝しています」などの言葉をいただけるようになりました。裨益者世帯の中には,壁のプラスティックシートをカモラや鉄板へと変更したり,壁装飾やベランダ作りで工夫したりするなど,より快適な住環境に自ら改良する事例が多く見られ,持続的な住環境改善が期待されます。カモラとは,ケニアで生息している低木で,住宅の壁資材としてよく使われる材木です。切断後ロバ馬車で運び,縦横に編みこんで壁にします。通気性が良く,気温の高いダダーブでは好んで使用されます。
 提供された仮設住宅の前で記念撮影に応じる裨益者家族
提供された仮設住宅の前で記念撮影に応じる裨益者家族 カモラを用いて装飾した住宅
カモラを用いて装飾した住宅
一方,この難民キャンプ周辺地域はケニアでも最貧困地域の一つとされており,就学率も他の地域と比べて低く,若者の失業率も高い状況です。そのため,地元住民の中には国際社会からの支援が難民に集中することを快く思わない人も多く,難民と地元住民との間で軋轢が生まれるようになりました。この「見えない壁」を取り除くために,仮設住宅建設のプロジェクトに加え,2017年から地元の若者たちへの生計向上支援を始めました。ダダーブは建物建設などに使用する土ブロック製造に適した赤土に恵まれていることから,ブロック製造訓練を地元の若者約100名を対象に開始しました。さらに,この若者たちがこのブロックを販売するなどのビジネスへと展開できるよう起業支援を展開し,今では住民からブロックの発注を受けるグループも出てきました。
 土ブロックの製造に励む地元の若者たち
土ブロックの製造に励む地元の若者たち 出来上がった土ブロック(凹凸を利用して積み上げるため,
出来上がった土ブロック(凹凸を利用して積み上げるため,
ブロックとブロックの間の隙間をセメントで埋める必要がない)
 ブロックを利用して建設された小学校の教室
ブロックを利用して建設された小学校の教室
ダダーブ難民キャンプとその周辺地域への支援,そして双方を繋いでいく機会を作ることによって,「見えない壁」が低くなっていけば,地域の平和が促進され,難民と地元住民が自ら共生の道を探ることも期待されます。私たちはこれからも地域の平和を目指して,人びとの後押しをする活動を継続していきます。
- 国際協力NGOピースウィンズ・ジャパンホームページ
ODAでも活躍する日本のNPO法人「道普請人(みちぶしんびと)」
土のうを使って,道直しと人材育成を支援する
原稿執筆:NPO「道普請人」福林良典・岩村由香
道はインフラの基本。開発途上国の農村部や地方では,学校,病院,市場に続く生活道路の状態が悪く,雨季には通れないことが多いのです。そこで,認定NPO法人「道普請人(Community Road Empowerment:通称CORE)」は,現地材料と人力で補修可能な「土のう」を使った道路整備手法の技術移転を行っています。
道普請人では,日本でも洪水などの災害の時に頼りとなる,「土のう」も使いながら世界27か国,累計175kmの補修を行ってきました。これは東京から静岡くらいの距離にあたります。ミャンマー,パプアニューギニア,ケニア,ブルキナファソ,ルワンダ,ウガンダの6か国では,ODA資金を使った外務省の日本NGO連携無償資金協力プロジェクト(以下N連プロジェクト)も実施してきました。この活動を通じて,現地の人々の中に「自分たちの道は自分たちで直す」という意識が芽生え,生活道路が改善され貧困削減につながります。道普請人では,この点をふまえ,地元の人への訓練も同時に進めた結果,その訓練者数は1万6,000人以上に達しました。
 息を合わせた土のう袋の締固め(ケニア)
息を合わせた土のう袋の締固め(ケニア) 「自分たちの道は自分たちで直す」という意気込
「自分たちの道は自分たちで直す」という意気込
みの伝わる作業風景(ケニア)
ウガンダからの現場報告(COREウガンダ事務所の岩村より)
道直しと訓練はこうして進むのです
2019年2月に首都のカンパラに事務所を開設し,現在日本人1人,現地職員6人の体制で活動しています。ウガンダの道路舗装率は1割以下でしかありません。このN連プロジェクト1期目の事業ではウガンダ中央部で150人への道直し訓練と若者の雇用創出に加え,政府との工法標準化や公立訓練校での土のうカリキュラム化も視野に入れ動いています。2期目以降は西部や東部へも戦略的に活動地域を広げていきたいと考えています。
道直しはどのような流れで行われるのでしょうか。まず,道路事業を担当する公共事業省などとの話し合いから道路状況の著しく悪い地域を割り出します。それから実際に該当地域にサンプル道路の調査に赴き,ニーズを確かめます。我々の活動は地域に主体性を持たせることを重要視しているため,実際に施工する道路や,訓練に参加する若者グループは,コミュニティ主導で選定してもらいます。選定された道路の視察をし,各道路の施工デザインに県政府からの承認を得られてから施工が可能となります。
COREウガンダの土のう訓練は,だいたい10日間ほど,1グループは25人から30人で行われます。まずは1日みっちりと理論の座学から始めます。座学では土のう工法の工程説明,基本的な道路維持管理手法や排水整備の勉強会,効率的な集団行動や起業に関するビジネス・スキル研修など多くの分野をカバーします。
 訓練初日の座学後に簡易テストが行われました。(カンパラ)
訓練初日の座学後に簡易テストが行われました。(カンパラ)
訓練生には安全対策グッズ(COREのロゴ付き安全ベストや手袋,防塵マスク,長靴)を支給し,いよいよ現場での実践に移ります。
 チェバンド道路における排水溝の設置(カンパラ)
チェバンド道路における排水溝の設置(カンパラ) 土のうを敷設し締固め,表層土で覆う作業中(カンパラ)
土のうを敷設し締固め,表層土で覆う作業中(カンパラ)
50メートルから300メートルなど距離はさまざまですが,訓練生である若者や農民に工法を教えながら,選定された道路の補修をします。沿線の草刈り,要補修部の掘削,土のう作成と敷設,20回の締固め,表層土を被せ,さらに締固めします。土のうを適切に締固めることで,コンクリートのように固くなるのです。同時に側溝の整備を行い,雨水により道路が簡単に泥沼化しないようにします。必要に応じて排水溝を設置したりします。道路状況はさまざまですので,エンジニアがアセスメントを行い,補修法を決定していきます。
 カリバ1道路の補修前の状況。雨が降ると水がたまり,
カリバ1道路の補修前の状況。雨が降ると水がたまり,
よけて通らなければなりませんでした。(カンパラ) 土のうを使った補修後の様子。水はけをよくするため,
土のうを使った補修後の様子。水はけをよくするため,
排水溝も作りました。(カンパラ)
ウガンダN連プロジェクト初年度となる今年は,対外広報にも力を入れています。訓練完了後には,在ウガンダ日本大使館,県政府高官,メディアを招いて訓練修了式を実施します。ほんの短期の訓練ですが,この修了証,県政府のお墨付きがあるため,将来的に起業した若者グループが小規模公共事業に参画する際に役に立つのです。式典の最後にテープカットにて道路が公式開通し,新しい土のう道の仲間入りです。
 亀田和明在ウガンダ日本大使より,訓練生
亀田和明在ウガンダ日本大使より,訓練生
一人ひとりに修了書の授与が行われた。
(ウガンダ) 喜びに沸く沿線住民とともに道路開通式が行われた。
喜びに沸く沿線住民とともに道路開通式が行われた。
(ウガンダ)
現場での苦労とやりがい。道路づくりを国レベルに推進できるよう,交渉開始
土のう工法の認知は平坦な道のりではありませんでした。道路行政官は施工距離にこだわります。土のう工法は,問題箇所の部分施工を得意とし,地域住民を道路の維持管理の担い手にする事業であることを説明する必要がありました。そこで,簡単なデモンストレーションを行ったり,すでに完成した施工箇所を見てもらうことでやっと納得してもらえました。さらに,ウガンダでは地方分権化が進み,日本の約3倍,130にのぼる県が存在します。後で「聞いていない」と言われないように,新しい地域で事業を始める際は,たくさんの人に挨拶・説明をしなければならず大変です。また国勢調査やセクター分析がしっかり整備されていないため,データ収集には毎度苦労が伴います。
また,住民の理解を得ることも課題でした。訓練開始直後,道行く人は懐疑的な目で見つめてきます。「インチキ集団がおかしなことを始めた,機械を使わずに道路が直るわけがない」が,道路完成の頃には一転,「道を良くしてくれてありがとう」に変わりました。「簡単な人力施工でも道が直る」と実感してもらえた時,一番やりがいを感じました。
私たちの活動は,土のう訓練だけではありません。広いウガンダで土のう工法のような簡便な道路維持管理手法を迅速に普及させるには,公共機関との協働が必要です。そこで現在,ウガンダで労働集約的な道路維持管理手法の研修を行う唯一の公的機関であるMELTC(通称メルテック)に土のう工法をカリキュラムとして取り入れるよう,交渉中です。正式に土のう工法がカリキュラムに組み込まれた暁には中央政府からの工法承認を狙っています。土のう工法が道路維持管理マニュアルに掲載され,土のう工法を用いた公共事業の発注が可能となる日を待ちわびています。
 カリキュラム化実現のため,MELTC講師を
カリキュラム化実現のため,MELTC講師を
対象とした土のう工法の講義(ウガンダ)
(MELTC=Mt. Elgon Labour-Based Training Centre) 訓練実施中はなるべく現場に出るようにしていま
訓練実施中はなるべく現場に出るようにしていま
す。カブンバ若者グループのメンバーとともに。
(ウガンダ)
ケニアで訓練修了生がビジネスを開始。公共事業を受注する企業に成長へ
ケニアでは2011年から6年間,N連プロジェクトを実施しました。土のう「“Do-nou”」で道が直るという声は瞬く間に広がり,今ではケニアの運輸・インフラ省で「“Do-nou”」を知らない人はいなくなりました。また,第2期の3年間は「住民へのチャリティーから住民のビジネスへ」という活動方針でプロジェクトが行われ,訓練を終えた若者が建設会社を立ち上げました。在ケニア日本大使館のサポートと道普請人の提案により,ケニア政府は数百人の若者の技能訓練費約5千万円を拠出しました。地方に住み,何のスキルもなかった若者が会社の社長になり,政府の入札に参加したり公共事業を依頼されたり,周囲の若者に雇用を生み出すという夢物語が少しずつ形になりました。採石場で日当200円を得ていた若者が,数百万円の公共事業を受注した日には,一同感動しました。
 運輸・インフラ省高官らへの土のう普及デモ(ケニア)
運輸・インフラ省高官らへの土のう普及デモ(ケニア)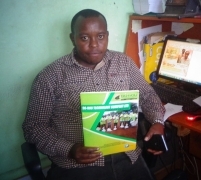 起業後,成功を収める土のう訓練生(ケニア)
起業後,成功を収める土のう訓練生(ケニア)
開発途上国の人々の生活道路の通行性を向上させ,くらしを豊かにすることに貢献したいという草の根の活動は,2007年12月のNPO法人設立から,事業ベースで本格的に始まりました。日本人職員も増えODAでも取り上げていただき,相手国行政,現地で研修を受けたスタッフ,地元の住民ら多くの人を巻き込んで,道直しとそれを通した人材育成へと展開しています。これまで培った経験と育成してきた人材を活かし,さまざまな国でより多くの人々のくらしの豊かさを目指して,活動していきます。





