ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第404号
TICAD7開催迫る!
日本とアフリカ,官民連携で関係強化をめざす
原稿執筆:外務省 TICAD事務局
TICAD初 ビジネス促進に向け,日本とアフリカの官民が一同に集結
第7回アフリカ開発会議(TICAD7:ティカッドセブン)は,いよいよ5日後の8月28日(水曜日)に開会します。TICAD7では,アフリカへの民間投資の促進や技術移転が大きなテーマとして挙げられており,ビジネスの分野では,TICAD7の全体会合において,日・アフリカ双方の官民が一堂に会してTICAD初となるビジネス関連の会合が開催される予定です。対アフリカ投資促進に向けた日本の官民連携の取組をアフリカ側に紹介し,アフリカの官民と建設的な対話を行います。
TICAD7の期間中,他にも以下のようなイベントが予定されています。
ビジネスで日本とアフリカをつなぐ
「日本・アフリカ ビジネスEXPO」を開催
日本貿易振興機構(JETRO)は,TICAD7会期中の8月28日から30日に,日本とアフリカ各国との貿易・投資の促進に向け,TICAD7の公式サイドイベントとして「日本・アフリカ・ビジネスEXPO」を開催します。日本企業等による製品,技術,サービスの展示紹介を行う「ジャパン・フェア」と,アフリカビジネスに関心を持つ日本のビジネスパーソン等を対象にアフリカの投資環境紹介や多角的な交流の機会を提供する「アフリカラウンジ」,アフリカ35か国によるテーマ別セミナーやアフリカで活躍する日本企業によるセミナーを開催する「イベントステージ」で構成されています。
技術で日本とアフリカをつなぐ
都市のゴミ問題解決のための研修を実施
8月26日(月曜日),27日(火曜日)には,JICA,環境省,横浜市等が主催するサイドイベント「アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP)」が開催される予定です。ACCPは,2030年までにアフリカ諸国がきれいな街と健康な暮らしを実現し,廃棄物管理に関するSDGsを促進するためのプラットフォームで,2017年4月に設立され,アフリカ35か国,64都市が参加しています。これまでに,アフリカ各国に向けた「廃棄物管理研修」を実施してきており,横浜市はこれまでの知見・経験や先進的な技術が評価され,この研修の拠点として位置づけられています。
 開講式
開講式 焼却工場視察の様子
焼却工場視察の様子
これに加え,8月27日から30日の4日間,パシフィコ横浜において,TICAD7公式サイドイベントが開催されます。公式サイドイベントは,一般の方にも公開され,アフリカに関する理解を深めるとともに意見交換の場を提供するものです。セミナー・シンポジウムおよびブース・パネル展示の2つの形態があり,国際機関,大学,研究機関,NGO(市民社会)等が実施します。これらのサイドイベントでは,保健,教育,ビジネス,IT等,アフリカ開発に関わる多岐にわたる分野が取り上げられる予定です。サイドイベントについては,事前予約が必要なものもありますので,各イベントの主催者にお問い合わせください。
こうしたさまざまなイベントが実施されるTICAD7。横浜でアフリカとのつながりを切り開いてください。
TICAD7を控えた今,一人でも多くの方に日本とアフリカの繋がりを知っていただき,アフリカを身近に感じていただくべく,人気アニメ「秘密結社 鷹の爪団」の主人公吉田くんの,新作動画が公開されました。
- 動画:「アフリカビジネスでWin-Winの巻
 」
」
これまでのTICAD7に関するバックナンバーも,ぜひご覧ください。
- 4月26日第396号 第7回アフリカ開発会議(TICAD7)を8月に横浜で開催
- 8月9日第403号 TICAD7開催近づく「ひと,技術,イノベーション」でアフリカ開発を後押し
ABEイニシアティブ
「アフリカをより身近に感じて,ビジネスチャンスをつかもう!」
外務省 国際協力局 国別開発協力第三課
日本からは物理的に遠いアフリカ。
「アフリカで自社製品のニーズはあるのだろうか」
「アフリカ人のビジネスパートナーはどうやって探せばいいのだろうか」
アフリカでのビジネスに関心はあっても,アフリカ大陸に簡単には行くことができず得られる情報も限られている中で,はじめの一歩を踏み出すには覚悟がいるものです。
ABEイニシアティブは,日本企業がアフリカに進出する際の水先案内人を担える人材を育成するプログラムです。このプログラムでは,アフリカの若者を日本に招き,日本の大学院で専門性を身に付けてもらうとともに,日本企業でのインターンの経験を通じて日本の企業文化を学んでもらいます。
2014年に受入れを開始して,これまでにアフリカ54か国から1200人以上の若者を受け入れています。各国および各大学での厳しい選考を通過して来日した彼らは,寝る間も惜しんで日々勉学に励む優秀な学生たちです。学生と言っても,母国では政府機関で働いていたり民間企業での就労経験があったり大学講師をしていたりとさまざまなバックグラウンドを持っています。
 映像制作等を手掛ける企業にて,日本文化についての
映像制作等を手掛ける企業にて,日本文化についての
ドキュメンタリー制作に取り組む様子 日本のモノづくりの心を体感する
日本のモノづくりの心を体感する
アフリカの学生
 大阪にある中小企業の現場では,日本人の丁寧できめ細やかな
大阪にある中小企業の現場では,日本人の丁寧できめ細やかな
実技指導を受けながら,技術や経営を熱心に学んでいます
情報通信事業等に力を入れている愛媛県の企業,株式会社フェローシステムは,人の縁を大事にしたい,困っている人を助けたいという気持ちから,大学院の夏期休暇中に行う2週間程度のインターン制度を活用し,これまでにアフリカ各国からたくさんの学生を受け入れました。インターンシップに参加したマラウイ出身の学生たちは,同社がマラウイでの事業展開を予定していると知り,オフィスを開設するに当たって必要となる情報を提供するなど,ビジネスが円滑に進むようサポートをした結果,同社はマラウイで現地法人を設立するに至りました。元々マラウイと縁があり,アフリカに対しても不安やマイナスなイメージは持っていなかった同社は,さまざまな国からインターンを受け入れその国の生の情報に触れたことで視野が広がり,現在はマラウイ以外の国でも支社をオープンすることも検討しており,今後もABEイニシアティブを活用してアフリカビジネスを成長させたいと考えているようです。
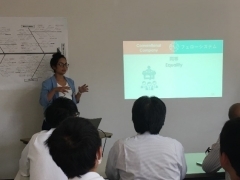 社員に対してインターンシップで学んだことを
社員に対してインターンシップで学んだことを
報告している様子(写真提供:フェローシステム) インターンシップ最終日に手渡された修了証書には
インターンシップ最終日に手渡された修了証書には
「縁」の文字が…!(写真提供:フェローシステム)
母国の保健省で働いていたモザンビーク出身のリンドさんは,大学院でグローバルヘルスを学び,修士課程修了後には臨床検査事業等を行う株式会社保健科学研究所で6か月のインターンを経験しました。この出会いをきっかけに同社はアフリカでのビジネスに関心を持ち,今後は医療の整備に貢献できるような事業として,健診事業や検査キットの普及事業を検討していると語ってくれました。インターンシップを通じて,高生産性,品質管理,顧客へのフィードバックやフォローアップ,同僚とどのように関係を構築するかなど,日本企業での働き方を身に付けたリンドさんは,同社が医療保健の分野でアフリカへ進出する際のパートナーとしての活躍が期待されています。
 所属先の保健省や日本大使館など,現地関係者に向けた帰国報告会で
所属先の保健省や日本大使館など,現地関係者に向けた帰国報告会で
日本での生活を振り返るリンドさん
日本の商習慣を身に付け,母国で幅広いネットワークを持ち,「母国と日本の架け橋になりたい」と話すABEイニシアティブの学生たち。地球最後のフロンティアと言われるアフリカの国々には,輝かしい可能性が秘められています!
ナイジェリア北東部に安定と復興を!
国連開発計画(UNDP)と行う,日本の紛争被害地域支援について
中野美緒(在ナイジェリア日本国大使館 草の根・人間の安全保障無償資金協力 外部委嘱員)
野口義明(国連開発計画(UNDP)ナイジェリア事務所 プロジェクト・マネージャー)
突然の襲撃,平穏な生活を奪われた人々
2014年,ナイジェリア北東部に位置するングウォム村では,突然の襲撃により村人2,500人全員が緊急避難しました。平和な地域を襲ったのはイスラム過激派組織ボコ・ハラムのテロ活動です。村は破壊され,住める場所ではなくなってしまいました。村の住民は突如として電気も水も使えなくなり,教育や就業の機会を奪われ,避難キャンプや近隣の村(ホスト・コミュニティ)での生活を余儀なくされました。このような襲撃は北東部一帯で継続して起こり,現在でも180万人の人々が避難生活を強いられています。
 ナイジェリア北東部(オレンジ部分),ングウォム村
ナイジェリア北東部(オレンジ部分),ングウォム村 襲撃により破壊され,廃墟となったングウォム村
襲撃により破壊され,廃墟となったングウォム村
緊急事態に対応せよ! 復興支援を経て3年かけて「元の生活」へ
この深刻な人道危機に対応するため,日本は国連開発計画(UNDP)を通して支援を開始。現在は破壊された地域を元のように安心して住めるように「ナイジェリア北東部における統合されたコミュニティー安定化支援」プロジェクトを実施しています。
このプログラムにより,紛争被害地域において,小学校・医療施設・井戸など20以上の公共施設,300世帯分の住居の再建を実現しました。再建の際には,避難民や帰還民を中心に3,000人以上を雇用しました。国際社会による被害者支援だけでなく,地域住民も共同で復興作業を進めてきたのです。
その結果,冒頭で述べたングウォム村では,2,000人以上の村人が故郷に帰り,元の生活を送ることができるようになりました。村が復興することで国際機関による人道支援事業の負担が減り,再建された学校や医療施設で提供されるサービスの質の確保のために国際人道支援機関と村が協力するなど,プロジェクトは人道支援と開発支援の同時進行となっています。
 廃墟だった村で避難民たちが再建を進めている
廃墟だった村で避難民たちが再建を進めている 支援により再建された井戸の前で。
支援により再建された井戸の前で。
村人約3,000人分の水の供給が回復した(ロコ村)
日本の支援に呼応し,パナソニック株式会社は企業市民活動の一環として,900台のソーラーランタンをングウォム村をはじめとした復興途上の村々に提供しました。被害地域ではほとんどの家庭や公共施設で明かりのない生活が続いていましたが,昼間にソーラーランタンを太陽光で充電し,夜間でも明かりのある暮らしができるようになりました。おかげで女性の夜間の安全確保や,子どもたちも夜間の勉強ができるようになったり,携帯電話の充電が可能となり,親戚に連絡が取れるようになりました。まさに,日本政府と企業がタッグを組み,オールジャパンでの支援の取組となったのです。
また,公共施設の再建により,避難先から村に戻った人々には,UNDPから作物のタネ,肥料,農薬,クワ,発動機付ポンプなどが贈られました。ポンプが贈られた住民は「これで川からの水を汲み上げ,農業を再開できます」,「村に戻っても,逃げた時に農機具は全てなくしてしまい,種や肥料を買う資金もありませんでした。頂いた支援のお蔭で今年の雨季から3年ぶりに農業を再開できます。大変ありがたい」と大喜びです。避難生活から故郷に戻り,以前は「当たり前」だった生活を再開できる喜びは計り知れません。
 地域住民に日本の企業からの支援によるソーラーランタンが
地域住民に日本の企業からの支援によるソーラーランタンが
受け渡され,アダマワ州危機対応局事務次官,横井UNDPナ
イジェリア北東部支所長,菊田ナイジェリア大使などが出席
した(写真提供:在ナイジェリア日本大使館) 灌漑農業に必要な発動機付ポンプを住民に贈る
灌漑農業に必要な発動機付ポンプを住民に贈る
野口UNDPプロジェクト・マネージャー
これからも続くUNDPと日本の支援,広島の教訓を活かした復興支援も
UNDPでは,各州政府の組織と連携して,農業関連の機材の供与だけでなく,1,200世帯以上の農家を対象に,農業普及員による技術指導が受けられる体制を構築しました。それまで各農家では個人的な経験だけに頼って作業の方法を決めていましたが,この指導によって,肥料の使い方や,種まきの際の種の間隔の決め方など,多くの事例に基づく効果的な手法を学び,実践するようになりました。その結果,面積当たりの収穫量を最大で2倍に増やすことができたのです。
さらに,新しい生活を始めるためには小規模ビジネスのスキルも必要です。UNDPは400名以上の避難民および帰還民に対して,3か月間の職業訓練を行いました。地域の技術専門学校,農業専門学校,科学技術学校と協力して行われ,卒業後は自身で事業を開始したり,就職することを可能にしました。卒業生である未亡人の女性は「紛争で夫を亡くして以来,村で仕立屋を営んで来ましたが,独学では出来ない部分もありました。今回,体系的な訓練を受けられたので,学んだ事を活かして収入を上げ,生活を良くしていきたいです」と話していました。
 支援によりビジネス用のミシンを供与された帰還民の女性。
支援によりビジネス用のミシンを供与された帰還民の女性。
これで生計を立てる見通しができた
さらに,地域の復興と安定化に向けて,州単位での行政能力強化を目的に,平成30年11月には国際協力機構(JICA)と連携して州政府高官3名を日本に招き,日本政府と広島県の戦後復興に関する経験の共有を行いました。日本を訪れた3名は,広島市の平和記念公園を訪れて広島県の復興過程について学び,「このような機会をいただき大変感謝しています。日本の教訓をナイジェリア北東部の復興政策に活かしたい」,「日本とナイジェリアの復興の背景に違いはあるものの,紛争のない平和な社会を構築するため,復興を実現するため,地方行政官の役割や心構え,住民や地域社会を中心に置いた行政サービス,住民の声を反映し復興に参加するよう促すことの重要性,中長期的な視点が必要であることなど,大変有益な学びを得ました」と話しています。
 広島県の復興過程を学ぶ北東部の政府高官
広島県の復興過程を学ぶ北東部の政府高官
(写真提供:国際協力機構)
紛争被害地域で働く,国際機関職員の想い
UNDP職員として紛争被害地域の現場で働く日本人プロジェクト・マネージャー,野口義明氏は,この地域への想いを語りました。「ナイジェリア北東部に行くとまず驚くのは,どこに行っても子どもがたくさんいる事です。ナイジェリア国民全体の平均年齢は18歳と言われており,この平均は出生率が下がりつつある南部の数字も含むので,北東部における平均はもっと低く,体感では10代前半ではないかと感じます。次に,キャンプやホスト・コミュニティで暮らす避難民は,いつ故郷に戻れるか分からない,大きな不安の中で何年も暮らしている事です。
これらの若い避難民たちが大きな不安や不満の中で暮らしている事は,それが暴力的過激主義による更なる危機を招く可能性をはらんでいます。UNDPが2017年に行った大規模な調査でも,収入や社会的繋がりを奪われた人,特に若者が過激主義に参加する傾向が明らかになっています。もし今いるたくさんの子どもたちが大人になった時に地域の村々が回復しておらず,安定した生活が送れなかったら,さらに大勢の過激主義者や避難民を産む事になり,その影響はヨーロッパや,さらには日本にも及ぶ可能性があります。
 多くの避難民が暮らすボルノ州都で撮影。
多くの避難民が暮らすボルノ州都で撮影。
電気もなく娯楽も少ない地区で外国人は珍しいらしく,
子どもたちが興味深そうに集まってくる 臨時の避難民キャンプとして使われている学校
臨時の避難民キャンプとして使われている学校
での避難民の様子。女性と小さい子どもが不安
を感じながら過ごしている
ナイジェリア北東部で国際機関の職員は警備された宿舎中に宿泊し,自由に外出することはできません。また移動には防弾車を使い,必要に応じて軍に護衛を付けてもらいます。支援する村に行くにも護衛の依頼など手続きが必要で,さらに事件が発生して予定が急きょ変わる事もあり,活動の制約が多い状況です。それでも,電気も水道もない場所で暮らす多くの避難民や帰還民の生活を少しでも早く安定化させる手助けをしたいと考えて,毎日の活動を行っています。
避難民と帰還民への復興支援に尽力する日本の支援は,ナイジェリアだけでなく国際的なメディアでも度々報道され,日本の支援の重要性が世界中で共有されています。北東部地域の安定化と復興への道のりはまだまだ続きますが,日本は切れ目のない人道支援と開発協力をこれからも目指していきます。
(注)文中,提供元の記述がない写真は全てUNDPナイジェリア 野口義明氏提供
- 参考
-
- 国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所
「ボコ・ハラムに破壊された村がUNDPと日本政府の支援で復活 」
」 - UNDPナイジェリア事務所ウェブサイト
UNDP, Integrated Community Stabilisation in North-East Nigeria (Japan-funded) Final Report, March 2018-March 2019
- 国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所





