ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第398号
東南アジア・インドの海洋プラスチックごみの流出経路を探る
日本政府とUNEPの連携プロジェクトがスタート
 街中に捨てられた大量のプラスチックごみ(タイ)
街中に捨てられた大量のプラスチックごみ(タイ)
原稿執筆:国連環境計画(UNEP)アジア太平洋事務所 政策・執行担当官 吉田鶴子
現在,世界中の関心が集まっている海洋プラスチックごみ問題。ビニール袋を大量に飲み込んだウミガメやクジラの話を聞いたことはないでしょうか?プラスチックは自然分解しないため,エベレストの頂上,マリアナ海溝,南太平洋の無人島,北極の氷の中に至るまで,思いがけないところで溜まっているのが確認されています。少なくともウミガメの86%,海鳥の44%,海洋哺乳類の43%が海洋プラスチックごみの影響を直接受けています。
海洋プラスチックごみの広まりにはいくつかの要因がありますが,まずは丈夫で安い素材として,プラスチックの生産・消費が1950年頃から爆発的に増えたことがあげられます(グローバル平均年9%増)。2015年には世界中で3億8800万トンものプラスチックが作られ,そのうちの99.5%は石油を原材料とする製品です。こうして増加したプラスチックがごみになった時の処理・処分は焼却や埋立てに頼っています。製品再利用(マテリアルリサイクル)は驚くほど広まっていないのです。また,開発途上国ではごみの回収をはじめとする廃棄物管理が脆弱であり,住民のポイ捨てや事業者の不法投棄なども横行しています。海洋ごみの8割が陸上で出たごみが回収・処理されずに流出したものだと考えられていますが,ごみの排出経路についてなど,まだ分からないことも多いのです。
 メコン川分流の河川敷に捨てられたごみ(カンボジア)
メコン川分流の河川敷に捨てられたごみ(カンボジア)
この難題に立ち向かうため,今年3月,日本政府と国連環境計画はメコン川流域およびインドにおける海洋プラスチックごみ排出対策への支援を始めました。カンボジア,タイ,ベトナム,ラオス,インドの政府機関や専門家と協力し,プラスチックごみがどこからどうやって河川に流出しているのかを探っていきます。調査には,衛星画像分析やドローンも取り入れ,2020年には調査結果を基に,アジア発の長期モニタリング手法モデルを発信予定です。
 ムンバイでごみを収拾する様子(インド)
ムンバイでごみを収拾する様子(インド)
昨年の世界環境デー(2018年6月5日)でインドのモディ首相は,2022年までに国内の使い捨てプラスチックを全廃すると明言しました。インドに対する支援では,海岸都市ムンバイやガンジス川沿いの都市でごみ管理向上のキャンペーンも計画しています。
不必要なプラスチックの製造・使用を減らし,包装は「捨てるなら,もらわない」。循環経済や廃棄物管理への投資を増やす。地球から海洋プラスチックごみをなくすために世界中の国々が多様な関係者と共に協力しあう時代の到来です。
- 参考文献:
- UN Environment Programme (2018).(PDF)
 (海洋プラスチックごみ問題に関する国連環境計画の報告書)
(海洋プラスチックごみ問題に関する国連環境計画の報告書) - IPBES (2019).
 (生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォームのアセスメントレポート概要)
(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォームのアセスメントレポート概要)
- UN Environment Programme (2018).(PDF)
ベトナムから海にごみを出さない!
廃棄物管理能力の向上を日本が技術協力でサポート
 海岸に積もるごみのすぐ横で魚を乾かす漁師
海岸に積もるごみのすぐ横で魚を乾かす漁師【写真提供:オンラインViet Nam News】
原稿執筆:国際協力機構(JICA)ベトナム事務所 企画調査員 菅藤祐子
 溝に流れる大量のごみ(ハノイ市)
溝に流れる大量のごみ(ハノイ市)
日本からベトナムに到着して目につくのは,おびただしい数のバイクと交通渋滞,そして道に散乱するごみの山。日本と同じく長い海岸線を持ち,海洋資源を多く有するベトナムは,海洋ごみを多く排出する国であると同時に,美しいマングローブやビーチがポリ袋をまとい,観光資源を損なうなどその影響を大きく受けている国でもあります。
 ハノイで環境公社(URENCO)の廃棄物収集員から
ハノイで環境公社(URENCO)の廃棄物収集員から日頃の活動状況を聴取する日本人専門家
そのようなベトナムで2014年に始まった日本の技術協力プロジェクトである「都市廃棄物総合管理能力向上プロジェクト」では,建設省を主な支援対象者として,中央政府や地方政府の能力向上を通じ,ベトナムにおける都市廃棄物の総合的な管理能力の向上を行いました。
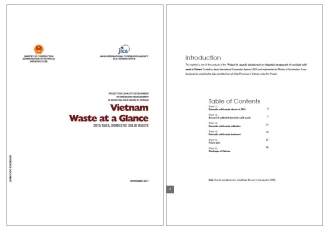 プロジェクトを通して作成された,
プロジェクトを通して作成された,ベトナムの廃棄物事情がよくわかる報告書
”Waste at a Glance 2016“
建設省に対しては,都市廃棄物に関する法制度の見直しを含む政策立案能力支援,また同省が地方政府(トゥアティエン・フエ省)に対して技術的サポートを行うための能力向上強化を図りました。トゥアティエン・フエ省に対しては,日本のごみ管理計画の内容を盛り込んだマスタープランの作成を支援し,コミュニティ自主管理コンポストや参加型3R(リデュース,リユース,リサイクル)の推進などの支援を行いました。これまでベトナムには全国の廃棄物データや地方政府による廃棄物概要に関する資料などはありませんでしたが,本プロジェクトによる作成支援で,毎年の廃棄物の統計の取り方やデータ更新の仕方を技術移転することができました。
 トゥアティエン・フエ省の小学校で行った3R活動。
トゥアティエン・フエ省の小学校で行った3R活動。校内で利用する分別ビンのポスターは学校で行われた
3Rコンテストで優勝した児童によるもの
国全体にかかわる廃棄物問題は,一つのプロジェクトだけで解決できるものではありません。たとえば日本で現在行われている廃棄物管理は,試行錯誤を繰り返しながら,長い年月を経て達成されたものです。また,コンポスト処理や3Rなど住民レベルでできることでも,行政による規定と予算がなければ持続的な活動はできません。
現在ベトナムでは,環境保護法改正が検討されていますが,リサイクルの分野についても,実効性のある政策が規定されることが期待されます。また,排出されたごみのリサイクルやリユースだけでなく,ごみの量そのものを減らすため(リデュース),スーパーのプラスチック袋の有料化などにも行政が力を入れ始めているところです。
一日も早くベトナム国民ひとりひとりが「ごみを減らす努力をし,これ以上環境を破壊しない」という意識を持ち,それに従った行動を起こすことができるよう,また,その行動の規範となる,より良い政策が立案・実行されるよう,日本は支援を継続していきます。
外務省/地球環境課 ツイッターフォローお願いします!
 Twitter@MofaJapan_Env
Twitter@MofaJapan_Env

ラオスの玄関口,ワッタイ国際空港設備の拡張・新設を支援

原稿執筆:在ラオス日本国大使館 二等書記官 廣瀬 久也
 完成したワッタイ国際空港(株式会社安藤・間提供)
完成したワッタイ国際空港(株式会社安藤・間提供)
ラオス人民民主共和国(以下,ラオス)はインドシナ半島に位置しており,東南アジア諸国連合(ASEAN)加入国のうち唯一の内陸国です。人口は649万人(2015年,ラオス統計局),面積は約24万平方メートル(本州と同程度),国土の約80%が山地です。主な宗教は仏教であり,穏やかな国民性と言われています。
日本とラオスの関係は深く,過去50年にわたり,良好な関係を築いています。日本が開発に関わったODAプロジェクトもいくつかあり,日本企業が質の高いインフラ工事に携わっています。首都ビエンチャン・ワッタイ国際空港プロジェクトも日本のODA(借款契約額90.17億円の有償資金協力)にて整備することになり,2015年から工事が始められ,2018年に終了しました。
ラオスの旅客数は年々増加しており,2014年時点の国際線利用者約69万人・国内線約30万人から,2023年にはそれぞれ約151万人・約46万人に達すると予測されています。首都に位置するビエンチャン・ワッタイ国際空港では,今後増加が見込まれる観光客などに対応するには規模が足りず,国際線旅客ターミナルビルの拡張,国内線旅客ターミナルビルの新設が急務となっていました。これを支援したのが,今回の日本のODAプロジェクトというわけです。
2018年8月に完成式典が首都ビエンチャン市にて実施され,日本政府から中根一幸外務副大臣(当時),ラオス政府からソムディー・ドゥアンディー副首相らが出席し盛大に行われました。完成式典は現地の主要紙4紙いずれも一面に写真入りで大きく報じられ,日本への感謝が示されているとともに,ラオスの関心の高さがうかがえました。

 ワッタイ空港の完成式典(左:JICA提供,右:株式会社安藤・間提供)
ワッタイ空港の完成式典(左:JICA提供,右:株式会社安藤・間提供)
さらに,同空港国際線旅客ターミナルを運営しているL-JATSは,ラオス政府と日本企業の合弁会社として1999年に設立され,約20年にわたり同ターミナルの運営を続けています。日本企業が取り組む初の海外空港ターミナル運営案件です。今後も空港内施設にレストラン・カフェなどの飲食店,免税店・お土産店などの新設およびリニューアルが計画されています。
日本は,今後とも質の高いインフラ整備でラオスを支援するとともに,日本企業のノウハウに基づく空港管理・運営を通じて利用者に満足して頂けるよう,施設整備,サービスの両面からしっかりと支援を続けていくことが期待されています。
拡張・新設された同空港はいつも観光客で賑わっており,ラオス人の友人は「ラオスの玄関口としてふさわしいワッタイ国際空港を新設してくれた日本の支援に感謝する」と言いました。


