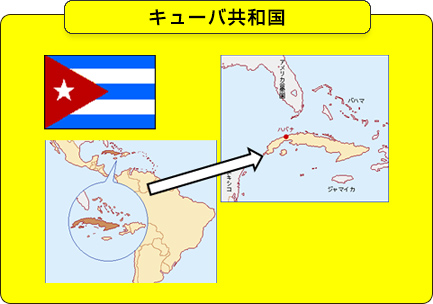ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第392号
ODAメールマガジン第392号では,以下3話をお送りいたします。(肩書きは全て当時のものです)
- 第1話:キューバ共和国より
「「医療大国」キューバにおける日本のプレゼンスと協力」 - 第2話:ジャパン・プラットフォームより
「難民に関するグローバル・コンパクトとジャパン・プラットフォーム(JPF)」 - 第3話:大臣官房ODA評価室より
「「ODA評価年次報告2018」の発行」
「医療大国」キューバにおける日本のプレゼンスと協力
原稿執筆:在キューバ日本国大使館 森田 みどり 一等書記官
キューバは米国フロリダ半島のわずか150キロに位置する,カリブ海では最大の島国です。革命,チェ・ゲバラ,カストロ兄弟,葉巻にクラシックカー,カリブ海のビーチ・・・。日本から遠く離れた地でありながら,「キューバ」と聞けば何かしらのイメージが湧く人は多いと思います。
-

 ハバナ旧市街のクラシックカーと街並み
ハバナ旧市街のクラシックカーと街並み
1959年のキューバ革命以降,社会主義体制を貫くキューバでは,医療は無料で提供されています。乳児死亡率4.3(WHO,2015年),平均寿命79歳(同2016年)という数値は,中南米諸国はもちろん,多くの先進国と比べても優秀です。また,自らの医療技術に自信と誇りを持ち,アフリカや中南米諸国に医師を派遣する「医療輸出国」でもあります。
その一方で,外貨不足等により財政難に陥っているキューバでは,医療機器の老朽化や故障が日常的な問題となっています。生活必需品にも事欠くキューバでは,あらゆる物が修理を繰り返しながら使われており,病院で見かける機材も,20年,30年使われ続けた年代物であることは珍しくありません。
特にキューバではがんが死因の第一位となっていますが,医療機器の老朽化が進み,検査結果が出るまでに時間がかかる,迅速な病理診断が困難,患者に負担の少ない治療がなかなかできないといった問題を抱えています。
そこで日本のODAにより,X線画像のデジタル化システムや,病理検査機材,内視鏡等を全国34の病院に供与しました。「精度の高い機材でより正確な診断ができるようになった」,「レントゲン写真がデータで共有できるようになって紛失や取り違えのリスクが減った」と,効果を実感している声が医師や技師から寄せられています。
 昨年の12月17日,
昨年の12月17日,
機材供与式で佐藤外務副大臣から
コバス・ルイス保健次官に目録を
授与(ハバナ市内の小児病院にて)
【写真提供:JICA】 供与された顕微鏡,遠心分離機などの
供与された顕微鏡,遠心分離機などの
病理検査機材
【写真提供:JICA】
また,機材の供与だけでなく,JICAによる医療機材の保守管理とがん早期診断能力強化のための技術協力も実施されています。医療機材の投入と,専門家による指導や研修を包括的に組み合わせることで,キューバにおけるがん診療サービスの拡充と質の向上を支援しています。
 アメイヘラス病院の放射線科医師と放射線技師
アメイヘラス病院の放射線科医師と放射線技師
【写真提供:JICA】 供与機材を用いた
供与機材を用いた
国立医療機器センター技師らによる他県の技師への研修
【写真提供:JICA】
コミュニティー・レベルでのきめ細かな支援も欠かせません。例えば,キューバ西部に位置するピナル・デル・リオ県の小児科病院では,毎年約2,000人の妊産婦に定期健診が行われていましたが,15年前に導入された超音波診断装置にはデータ保存機能がなく,白黒で解像度も低いといった問題がありました。
そこで草の根・人間の安全保障無償資金協力により,新しい日本製の超音波診断装置を供与しました。高性能な機材が導入され,健診に欠かせない正確な診断ができるようになっただけでなく,胎児の発育状況や先天異常などの診断も可能となったと,現地から評価されています。
 以前に使われていた旧式の
以前に使われていた旧式の
超音波診断装置 新たに導入された日本製機材を
新たに導入された日本製機材を
使っての健診
キューバ医療界で日本の製品や技術は高い評価と信頼を得ており,日本の医療機器関連メーカーの名前は広く浸透しています。キューバの病院を訪れると,大切に使われてきた日本製の医療機器をよく見かけ,JICAや民間の研修で日本を訪れたことがあるという医師や技師も少なくありません。
高い医療水準を誇るキューバですが,医療従事者がさらに研鑽を積み,より良い環境で質の高いサービスを提供できるよう,協力の余地はまだまだ残されています。
ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援
【第13弾 難民に関するグローバル・コンパクトとジャパン・プラットフォーム(JPF)】
原稿執筆:ジャパン・プラットフォーム(JPF)助成事業推進部 モシニャガ アンナ
日本ではほとんどニュースとして取り上げられませんでしたが,2018年12月,多種多様な関係者を巻き込んだ約2年間にわたる協議や交渉を経て,「難民に関するグローバル・コンパクト 」(Global Compact on Refugees, 以下GCR)と「安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト
」(Global Compact on Refugees, 以下GCR)と「安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト 」(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, 以下GCM)が採択されました。
」(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, 以下GCM)が採択されました。
紛争や迫害などによって世界中で家を追われている人々はかつてないペースで増え続けており,2017年末時点でその数は過去最多の6,850万人 を記録したとされています。貧困,社会・経済的格差,気候変動や環境破壊などを理由に,安全でより安定した生活を求めて,移住せざるを得ない人々も増えています。
を記録したとされています。貧困,社会・経済的格差,気候変動や環境破壊などを理由に,安全でより安定した生活を求めて,移住せざるを得ない人々も増えています。
GCRとGCMはそのなかでも,国境を越えて移動するからこそ国際的な注目を集める「難民 」と「移民」のそれぞれに特化した国際的な合意文書になります。ここでいうコンパクトとは「法的拘束力はないものの,コンセンサスによって原則や具体的な行動に向けて加盟国の政治的コミットメントを引き出す合意」という意味で使われています。つまりGCRもGCMも,国際的な合意文書を作成することで,移民や難民の支援の現場における改善を意図しています。
」と「移民」のそれぞれに特化した国際的な合意文書になります。ここでいうコンパクトとは「法的拘束力はないものの,コンセンサスによって原則や具体的な行動に向けて加盟国の政治的コミットメントを引き出す合意」という意味で使われています。つまりGCRもGCMも,国際的な合意文書を作成することで,移民や難民の支援の現場における改善を意図しています。
ここでは,JPFも積極的にフォローしてきたGCRに着目して,その意義を考えたいと思います。
 2018年6月にジュネーブで開催された
2018年6月にジュネーブで開催された
「難民に関するグローバル・コンパクト」
第五回公式協議
【写真提供:モシニャガ アンナ/JPF】 第五回公式協議でNGOの
第五回公式協議でNGOの
共同声明を読み上げる筆者
【写真提供:モシニャガ アンナ/JPF】
GCRの発端は,2015年にヨーロッパ諸国が特に大規模な「難民危機」と呼ばれる事態に直面したことで,2016年に国連初となる難民と移民に関するサミット が開かれたことにあります。
が開かれたことにあります。
本会合では,国連加盟国によって全会一致で「難民と移民のためのニューヨーク宣言 」(New York Declaration)が採択されました。事態の深刻さに鑑みれば,単なる政治的な宣言では,到底物足りないとする声がきかれました。
」(New York Declaration)が採択されました。事態の深刻さに鑑みれば,単なる政治的な宣言では,到底物足りないとする声がきかれました。
その一方で,各地で移民と難民の排斥を訴える動きが広がるさなかに,より公平で予測可能な形での責任の分担を実現するために国際社会で取り組むべきことがあると合意し,2つのグローバル・コンパクトの策定を開始させたこの宣言は画期的と称する声も多くありました。
さらに,ニューヨーク宣言に付随して,国家間の取組にとどまらず,社会を構成する全ての主要関係者(政府,市民社会,民間企業など)を巻き込んだアプローチを推奨する「包括的難民対応枠組み」(Comprehensive Refugee Response Framework,以下CRRF)も制定されました。
GCRの文書自体は,このCRRFと,その実践のために各国政府や関係者がとり得る具体的な措置や活動が含まれた行動計画の二部構成となっています。これらを組み合わせることで難民対応における一つの標準(Point of reference)を設定しようとする試みでもあります。
具体的には,GCRは相互依存関係にある4つの目的を掲げています:
- 難民受入国が受ける影響の軽減
- 難民の自立強化
- 第三国における解決策(定住や補完的ルートによる受入など)へのアクセス拡大
- 出身国における安全かつ尊厳ある帰還のための環境整備
これらの目的を果たすために,政治的意思を動員し,難民やその受入地域と出身地域に対する支援基盤強化を目指し,各国と関係者間における,より公平で持続的かつ予測可能な貢献のための取り決めを促しています。
実のところ,GCRが提示するさまざまな取り決めで真新しいものはほとんどありません。各方面や分野に散らばっていた難民対応の方法や手段を集約し,拠り所をつくったことがGCRの新しいところであり,評価すべきところだとされています。
-

 2018年12月にジュネーブで開催された
2018年12月にジュネーブで開催された
国連難民高等弁務官との対話会合
【写真提供:モシニャガ アンナ/JPF】
難民や国内避難民など大規模な強制移動を伴う人道危機への対応は,JPF設立当初からの重要課題の一つであり,近年その重要性は増す一方です。GCRは,決して万能な合意ではありませんが,難民発生を伴う人道危機対応においては,これまで以上に多くの関係者間を巻き込んだ包括的な対応を促すことなどが期待されており,それが実現すれば歴史的な金字塔になり得る可能性があります。
そのためにはNGOだけでなく,社会を構成する全てのステークホルダーが自分ごととして難民をはじめとする強制移動の問題を捉え,長期的な視点をもって,時間と労力と資源を惜しまずに解決のために取り組んでいく必要があります。
JPFでは,今後もGCRに関連する動向を注視しながら,こうしたマルチステークホルダーアプローチを掲げるGCRの方針に則った支援を展開させていくために,出来る限りの努力を続けていきます。
「ODA評価年次報告2018」の発行
原稿執筆:大臣官房ODA評価室
この度,外務省は「ODA評価年次報告2018」を発行しました。
今回の年次報告は外務省が行うODA評価に軸足を置き,デザインを一変し,よりわかりやすく読みやすい報告となっています。
2017年度に外務省が実施したODA評価の全体像を紹介するとともに,2016年度に実施したODA評価結果のフォローアップ状況をとりまとめています。また,ODA評価の現場の声をお届けするコラムも盛りだくさんにご紹介しています。
ODAにご関心のある方は是非ご覧ください。
外務省ホームページにも近々掲載予定ですので,どうぞお楽しみに!
また,この年次報告で紹介している外務省による各ODA評価の個別報告書も,外務省ODAホームページに掲載しておりますので,ぜひこちらもご覧ください。
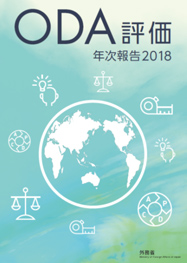 (ODA評価年次報告2018)表紙
(ODA評価年次報告2018)表紙
最近の開発協力関連トピック
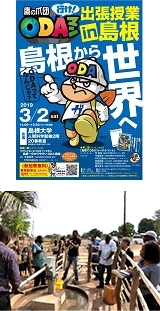
- (1)ODAマンが島根にやってくる!
すっかりおなじみ「ODAマン」の出張授業 が3月2日(土曜日),島根大学で開催されます!原作者のFROGMAN氏と一緒にODAを楽しく学べるこの機会を,お見逃しなく!!
が3月2日(土曜日),島根大学で開催されます!原作者のFROGMAN氏と一緒にODAを楽しく学べるこの機会を,お見逃しなく!! - (2)【各国の言葉が伝える!開発協力】
現地の人々に日本の開発協力を知ってもらうため,在外公館は,現地の記者を開発協力の現場に招いて報道してもらうツアーを実施しています。今回はザンビア で実施したプレスツアーの報告を公開しました。
で実施したプレスツアーの報告を公開しました。