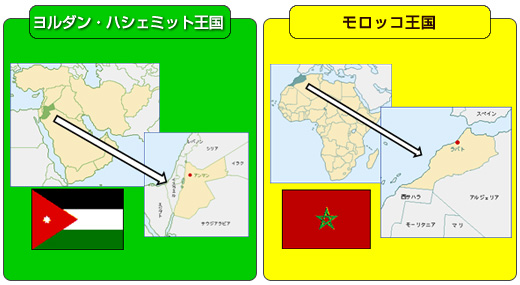ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第329号
ODAメールマガジン第329号は,シリーズ「中東の難民問題」第11弾としてヨルダン・ハシェミット共和国からの「日本の支援」,シリーズ「TICAD VI」第6弾としてモロッコ王国から「緑のモロッコ」と国際協力局政策課から「グローバルフェスタJAPAN2016 写真展「“誰も取り残さない”世界を目指して leaving no one left behind」展示作品の募集について」をお届けします。
日本の支援
原稿執筆:在ヨルダン日本国大使館 吉田 憲正 一等書記官
これまで4回に亘りシリア危機の影響を受けるヨルダンの状況と国際社会の支援について紹介してきましたが,最終回となる今回は,日本の支援について説明したいと思います。
ヨルダンは,不安定な周辺国に囲まれる中,国内が比較的安定している国です。日本はこれまで,中東地域の平和と安定のためにはヨルダン国内の政治的・社会的な安定と経済的な発展こそが重要であるとの考えに基づき,ヨルダンに対する支援を行ってきました。特に,2011年に勃発したシリア危機以降は,シリア難民を大量に受け入れるヨルダンの社会的・経済的な負荷を考慮して,支援を拡大してきています。
支援の主な対象は,シリア難民と多くの難民を受け入れているホスト・コミュニティです。日本は早い段階からホスト・コミュニティの重要性を認識し,その支援に注力してきました。特に,水とゴミ処理分野への支援をヨルダン政府に対して継続的に行ってきています。また,シリア難民キャンプへの支援は,主に国連等の国際機関及びNGOを通じて行っています。以下に日本の支援の例を紹介します。
【技術協力及び無償資金協力による二国間援助】
ヨルダンは乾燥地に位置しており,元来水資源が逼迫していましたが,シリア難民の流入により水需要が急増し,事態が深刻化してきています。こうした状況は特にシリア難民が多数居住するヨルダン北部4県(イルビッド,アジュルン,ジェラシュ,マフラク)において顕著であることから,日本は調査団を派遣し,上下水道サービスの現状やシリア難民の流入による影響を調査しました。この調査の結果,ただでさえ少ない水供給が難民の流入によりさらに減少し,水不足のためにトイレの水も流せず不衛生な状態を甘受せざるを得ない現状が分かってきました。
これら調査結果を踏まえ,水セクターの既存施設(送配水配管網とポンプ)の整備・改修等を行うための無償資金協力贈与契約を締結し,ホスト・コミュニティを中心とした対象地域住民への上下水道サービスの改善を目指して支援を行っています。
 配水管の漏水調査を行うJICA調査団
配水管の漏水調査を行うJICA調査団 日本の支援で供与したゴミ収集車
日本の支援で供与したゴミ収集車
| 年度 | 円借款 | 無償資金協力 | 技術協力(JICA) |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | - | 12.07 | 9.72(9.23) |
| 2012年度 | 122.34 | 16.76 | 8.13(7.62) |
| 2013年度 | 120.00 | 57.54 | 11.34(10.87) |
| 2014年度 | - | 31.16 | 9.18 |
- (注)1 年度の区分及び金額は原則,円借款及び無償資金協力は交換公文ベース,技術協力は予算年度の経費実績ベース。
- 2 2010年~2013年度の技術協力においては,日本全体の技術協力の実績であり,2014年度の日本全体の実績についてはJICA実績のみを示している。()内はJICAが実施している技術協力の実績及び累計。
【国際機関を通じた支援】
日本はヨルダン国内に滞在するシリア難民児童への教育支援等を実施するUNICEFの活動を支援してきました。シリア難民の子どもたちに学習の場が提供されなければ,この世代の子どもたち全体が「ロスト・ジェネレーション(失われた世代)」になる危険性があると言われており,UNICEFは難民キャンプ内外で学校に通うことができない子どもたちのため,Makaniセンター(Makaniはアラビア語で「私の場所」という意味)を運営し,代替的な教育の機会を提供しています。
なお,2013年から2016年の4年間,ヨルダンにおける国際機関等を通じた支援の総額は,約1億3,900万米ドルに達しています。
 UNICEFを通じてザアタリ難民キャンプの
UNICEFを通じてザアタリ難民キャンプの
Makaniセンターに整備された
コンピューターに関する授業の様子 UNOPSを通じて難民キャンプに
UNOPSを通じて難民キャンプに
配備された救急車
日本は,本年開催された伊勢志摩サミット等において,中東地域の復興・開発を後押しすることで,中東不安定化の根本原因の解決を促すため,同地域に対して総額約60億ドルの支援を打ち出すなど,引き続き,シリア難民支援を含め中東地域への安定化支援を推進していく考えです。
これまで紹介してきたシリア難民の現状以外にも,現在,ヨルダンとシリア国境地帯には10万人以上とも言われるシリア人がヨルダン国内に入ることができずに滞留しているなど,シリア難民・避難民の悲惨な状況は続いています。こうした現状を直視し,国際社会が協調してシリア危機の収束とシリア難民支援を推進していくことが求められています。
緑のモロッコ
原稿執筆:在モロッコ日本国大使館 石井 彩 二等書記官
アフリカの開発をテーマとして,まもなくケニアの首都ナイロビで開催されるTICAD VI。アフリカにおける人口増加や気候変動に対応するためにも,農業の生産性向上は重要な課題のひとつです。
モロッコは北アフリカに位置するため,皆さんはモロッコというと「緑」よりも「砂漠」を想像されるかもしれませんが,今回はモロッコの「緑」の増加につながる農業関連プロジェクトを紹介します。
 アトラス山脈の土漠と緑
アトラス山脈の土漠と緑
実はモロッコでは近年,農業を含む「緑」に関連する取組が活発です。
特にモロッコ政府は「緑のモロッコ計画」を発表し,2020年までに農業セクターで115万人の雇用を創出,300万人の農村地域の住民の収入を3倍にすることを目指しています。
日・モロッコ外交関係樹立60周年を迎えた今年3月,日本政府はモロッコ政府と有償資金協力「緑のモロッコ計画支援プログラム」の交換公文に調印しました。国民の3割強が農業従事者と言われるモロッコにおいて,このプロジェクトのパートナーであるアフリカ開発銀行とともに,若年層,女性,小規模農家の経済参画を促す農業振興を支援していきます。
 緑豊かなアウザウド滝
緑豊かなアウザウド滝 円借款「緑のモロッコ計画支援プログラム」
円借款「緑のモロッコ計画支援プログラム」
交換公文に署名する黒川大使
この有償資金協力に加え,JICAを通じた民間企業主導による取組も実施中です。
(株)鳥取再資源化研究所は土壌改良材「ポーラスα(アルファ)®」を使って,モロッコ南部でトマトやインゲンなどの農作物を栽培する実証実験を行い,この結果,通常の半分の灌水量で収穫量20%以上の増加という素晴らしい成果を得ました。
粉砕した廃ガラス瓶を炭酸カルシウムなどとともに高温で熱し製造される「ポーラスα®」は,この製造過程で生じる細かい孔に水をキャッチさせることにより,土壌内の保水性を向上させます。乾燥地では利用できる農業用水が限られることから,この日本の技術がモロッコにおける農作物栽培に貢献することが期待されます。
(株)鳥取再資源化研究所は鳥取大学とも連携し,この技術の開発を進め,これからモロッコの農家への普及を図っていくところです。
 「ポーラスα®」製造現場(奥に廃ガラス瓶が集積されている)
「ポーラスα®」製造現場(奥に廃ガラス瓶が集積されている)
((株)鳥取再資源化研究所提供写真)
 モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場(栽培の様子)
モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場(栽培の様子)
((株)鳥取再資源化研究所提供写真)
モロッコに進出している日系企業は50社を超えており,アフリカ大陸において南アフリカやエジプトに次ぐ日系企業進出数を誇ります。
モロッコは自動車や航空機産業における投資促進にも力を入れていますが,温暖化の影響を受けやすいアフリカ大陸で干ばつ被害を予防し,農業生産性を向上させていくことも欠かすことはできません。日本は有償資金協力や無償資金協力,技術協力やボランティア等の派遣を通じて,灌漑技術開発の支援などモロッコの農業セクターの能力向上に貢献してきました。
今後は官民連携などの新しいかたちも取り入れて,日本のノウハウを活かした協力を行っていきます。
 モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場
モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場
(トマトの収穫の様子)(1)
((株)鳥取再資源化研究所提供写真) モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場
モロッコ南部の「ポーラスα®」実証実験現場
(トマトの収穫の様子)(2)
((株)鳥取再資源化研究所提供写真)
グローバルフェスタJAPAN2016 写真展
「“誰も取り残さない”世界を目指して leaving no one left behind」
展示作品の募集について
原稿執筆:国際協力局政策課広報班
グローバルフェスタJAPAN2016では「“誰も取り残さない”世界を目指して leaving no one left behind」をテーマに,世界各地で開発途上国の人々と一緒に汗を流す日本人の国際協力活動の様子等の写真を募集し,グローバルフェスタの会場で写真展を開催いたします。
この写真展では,NGO,企業,国際機関等の活動も含めた国際協力活動について,来場者の方に写真を通して触れていただき,国際協力をより身近なものに感じていただきたいと考えております。
現在展示作品を募集中ですので,皆様奮ってご応募下さい!
最優秀賞作品と優秀賞作品には,コンパクトデジタルカメラやICレコーダーが贈呈されます!
(締め切り8月31日(水曜日)必着)
<グローバルフェスタJAPAN2016>
日時:2016年10月1日(土曜日),2日(日曜日)10時~17時
(写真展は期間中終日開催)
場所:お台場シンボルプロムナード公園(東京都江東区)
主催:グローバルフェスタJAPAN2016実行委員会
共催:外務省,独立行政法人国際協力機構(JICA),特定非営利活動法人国際協力NGOセンター(JANIC)
<写真展に係るお問い合わせ先>
外務省国際協力局政策課 広報班
グローバルフェスタJAPAN2016 写真展係
電話:03-5501-8000(内線:3531)
Eメール:gfj-photo@mofa.go.jp