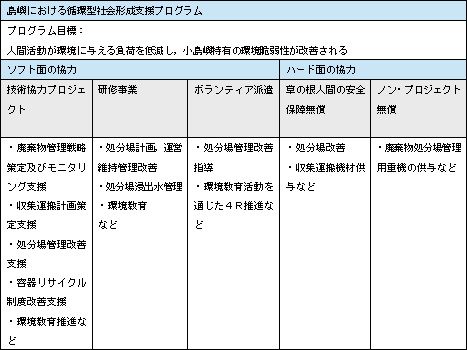ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第300号
ODAメールマガジン第300号は,ミクロネシア連邦からの「ミクロネシア連邦と日本の知られざる関係」と「ミクロネシア連邦の廃棄物問題と我が国の取り組み」をお届けします。
ミクロネシア連邦と日本の知られざる関係
原稿執筆:在ミクロネシア日本国大使館 佐藤 庸昭 二等書記官
太平洋のなかで最も日本に近い赤道以北の地域はギリシャ語で小さい島々を意味する「ミクロネシア地域」と呼ばれています。多くの日本人の方々はグアムやパラオなどを思い浮かべるかもしれませんが,この地域に「ミクロネシア連邦」という国があります。
ミクロネシア連邦は,グアムの南側,パラオの東側にある約600の島々から構成されている島国で,西側から順にヤップ州,チューク州,ポンペイ州,コスラエ州という4つの州による連邦制度が採用されています。日本から直行便はなく成田からグアム経由で約5時間かかります。
日本との歴史的な関係を見ると,第2次世界大戦までの約30年間,国際連盟による委任統治領として多くの日本人が暮らした歴史があり,今でも日系人が多く暮らしています。
このような関係から,英語が共通語のミクロネシア連邦でも,日本語がそのまま使われている用語がたくさんあります。その例が「ヤキュウ(野球)」です。ミクロネシアで「ダイニ」と呼ばれる「第2野球場」で大人から子供まで「ヤキュウ」を楽しんでいます。
また,経済的な関係を見ると,かつお・まぐろ類の漁場として多くの日本漁船がミクロネシアの排他的経済水域(EEZ)内で操業しています。日本の漁業会社は漁場への容易なアクセスや安定的な操業を確保できるようにミクロネシア連邦で合弁会社を設立するための直接投資も行っています。皆さんもミクロネシア産のかつおやまぐろを知らず知らずのうちに召し上がっているかもしれません。
 日本の漁業会社との合併会社によって運航されるまき網漁船。
日本の漁業会社との合併会社によって運航されるまき網漁船。
経済発展を模索するミクロネシアでは
このような形での直接投資は高い評価を受けています。
ミクロネシアは,多くの太平洋島嶼国と同様に,自立的な経済発展や産業振興を行う上で,(1)人口が少ないこと,(2)島々が太平洋上の広範囲に散らばっていること,(3)主要な海外マーケットから遠く離れていること,などの課題を抱えており,自給的農業や漁業が主な産業となっています。
そのため国家を運営する財源としては,コンパクト協定にともなう米国からの財政支援が全体の約5割を占め,独自の財源としては外国漁船がミクロネシアの排他的経済水域(EEZ)内で操業するための入漁料収入が大きな割合を占めています。
 日本の無償資金協力により供与された貨客船「フォー・ウィンズ」と引渡式の様子
日本の無償資金協力により供与された貨客船「フォー・ウィンズ」と引渡式の様子
日本はミクロネシア連邦に対して長年支援を行ってきました。ミクロネシア連邦の持続的な発展のためのインフラ整備,ボランティア派遣や研修事業などの人材育成支援がその代表です。
例えば,近年では海上輸送サービスの改善や安全性の向上,社会経済の発展を目的として貨客船「FOUR WINDS(フォー・ウィンズ)」を政府開発援助(ODA)により供与しました。同船は,多くの島からなるミクロネシアで離島間を移動する住民の足として活躍しています。
また,環境分野では,廃棄物の管理(リデュース,リユース,リサイクルの3R活動)に対する支援を行っています。ミクロネシア連邦のような面積の小さな国ではわずかな廃棄物でも環境に大きな影響を与えかねない問題です。日本の技術や知見,そして,ボランティアや研修など一緒に課題に取り組んでいく姿勢の日本の支援が,ミクロネシアの人々に高く評価されています。
 草の根無償資金協力により整備されたヤップ州ゴミ処分場と引渡式の様子
草の根無償資金協力により整備されたヤップ州ゴミ処分場と引渡式の様子
このように歴史的にも経済的にも,ミクロネシア連邦は日本と強いつながりを持っています。
ミクロネシア連邦の憲法は「海は我々を結びつけるものであり,引き離すものではない。」との一節があります。太平洋という海洋で結ばれている日本とミクロネシア連邦との間で,これからも良好な関係が将来に渡って維持されることを望んでやみません。
ミクロネシア連邦の廃棄物問題と我が国の取り組み
原稿執筆:JICAミクロネシア支所 渡辺 敬久 企画調査員
ミクロネシア連邦は,東西3,200キロメートルにわたって点在する600余りの小さな島々から成り立つ小島嶼国です。政治的に独立する四つの州によって成り立ち,人口は4州合計で10万人程度です。
このミクロネシア連邦では,生活スタイルの西洋化に伴い,自然界での分解速度が遅いゴミ(プラスチック類や廃車等)が急激に増えており,また島外への搬出も困難です。その結果,行き場を失ったゴミが島を汚すという問題が深刻となっています。
このような問題に対し,日本国政府は「島嶼における循環型社会形成支援プログラム」の下,様々な協力スキームを組み合わせ,ソフトとハードの両面からの包括的な協力を実施しています(下表参照)。
協力の一例として,廃棄物最終処分場の改善があります。
ミクロネシア連邦ではこれまで,コスラエ州,ヤップ州,ポンペイ州において,我が国の協力によって,準好気性廃棄物処分場(通称福岡方式)が一部導入されました。この方式は,廃棄物処分場の底部に浸出水集排水管を設け,浸出水を埋立地から速やかに排出するとともに,自然換気によって集水管から埋立地内部へ空気を取り込むことで廃棄物の好気的な分解を促進するものです。
これにより,悪臭が低減し,また分解速度の促進によって処分場の寿命が延び,さらには,強力な温室効果ガスであるメタンの発生を抑えるなどの効果があります。この方式は,構造が単純であるため,低いコストと技術で導入できる利点があります。
ポンペイ州の最終処分場は,技術協力プロジェクト”大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト(J-PRISM)”を通じて, 2013年6月に準好気性に一部改善されました。
この際,ポンペイ州に加えて各州からもカウンターパートを招集し,JICA専門家による指導の下,カウンターパートたちの力で改善工事を行いました。工事に要した費用は200万円足らずで,これまで見積もられていた新規処分場建設費用16億円と比べ,部分的改修ではあるもののはるかに安く仕上げることができました。
 J-PRISM専門家とカウンターパートによるポンペイ州の最終処分場改善風景
J-PRISM専門家とカウンターパートによるポンペイ州の最終処分場改善風景 改善後の最終処分場(2013年6月撮影)
改善後の最終処分場(2013年6月撮影)
その結果,ポンペイ州では,今後自分たちの力で,処分場の改善を続けたいという動きが高まってきています。2014年12月には,関連する本邦研修にも参加したJ-PRISMのカウンターパートが中心となり,処分場浸出水の処理改善のため,浸出水循環ポンプや,現地資材を工夫したドラム缶を使用したろ過装置が設置されました。
また,現在は処分場を新たな区画に拡大するための準備として,区画整備が実施されています。さらに今後,日本の無償資金協力を通じて,ポンペイ州の処分場用に重機が導入される予定です。処分場のさらなる改善と日々の運営のため,この重機が大いに活用されることでしょう。
さて,このように処分場の改善は進んでいますが,一方で,処分場から遠い地区では,廃棄物の収集・運搬が困難という問題があります。そこで,処分場に廃棄物が適切に持ち込まれるようにするため,日本の無償資金協力を通じて,ポンペイ州の自治体に廃棄物収集車が整備される予定です。この計画を踏まえ,ポンペイ州の自治体では,収集車を活用した収集・運搬計画を策定しているところです。
なお,効率的な収集・運搬や処分場の運営の計画に当たっては,廃棄物発生量や処分場への搬入量といった基礎的な情報が重要です。これまで,4州の環境関連JICAボランティアが中心となってカウンターパートと共に実施した調査では,実測とアンケートにより,廃棄物発生量と搬入量を定量的に推定しました(2011~2013,通称J-AWARE調査)。その結果は,各州の廃棄物管理計画の策定時に,基礎情報として役立てられています。
2015年5月現在も,J-PRISMでは同様の調査を実施しております。カウンターパートは,2011年から経験を積んでいるため,専門家による最小限の指導の下,独自に調査を進めていくことが可能になっています。
機材の供与などのハード面の協力に加え,関係者一人一人の技術・能力を高める技術協力は,日本が得意とする協力です。技術協力による能力開発の成果は,目で見ることは難しいですが,ミクロネシアに住んでいると,カウンターパートの変化を確かに感じることができます。
いずれこの国の人々が,廃棄物分野だけでなく様々なセクターで自立し,最終的に援助を必要としなくなる日が来ることを,願っております。
このODAメールマガジンでは,ODAの現場で働いている人々や,実際にODA事業を視察した方々の生の声をお伝えしていますので,本メルマガに掲載されている内容は執筆者個人の感想に基づいた意見であり,政府の立場を示すものではありません。