ODA(政府開発援助)
第508回ODA出前講座 開催報告
中京大学
令和5年1月24日
2022年12月、中京大学にて国際協力局緊急・人道支援課の児玉光也課長補佐がODA出前講座を実施しました。今回は「日本の緊急・人道支援の現状と課題 JDR医療チーム及び感染症対策チームを中心に」をテーマとした講義を行い、法学部の2年生~4年生250名が受講しました。

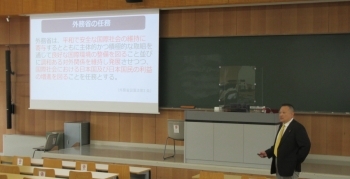
参加者からの感想(抜粋):
- 発展途上国に対して、お金を貸す、お金を提供する、技術を提供するといった支援を日本は行っており、その場しのぎではなく持続的な経済成長を手助けしていることや、自然災害、難民に対する支援など人道支援も行っていて、自然災害や人道支援など国際緊急援助を必要とする人々が年々増加傾向にあるという課題も勉強になりました。
- 日本外交の5つの取組や災害にも自然災害、人為災害、特殊災害と種類が様々あること、災害発生のメカニズム、国際緊急援助隊の派遣決定プロセスなど、今まで知らなかった知識を新たに知ることができ参加できて非常によかったです。
- JDRの活動を詳細にお話いただき、モザンビークで起きたサイクロンの被害とその対応のために派遣された医療チームの活動やサモアでの麻疹への対応、災害サイクルの緊急対応期での活動の重要性を理解することができました。
- 実際に多くの経験をされてきた講師の方から貴重なお話を目の前で聞くことができ、日本と国際社会の平和と安定の確保、開発協力、日本経済の成長と繁栄の追求、日本についての理解の促進、「国民と共にある外交」の推進を行っているということがよくわかりました。
- 今回の講座を通して人道支援というものがあり、日本も活動していることは知っていましたが、日本の貢献度の世界順位や支援拠出額、派遣先と派遣チーム数など、日本は人道支援に積極的であり、貢献度がすごく高いということがわかりました。
- 日本政府の人道支援について講座を受ける前は全く想像もつきませんでした。しかし講座を受け、自然災害、人為災害や特殊災害などのあらゆる災害に対して支援を行っていることがわかりました。災害の多い日本だからこそこのような活動についてもっと学び、国際的なつながりについても発展させていけたらよいのにと思いました。
- 国際緊急援助隊の存在自体をあまり知らなかったので新鮮な話ばかりでした。要請があった翌日に派遣員を募って派遣するという迅速な対応が、国際緊急援助隊の強みだと感じました。日本の緊急援助が世界的に知れ渡れば初期対応も迅速にできて甚大な被害が起きてももっと助けられるのではないかと思いました。
- 災害が起こり、もしも自分たちが被災者となった場合、今までは自衛隊や政府などが援助してくれる程度にしか思っていませんでした。しかし国際緊急援助隊という救助チームや医療チーム、自衛隊などが一緒に被災者を助けるために活動していたことを知ることができました。自分が被災したときには救助してくれた方々へ本当に感謝しなければならないと改めて感じ、こういったお話を聞けてよかったです。
- 災害は日本にとって身近な課題なので、地震、津波や台風などの被害が起きたときや、外国で助けが必要になったときに足を運んで支援やボランティアをしてみたいと感じました。
- ODAについてはただ勉強をしているだけという感じでしたが、実際に現地に行って活動している方のお話を聞くことで、支援を必要としている国や地域での危機感をより強く実感できました。また国際緊急援助隊は5つのチームから構成されており、具体的にどのような活動をしているのか、さらに実際に現地に行って救助を行い、援助物資を供与するだけがODAの活動ではないということを理解できました。
- 「災害時は人の生存時間が72時間であることを考慮して、72時間以内にチームを立ち上げている」というお話を聞いた時には、仕事に対する熱い思いを直に感じることができました。

