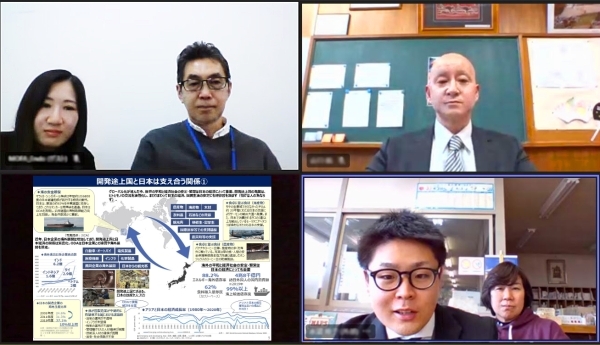ODA(政府開発援助)
第506回ODA出前講座 開催報告
栃木県高等学校教育研究会国際理解教育部会
令和5年1月16日
2022年12月、栃木県高等学校教育研究会国際理解教育部会にて国際協力局政策課の永澤浩之広報班長と石原芙美香外務事務官がオンラインでODA出前講座を実施しました。今回は「日本の開発協力」をテーマとした講義をライブ配信にて実施し、同部会に所属する国際理解教育の担当教員30名が受講しました。
参加者からの感想(抜粋):
- 日本の技術を用いた地下鉄の発展が、結果的にインド女性の職の幅を広げることにつながっているという話を聞いて驚きました。目に見える技術の進歩だけでなく、女性の社会的な立場にまで貢献されているのだなと思いました。
- ODAが実際にどのように使われているのか、どのような方針でやっているのか、実際にその支援がうまくいっているのかなど知ることができました。世界の状況がいかに深刻であるかを知るのに数字で示せるのはとても効果的だと思いました。
- 世界の国々がそれぞれに置かれた立場の枠を越え、SDGsを実践しつつ、協働して関係を構築していくことが、私たちにとってより住みやすい未来へ繋がっていくのだとの思いを強く持ちました。
- 実際に活躍している方々の生の声を聞くことができ、ただ資料を眺めるよりも臨場感や説得力を感じることができました。
- 開発途上国への支援は日本からの一方通行のイメージがありましたが、漁業やインフラ整備など、まわりまわって日本に暮らす我々にも大きな恩恵や意義があることがわかりました。
- 途上国、先進国にかかわらず、私たちはみんな対等な立場であると改めて感じました。日本だけ良ければいいという考えは間違いであり、周りの国との関係性を友好に保つ必要があると感じました。
- 現在もODAの予算についてニュースとなっていて、とてもタイムリーな内容でした。講演内容は世界の政治経済活動で日本の今後のあるべき姿を再考するよい機会となりました。日本のODA活動は情けは人のためならずという考え方を基本としているとわかりました。
- ODAの援助についての紹介は非常に参考になります。デリーメトロの建設によりインドの女性の私生活に変化をもたらした点や、インドネシアにおいて母子手帳を導入が乳児・妊婦高死亡率が改善や妊婦の検診率、出生率の低下につながったなど教室で生徒に国際協力のあり方について考えさせる適切なトピックだと考えます。