ODA(政府開発援助)
第384回ODA出前講座 開催報告
津田塾大学
平成30年1月26日
2017年11月29日(水曜日),国際協力局国別開発協力第二課の椿本主査を講師として派遣しました。今回の出前講座では,同大学の学芸学部国際関係学科2~4年生90名を対象に「日本のODAと南アジアにおける協力」というテーマで講義を行いました。
講義概要:日本のODAと南アジアにおける協力
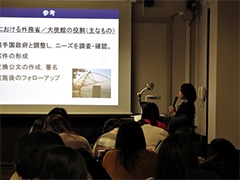

参加者からの感想(抜粋)
- これまでは日本の方針が中心であると考えていたが,相手国のニーズを考慮して開発支援の内容を決定するという点に,ODAに関する意識の変化があった。
- 特に興味を持ったのは,支援前にヒアリング調査をし,その後実施,そしてフォローアップまでしていることだ。支援したら放置するのではなく,フォローをするからこそ,今までの支援がうまくいっているのだと思った。
- これまでODAの目的は支援を受ける国の貧困削減や社会の安定化などであると思っていたが,日本外交においてはそこがゴールではなく,日本とそれらの諸国との経済関係の深化,人的・文化交流の拡大などを目標に活動しているのだと思った。
- 日本ばかりが支援をしているのではなく,お互いが助け合っているのだと強く感じた。その証拠に,東日本大震災では逆に日本に支援がたくさんきて,それにより日本は救われた。このように,海外と日本が相互に助け合うことが,どちらの国にとっても良いことであり,国際協力において最も大切なことの1つなのだと感じた。
- 日本はアジアへのODAの分配が非常に多いということを初めて知った。勝手なイメージでアフリカのほうが開発途上国が多いと思っていたので,自然にODAもアフリカ地域への配分が多いと思っていた。しかし,日本がアジアの成長を牽引するような国であり続けること,そして世界で日本の存在感を高めることを目的とした時に,アジアへのODAが増えることに納得がいった。
- ODAによって国際社会の平和構築に貢献し,日本の経験や知見を広めるのはもちろん,将来のビジネスパートナーになりうる国の成長に貢献することも重視されているのではないかと思った。
- 南アジアという普段あまり聞き慣れない地域における日本のODAの事業内容を知れたことは,今後自分がその地域に行く時に少し見方が変わると思うので,非常に良かった。日本と同じような地下鉄が走っているなんて驚きだ。
- ODAにおいては,主に支援する国のインフラを建設したり改善するという取組が行われているイメージを持っていたが,そういった事業だけでなく,女性の地位向上や保健問題の改善といった人的な支援も様々な面から行われているのだなと思った。

