ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第439号
サッカーボールがもたらす生活の質の向上
マラウイのコミュニティ開発で学んだこと

東京オリンピック・パラリンピック要人接遇事務局 比嘉 陽子
JICA海外協力隊には190以上もの職種があることを御存じでしょうか。この中に、「コミュニティ開発」という職種があります。教員や看護師などに比べ、職務内容のイメージがわきにくいのですが、住民の生活向上のために分野にとらわれず様々な活動ができる職種です。地域の課題やニーズ、地域的・人的資源、隊員の強みによって活動内容が変わってきます。
マラウイでコミュニティ開発に奔走
暮らしぶりの向上には何が大切か考える日々
 成人識字教室で試験監督を務めました。相談しながら答えを記入する生徒さんも多いのですが、それでも学習が進むことが大切です。
成人識字教室で試験監督を務めました。相談しながら答えを記入する生徒さんも多いのですが、それでも学習が進むことが大切です。
 先生は長い身体を折り曲げて生徒さんからの質問に答えます。椅子や机がないため、床に座って授業を受けています。
先生は長い身体を折り曲げて生徒さんからの質問に答えます。椅子や机がないため、床に座って授業を受けています。
私は、アフリカ東部の小さな内陸国、マラウイという国に「コミュニティ開発」隊員として2年間派遣されていました。配属先は、首都からバスで7時間かかるゾンバ県庁のコミュニティ開発局。住民の生活向上のための国の施策、NGOや国際機関の資金協力によるさまざまなプロジェクトの実施主体です。毎日、同僚の現地職員たちとオフロードバイクで村々を回り、プロジェクトの実施状況や実施後の状況をモニタリングさせてもらいました。
住民の暮らしぶりやニーズ、解決すべき課題、配属先の部署で支援できるプログラムを検討する中で、自分の活動を「生計(収入)向上のための活動」と、「お金にかかわらず生活の質が向上する工夫の普及」という2本柱にすることにしました。前者についてはビジネスの支援と読み書き算数教室に取り組みました。住民の中には、グループを作って共同ビジネスを立ち上げる人々がいます。このグループを回って、商品の卸先や個包装に課題を抱えるグループには、JICAが世界の発展途上国で進めている「一村一品」事業の現地事務所担当者につないだり、広報に課題を抱えているグループには、新聞記者を紹介して記事を書いてもらったりしました。ある日、村のベーカリーグループで、「伝統的な薪ストーブを使ってパンを焼いているが、煙がひどく目が痛くなってしまう。さらに薪の消費が早すぎるので改善策を提案して欲しい」との要望があり、熱効率の良い燃焼方式を調べたこともあります。
そうして色々なグループを回っているうち、帳簿付けや計算が苦手な人が多いという共通課題を見つけました。コミュニティ開発局には成人識字教室というプログラムがあり、各村々で成人を対象にした読み書き算数教室の運営を支援することができます。そこで、マラウイ人の同僚と村々を回り、成人識字教室を開こうと呼びかけました。同僚は人々のやる気を引き出すのがとても上手で、「私たちは収入の向上を必要としているけれど、そのために必要なことは何か?日本から来たYokoに聞いてみなさい」と私に話を振ります。私は、皆からの質問に答えつつ、「読み書き算数は基礎としてどうしても必要」と話します。そこで同僚が「さぁ、立ち上がりましょう。成人識字教室を開いて、頑張りましょう」と演説すると、どの村でも拍手が起きました。こうして、40の村で40人の教師と26人の教室運営委員、教室運営を監督する4人のスーパーバイザーを集めることに成功し、成人識字教室を軌道に乗せることにつながりました。
 3つの石の間に薪を集め、火を炊く方法。この方法だと熱伝導が効率的でないため、大量に薪が必要で、かつ調理に時間がかかっていました。
3つの石の間に薪を集め、火を炊く方法。この方法だと熱伝導が効率的でないため、大量に薪が必要で、かつ調理に時間がかかっていました。
 導入されたカマドを使って、トウモロコシの粉を溶いた乳幼児向けのおかゆを作っています。2つの鍋で同時に調理が可能になり、少ない薪で十分な火力が得られます。
導入されたカマドを使って、トウモロコシの粉を溶いた乳幼児向けのおかゆを作っています。2つの鍋で同時に調理が可能になり、少ない薪で十分な火力が得られます。
「生活の質が向上する工夫の普及」については、主にカマドの普及と、栄養学講座・料理教室に取り組みました。村では、地面に石を3つ並べた上に鍋を置き、薪を焚いて調理することが一般的ですが、この方法だと熱が空気中に逃げてしまい鍋への熱伝導効率が悪く、薪を大量に消費するため、薪を集めに行く時間や労力がかなりかかります。そこで、日本の伝統的なカマドの作り方教室を開くことにしました。近隣の県でカマド普及活動をしている隊員がいたので来てもらい、私も住民と一緒に教えてもらいました。カマドを使うことによって薪の使用量が2分の1になり、調理時間も短くなるため大変喜ばれました。また、気候変動に対して脆弱なマラウイでは森林減少が問題になっており、薪の使用量が減ることは森林保全にも繋がります。
 みんなで集まり、カマド作りを教えてもらいました。レンガ、粘土か蟻塚の土、砂、灰、牛糞、枯草などをよくこねて作ります。
みんなで集まり、カマド作りを教えてもらいました。レンガ、粘土か蟻塚の土、砂、灰、牛糞、枯草などをよくこねて作ります。
 作業は皆が体験できるように交代して進めます。帰宅すると皆、自分たちでそれぞれ自宅にカマドを作りました。
作業は皆が体験できるように交代して進めます。帰宅すると皆、自分たちでそれぞれ自宅にカマドを作りました。
 カマドは長期間使用するとひび割れが入るため、定期的なメンテナンスが必要。村を巡回する際にカマドも異常がないか相談に乗ります。
カマドは長期間使用するとひび割れが入るため、定期的なメンテナンスが必要。村を巡回する際にカマドも異常がないか相談に乗ります。
マラウイの主食であるトウモロコシの栽培には、約4か月間安定した降水量が必要であるため、干ばつなどの影響により不作となる年も多く、度々食糧難に襲われます。そこで、日照りに強いアフリカ古来の雑穀など、飢餓期にも比較的手に入りやすい食材を用いた料理教室を開催、ケニアなど近隣諸国のレシピを紹介しました。また、併せて栄養学講座を実施、五大栄養素の働きや望ましい栄養バランスについて図表を使って確認しました。レシピは、好評だったものや不評だったもの、反応はさまざまでしたが、皆さん毎回喜んで参加してくれました。
サッカーボールが届いた!
スポーツがもたらす力に気づいた日
 ビニール袋やボロ布、ゴミくずなどの不要品を丸めて縛っただけの手作りのサッカーボール
ビニール袋やボロ布、ゴミくずなどの不要品を丸めて縛っただけの手作りのサッカーボール
 手作りのサッカーボールで夢中になって遊ぶ子どもたち
手作りのサッカーボールで夢中になって遊ぶ子どもたち
そうして活動しているうち、地元住民の生活の質の向上のために熱心に活動していて、普段から私の活動を助けてくれている地方の政治家の方が事務所に私を訪ねて来て言いました。「地元の青少年が非行に走らずスポーツに打ち込める環境を作りたいので、地元で地区対抗サッカートーナメントを開催したいと思っている。優勝チームへの景品を何か提供頂けないか。ほとんどのチームのボールは古すぎてボロボロだし、ボールを持っていないので手作りの代用品でプレーしているチームもある」。
 Pass onプロジェクトで届けられた真新しいサッカーボール。
Pass onプロジェクトで届けられた真新しいサッカーボール。
 サッカー人気は根強く、プロジェクトで行われた試合には約1,000人もの人々が集まりました。
サッカー人気は根強く、プロジェクトで行われた試合には約1,000人もの人々が集まりました。
当時、マラウイの就業率は、求人人口に対して14%でした。たとえ大学まで卒業しても就職先はなく、70%は自給のための農作業のみに従事、「学校に通っても無意味だ」と言う大人もいました。一部の地域では頻繁に洪水が起きて作物が流され、他の地域では干ばつで作物が全滅することもしばしば。こうした中で、青少年が「頑張っても報われない」という気持ちに陥り非行に走ってしまわないよう何かしなければいけない、と願う大人たちがいました。スポーツはルールに則りフェアプレー精神をもって行われることから、規範意識、チームメイトや対戦相手へのリスペクトと思いやりを育み、健全な心身を育成する手段であるということは研究結果としても明らかになっています。
ちょうどその頃、日本のNPO法人Dooooooooの「Pass onプロジェクト」に出会いました。同プロジェクトを通じて、横浜F・マリノスに当時所属していた中町公祐選手寄贈のサッカーボールを、トーナメントに参加する全12チームに、そして優勝チームには慶應義塾大学ソッカー部からユニフォームを寄贈して頂きました。サッカーはマラウイで最も人気のあるスポーツです。大人も子どももサッカーが好きなので、このトーナメントは大きなエンターテイメントとして歓迎されました。試合を観戦する子どもたちは息をのみ、ハラハラドキドキ大喜び。最終決戦はクリスマスの日に行われ、なんと1,000人もの人々が観戦にやってきました。
 トーナメントに優秀し、寄贈された真新しいサッカーボールを掲げる優勝チームの皆さん。優勝賞品として、黄色いユニフォームも寄贈されました。
トーナメントに優秀し、寄贈された真新しいサッカーボールを掲げる優勝チームの皆さん。優勝賞品として、黄色いユニフォームも寄贈されました。
 古くなったサッカーボールを譲り受けた子どもたち。貴重な本物のボールが届きました!
古くなったサッカーボールを譲り受けた子どもたち。貴重な本物のボールが届きました!
村長さんによるスピーチの後、私にもマイクが回ってきたので、私は有名な映画「Pay it Forward」のアイディアを話しました。「誰かから善意を受けたら別の人3人に善意を渡してください。そうすると善意が拡散されて世界が良くなります。今日、私は、ボールを持ってきました。このボールを受け取った人たちは、どうか誰かに善意を渡してください」。
後日、小学校を訪問したら子どもたちが楽しそうに古いサッカーボールで遊んでいました。先生によると、トーナメントに参加したチームが、それまでに使っていた古いボールを小学校に寄贈してくれたのだそうです。まさにPay it Forward!善意が拡散され始めていました。また、その隣では古いボールを譲ったチームが練習に打ち込み、生き生きと走り回っていました。彼らの笑顔を見ているうちに、スポーツもまた生活の質を向上させる一つの手段であることに気がつきました。これは、それまでスポーツとは縁遠かった私にとっては、大きな発見でした。
 所得向上意識を高めるため、小規模農家の関係者と市場のニーズを調査中の筆者(左)
所得向上意識を高めるため、小規模農家の関係者と市場のニーズを調査中の筆者(左)
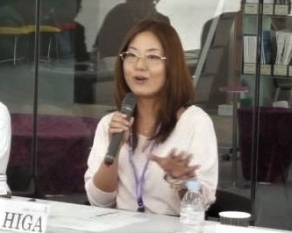 民間企業勤務時代には、国際交流基金が主催する海外の若手リーダーを日本に招へいするプログラムに、日本人メンバーとして参加しました(2014年)。
民間企業勤務時代には、国際交流基金が主催する海外の若手リーダーを日本に招へいするプログラムに、日本人メンバーとして参加しました(2014年)。
スポーツの持つ力は、こればかりではありません。JICA海外協力隊の活動を終了し、帰国してから外務省の「草の根文化無償資金協力事業」を通して、スポーツや文化、高等教育分野における事業に従事しましたが、そこでもまたスポーツの持つ力に改めて気づかされる案件が沢山ありました。例えば、紛争終結後も民族間に対立感情が残るボスニア・ヘルツェゴビナのモスタル市に、民族隔てなく通えるスポーツアカデミーの設立を支援した案件では、子どもたちは笑顔で1つのボールを追いかけ友情を育み、保護者間でも民族を超えた交流が生まれました。ラオスでパラパワーリフティングの練習環境を整備した案件では、スポーツをきっかけに障害を抱えた方が社会に参画し自信をつけていくといった声が聞かれました。生活の質の向上には、必ずしも現金や衣食住だけが重要なわけではありません。より良く幸せに生きる為にはどのような手法が取りえるのか、個別の背景をよく観察し、様々な手法を検討してみることが大切だと、マラウイでの活動を通して学びました。実際に現地でこうした活動を行い、現地の方とのコミュニケーションを通して化学反応が起き、自分一人では思いつけなかった方法を発見する。これこそが「コミュニティ開発」という職種の醍醐味だと思います。


