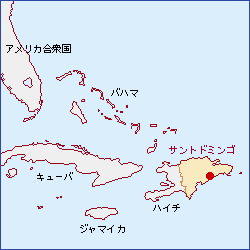ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第356号
ODAメールマガジン第356号は,ドミニカ共和国からシリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第7弾として「国民に広く浸透している「日本人の病院」 ルイス・アイバール衛生都市」を,明和工業株式会社よりシリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取組」第4弾として「SDGsはアカペラや文化祭と同じ?色々な役割を重ねて大きな目標を成し遂げる,全員参加型の新しい国際協力」を,また,国際協力局政策課より「グローバルフェスタJAPAN2017 写真展『Share your Piece わたしたちが伝えたい世界』展示作品の募集について」をお届けします。なお,肩書は全て当時のものです。
国民に広く浸透している「日本人の病院」 ルイス・アイバール衛生都市
原稿執筆:在ドミニカ共和国日本国大使館 遠矢 覚 二等書記官
ドミニカ共和国は,カリブ海で2番目に大きいエスパニョーラ島の3分の2を占め,ハイチ共和国と国境を接している国です。((注):1番大きな島はキューバ島)
ドミニカ共和国のルイス・アイバール国立病院は,1946年に首都サント・ドミンゴに設立され,低所得者を対象に無料で医療サービスを行っており,貧しい住民達の健康改善に貢献することが期待されていました。
1980年代,ドミニカ共和国では下痢などの消化器系の病気が幼児死亡率のトップという状況にもかかわらず,医療器材も医師も不足しており,長年にわたって胃カメラ1台,医師も4人しかいないといった状況であり,また,医療レベルも低く,医療器材を使用した検査は,1日に2人程度しか実施できませんでした。
こうした問題を解決するため,日本は1989年より同病院に対して積極的に支援を行ってきました。具体的には,日本のODAにより消化器疾患センター及び専門医を養成するための医学教育センターを建設するとともに,専門家を派遣した画像診断技術などの技術指導を行いました。
 施設内には活動された日本人専門家の写真が掲示されている
施設内には活動された日本人専門家の写真が掲示されている
1990年~1996年に消化器疾患研究と臨床に関するプロジェクト,1999年~2004年に医学教育プロジェクト,2005年~2010年に中米カリブ地域対象画像診断技術向上研修を実施しましたが,これら技術協力事業において22年にわたり中心的存在として携わってこられた大分大学の森宣(ひろむ)教授は,2016年にドミニカ共和国で最高位の「最高国民栄誉賞Duarte-Sanchez-Mella賞」を受賞されています。
 勲章を受賞した森教授
勲章を受賞した森教授
その後も,日本では当たり前に使用されている患者情報管理システムを参考にして,1患者1番号1カルテ方式を導入し,来院する患者の情報を機能的に整理できるようにしました。また,最近では,最新の医療機材も供与しており,同病院の医療環境は格段に改善されました。
 麻酔機
麻酔機 薬品保冷庫
薬品保冷庫
こうした努力により,ルイス・アイバール国立病院の1週間あたりの患者数は,日本が協力を始める前の1年間の患者数に匹敵するほどに増大し,民間病院よりも質の高い診察を受けられることから,低所得層や地方部からの患者が増え,国民全体の受診機会も広がりました。
また,日本からの技術移転の結果,同病院は画像診断では中米・カリブ地域でトップレベルの医療技術を誇り,他のカリブ諸国からも患者が来訪するまでになりました。

 連日多くの人が病院に押し寄せている
連日多くの人が病院に押し寄せている
現在では,ルイス・アイバール国立病院のほか,消化器疾患センターや医学教育センターを含む施設群は「ルイス・アイバール衛生都市」と名付けられ,患者がタクシーでこの衛生都市へ行く場合,「Hospital de los japoneses(日本人の病院)」といえば運転手に通じてしまうほど,ドミニカ共和国における日本のODAのシンボル的な存在となっています。
 消化器疾患センター
消化器疾患センター 医学教育センター
医学教育センター
また,消化器疾患センターと医学教育センターのロゴには,日本の協力に対する感謝を表すため日本の国旗があしらわれています。
 消化器疾患センター
消化器疾患センター 医学教育センター
医学教育センター
SDGsはアカペラや文化祭と同じ?
色々な役割を重ねて大きな目標を成し遂げる,全員参加型の新しい国際協力
原稿執筆:明和工業株式会社 海外事業部 事業部長
国連環境計画(UNEP)日本ユース環境大使 徳成 武勇
持続可能な開発目標(SDGs)って,知っていますか?最近,世界的有名人のピコ太郎さんがPR役に抜擢されたこともあり,名前を耳にしたり,自分で少し概要を調べてみたりしたという人も増えてきたのではないかと思います。「Leave no one behind(地球上の誰をも置き去りにしない)」というスローガンのもと,貧困削減や教育,生物多様性保全といった課題別に設定された17の目標。…でも,率直なところ,「何だか高尚で難しそう」「国連が定めた目標なんて,自分には遠すぎて関係のないことだろう」「国際協力より自分の日々の仕事の方が大事」という第一印象を抱いた人も,きっと少なくないはず。実は私もそのうちの一人でした。そんな,SDGsの盛り上がりについてちょっと距離を置いて眺めていた自分が,今回の目標ほど全員参加型の国際協力を推し進めるのに適しているものはないと感ずるに至った経緯を,体験談を織り交ぜながら簡単に紹介したいと思います。
身の上話から始めてしまいますが,私は石川県金沢市生まれで,小学校から大学院までを,ずっと金沢で過ごしました。学生時代は理学部化学科に所属しており,期末試験に追われつつ,どちらかと言うと普段はアカペラサークルでの活動の方に熱が入っていた,日本ではどこにでもいるタイプの普通の学生(というと他の学生に失礼?)だったと思います。修士号を取った後は一念発起し,ケニアの環境コンサルティング会社で革靴やスーツを土埃で赤褐色に染めながら3年半を過ごしましたが,ここで強調したいのは,国際協力に対して昔から特別意識が高かったわけでも,国際経験があったわけでもないという部分です。
ケニアでの生活を終えて勤め始めたのは,地元金沢の中小企業である明和工業という会社です。社員50人の小さい会社ながらも,東京大学や東京工業大学,産業総合研究所など,一流の研究機関との共同開発で培った技術力が自慢の環境プラントメーカーです。現在私達が途上国に展開しようとしているプラントはバイオマス炭化装置といい,簡単に言えば「農業残渣や畜糞,汚泥などの有機ゴミを炭にする廃棄物処理プラント」のことを指します。処理後に得られる炭は燃料利用できるだけでなく,農業用に畑に撒けば,自然肥料や土壌改良材として有効に使えるという特徴を持ちます。
 下水汚泥炭と水のみで育った野菜
下水汚泥炭と水のみで育った野菜
今,世界の人口は70億人を超えており,その増加率が一番高いのがアフリカ大陸です。その人口がどんどん都市に集中しているので,どうしてもゴミの量は増える傾向にあり,多くの最終処分場はとっくに限界容量を超えてパンク寸前。その約7割は有機ゴミですし,高い輸入化学肥料に手が出ない農家も多くいますから,炭にして再利用する仕組みを作ることができれば,皆が喜ぶ社会インフラになるのではないか?と考えました。
 ナイロビ市に位置する最終処分場の光景
ナイロビ市に位置する最終処分場の光景
途上国ではゴミはプラスチック等全て混ざった状態で出て来るのが普通で,そのままでは適切な炭化処理もできませんが,設置場所をうまく考えれば,アフリカでも活躍できる技術のはず。例えば野菜市場に設置することで,市場で出てきた大量の野菜ゴミを炭化し,そのまま農家の方々の自家利用や卸売による収益向上に役立てられないか?実現できれば,まさにLeave no one behindという目的に資するプロジェクトが,途上国政府や民間事業者,コミュニティ,農家の人々と作れるかもしれない。そう考えると,試さずにはいられなくなったわけです。その頃ちょうどケニアで第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)が開催されたため,出展と現地視察を兼ねて社長と現地に渡航。そこから本格的な検討がスタートしました。
 大量の野菜とそれを売る地方農民女性たち
大量の野菜とそれを売る地方農民女性たち
とはいえ,中小企業単体で,利益が出るまでその試行錯誤をアフリカで続ける体力は無いのも現実。そこで重要なのが,ゴールを共にする協力者との連携です。明和工業では国際協力機構(JICA)の中小企業支援制度を活用し,ケニアにおいて1年間の実現可能性調査を行います。この中ではJICAのみならず,現地事情に明るいアドバイザーや,日本や現地の研究機関,現地政府といった,多種多様なステークホルダーを巻き込みながら,どうすれば良い事業が実現できるかを皆で模索していきます。また,装置の設計を最適化するには社内の技術スタッフや社長にも知恵を出してもらう必要がありますし,そのためにはアフリカ側の生の意見やニーズを取り入れることも欠かせませんから,ABEイニシアティブという日本政府の奨学金プログラムに参加しているアフリカ人インターンの受け入れ等を通じ,お互いに学び合う機会を作り出していこうとしています。まだ事業化のための調査を行っている段階で言うのも憚られますが,多種多様な組織や個人が1つの目標に向かって協力し合えば,自分一人で初めに想像していた以上のインパクトを生み出し得るものと,日々実感を強めています。
 炭化装置の仕組みを学ぶアフリカ7か国・14人のABEイニシアティブ研修生たち
炭化装置の仕組みを学ぶアフリカ7か国・14人のABEイニシアティブ研修生たち
ここでSDGsに話を戻します。SDGsは大目標だけで17個もあり,覚えるだけでも大変ですが,目標が多様化し,誰もがいずれかの目標について主体的に参加できる用意が整ったという見方もできるのではないかと思います。即ち,Leave no one behindというスローガンは,受益者のみならず,私達のような中小企業を含めた全員が積極的に関わるための合言葉とも取れると思うのです。異なる得意分野を持ったパートナーを集め,知恵と特技を持ち寄り,社会インパクトの創出を目指していく。これはちょうど自分が夢中になっていたアカペラで,異なる音程を出す5~6人が声を重ねることで美しいハーモニーを作り上げ,聞く人に喜んでもらおうとすることと,構造としてはほとんど同じ。職場の一大プロジェクトや文化祭,スポーツ,研究活動など,人それぞれで類似する経験をお持ちの方もいるかと思いますが,それに重ねればSDGsが身近に感じてくる部分もあるのではないでしょうか。全員参加型の,新しい国際協力。SDGsがその幕開けだったと2030年に言えるよう,実現に向かって協力の輪をあちらこちらで広げていく流れを,できるだけ多くの方と共に,夢中になって作っていければと思います。
 アジア太平洋地域でSDGsの普及に取り組む,UNEPユース環境大使の仲間たちと
アジア太平洋地域でSDGsの普及に取り組む,UNEPユース環境大使の仲間たちと
グローバルフェスタJAPAN2017 写真展
『Share your Piece わたしたちが伝えたい世界』展示作品の募集について
原稿執筆:国際協力局政策課広報班
グローバルフェスタJAPAN2017では「Share your Piece わたしたちが伝えたい世界」をテーマに,世界各地で開発途上国の人々と一緒に汗を流す日本人の国際協力活動の様子等の写真を募集し,グローバルフェスタの会場で写真展を開催いたします。
この写真展では,NGO,企業,国際機関等の活動も含めた国際協力活動について,来場者の方に写真を通して触れていただき,国際協力をより身近なものに感じていただきたいと考えております。
現在展示作品を募集中ですので,皆さま奮ってご応募ください!
最優秀賞作品と優秀賞作品には,コンパクトデジタルカメラ(Tough TG-5)やICレコーダーが贈呈されます!(締め切り9月3日(日曜日)必着)
 平成28年最優秀賞受賞作品(個人部門)
平成28年最優秀賞受賞作品(個人部門)
グローバルフェスタJAPAN2017
- 日時:
- 2017年9月30日(土曜日),10月1日(日曜日)10時~17時
(写真展は期間中終日開催) - 場所:
- お台場シンボルプロムナード公園(東京都江東区)
- 主催:
- グローバルフェスタJAPAN2017実行委員会
- 共催:
- 外務省,独立行政法人国際協力機構(JICA),特定非営利活動法人国際協力NGOセンター(JANIC)
写真展に係るお問い合わせ先
外務省国際協力局政策課 広報班
グローバルフェスタJAPAN2017 写真展係
電話:03-5501-8000(内線:3561)
Eメール:gfj-photo2017@mofa.go.jp