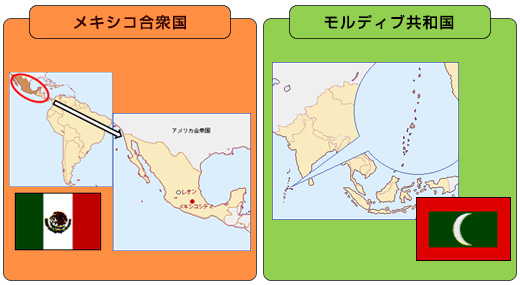ODA(政府開発援助)
ODAメールマガジン第355号
ODAメールマガジン第355号は,メキシコ合衆国からシリーズ「日本と世界の懸け橋 日系社会とODA」第2弾として「榎本殖民とチアパスコーヒー」及び,シリーズ「『目に見える形』で感謝されている日本の援助」第6弾として「大地に日の丸たなびく」を,モルディブ共和国からシリーズ「周年記念と開発協力」第7弾としてモルディブ共和国から「日・モルディブ外交関係樹立50周年」を,また,外務省国際協力局地球規模課題総括課からシリーズ「SDGs 誰一人取り残さない日本の取組」第2弾として「SDGs 日本を元気にし,世界を元気にする取組」をお届けします。なお,肩書は全て当時のものです。
榎本殖民とチアパスコーヒー
原稿執筆:在メキシコ日本国大使館 佐々木 秀明 二等書記官
今年5月,メキシコ南東部のチアパス州において,「日本人メキシコ移住120周年記念」を祝う記念式典及び文化行事が,現地日系人の方々の主催で開催されました。式典では記念碑への献花が行われ,武井外務大臣政務官を始めとする参加者一同は,先人達の苦難に思いを馳せつつ,今日に受け継がれる殖民団の足跡を再確認しました。
 アカコヤグア市榎本殖民記念碑
アカコヤグア市榎本殖民記念碑 日本人メキシコ移住120周年記念
日本人メキシコ移住120周年記念
日本文化フェスティバル(中央は武井政務官)
メキシコへの日本人移民は,1897年(明治30年)3月に始まりました。横浜を出港した第1団35名は,同年5月に現在のチアパス州プエルト・マデロに上陸しています。同移民は,提唱者であった榎本武揚外務大臣の名前を冠して「榎本殖民」と呼ばれており,中南米への最初の組織的移住としても知られています。
 榎本殖民団
榎本殖民団
榎本殖民一行は,チアパス州のエスクィントラに入植しましたが,コーヒー栽培の知識に乏しかったことや資金が不足したこともあり,結果的に事業自体は軌道に乗りませんでした。しかし,一部の人々はそのまま現地に残り,その後の移住者とともに日系社会を形成しました。その間には,小学校の建設や西和辞典の編纂なども行っています。
 チアパス産コーヒーショップのメンバー
チアパス産コーヒーショップのメンバー マヤビニック・コーヒーを販売するカフェ
マヤビニック・コーヒーを販売するカフェ
さて,そのチアパス州は,古くから先住民族の人口が多い地域であり,現在に至るまで農業が主産業です。メキシコの国家開発計画においても社会開発の重要性が強調されており,生活改善に向けた取組が強く求められています。
こうした中,歴史的に同州との関わりの深い日本は,JICAとともに様々な技術協力を行ってきました。例えば,主要な農産品であるコーヒー分野では,慶應大の山本教授が中心となって同州の生産者協同組合・団体に対して技術支援を行い,生産から販売に至る公正取引(フェアトレード)を確立させることによって,生活水準の向上を図りました。また,生活改善の一環として,農村開発プロジェクトも実施しており,女性を中心とした住民主体の取組を支援しています。
 チアパス州の住民自らがプロジェクトを立案して実施
チアパス州の住民自らがプロジェクトを立案して実施
榎本殖民が果たせなかったコーヒー栽培による生活自立を,時を超えて,現代の日本人が国際協力という形でチアパス州にもたらしています。
 生活改善の一環としての家庭菜園
生活改善の一環としての家庭菜園 チアパス大学の学生も
チアパス大学の学生も
講義実習を通して参加
大地に日の丸たなびく
原稿執筆:在メキシコ日本国大使館 佐々木 秀明 二等書記官
日本の国旗である「日の丸」。日本国内はもちろん,海外でも大使館や総領事館で見かけた経験のある方は多いでしょう。それでは,外国政府機関において「日の丸」を常時掲揚している組織があることを,皆さんは御存じでしょうか。それはメキシコにあります。それも,2か所存在しているのです。
一つ目は,日墨産業技術教育センター(CETMEJA)です。同センターは,工作機械・仕上げ・金属加工・コンピューター・工学電子および電子通信の6過程を持つ,産業技術・サービス教育高校です。
1980年代,日本はメキシコの電子技術の向上に貢献するため,JICA技術協力「日墨技術学院」(1982年~1987年)を実施した結果,CETMEJAが設立されるに至りました。その後,同学院は公共教育省傘下の職業訓練校となり,今日では毎年100名前後の若手技術者をメキシコ産業界に輩出しています。
 日墨産業技術教育センター(CETMEJA)
日墨産業技術教育センター(CETMEJA) CETMEJAで開催された日本祭
CETMEJAで開催された日本祭
二つ目は,職業技術教育活性化センター(CNAD)で,メキシコの職業訓練教員の能力向上を図る機関です。1990年代,メキシコはNAFTA(北米自由貿易協定)を締結するなど経済の自由化を進める中で,工業力の強化を重視していました。その一環として,メカトロニクス分野の技術者を養成するために教員の再訓練が求められたことから,日本はJICA技術協力「職業技術教育活性化センタープロジェクト」(1994年~1999年)を実施し,その結果CNADが誕生しました。
 職業技術教育活性化センター(CNAD)
職業技術教育活性化センター(CNAD) 日本人専門家から
日本人専門家から
CNADインストラクターへの技術移転
今日,両センターは第三国研修を通じて,中南米各国の技術者人材育成にも貢献しています。CETMEJAは「上級電子制御」(2001年~2003年)を実施し,中堅技能者の継続的な育成・供給に加えて,製造分野における技術的なアドバイスと指導を行っています。またCNADは,産業界のニーズに対応するために,応用ロボット工学技術に関する教育・訓練を支援する「ロボット応用工学」(2005年~2010年)を実施しています。
 ロボットのプログラミングを指導する専門家
ロボットのプログラミングを指導する専門家 数値制御の技術を伝える専門家
数値制御の技術を伝える専門家
このように,両センターの発展は日本の協力の賜物であり,その象徴が「日の丸」です。さらに近年では,日本のシニアボランティアが両センターにおいて中南米の産業力強化に汗を流しています。日本とメキシコの国際協力成果は中南米全域に広まりつつあります。
 西山シニアボランティアとCETMEJAの学生
西山シニアボランティアとCETMEJAの学生
日・モルディブ外交関係樹立50周年
原稿執筆:在モルディブ日本国大使館 安部 正道 参事官
ODAメールマガジンをご覧の皆さん,キヒネット?(ディベヒ語でお元気ですか)。
今回は,「日・モルディブ外交関係樹立50周年」を迎えたモルディブの首都マレからお届けします。
皆さんは,モルディブというと,まず何をイメージしますか。青く澄みとおった海…,美しい珊瑚礁の島々…,それとも新婚旅行…でしょうか。
日本からスリランカ,シンガポールやタイで乗り継ぎ,約12時間のフライトで首都マレの空港に到着。そこからフェリーに乗って10分間行けば,首都マレ島です。一体どんな場所なのでしょうか。
 ラーム環礁フォナドゥ島/折り鶴に挑戦する子どもたち
ラーム環礁フォナドゥ島/折り鶴に挑戦する子どもたち
【写真提供:石田 一成 元青年海外協力隊】
1 モルディブのあれこれ
モルディブはインドの南西に広がる約1,200の島々から成る国です。東西は東京から伊豆大島までの距離くらいですが,南北は東京から札幌までの距離に匹敵し,南北に細長い国です。国土の大半が海で,陸地面積は全部の島をあわせても東京23区の半分くらいです。
人口は40.7万人(モルディブ人約34万人,外国人約6万人)。モルディブは極めて若年層が多い国で,25歳以下が47.5%を占めています。日本からモルディブへの観光客は年間約4万人で,在留邦人は177名(平成28年10月現在)です。
 ラーム環礁フォナドゥ島
ラーム環礁フォナドゥ島
独立記念日イベントで的当てゲームをする子どもたち
【写真提供:石田 一成 元青年海外協力隊】
ところが,人口40.7万人の3分の1が首都マレに集中しているため,マレは世界でも有数の超過密都市になっています。首都マレの市民の足は専らオートバイで,あらゆる通りにオートバイがところ狭しと駐車されています。在モルディブ日本国大使館は,そんな街の喧騒の中,オフィスビルの8階にあります。
 首都マレ島の政府合同庁舎前の通り
首都マレ島の政府合同庁舎前の通り
奥の方まで,道路の両脇にオートバイがぎっしりと並ぶ
モルディブにある約1,200の島々のうち,有人島は200ほどです。個々の島の中には,特定の役割を担っている島があり,なかなか面白いです。例えば,首都マレ島の周辺には,空港島,燃料島,拘置所島,刑務所島,ゴミの島などが点在しています。
モルディブ人の主な食事は何でしょうか。モルディブには色々な食材が輸入されていますが,モルディブ人の食卓に欠かせないのはカツオ料理です。モルディブ人の年間一人当たりの水産物消費量は144キログラム(国連食糧農業機関,2009年)で,日本の約2倍です。なお,モルディブではカツオを燻製にしたかつお節(なまり節)を製造しており,日本のかつお節と本当に同じ匂いがします。これは,近隣国ではモルディブ・フィッシュと呼ばれ,カレー料理やスープの重要な食材となっています。
 モルディブ・フィッシュ
モルディブ・フィッシュ
日本のかつお節と同じ匂いがします
忘れてはならないのは,モルディブはイスラム教徒(スンナ派)の国であることです。毎日,1日5回のお祈りの時刻には多くの商店が一時閉店し,金曜礼拝ともなれば,モスクからその前の道路までが礼拝をする人々で埋め尽くされるほど,敬虔な人々が集います。
 首都マレ島の砂浜での看板
首都マレ島の砂浜での看板
水着を着ての海水浴は禁止なので,着衣のまま海に入ります
2 日・モルディブ外交関係樹立50周年
モルディブは1965年に独立し,その2年後の1967年11月14日,日本との外交関係を樹立しました。50周年にあたる2017年には,日・モルディブ両国はロゴマークを制定し,色々な記念行事を計画しています。また,50周年の記念日である11月14日には,両国からそれぞれ記念切手が発行される予定です。
駐日モルディブ共和国大使館は40周年にあたる2007年に東京に開設され,一方,在モルディブ日本国大使館は2016年1月にマレに開設されました。
 日・モルディブ外交関係樹立50周年のロゴマーク
日・モルディブ外交関係樹立50周年のロゴマーク
3 日本とモルディブの友好関係
日本は1970年代から経済協力を開始し,地場産業の育成,環境・気候変動対策・防災,及び社会経済の発展に大きな成果を上げてきました。また1982年から派遣している青年海外協力隊の隊員は330名(平成29年8月1日現在)にも上り,モルディブ社会が日本人ボランティアならではの働きに注目しています。
このような経済協力ですが,日・モルディブ関係と絡み,重要な流れをお話ししましょう。国と国の友好関係はこのようにして深まっていくのだという好例です。
(1)1987年,首都マレ島はサイクロンによる高潮の被害を受け,首都機能が麻痺しました。それに対し,日本は,1987年から無償資金協力によって首都マレ島をぐるっと取り囲むように護岸(防波堤)を建設し始め,2002年に工事が完成しました。その総額は75億円に及びます。
 首都マレ島の北岸
首都マレ島の北岸
マレは,日本が無償資金協力で建設した護岸(防波堤)によって,
津波や高波から守られています
(2)護岸の完成から2年後の2004年,スマトラ沖大地震及びインド洋大津波が発生し,モルディブにも津波が押し寄せましたが,日本が建設した護岸のおかげで,首都マレ島の首都機能と住民が守られました。これに対し,モルディブ政府は感謝を示すために,2006年,日本国民に対して〈グリーン・リーフ(緑の葉)賞〉を贈りました。同年,日本は,円借款「モルディブ津波復興計画」(総額27.33億円)を実施しました。
 ラーム環礁フォナドゥ島/笑顔の素敵な少年
ラーム環礁フォナドゥ島/笑顔の素敵な少年
【写真提供:石田 一成 元青年海外協力隊】
(3)それから5年後の2011年,東日本大震災が起こった際,モルディブは「今度はモルディブが日本を助けよう」と呼びかけ,モルディブ国内で「24時間テレビ」を放送して義援金を募り,首都マレ島では日本に連帯を示すためのウォークが行われ,東日本大震災から1週間後には,全国民による黙祷の時が持たれました。その後,モルディブ政府と「24時間テレビ」の義援金を合わせ,日本にモルディブ特産のツナ缶(約60万個)を送りました。
(4)2014年4月には,ヤーミン大統領が訪日し,安倍総理大臣との間の首脳会談を経て,「40年以上にわたる友情と信頼に基づく協力の新たな段階に向けて」と題する共同声明が発出されました。2017年に外交関係樹立50周年を迎え,両国の友好関係はさらに増進しています。
 首都マレのモルディブ国立大学
首都マレのモルディブ国立大学
日本語クラス学生たちに書道教室を開催
名前を大きく堂々と!
【写真提供:佐々木 友香 元青年海外協力隊】
4 現在の対モルディブ経済協力
現在,我が国の対モルディブ経済協力の二本柱は,「地場産業の育成」と「環境・気候変動対策・防災」です。
モルディブは,青く澄みとおった海や美しい珊瑚礁の島々を売りにした高級リゾートホテル等を中心とする観光産業から多くの収入を得ていますが,観光業は世界経済の動向等に左右されるなど,脆弱性を持っています。我が国は,漁業をはじめとする開発ポテンシャルの高い地場産業の育成を中心とした支援を行っています。
 シャビヤニ環礁ミランドゥ島
シャビヤニ環礁ミランドゥ島
モルディブでは珍しいストレートヘアに子どもたちが興味津々!
【写真提供:灰田 瞳 元青年海外協力隊】
例えば,この数年,「持続的漁業のための水産セクターマスタープラン策定プロジェクト」を実施してきており,モルディブの更なる水産振興をしようとしています。同プロジェクトを推進する中で,モルディブでとれるソデイカの料理を新たに提案するという,水産資源の付加価値向上に向けた努力もしています。
一方,1,200の島々から成るモルディブでは,気候変動による海面上昇や津波等の自然災害に対して極めて脆弱です。我が国は,気候変動への対応,再生可能エネルギー利用の促進など,環境・気候変動対策,及び防災分野への支援を重点的に行っています。
例えば,昨2016年10月,我が国とモルディブは「地上デジタルテレビ放送網整備計画」(供与限度額27.92億円)に関する書簡を交換しました。日本方式による地上デジタルテレビ放送網の整備を行うことで,モルディブ国民の情報(気象情報や防災情報を含む)へのアクセス向上を図り,気候変動・防災対策に寄与することが期待されています。
さらに,青少年育成・教育をはじめとする人材育成分野への青年海外協力隊(JOCV)による支援も継続しており,モルディブ側から高い評価を得ています。
 最南端シーヌ環礁マラドゥ島
最南端シーヌ環礁マラドゥ島
現地人教諭による体育科授業の充実を目指して
奮闘する青年海外協力隊(JOCV)の鈴木隊員。
遊びの時間だった体育が,子どもたちの発育を支える
大切な授業になる!
【写真提供:齋藤 博 JICAモルディブ支所長】
今後とも,日本とモルディブの友好関係が更に深まるように,我々がそのための架け橋となれるように,様々な協力を継続していきます。
SDGs 日本を元気にし,世界を元気にする取組
原稿執筆:国際協力局地球規模課題総括課 福留 健太 外務事務官
持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)とはミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットにおいて採択された17の目標のことです。
人やモノ,資本が国境を越えて移動するグローバルな世界では,気候変動,災害,感染症といった地球規模の課題もグローバルに連鎖して発生しているなか,採択されました。
SDGsは,2030年に向けて途上国のみならず,先進国も含め国際社会が一体となって「誰一人取り残さない」をキーワードに経済,社会,環境の総合的な向上を目指しています。一人で厳しい生活の中,子育てしているお母さんやその娘さんも,障害を持って生まれた男の子であっても,誰一人取り残さず,全ての人々が,その持てる能力を最大限に発揮し,あらゆる場で活躍できる多様性と包摂生のある社会の実現に向けて,SDGsを推進しています。いわばSDGsとは,「日本を元気にし,世界を元気にする取組」なのです。
 持続可能な開発目標(SDGs)の詳細
持続可能な開発目標(SDGs)の詳細
【出典:外務省ホームページ】
今回は,7月17日にニューヨークで開催された国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)についてご紹介します。HLPFとは,国連経済社会理事会の下で毎年開催される閣僚級の会議で,SDGsの国際的なフォローアップとして最重要視されているフォーラムです。特に,SDGs達成に向けた各国の取組を発表する「自発的国家レビュー」が注目度の高いイベントで,本年度は岸田外務大臣がSDGs達成に向けた日本の取組をアピールしました。
 国連ハイレベル政治フォーラムで
国連ハイレベル政治フォーラムで
日本の取組を発表する岸田外務大臣
【出典:外務省ホームページ】 国連ハイレベル政治フォーラムで
国連ハイレベル政治フォーラムで
日本の取組を発表する岸田外務大臣
【出典:外務省ホームページ】
SDGs達成のため,日本が重視している考えに官民パートナーシップ(Public Private Action for Partnership:PPAP)があります。これは,SDGsを達成するうえでは日本国内における様々な関係者の取組が不可欠で,そのためには政府が民間企業や地方自治体,NGOなど多様なアクターと協力しながらオールジャパンで国民的運動へと活性化させていくことが重要であるということです。
一方,一般にはまだ十分に認知されていないSDGsをより広く知ってもらうために吉本興業株式会社やSDGsの替え歌バージョンを披露したピコ太郎氏など,エンターテイメント業界とも連携をし,認知度向上と更なる取組推進を図っています。実際にHLPFにはピコ太郎氏も参加し,17の目標の「17」を模したポーズ等が話題になりました。
 「17」を模したポーズをとる岸田外務大臣とピコ太郎氏
「17」を模したポーズをとる岸田外務大臣とピコ太郎氏
【出典:外務省ホームページ】
他にも,ジャパンSDGsアワードの創設やSDGsにコミットする団体へのロゴマーク付与など,認知度向上のため様々な取組を行っています。
加えて,地方でのSDGs普及・促進も強化していきます。例えば,岸田外務大臣が6月に石川県を訪問し,独自の技術で課題解決を支援する地元企業の先進的な取組を視察し,石川県の魅力をさらに世界に発信する方針について議論しました。
日本企業のSDGs達成を支援するため,途上国での事業形成を支援するJICAの「SDGsビジネス調査」も今後積極的に展開していきます。
このような国内の取組に限らず,日本は国際協力の面でもリーダーシップを発揮しています。HLPFにおいて岸田外務大臣は,これからの社会の担い手となる若年層に焦点を当て,教育,保健,防災,ジェンダー分野などを中心に2018年までに10億ドル規模の支援をすることを表明しました。具体的には,貧困層の支援の拡充,基礎的栄養状況の改善,識字率向上や職業訓練支援など,子ども・若者育成のための施策を重点分野とし,日本独自の高い技術を活かして,SDGsに係る国際協力を今後更に深化・発展させていきます。
例えば,シリアでは7つの国際機関と連携し,現場のニーズを踏まえ,校舎復旧,教員養成,保健に関する意識向上,避難民への教育等複数の目標を同時に達成する支援を実施します。このような次世代に注目した包括的な支援を持続的に行います。
今後は,2019年に開催される首脳級のHLPFを見据えて,実施方針に掲げた施策を着実に実行していく予定です。その過程で,世界のロールモデルとして国内実施,国際協力の両面において「誰ひとり取り残さない」持続可能な社会への変革を主導していくことが,我が国に課された大きなミッションなのです。
次世代に向けて,SDGsの実施方針を基に盛り込まれた関連施策を更に深化させ,総合的かつ強力に実施していきます。そのような具体的取組を今後のODAメールマガジンでも発信していく予定です。