ODA(政府開発援助)
第437回ODA出前講座 開催報告
実践女子大学
令和元年8月20日
2019年7月17日,実践女子大学にて,アフリカ部アフリカ第一課の小林主査が,ODA出前講座を実施しました。今回は,人間社会学部人間社会学科・現代社会学科3年生以上の学生約60名を対象に「外交における開発(国際)協力の役割,アフリカの事例」をテーマにした講義を行いました。

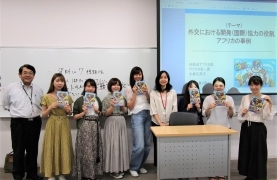
参加者からの感想(抜粋)
- 食料や資金を提供し発展に繋げているだけではなく,職業訓練学校の設立など,治安が安定してからの社会で役立つ支援を行っていることを知り,大変興味がわいた。
- 人として生まれ,人ということは同じなのに,地域によって格差があることは良くないと思ったので,ODAへの意識が変わった。
- ODAへの知識が今までよりも深まった。政府間,国家間で行っているものなので,あまり身近に感じられず,他人事でしかなかったが,日本の取り組みなどを知り,もっと知りたいと思うようになった。
- ODAは,開発途上国などへの開発協力だけでなく,「平和」というものにも繋がるということを学んだ。
- ODAのイメージは,貧しい国への医療援助や教育支援などだったが,インフラ・技術指導などの人材育成の様な,国の成長を支える活動をしていることを知り,ODAのイメージが大きく変わった。
- 開発途上国と一口に言っても,それぞれが抱えているニーズは違うのだと思った。その中でその国のニーズに応えて,一緒に進むのは難しく,やりがいがあるのだろうと思った。
- ODAやアフリカについて考える機会が少なかった中,日本がこんなにもアフリカの国々と近しい関係だったことに驚いたアフリカ=貧しい国と思っていたが,実際はそんなことはなく,テレビや写真でイメージを植え付けられてしまっていたが,今回の話を聞いてイメージが改まるいい機会だった。
- 開発途上国でも日本と同様にジェンダーにおける問題があり,女性を尊重できる社会にするための協力をしていて,女性と社会のあり方まで変えていく取り組みに感銘を受けた。
- TICADを1993年に日本が立ち上げ,今後の開発に貢献していることや,日本も資源エネルギーを頼っている点があることを知られて良かった。
- 日本が支援を受ける側というイメージがなかったので,震災の時に多くの国や地域,国際機関からお見舞いがあったと知りとても驚いた。このようにお互いに支援し合うということは,とても良い取り組みで,開発途上国や先進国など関係なく,その国の強みを活かせて良いと思った。
- 開発途上国として援助しているのではなく,資源が少ない日本にとっては大切なビジネスであり,しっかりとビジネスとして成り立っていることをとても考えさせられた。
- 金銭の支援だけでなく,日本人空手家の受け入れなどユニークな一面を知ることができた。
- 今まで開発協力はやりたい人が行うというイメージを持っていた。しかし,今回の講義で,具体的にこのようなことには資金を使って良いポイントなどを定めた「開発協力大綱」の存在や,日本が行う支援の種類を知り,開発協力にはしっかりとした基盤があり,信頼できる頼もしい存在であると考えるようになった。
- 196か国中,146か国が開発途上国ということに少し驚いた。自分が先進国にいると積極的にまず知ろうとしないと一生関わらずに終わってしまうと思った。
- 日本は国債が何兆円もあるとよくニュースで聞くが,なぜ円借款や無償資金協力といった開発協力ができるのかわからなかった。
- ODAは「豊かな国が貧しい国に手を差し伸べる」というイメージが強く,慈善活動と思われがちなイメージをもっと改善した方が良いと思った。ビジネスチャンス,国際的課題への対処という部分をもっと打ち出すべきだと思った。
- アフリカの様に地域で貧困の差がある国はたくさんあると思うので,援助して足りない部分やもっと行った方が良いことなど,視野を広げて考えていくべきだと感じた。世界には自立している国はなく,どこの国も支え合って成り立っていると思うので,今でも紛争やテロなどあるが,それぞれの国を尊重し,協調し合うことが大切だと思った。
- 様々な国に支援を行っている日本だが,まだ中には邦人が立ち入れない国があり,直接支援が難しい国があることを知った。直接支援が難しいとなると,その国の経済発展のスピードがゆっくりだったり,人々の暮らしがなかなか向上していかなかったりするので,紛争や混乱が少しでも早く落ち着いて,次の行動ができるような環境作りやそういった支援を行っていかなければならないと感じた。
- このような支援が,受けたら終わりではなく,受けた国が別の国を支援する立場になると知り,絶えず続いていくことに素晴らしいなと思った。
- 「たびレジ」を知らなかったが,今度海外旅行をする時には使いたい。
- 外務省から発行される資料はとてもユニークで,ODAを知る1つのステップを踏みやすいものだと感じた。

