ODA(政府開発援助)
第401回ODA出前講座 開催報告
(公社)青年海外協力協会(JOCA)沖縄事務所
平成30年8月9日
2018年7月7日,沖縄の青年海外協力協会(JOCA)で,国際協力局国別開発協力第一課の大石開発政策上級専門員を講師として,ODA出前講座を実施しました。今回は,同協会の平成30年度おきなわ国際協力人材育成事業に参加する高校生32名を対象に「日本の国際協力 ミャンマーとラオスに対する国際協力を中心に」というテーマで講義を行いました。
講義概要:日本の国際協力 ミャンマーとラオスに対する国際協力を中心に

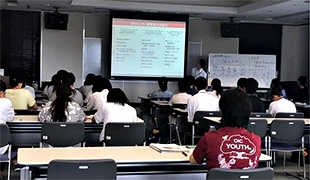
参加者からの感想(抜粋)
- 日本のODAの概要をはじめ,プロジェクトで訪問予定のミャンマーとラオスのODAについて十分に理解することができた。
- はじめODAとは,資金的な支援を行っているものだと思っていたが,技術支援など,現地の人と歩み寄った活動もしているのだと感じた。
- 今回の講義を聴き,日本も支援を受け先進国になれたということを知った。日本が開発途上国に対して支援を行うということは,恩返しにもなるいい機会だと思った。日本だけが頑張っているわけでもなければ,何かをしてあげているのではなく,協力し合っていることだと知った。
- 国際協力に関する考えがとても変わった。「協力」という言葉通り,一方的な支援ではなく,携わる相手国のことを思いやり,足りない技術を補い合うことだと分かった。
- 日本は支援をしてそれで終わりにしようとしているわけではなく,先のことを考えているから,これまで以上に意味のある活動だと思えた。
- 国際協力と聞くと,ものすごく大きなプロジェクトで難しいものだというイメージが強かったが,講演を聴いて,まずは知ることこそが,国際協力への第一歩につながっているような気がした。
- 国際協力で活躍できるのはどんな人材かということもわかった。また,国際協力を職業として考えた場合,国連や外務省だけでなく,民間の企業が行っていることもあるので,将来の夢が広がったなと思った。
- 外交,国際協力の原点は人と人との関わりだと分かったので,異文化交流を大切にしていきたい。最初は小さいことでもいいから国際協力をしていきたいと思った。
- 「グローバル人材」になるために,今どんなことをするべきか,国際協力は国と国同士だけが行うものではないこと,私たち個人でもできることがたくさんあるということを学べた。
- 今回の講義を聴いて,机に向かう勉強だけではなく,自分の「幅」を広げたいと思った。
- 途中途中でクイズや考える時間があって勉強になったし,楽しかった。ODAについて深く知ることができ,国際協力についても考えることができて良かった。

