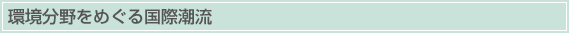| >>概況 >>関連国際会議等 |
Last Updated: 2014. 12. 16 |
近年,人類の活動範囲・規模・種類の拡大に伴い,気候変動,オゾン層の破壊,生物多様性の損失,汚染物質の拡散等の地球環境問題が顕著化し,地球と人類に対する脅威となっています。これらの問題は一国のみでの対応が困難であり,国境を越えた地球規模での取組が必要です。
また,このような環境問題は,自然資源の減少や汚染による健康被害等により,人々の生存及び生活を脅かすとともに,将来世代の発展基盤も脅かします。人間の安全保障の視点からも,持続可能な開発によって,経済,環境,社会の両立を図っていくことが重要です。
環境問題は,1970年代から国際的に議論されるようになり,1992年の国連環境開発会議(地球サミット),2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)を経る中で,気候変動枠組条約,生物多様性条約,砂漠化対処条約等の重要な国際的枠組が整備されました。一方,開発援助を巡っては,1980年代以降,開発援助に伴う環境破壊が問題となり,環境配慮の重要性が強く指摘されました。環境問題の改善を図る援助の実施とともに,様々な開発援助の取組の中で環境の視点を入れ込み,環境に配慮した開発を実施することが重要です。
2001年にまとめられたミレニアム開発目標(MDGs)は,こうした流れを受けて,目標7「持続可能な環境の確保」として,ターゲット9「持続可能な開発の原則を各国の政策や戦略に反映させ,環境資源の喪失を阻止し,回復を図る。」,ターゲット10「2015年までに,安全な飲料水を持続的に利用できない人々の割合を半減する。」,ターゲット11「2020年までに,最低1億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する。」といった目標を定めており,国際社会としてその実現に取り組むことが求められています。
ブラジルのリオデジャネイロで開催された国連持続可能な開発会議(リオ+20)は,1992年の地球サミットから20年を経たことを契機に開催されたもので,グリーン経済への移行に向けた取組の推進や持続可能な開発を推進するための制度的枠組み等について合意がなされました。我が国も積極的に議論に参加したほか,「緑の未来」イニシアティブ(PDF)![]() を発表しました。また,この機会に合わせ,リオ+20会議場に隣接して,「日本のグリーン・イノベーション―復興への力,世界との絆」をテーマに,官民協力の下,日本パビリオンが設置され,のべ約2万人が来館しました。
を発表しました。また,この機会に合わせ,リオ+20会議場に隣接して,「日本のグリーン・イノベーション―復興への力,世界との絆」をテーマに,官民協力の下,日本パビリオンが設置され,のべ約2万人が来館しました。
![]() 国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)・京都議定書第7回締約国会合(CMP7)等(2011年)
国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)・京都議定書第7回締約国会合(CMP7)等(2011年)
2011年末に南アフリカ共和国のダーバンで開催された気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)等では,将来の枠組み構築のための新しい特別作業部会の設置,京都議定書第二約束期間に向けた合意,緑の気候基金の基本設計の合意及びカンクン合意の実施のための一連の決定,という4つの大きな成果がありました。京都議定書については,我が国を含むいくつかの国は第二約束期間には参加しないことを明らかにし,そのような立場を反映した成果文書が採択されました。
![]() 生物多様性条約第12回締約国会議・カルタヘナ議定書第7回締約国会合 (2014年)
生物多様性条約第12回締約国会議・カルタヘナ議定書第7回締約国会合 (2014年)
平昌(韓国)で開催された生物多様性条約第12回締約国会議では,愛知目標の中間レビューが行われるとともに,途上国に対する生物多様性に関する国際的な資金フローを2倍にすること等に一致しました。また,同地で開催されたカルタヘナ議定書第7回締約国会合では,締約国が議定書の義務を確実に履行できるようになるため,遺伝子組換え生物等の生物多様性保全への影響に関するリスク評価等を効果的に実施するためのガイダンス文書の作成の進め方等を決定しました。
![]() G8北海道洞爺湖サミット(2008年)
G8北海道洞爺湖サミット(2008年)
・環境・気候変動(サミット文書)(骨子 /仮訳 /英文 )
日本が議長として開催した2008年の北海道洞爺湖サミットで,我が国は森林,生物多様性等の環境問題も取り上げるなど地球環境問題でのイニシアティブを発揮しました。
写真出典:外務省「ミレニアム開発目標MDGs」ハンドブック
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()