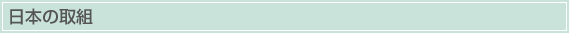| >>環境分野における政策方針 >>環境分野における事例 |
Last Updated: 2011. 04. 01 |
ODAを中心とした環境協力の更なる充実を図っていくために、日本は2002年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD、ヨハネスブルグ・サミット)」の際に「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)」を発表し、これに基づいてさまざまな取り組みを行っています。
パンフレット1:我が国の環境ODA1(和文(PDF)![]() )
)
パンフレット2:気候変動に関する日本の国際協力(和文(PDF)![]() /英文(PDF)
/英文(PDF)![]() )
)
・政府開発援助(ODA)大綱・中期政策での扱い(抜粋)
ODA大綱(2003年8月)
I.理念 ――目的、方針、重点
2.基本方針
(3)公平性の確保
ODA政策の立案及び実施に当たっては、社会的弱者の状況、開発途上国内における貧富の格差及び地域格差を考慮するとともに、ODAの実施が開発途上国の環境や社会面に与える影響などに十分注意を払い、公平性の確保を図る。
3.重点課題
(3)地球的規模の問題への取組
地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、麻薬、国際組織犯罪といった地球的規模の問題は、国際社会が直ちに協調して対応を強化しなければならない問題であり、我が国もODAを通じてこれらの問題に取り組むとともに、国際的な規範づくりに積極的な役割を果たす。
II.援助実施の原則
(1) 環境と開発を両立させる。
III.援助政策の立案及び実施
3.効果的実施のために必要な事項
(2)適正な手続きの確保
ODAの実施に当たっては、環境や社会面への影響に十分配慮する手続きをとるとともに、質や価格面において適正かつ効率的な調達が行われるよう努める。同時に、これらを確保しつつ、手続きの簡素化や迅速化を図る。
ODA中期政策(2005年2月)
3.重点課題について
(1)貧困削減
(ロ)貧困削減のためのアプローチ及び具体的取組
(c)成長を通じた貧困削減のための支援
(ii)均衡の取れた発展
なお、貧困層は自然資源を直接生活の糧としている場合が多いこともあり、環境劣化により特に深刻な影響を受けるため、成長を通じた貧困削減においては、特に持続可能な開発の視点に十分留意する。
(2)持続的成長
(ロ)持続的成長のアプローチ及び具体的取組
(a)経済社会基盤の整備
インフラの建設に当たっては、環境社会配慮を徹底する。
(3)地球的規模の問題への取組
地球温暖化を始めとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、麻薬、国際組織犯 罪といった地球的規模の問題は、国境を越えて個々の人間の生存にかかわる脅威である。国際社会の安全と繁栄を実現するために、我が国はODAを用いて積極的に貢献する。中期政策では、これらの地球的規模の問題のうち、特に貧困削減と持続的成長の達成に密接かつ包括的に関係する環境問題、及び2004年12月に発生したスマトラ島沖大地震及びインド洋津波災害を踏まえ、地震、津波を始めとする自然災害への対応を取り上げる。
(イ)環境問題及び災害への取組に関する考え方
(a)環境と開発の両立を図り、持続可能な開発を進めていくことは世界共通の課題である。地球温暖化の進行、開発途上国における経済成長に伴う深刻な環境汚染、人口増加や貧困を背景とした自然環境の劣化の急速な進行などは、開発途上国の人々の生活の脅威となっている。これら環境問題の解決のためには、広範にわたる一貫した取組が必要である。また、地震や津波などによる災害は、発生直後の被害のみならずその後も人間の生存や社会経済開発を脅かす問題であり、その対応のためには開発途上国の自助努力を支援するとともに緊急対応、復興、予防の各段階に応じた包括的かつ一貫性のある取組が重要である。
(b)我が国は、環境問題に対して、「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)」、「京都イニシアティブ」などに基づき、また、災害問題に対して、「防災協力イニシアティブ」を踏まえて、ODAを活用して積極的に取り組む。
(ロ)環境問題への取組に関するアプローチ及び具体的取組
1)再生可能エネルギー、省エネルギーといった温室効果ガスの抑制・削減(京都メカニズム活用のための支援を含む。)、気候変動による悪影響への適応(気象災害対策を含む。)などの「地球温暖化対策」、2)大気汚染対策、水質汚濁対策、廃棄物処理などの「環境汚染対策」、及び、3)自然保護区の保全管理、森林の保全・管理、砂漠化対策、自然資源管理などの「自然環境保全」の3つを重点分野として、以下のアプローチ及び具体的取組により協力を推進する。
(a)環境問題への取組に関する能力の向上
各国の実情に応じ、開発途上国の関係当局や研究機関などの環境問題への取組に関する能力を総合的に高めるため、人材育成支援を推進するとともに、的確な環境監視、政策立案、制度構築、機材整備などに対する協力を行う。
(b)環境要素の積極的な取り込み
我が国が策定する開発計画やプログラムなどに環境保全の要素を組み込むとともに、適切な環境社会配慮が実施又は確認された開発途上国の事業に対し協力を行う。
(c)我が国の先導的な働きかけ
政策対話、各種フォーラムなどの適切な協力方法を通じて開発途上国の環境意識の向上を図り、環境問題に対する取組を奨励する。
(d)総合的・包括的枠組みによる協力
地域レベルや地球規模の環境問題の解決のために、多様な形態の協力を効果的に組み合わせて総合的・包括的枠組による協力を実施する。
(e)我が国が持つ経験と科学技術の活用
我が国が環境問題を克服してきた経験・ノウハウや複雑化する環境問題に対する科学技術を活用した途上国への支援を行う。それらの経験・ノウハウや、観測、データ解析、対策技術などに関する科学技術は、地方自治体、民間企業、各種研究機関、NGOなど我が国政府機関以外の組織にも幅広く蓄積されており、支援においてはそれらとの積極的な連携を図る。また、専門的知見や実施体制を有する国際機関などとの連携も図る。
(ハ)災害への取組に関するアプローチ及び具体的取組
地震や津波などによる災害に対して我が国が国際的に高い比較優位を有する自国の経験や技術(観測などに関する科学技術を含む。)、人材を活用して、上記(ロ)と同様のアプローチにより取り組む。
・イニシアティブ・資金コミットメント
![]() 気候変動分野における日本の2012年末までの途上国支援(2009年12月)
気候変動分野における日本の2012年末までの途上国支援(2009年12月)
・概要(和文(PDF)![]()
・実績(2010年9月末時点)(和文(PDF)![]() /英文(PDF)
/英文(PDF)![]() )
)
![]() 「いのちの共生イニシアティブ」(生物多様性保全に関する途上国支援イニシアティブ)(2010年10月)
「いのちの共生イニシアティブ」(生物多様性保全に関する途上国支援イニシアティブ)(2010年10月)
・概要(和文(PDF)![]() /英文(PDF)
/英文(PDF)![]() )
)
・抜粋(和文(PDF)![]() /英文(PDF)
/英文(PDF)![]() )
)
・本文(和文(PDF)![]() /英文(PDF)
/英文(PDF)![]() )
)
![]() 持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)(2002年8月)
持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)(2002年8月)
・概要(和文/英文)
・本文(和文/英文)
・概要(和文/英文)
・本文(和文/英文)
・気候変動対策
タイ国「バンコク都気候変動削減・適応策実施能力向上プロジェクト」 地球温暖化問題に対処するための技術協力
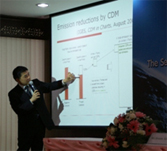
タイの気候変動への取組みを
発表する様子
バンコクには1千万近くの市民が居住し、タイ全体の24%の温室効果ガスが排出されています。2007年5月9日にバンコク首都圏庁(BMA)が温暖化問題に真摯に取り組むことを宣言し、2007年から2012年の5年間で温室効果ガスを15%削減することを目指し、アクションプランが採択されました。 具体的なアクションプランとしては1)大量輸送網システム、2)省エネ及び再生可能エネルギー、3)ビル・家屋の改造・効率化、4)廃棄物・廃水管理、5)都市緑化、の5つの柱を設定し、取組を推進することとしており、本プロジェクトでは、これらのアクションプランを効果的に実施していくためのBMAの能力強化を行っています。
エジプト「ザファラーナ風力発電計画」(有償資金協力、2003年度、134.97億円)

ザファラーナ風力発電計画(エジプト)
エジプトは、化石燃料への依存度を下げるために新・再生可能エネルギーの活用促進に取り組んでいます。日本は、紅海沿岸のザファラーナ地区の120MWの風力発電所の新設を支援し、2009年7月に完成しました。この発電所の稼働によって、同規模の火力発電所を稼働させた場合に比べ、年間約25万トンのCO2排出削減することができると期待されています。このプロジェクトは、2007年6月22日に国連CDM理事会の承認を得て、CDM事業として登録されています。
ラオス 森林資源情報センター整備計画:REDD+への貢献

森林資源情報センター整備計画
(ラオス)
ラオス政府は、2020年までに森林被覆率を70%まで回復する計画を立て、森林法の整備等に取り組む一方で、REDD+に向けた準備も進めています。REDD+を実施するには、衛星情報の解析等による森林資源情報の整備が不可欠です。そこで、我が国は、森林資源の状況を把握し、森林保全を促進するための施設・機材の整備、人材育成の支援を行っています。
・環境汚染対策
モンゴル・ウランバートル大気汚染対策に対する協力(技術協力および有償資金協力)

ウランバートル大気汚染対策
(モンゴル)
モンゴルの首都、ウランバートル市では、急激な人口や自動車の増加に伴い、特に冬季は住居暖房や集中暖房のための小型ボイラー、石炭火力発電所等における生石炭燃焼による大気汚染が著しく、市民の健康に深刻な影響を与えています。このような状況を解決するため、我が国は、大気汚染対策を講じる姿勢を強く打ち出しているウランバートル市とともに、大気汚染のモニタリングや汚染源への規制等を行う仕組みを関係機関とともに構築するため技術協力を実施しています。
また、燃焼効率の悪い旧型ボイラーの取替えや、燃焼負荷の低いバイオブリケット炭などの製造等、大気汚染対策に資する民間ビジネスを対象に、有償資金協力を活用した長期資金の融資を行い、ウランバートル市の大気環境の改善に貢献しています。
パレスチナ「ジェリコ及びヨルダン渓谷における廃棄物管理能力向上プロジェクト」(技術協力プロジェクト:2005年9月~2010年2月、3.9億円)

ジェリコ及びヨルダン渓谷における廃棄物管理能力向上プロジェクト
(パレスチナ)
パレスチナは、イスラエルの占領政策により、土地利用、移動や経済活動に大きな制約があり、政治的にも経済的にも厳しい状況にあります。多くの自治体では、財政難などで廃棄物管理が十分できない状況でした。日本は、広域廃棄物管理を推進するというパレスチナ自治政府の方針に基づき、パレスチナで初めて設立された広域廃棄物管理サービス公社の立ち上げを支援し、その経営の強化、更には他地域への経験普及を通じて、廃棄物管理に関する能力強化支援を行いました。プロジェクト終了時の評価では、90%の住民が廃棄物サービスに満足しているという回答を得ており、また、廃棄物サービス料金の徴収率は93%に達し、財務面の改善も見られます。
・自然環境保全
ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム協力II (マレーシア)
自然環境保全を総合的に推進する技術協力

ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム(マレーシア)
2002年より5年間実施した「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」では、自然環境保全のための包括的な手法・体制が持続可能な形で確立されることを目標に、研究・教育、公園管理、環境啓発等への支援を行いました。2007年より開始したフェーズIIでは、フェーズIで培われた現場活動の成果を行政制度に反映させるため、サバ州生物多様性条例で定められた生物多様性センターの機能強化など、現場での保全活動を推進するための行政制度の強化に取り組んでいます。
サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト(パラオ) 地球規模のサンゴ礁保全のための技術協力

国際サンゴ礁センター(パラオ)
パラオ政府は、サンゴ礁及び関連する海洋生物の研究活動やその保全についての啓発活動を行うセンターの設立を計画し、日本の無償資金協力によって2001年1月にパラオ国際サンゴ礁センターが開館しました。本プロジェクトでは、同センターの組織強化・自立発展を支援するため、同センターの中期戦略計画に即して2002年10月から2006年9月まで4年間の協力を実施し、同センターの研究機能、啓発・教育機能の強化を図っています。また同センターは、地球規模サンゴ礁モニタリングネットワークのミクロネシア地域の拠点としての機能を担っており、地球規模のサンゴ礁保全への貢献が期待されています。
「アマゾン森林保全・違法伐採防止のためのALOS衛星画像の利用プロジェクト」

アマゾン森林・違法伐採防止のためのALOS衛星画像の利用プロジェクト
(ブラジル)
広大なアマゾンの各地で行われる違法伐採を地上パトロールで摘発することは難しいため、人工衛星を用いた宇宙からの監視が違法伐採取締りに重要な役割を担います。本プロジェクトでは、衛星データを用いた違法伐採モニタリングに係わるシステムの開発や人材育成活動を行っています。
サラワク州における生物多様性保全地域の発展(マレーシア)
国際機関(ITTO:国際熱帯木材機関)を通じた熱帯林保全の推進

青少年への意識向上教育の様子
(マレーシア。写真提供:ITTO)
日本は、熱帯林の持続可能な経営を推進する専門機関であるITTOを通じ、マレーシアのサラワク州において生態系保全にむけた州政府の取組を支援してきました。1993年からの支援で保全の強化や保護区の拡大が推進されたLanjak Entimau野生生物保護区は、オランウータン等の野生生物が生息しており、現在ユネスコ世界自然遺産の暫定リストに掲載されています。ITTOは、日本などの支援を受け、さらに2005年からPulong Tau国立公園とその周辺において、州政府・民間企業・地域住民が協力し、生態系調査、地域住民の意識向上及び熱帯林と共生するための職業訓練、隣接するインドネシア側の国立公園との連携を図るといった多面的な活動を通じ、国立公園の生物多様性保全を推進しています。
 Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。
写真出典:外務省「ミレニアム開発目標MDGs」ハンドブック
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()