2 中東地域情勢
(1)中東和平
ア 中東和平をめぐる動き
2014年4月にイスラエル・パレスチナ間の交渉が頓挫して以降、中東和平プロセスは停滞したままの状況が継続している。イスラエルによるヨルダン川西岸地区への入植活動が継続する一方で、ガザ地区からのロケット弾による攻撃も散発的に発生しており、対話の再開には至っていない。
トランプ米国政権は発足以来、米国大使館のエルサレム移転を始めとする一連の親イスラエル政策を実施するとともに、1月には「和平ビジョン」を公表した。5月、イスラエル新政権発足の土台となったリクード党と「青と白」党との間の連立合意において、7月1日以降のヨルダン川西岸地区へのイスラエルの主権適用に関する手続が同ビジョンに沿う形で記載されたことにパレスチナは反発し、緊張が高まった。
8月には、イスラエルによる西岸地区への主権適用の一時停止とともに、イスラエルとアラブ首長国連邦が国交正常化に合意するという歴史的な動きがあった。アラブ首長国連邦がエジプト、ヨルダンに続きイスラエルと国交を有する3番目のアラブ諸国となったのに続き、バーレーン、スーダン、モロッコもイスラエルとの国交正常化に合意した。こうした一連の合意により地域の緊張緩和と安定化が進むことが期待される中、日本は、中東和平問題については、イスラエル・パレスチナの当事者間の対話に基づく「二国家解決」を支持しており、以下に記載の取組などを通じて引き続き尽力していく。
イ 日本の取組
日本は、国際社会と連携しながら、イスラエル及びパレスチナが平和に共存する「二国家解決」の実現に向けて、関係者との政治対話、当事者間の信頼醸成、パレスチナ人への経済的支援の3本柱を通じて積極的に貢献している。日本独自の取組として、ジェリコ農産加工団地(JAIP)を旗艦事業とし、日本、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンの地域協力により、パレスチナの経済的自立を促す中長期的取組である「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。2020年末時点において、JAIPではパレスチナ民間企業16社が操業し、約200人の雇用を創出している。
また、パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)を通じて東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員し、パレスチナの国造りを支援している。
(2)イスラエル
イスラエルは、高度な先端技術開発やイノベーションに優れており、日本の経済にとって重要な存在であると同時に、中東地域の安定にとっても重要な国となっている。
イスラエルでは、1年間で3度の総選挙(2019年4月、9月、2020年3月)を経て、新型コロナ対策が喫緊に求められる状況の下、2020年5月に連立内閣(緊急事態挙国一致内閣)が発足した。しかし7月以降、政府の新型コロナ対応、経済危機対応、ネタニヤフ首相への汚職疑惑(収賄、詐欺、信用失墜の疑惑により、計3件の事案について2020年1月に正式起訴)などをめぐる国民の不満が高まったことで、反首相・反政府抗議活動が国内各地で発生した。社会・経済的代償を強いる防疫施策に関する議論が閣内不和を加速化させ、12月には予算が成立せず、国会が解散に追い込まれ、2021年3月に再び選挙が行われることとなった。新型コロナ対応を含め、内政的には引き続き不透明な状況が続くことが予想される。
日本との関係では、新型コロナの影響を受け、2020年に予定されていたエルアル航空による直行便就航が2021年に延期になったほか、人の往来に大きな制約がかかる中、首脳電話会談(9月及び12月)や外相電話会談(7月)が実施され、新型コロナ流行下においても様々なレベルで活発な交流が続けられた。
(3)パレスチナ
パレスチナは、1993年のオスロ合意などに基づき、1995年からパレスチナ自治政府(PA)が西岸及びガザ地区で自治を開始し、2005年1月の大統領選挙でアッバース首相が大統領に就任した。しかし、その後、アッバース大統領率いるファタハと、ハマスとの間の関係悪化により、ハマスが武力でガザ地区を掌握した。2017年10月には、エジプトの仲介を経て、ファタハとハマスがガザにおけるパレスチナ自治政府への権限移譲に向けて原則合意したが、合意の履行は進んでおらず、依然としてヨルダン川西岸地区をファタハが、ガザ地区をハマスが実効支配する分裂状態が継続している。
2020年5月以降、イスラエルによるヨルダン川西岸地区への主権適用をめぐってパレスチナ自治政府は反発し、パレスチナはイスラエルとの各種協力の停止を表明、これに伴い、パレスチナ自治政府は、イスラエルが代理徴収している税還付金の受け取りも拒否し、財政的に厳しい状況に陥ったが、11月、過去の諸合意を遵守するとのイスラエル政府からの書簡を受領したことを受け、パレスチナ自治政府はイスラエルとの協力再開を表明した。
日本との関係では、1月、ホーリー・パレスチナ解放機構(PLO)執行委員兼難民問題担当局長が訪日し、鈴木馨祐(けいすけ)外務副大臣とパレスチナ難民支援について意見交換を行った。また、5月にオンラインで開催された「パレスチナ支援調整委員会(AHLC)閣僚級会合」に鈴木外務副大臣が出席し、新型コロナ感染拡大に対して、国際社会が協調してパレスチナを支えていくことの重要性を強調しつつ、引き続き「平和と繁栄の回廊」構想など、独自の取組を推進することで中東和平に適した環境醸成に貢献していくと表明した。
(4)イラン
日本の約4.4倍の国土を有し、人口約8,300万人を抱えるイランは、豊富な天然資源に恵まれたイスラム教シーア派の地域大国である。1月に、米国によるソレイマニ・イラン革命ガード・コッヅ部隊司令官の殺害及びイランによるイラク国内の米軍が駐留する基地への報復攻撃が発生し、緊張が高まった。その後、米国・イラン双方が事態の更なる悪化を避ける意向を明らかにしたことで、極度の緊張状態は緩和されたものの、米国とイランの対立を背景として、引き続き高い緊張状態が継続している。4月には、イラン革命ガードがイラン初の軍事衛星搭載ロケットの打ち上げに成功したと発表したほか、ペルシャ湾の公海上を航行中の米海軍の艦船にイラン革命ガードの艦船が異常接近する事案が発生した。また、7月にはイラン国内のウラン濃縮施設での火災、11月にはイラン国内で原子力科学者が殺害される事件が発生した。
イランの核問題をめぐっては、イランは、米国によるイラン核合意(包括的共同作業計画(JCPOA))からの離脱とその後の米国による対イラン制裁の再開により核合意で得られるはずの経済的利益が得られていないとして、2019年7月以降、核合意上の義務を段階的に停止する対抗措置を取ってきた。2020年1月には、ウラン濃縮活動におけるいかなる制約も取り払うことを発表した。こうした動きを受け、核合意の当事国である英国、フランス、ドイツの3か国は、同月、イラン核合意の維持に向け、同合意に基づく紛争解決手続を開始することを表明した。また、イラン核合意の「採択の日」(2015年10月)から5年となる2020年10月にイラン核合意及び国連安保理決議に基づく対イラン武器禁輸措置が解除されることに先立ち、米国は、8月に国連安全保障理事会に対し、イランによる核合意の重大な不履行を通知した。米国は、同通知により、安保理決議第2231号の規定に基づき9月20日以降、イラン核合意は事実上廃棄され、イラン核合意以前の対イラン国連安保理制裁が再適用されたと主張している。しかし、その他のイラン核合意当事国は、核合意から離脱した米国による通知には効力がなく、引き続きイラン核合意は有効であるとの立場をとっている。また、12月にはイラン国会において、イランに20%の濃縮ウラン製造などを義務付ける法案が賛成多数で可決された。これを受け、2021年1月にイランは20%の濃縮ウランの製造を開始した。
2020年11月の米国大統領選挙で勝利したバイデン次期大統領は、イランによる核合意の厳格な遵守を条件として、米国が核合意に復帰する可能性に言及しており、バイデン政権成立後のイランをめぐる情勢が注目される。
日本は、米国と同盟関係にあり、同時にイランと長年良好な関係を維持してきた立場から、2019年6月の安倍総理大臣のイラン訪問や、同年12月のローハニ・イラン大統領の訪日を始め、中東地域における緊張緩和と情勢の安定化に向けた外交努力を行ってきた。2020年1月には、中東において緊張が高まる中、事態の更なる悪化を避けるための外交努力の一環として、安倍総理大臣が、地域に大きな影響力を有するサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーンの3か国を訪問した。また、2月に茂木外務大臣がザリーフ外相との間で日・イラン外相会談を行った。新型コロナの感染拡大の中においても、5月に日・イラン首脳電話会談を、3月及び10月に日・イラン外相電話会談をそれぞれ行い、イランに対し、地域の緊張を高める行動を取らないよう自制を働きかけるとともに、核合意の遵守などを求めた。

(5)トルコ
トルコは、地政学上重要な地域大国であり、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として地域の安全保障において重要な役割を果たすとともに、欧米、ロシア、中東、アジア、アフリカへの多角的な外交を積極的に展開している。また、1890年のエルトゥールル号事件1に代表されるように、伝統的な親日国である。
2018年6月の大統領選挙後、議院内閣制から実権型大統領制へと移行し、行政権の全てが大統領に属する体制となった。大統領の支持率は安定しているが、与党から離脱したババジャン元副首相とダヴトオール元首相が新党を結成するなどの動きが見られた。新型コロナの感染拡大が経済面に悪影響を及ぼしたこともあり、財務大臣及び中央銀行総裁が交代した。
外交面においては、東地中海において、エネルギー資源の探査を目的としたトルコの調査船派遣をめぐり、ギリシャ及び欧州連合(EU)との間で緊張が生じた。米国との間では、ロシア製のミサイル防衛システム(S-400)の導入により制裁が課され、両国関係の懸案となっている。一方、ロシア・トルコ関係では、ガスパイプラインや原子力発電所の建設など、エネルギー分野において緊密な関係が築かれている。シリア情勢に加え、ナゴルノ・カラバフをめぐる紛争においてもロシアとの間で緊密な意思疎通が行われ、11月、トルコはナゴルノ・カラバフ紛争の停戦合同監視センターへの要員派遣を決定した。
日本との関係では、新型コロナの影響から要人往来や対面での協議が困難な中、オンラインで緊密なコミュニケーションが図られた。4月には、安倍総理大臣はエルドアン大統領と電話会談を行い、新型コロナへの対応における連携を確認した。5月には、安倍総理大臣はエルドアン大統領と共にイスタンブール近郊に建設されたバシャクシェヒル「松と桜」都市病院の開院式典にオンラインで出席した。同病院は日本企業とトルコの大手建設会社が官民連携方式(PPP)で建設した大規模総合病院であり、新型コロナ患者の受入れも行った。さらに、安倍総理大臣の辞任(9月)及び菅総理大臣の就任の際(10月)はそれぞれエルドアン大統領と電話会談を行うなど、緊密なやりとりがなされている。また、トルコでは2月にエラズー県において、10月にはイズミル県でそれぞれ地震が発生し、多くの犠牲者が発生したことを受け、菅総理大臣及び茂木外務大臣からお見舞いを伝えた。

(6)湾岸諸国及びイエメン
湾岸諸国2は、日本にとってエネルギー安全保障などの観点から重要なパートナーである。近年、石油依存からの脱却や産業多角化、人材育成などを重要課題として経済、社会の改革に取り組んでおり、日本としても、こうした改革は中東地域の長期的な安定と繁栄に資するとの観点の下、その実現に向けて協力、支援を行ってきている。具体的には、サウジアラビアの脱石油依存と産業多角化のための「サウジ・ビジョン2030」を踏まえ、日本とサウジアラビアが二国間協力の羅針盤として策定した「日・サウジ・ビジョン2030」や、日本とアラブ首長国連邦の間の「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ」に基づく協力などを進めている。
1月には、地域の緊張が高まる中、安倍総理大臣がサウジアラビア、アラブ首長国連邦及びオマーンを訪問し、各国との間で、事態の悪化を防ぐため、全ての関係者が自制的に対応し、あらゆる外交努力を尽くすべきとの認識で一致するとともに、地域の様々な問題について平和的な、そして対話を通じた解決に向けた機運を醸成していくことが重要であるとの認識を共有した。また、安倍総理大臣は、各国との二国間関係強化を図るとともに、オマーンにおいてはカブース国王崩御の弔問を実施した。
10月には、茂木外務大臣がサウジアラビアとクウェートを訪問した。サウジアラビアでは、幅広い分野で両国の戦略的パートナーシップを一層強化していくことで一致するとともに、G20リヤド・サミットの成功や、中東地域の平和と安定に向けた協力を確認した。クウェートではサバーハ首長の薨去(こうきょ)に伴う弔問を行うとともに、包括的パートナーシップの発展に向けた協力を進めていくことで一致した。
新型コロナの影響により、要人往来が減少した中であったが、菅総理大臣とムハンマド・サウジアラビア皇太子(11月)、ムハンマド・アブダビ皇太子(12月)がそれぞれ電話会談を行うとともに、外相電話会談をカタール(4月)、クウェート(4月)、サウジアラビア(7月、9月)、アラブ首長国連邦(7月)との間でそれぞれ行い、各国との関係強化や中東情勢の緊張緩和と情勢の安定化に向けた協力を確認した。12月には、「日・サウジ・ビジョン2030」の閣僚会合をオンラインで開催し、協力の進展を確認するとともに、今後の協力の方針について意見交換を行った。
イエメンでは、グリフィス国連事務総長特使を始めとした国際社会による仲介努力にもかかわらず、イエメン政府及びアラブ連合軍と、ホーシー派との間での衝突が継続している。また、中央政府と、同国南部の自治を志向する南部移行評議会(STC)との間でも衝突が継続していたが、12月、両者による新政府樹立などを内容とする「リヤド合意」に基づき、新内閣が発表された。長期化する衝突の影響により、イエメンでは厳しい人道状況が継続しており、日本は2015年以降、国連機関などと連携し、イエメンに対し、合計約3億米ドル以上の支援を実施してきている。6月に、オンライン形式で開催された「イエメン人道危機に関するハイレベル・プレッジング会合」では、鈴木外務副大臣から、イエメンの人道状況を改善するとともに、政治的解決を実現すべく、引き続き貢献していくことを表明した。
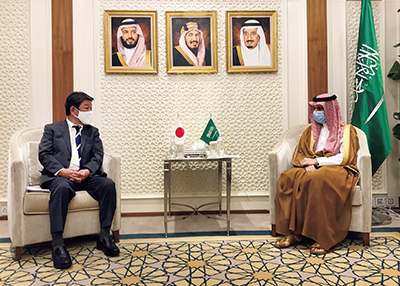
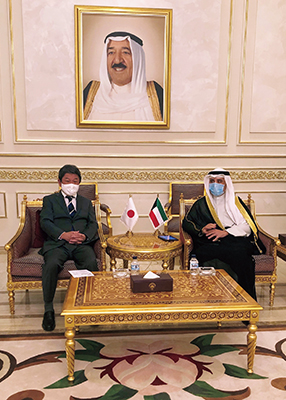
(10月3日、クウェート・クウェート)
(7)イラク
イラク情勢は、2020年を通して米国とイランの対立を背景とする地域の緊張状態の影響を大きく受けた。1月3日に米国がイラク国内でソレイマニ・イラン革命ガード・コッヅ部隊司令官及びムハンディス・イラク人民動員部隊機構副長官ほかを殺害すると、1月5日にイラク国民議会は外国軍駐留の終了を求める決議を可決、1月8日にはイランがイラク国内の米軍駐留基地に対して弾道ミサイルによる報復攻撃を行った。また、3月には米軍駐留基地へのロケット攻撃で米軍兵士ほかが死傷したことを受け、米国がシーア派武装組織の拠点を空爆した。また、米国大使館や米軍の駐留する基地などを狙った攻撃が頻発した。
また、これと併行して、イラク軍や治安機関による「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」掃討作戦を支援してきた米国主導の有志連合軍は、イラク国内での作戦の進捗状況及び新型コロナの感染拡大を背景に、3月末以降、イラク軍に任務を委譲して複数の基地から撤退を進めており、米国は、2021年1月15日までに駐留部隊を2,500人規模に削減した。しかし、バグダッドを含むイラク中部・北部などでISILによる散発的なテロが依然として継続しており、駐留米軍に関するバイデン新政権の対応が注目される。また、イラク北部では、6月以降、トルコ軍がクルディスタン労働者党(PKK)に対し、地上戦を含む軍事作戦を実施している。
内政面では、民衆デモが続く中、2019年12月にアブドルマハディー首相が任期途中で辞職し、2020年5月にカーズィミー首相を首班とする新内閣が発足した。カーズィミー首相は、就任以来、油価下落や新型コロナの感染拡大による財政難への対応、国民生活の改善、治安回復などの多くの課題に取り組んでいる。
日本は2003年以降一貫して対イラク支援を継続しており、2020年には、ISILからの解放地復興や難民帰還支援などのための約4,000万米ドルの支援などを国際機関経由で実施した。
(8)アフガニスタン
2020年は、アフガニスタンの和平プロセスにおいて重要な動きが見られた。約1年半にわたり直接協議をしてきた米国とタリバーンは、アフガニスタン全土で戦闘行為を大幅に抑制する1週間の「暴力削減」期間を経て、2月29日、アフガニスタン駐留米軍の条件付き撤収及びアフガニスタン人同士の交渉(和平交渉)開始などを含む合意に署名した。また、同日、アフガニスタン及び米国は、カブールで、米国・タリバーン合意の内容を追認する共同宣言を発表した。
アフガニスタン政府及びタリバーンの双方は、米国・タリバーン合意に基づき、和平交渉の前提となる信頼醸成措置として囚人の相互解放を実施した後、9月12日に和平交渉をドーハ(カタール)で開始した。和平交渉の開会式には日本から鈴木外務副大臣がオンライン形式で出席し、和平交渉の開始を歓迎し、アフガニスタン人主導の和平プロセスを支持すると述べるとともに、和平交渉が着実に進展することへの強い期待を表明した。
アフガニスタン治安部隊とタリバーンの間では、2018年6月の初停戦に続き、2020年5月及び7月のイスラム教の祝祭に合わせて一時的な停戦が成立したが、和平交渉開始後も激しい衝突が継続している。また、ISIL系組織によるテロも頻発するなど、治安状況は引き続き不安定である。米国はアフガニスタン駐留部隊の段階的撤収を進め、2021年1月15日までに2,500人規模に削減しており、バイデン新政権の下で、NATO主導の「確固たる支援任務(RSM)」の今後の方針が注目される。
内政面では、2019年9月の大統領選挙の最終結果が2020年2月に発表され、ガーニ大統領の再選が確定した。しかし、対立候補であったアブドッラー前行政長官は選挙の不正を主張し、ガーニ大統領の2期目就任宣誓式と同日に独自の「大統領」就任を宣言するなど、内政上の混乱が見られた。これに対し、国内や米国からの働きかけもあり、両者は5月に包摂的な政府樹立のための政治合意に署名し、アブドッラー氏は新設の国民和解高等評議会の議長に就任した。
日本は、2001年以降、68億米ドル以上の対アフガニスタン支援を実施してきており、主要ドナーとしてアフガニスタンの復興に貢献している。11月に行われた日・アフガニスタン外相電話会談では、アトマル外相から日本の支援に対する深い謝意が表明された。11月にオンライン形式で開催された「アフガニスタンに関するジュネーブ会合」では、茂木外務大臣がビデオ・メッセージを通じて、アフガニスタン自身の改革努力を前提に、2021年から2024年まで、過去4年間と同水準となる年間1億8,000万米ドル規模の支援維持に努めることなどを表明した。アフガニスタン支援に尽力した中村哲氏が銃撃テロ事件で逝去(せいきょ)してから1年を迎えた12月には、ガーニ大統領が同氏の功績を称えるメッセージ映像を発表した。

(9)レバノン
2019年10月以降、増税措置などへの反対を契機とする大規模反政府デモが発生し、ハリーリ首相が辞職した。2020年1月、ディアブ内閣が成立するも、2月以降、レバノンでも新型コロナの感染が拡大し、それに伴う経済活動停滞により更に経済が悪化した。3月、政府は外貨建て国債の返済延期を表明した。
こうした中、8月、ベイルート港で大規模爆発が発生し、190人が死亡、6,500人以上が負傷し、約30万人が家を失い、被害総額は約150億米ドルと推定されている。また、この爆発の原因として政府の長年の怠慢や汚職体質を非難する大規模反政府デモも発生し、同月にはディアブ首相が辞職した。その後、新政権樹立に向けた組閣作業は難航し、内政安定化や行財政改革などの実施に向けた見通しは立っていない。こうした中、国際社会は、必要な人道支援を行う一方、レバノン政府に行財政改革や汚職対策などの迅速な実施を要求している。
日本は、人道状況が悪化するレバノンを支援すべく、難民支援及びホスト・コミュニティー支援として、2012年以降、計2億2,000万米ドル以上の支援を行っている。
また、8月のベイルート港での大規模爆発を受けて、緊急援助物資の供与を行ったほか、9月には国際機関を通じて500万米ドルの緊急無償資金協力を行った。さらに、日本のNGOは、日本からの財政支援の下で約120万米ドルの草の根人道支援プログラムを実施している。こうした支援について、8月にオンラインで開催された「ベイルート及びレバノン国民に対する支援のための国際会議」で中山展宏外務大臣政務官が、12月に同じくオンラインで開催された「レバノン国民に対する支援のための国際会議」では鷲尾英一郎外務副大臣が、それぞれ発信した。
(10)シリア
ア 情勢の推移
2011年に始まったシリア危機は、10年目を迎えたものの情勢の安定化及び危機の政治的解決に向けた見通しが立っておらず、今世紀最悪の人道危機と言われる状況が継続している。
イドリブ地域では、2019年4月以降、ロシアの支援を受けたシリア政府軍と反体制派との間で戦闘が激化して、96万人以上の国内避難民が発生するなど人道状況が悪化した。2020年2月、シリア政府軍は2012年以来初めてダマスカス・アレッポ間の高速道路(M5)を制圧した。その後もイドリブ地域での戦闘が継続する中で、3月にはトルコが「春の盾」作戦を開始した一方、同月には露・トルコ首脳会談が開催され、両国はイドリブ地域における停戦や「安全回廊」の設置、共同パトロールの実施などを柱とする追加議定書に合意した。同合意以降、イドリブ地域における停戦はおおむね維持されているものの、散発的な衝突や空爆なども引き続き起きており、イドリブ情勢は引き続き予断できない状況が続いている。
紛争の長期化に伴う社会・産業インフラの荒廃などにより、シリア経済が悪化してきていた中、特に、2020年に入ると、隣国のレバノンでの経済危機や、新型コロナのシリア国内での感染拡大などで、経済悪化が更に加速するとともに、シリア通貨の価値の大幅な下落が見られるようになった。こうした中、シリア国民は、急激な物価上昇と所得減少や失業などに伴う購買力低下、食料品や日用品の不足などに直面しており、シリア政府が物価安定に向けた有効な手立てを立てられない中、シリア国内での人道状況の更なる悪化が懸念されている。
イ 政治プロセス
政治プロセスについては、2018年以降、シリア人対話が中断していた状態が続いていたが、2019年10月から国連の仲介により「憲法委員会」が活動を開始した。同委員会はシリア憲法の改革についてシリア人同士が議論することを目的としているが、これまで複数回の会合が開かれているものの具体的な議論の進展は見られない。この点、2020年7月にはシリア人民議会選挙が実施され、また、現行憲法に基づけば2021年にはシリア大統領選挙の実施が見込まれる中、国際社会は、シリア危機の政治的解決を求める国連安保理決議第2254号に沿った政治プロセスの進展を図るべく、シリア政府に対してその建設的な関与を引き続き求めている。
ウ 日本の取組
日本は、一貫して、シリア危機の軍事的解決はあり得ず、政治的解決が不可欠であると同時に、人道状況の改善に向けて継続的な支援を行うことが重要との立場をとっている。そのため日本は、シリア情勢が悪化した2012年以降、計29億米ドル以上のシリア及び周辺国に対する人道支援を実施してきた。
日本は、2019年来人道状況が悪化していた北西部に対する支援として、2020年3月に470万米ドルの緊急人道支援を実施した。また、12月には、北東部カミシリ県の中核病院であるカミシリ国立病院の修復や医療機材の供与を通じて安定的な保健医療サービス供給をはかることを目的として、600万米ドルの新規支援を行うことに加えて、食料や越冬準備のための緊急人道支援として、720万米ドルの新規支援を決定した。
(11)ヨルダン
ヨルダンは、混乱が続く中東地域において、新型コロナの感染が拡大する中でも比較的安定を維持している。アブドッラー2世国王のリーダーシップの下で行われている過激主義対策、多数のシリア難民の受入れ、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。
日本との関係では、4月には外相電話会談、首脳電話会談が行われ、新型コロナが拡大する中、緊密な連携を確認し、中東地域が不安定化しないことが重要であるとの認識を共有した。また、9月には安倍総理大臣の辞任に際して再度首脳電話会談が行われるなど、首脳・閣僚級の対話が活発に行われている。両国は、戦略的パートナーシップの下、外交、安全保障や経済など、幅広い分野における二国間関係の更なる発展と中東地域の安定に向けた協力の進展を図ってきており、新型コロナ対策においても、6月にはヨルダンから日本に対し医療用マスクなどの医療用品が提供されたのに対して、日本からヨルダンに対しても保健・医療分野での無償資金協力を行った。
日本は地域安定の要であるヨルダンとの関係を重視しており、10月には第2回外務・防衛当局間協議を開催するなど、安全保障面での協力を継続しつつ、8月には日・ヨルダン投資協定が発効し、経済面での協力も進展している。また、2018年11月のアブドッラー2世国王訪日時に署名した開発政策借款3億米ドルのうち1億米ドルを2020年3月に、さらに1億米ドルを12月に拠出し、ヨルダンを経済・財政的にも継続的に支援している。
1 エルトゥールル号事件の詳細については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page22_001052.html 参照

2 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート及びバーレーン
