2 中東地域情勢
(1)アフガニスタン
中東、中央アジア、南アジアの連結点に位置し、歴史的に様々な宗教、文化、民族が交錯してきたアフガニスタンは、地政学的に重要な国である。
アフガニスタンでは、タリバーンが2021年8月に首都カブールを制圧し、翌月に「暫定政権」の樹立が発表されたが、民族・宗教的包摂性の欠如が指摘されている。また、女子中等・高等教育の停止を始め、女性・女児の権利の大幅な制限が報告されており、国際社会は深刻な懸念を表明している。さらには、ISIL系組織により、教育機関、モスク、外交団などを標的としたテロが各地で発生するなど、治安情勢の悪化も懸念されている。
こうした中、日本は、包摂的な政治体制の構築、女性・少数派を含む全てのアフガニスタン人の権利の尊重、テロとの決別などの国際社会の懸念について、タリバーン幹部に対し、直接の働きかけを継続している。
国連の発表によると、アフガニスタンにおいては、人口の約3分の2が人道支援を必要としており、近年の干ばつや洪水、地震を始めとする自然災害も重なり、深刻な経済停滞と食料不足が問題となっている。こうした危機的状況を踏まえ、日本は、ほかのドナー国(援助国)とも連携しつつ、タリバーンによるカブール制圧以降も国際機関などを経由し人道支援やベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)に応える支援を継続してきた。2022年も、6月に発生した東部における大規模な地震被害に対して緊急援助物資の供与及び300万ドルの緊急無償資金協力を実施したほか、12月には、食料、保健、水・衛生、農業などの人道ニーズなどを支援するため、令和4年度補正予算において約9,800万ドルの追加的支援を決定した。これにより、2021年8月以降の日本による支援額は約3億3,900万ドル規模となった。
日本は、引き続きアフガニスタンの人々に寄り添う支援を行い、アフガニスタンを取り巻く地域の安定の確保に貢献していく考えである。
(2)中東和平
ア 中東和平をめぐる動き
2014年4月にイスラエル・パレスチナ間の交渉が頓挫して以降、中東和平プロセスの停滞は継続している。バイデン米政権発足後、当事者間の協力再開の動きが一時見られ、ハイレベルでの接触など前向きな動きもあったが、2022年3月以降は、エルサレムを含め、イスラエル及びパレスチナにおいて暴力行為や衝突が断続的に発生し、多数の死傷者が出る等足元の治安情勢が悪化するなど、不安定な緊張状態が継続している。ガザ地区では、8月1日のイスラエルによるパレスチナ武装勢力幹部の拘束を契機に緊張が高まり、同月5日以降、イスラエル国防軍(IDF)とパレスチナ武装勢力の間で攻撃の応酬に発展、エジプトの仲介による停戦までの3日間で、パレスチナ側で43人死亡、300人が負傷する事態となった。
イ 日本の取組
日本独自の取組としては、日本、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンの地域協力により、パレスチナの経済的自立を中長期的に促す「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。2022年末時点において、旗艦事業のジェリコ農産加工団地(JAIP)ではパレスチナ民間企業14社が操業し、約200人の雇用を創出している。また、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」を通じて東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員し、パレスチナの国造りを支援している。
(3)イスラエル
高度な先端技術開発やイノベーションに優れているイスラエルは、日本の経済にとって重要な存在であると同時に、中東地域の安定にとっても重要な国となっている。
イスラエルでは、ヤミナ党のベネット党首率いる連立政権内での対立が深まり、離反議員が続出するなど、政権運営に行き詰まった。ベネット首相は、6月に国会の解散法案を成立させ、11月1日の総選挙実施を決めて退陣、政権発足時に合意されていた首相輪番制の下、ラピード首相代理兼外相が首相に就任した。2019年4月以来、約3年半で5度目となる11月の総選挙では、連立与党ブロックとネタニヤフ前首相率いる右派ブロックが争い、後者が過半数となる64議席を獲得、ネタニヤフ前首相が組閣指名を受け、12月に右派政党を含む新政権が発足した。
日本との関係では、2022年は外交関係樹立70周年に当たり多くの行事が日本とイスラエルで行われ、8月にはガンツ副首相兼国防相、9月にはラズヴォゾフ観光相が訪日した。11月には「あり得べき日・イスラエル経済連携協定(EPA)に関する共同研究」の立上げが発表された。

(4)パレスチナ
パレスチナは、1993年のオスロ合意などに基づき、1995年からパレスチナ自治政府(PA)が西岸及びガザで自治を開始し、2005年1月の大統領選挙でアッバース首相が大統領に就任した。しかし、その後、アッバース大統領率いるファタハと、ハマスとの間の関係が悪化し、ハマスが武力でガザを掌握した。2017年10月にはエジプトの仲介により、ガザにおけるパレスチナ自治政府への権限移譲が原則合意され、また2022年10月にはアルジェリアの仲介で、パレスチナ立法評議会選挙の1年以内の実施などを掲げる、パレスチナ諸派間の和解文書である「アルジェ宣言」が署名されたが、その具体的な履行の見通しはついておらず、依然として西岸をファタハが、ガザをハマスが支配する分裂状態が継続している。
日本との関係では、9月にハムダッラー前首相が、アッバース大統領の名代として故安倍晋三国葬儀に参列し、岸田総理大臣と意見交換を行った。
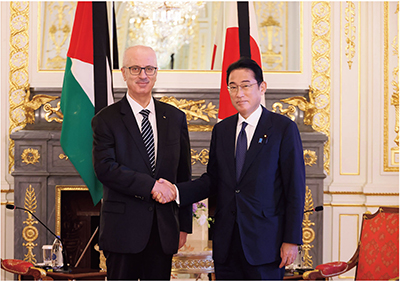
(9月28日、東京 写真提供:内閣広報室)
(5)イラン
イランは、約8,500万人の人口と豊富な天然資源を誇るシーア派の地域大国であり、日本とは90年以上にわたり伝統的な友好関係を発展させてきている。
近年では、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)ワクチンの供与を含む医療・保健、環境、防災、領事などの分野での二国間協力が行われている。
イランの核問題をめぐっては、イランは、米国のトランプ前政権によるイラン核合意(包括的共同作業計画(JCPOA))からの離脱とその後の米国による対イラン制裁の再開により、核合意で得られるはずの経済的利益が得られていないとして、2019年7月以降、核合意上のコミットメントを段階的に停止する対抗措置を取ってきており、2022年末現在、60%までの濃縮ウランの製造を行っている。また、イランは、国際原子力機関(IAEA)による抜き打ち査察を可能にしていた追加議定書の履行停止なども行っている。
バイデン米国政権は、イランによる核合意の厳格な遵守を条件として、米国も核合意に復帰する用意があると発表しており、2021年4月以降、米国及びイラン双方による核合意への復帰に向けた協議が、欧州連合(EU)などの仲介によりウィーンで断続的に行われてきたが、交渉は難航しており、米国及びイランによる核合意上のコミットメント遵守への復帰は実現していない。
このような中、2022年3月には、イランはイスラエルによるイランへの攻撃の拠点がイラク北部にあると主張し、イラク北部エルビル市に向けてミサイル攻撃を実施した。5月には、テヘラン市におけるイラン革命ガード大佐の殺害事案や、同市郊外のイラン国防軍需省研究施設における事故が相次いで発生した。さらに、同月、イランは、ペルシャ湾の入り口に位置するホルムズ海峡において、ギリシャ船籍の石油タンカー2隻が違反行為を行ったと主張し、これらの船舶を拿(だ)捕した。また、9月以降、イランによるイラク北部へのロケットなどによる攻撃が断続的に発生した。10月には、イラン南部シーラーズ市内のシーア派聖 廟(びょう)でISILによるテロ事件も発生した。このように、イランをめぐる情勢は高い緊張状態が継続している。
一方、2021年4月以降、外交関係を断絶しているイランとサウジアラビアが協議を実施しており、2022年4月にも、イラク・バグダッドにおいて5回目となる両国間の協議が実施された。また、イランとカタール、オマーン、UAEなど近隣諸国との間でも協議が行われている。
イラン国内では、9月には、ヒジャブ(髪を隠すために被るスカーフ)の乱れを理由に、警察に逮捕されたマフサー・アミーニ女史が死亡したことに端を発する抗議活動が発生し、デモ隊と治安部隊との衝突が継続した。これを受けて、平和的な抗議活動に対する実力行使を控えることをイラン政府に求めるG7外相声明や人権理事会共同声明などが発出された。また、11月に実施された人権理事会特別会合において、イランの人権状況悪化を調査する事実調査ミッションの設置を決定する決議が採択され、12月にも、国連経済社会理事会において、イランを「国連女性の地位委員会(CSW)」から除名する決議が採択された。
ロシアによるウクライナ侵略をめぐっては、イランによるロシアへの無人航空機(ドローン)の提供について、国際社会からの非難が高まった。その後、イランは、ウクライナ侵略開始前にロシアに対してドローンを供与したことを明らかにした。
日本は、米国と同盟関係にあると同時にイランと長年良好な関係を維持してきた。2月には、林外務大臣とアブドラヒアン外相との電話会談及び岸田総理大臣とライースィ大統領との電話会談を実施した。さらに、9月には、岸田総理大臣が、訪問中のニューヨーク(米国)において、ライースィ大統領との間で初めてとなる対面での会談を実施するなど、あらゆる機会を捉えて、イランに対し、イランに関わる諸課題について懸念事項を直接伝達するなど、中東地域における緊張緩和と情勢の安定化に向けた独自の外交努力を行ってきている。
(6)トルコ
トルコは、地政学上重要な地域大国であり、北大西洋条約機構(NATO)加盟国として地域の安全保障において重要な役割を果たしており、欧米、ロシア、中東、アジア、アフリカへの多角的な外交を積極的に展開している。また、1890年のエルトゥールル号事件2に代表されるように、伝統的な親日国である。
2018年の議院内閣制から実権型大統領制への移行後、エルドアン大統領は、新型コロナ対策において強いリーダーシップを発揮し、支持率を一時回復させた。しかし、以前から芳しくない経済指数は改善せず、インフレが加速する中、政策金利を繰り返し引き下げたことでリラは市場最安値を更新し続けた。インフレの加速は、同大統領を支持してきた保守的な労働者や中低所得層の生活を圧迫しており、2023年に建国100周年と大統領選・議会選挙を控える中、エルドアン大統領の支持率は低迷している。
外交面においては、引き続き、これまで関係の悪化が懸念されていた域内諸国との対話再開と関係の再構築が進められた。エルドアン大統領は2月にアラブ首長国連邦(UAE)を9年ぶりに、4月にサウジアラビアを5年ぶりに、10月にアルメニアを13年ぶりに訪問し、首脳会談を行った。8月に外相会談を行ったイスラエルとは、4年ぶりに互いに大使を任国へ派遣した。また、ロシアによるウクライナ侵略をめぐっては、両国との良好な関係をいかした積極的な仲介外交を展開しており、黒海を通じたウクライナからの穀物輸出再開の実現に大きく貢献した。
日本との関係では、林外務大臣が3月にトルコを訪問し、チャヴシュオール外相と会談を行った。9月に行われた故安倍晋三国葬儀にはチャヴシュオール外相が参列し、外相会談が行われた。首脳レベルでは、9月の国連総会の際に岸田総理大臣がエルドアン大統領と首脳会談を実施した。

(9月20日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)
(7)イラク
イラクは、2003年のイラク戦争後、2005年に新憲法を制定し、民主的な選挙を経て成立した政府が国家運営を担っている。
外交面では、イラン、サウジアラビア、トルコといった地域大国の間に位置し、近隣諸国との関係強化やバランス外交を志向している。特にサウジアラビアとイランの仲介に努めており、4月にはバグダッドで第5回サウジアラビア・イラン協議を開催し、6月にはカーズィミー首相が両国を歴訪した。
内政面では、2021年10月の第5回国民議会選挙で最多議席を獲得したサドル派(シーア派)が新政府形成を目指していたものの、主要な政治連合勢力であるシーア派調整フレームワーク(SCF)と対立し、新政府が発足できず、混乱状態が継続していた。6月にはサドル派議員が総辞職し、8月にサドル師が政界引退を発表すると、10月に国民議会はラシード大統領を選出し、同大統領が指名したスーダーニー首相候補による内閣が承認され、国民議会選挙から1年余りを経て新政府が発足した。
日本は2003年以降、一貫して対イラク支援を継続しており、新政府発足直後の11月には、髙木啓外務大臣政務官が首都バクダッド及び南部のバスラ県を訪問し、イラク新政府にとって初の外国賓客として、スーダーニー首相及び主要3閣僚(ダーウド貿易相、ファーデル電力相、アブドゥルガニー第二副首相兼石油相)と会談した。髙木政務官は、バグダッド国際見本市に出席したほか、日本の対イラク支援の象徴的な円借款案件である「ハルサ火力発電所改修計画」及び「バスラ上水道整備計画」の完工式典に出席し、「バスラ製油所改良計画」の視察を行った。

治安情勢については、8月に新政府形成をめぐる混乱からバグダッドのインターナショナルゾーン内で武力衝突が発生したほか、イラク北部のクルディスタン地域(KR)に対する攻撃が問題となっている。トルコ軍がKRのクルディスタン労働者党(PKK)に対し、地上戦を含む軍事作戦を継続しているほか、イラン革命ガードは、KRのイラン・クルディスタン民主党(KDPI)に対し、ミサイル及びドローンによる攻撃を実施した。
(8)ヨルダン
ヨルダンは、混乱が続く中東地域において比較的安定を維持しており、アブドッラー2世国王のリーダーシップの下で行われている過激主義対策、多数のシリア・パレスチナ難民の受入れ、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。
日本との関係では、両国の皇室及び王室は伝統的に友好な関係にあり、9月には故安倍晋三国葬儀に伴いアブドッラー2世国王が訪日した。
首脳レベルでは、1月に岸田総理大臣が同国王と首脳電話会談を実施し、戦略的パートナーシップの下、協力関係を今後更に発展させることを確認した。9月には故安倍晋三国葬儀で訪日した同国王と首脳会談を実施し、中東和平を含む地域情勢について協議し、地域の長期的な安定に向けて、緊密に連携していくことを確認した。
外相レベルでは、9月にニューヨークで林外務大臣がサファディ副首相兼外相と外相会談を行い、「二国家解決」に基づく中東和平実現及び難民支援の重要性を共有した。また、第3回外相間戦略対話の実施及び日本・エジプト・ヨルダン三者協議など二国間関係及び各種の協力枠組みを更に発展させていくことで一致した。
加えて、12月には防衛省による令和4年度統合展開・行動訓練を初めてヨルダンで行い、同月に第4回外務・防衛当局間協議を開催するなど、安全保障面でも協力を積み重ねてきている。また、同月、日本は開発政策借款1億ドルを拠出し、経済・財政的支援を行っている。
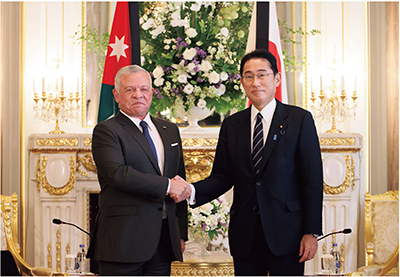
(9)湾岸諸国とイエメン
湾岸諸国は、日本にとってエネルギー安全保障などの観点から重要なパートナーである。特に2022年は、ロシアのウクライナ侵略などを受けエネルギー価格が高騰し、国際エネルギー市場の安定化に向けた湾岸産油・産ガス国の役割が重要となった。一方、湾岸諸国は、近年、石油依存からの脱却や産業多角化などを重要課題として社会経済改革に取り組んでおり、日本としても、こうした改革は中東地域の長期的な安定と繁栄に資するとの観点の下、その実現に向けて協力、支援を行ってきている。包括的な二国間協力の枠組みとして、サウジアラビアとの「日・サウジ・ビジョン2030」や、アラブ首長国連邦(UAE)との「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)」などが設置され、これらの下で幅広い分野の協力を進めている。
サウジアラビアにおいては、2016年に策定された「サウジ・ビジョン2030」の下で、産業多角化(国内産業育成)、人材育成、公共投資基金(PIF)を通じた積極的な投資、観光地やインフラ開発などに加え、観光査証の発給開始、女性の社会参画の推進、娯楽産業の振興など、包括的な社会経済改革が進められている。同国のこうした改革努力を後押しするため、日本は、岸田総理大臣とムハンマド・サウジアラビア皇太子兼首相の間での2月、3月及び9月の3回の電話会談、林外務大臣とファイサル・サウジアラビア外相の間での3回の会談(2月は電話、7月及び9月は対面)を通じて、国際原油市場の安定化に向けた連携を確認した。また、「日・サウジ・ビジョン2030」の枠組みの下での様々な分野での協力を一層推進し、両国の戦略的パートナーシップを強化させることを確認した。
外交関係樹立50周年を迎えたUAE(160ページ コラム参照)とは、3月の林外務大臣のUAE訪問、6月及び9月のジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使の訪日など、活発な要人往来が行われたほか、岸田総理大臣もムハンマド大統領(5月に大統領就任)との間で3月及び9月の2回にわたって電話会談を行い、両国間の戦略的パートナーシップの一層の強化や国際原油市場の安定化に向けた連携を確認した。5月にはハリーファ大統領の逝去に伴い、甘利明総理特使がUAEを弔問した。9月には、林外務大臣とジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使の間で、「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)の実施に関する共同宣言」に署名したほか、防衛装備品・技術移転協定の実質合意、11月からのUAEの一般旅券所持者を対象とした査証免除措置の導入など、両国間の協力が大きく進展した。
同じく外交関係樹立50周年を迎えたオマーンとバーレーンには、6月に本田太郎外務大臣政務官が訪問し、外相などと会談したほか、バーレーンとの間で投資協定に署名した。バーレーンとの間では、2回の首脳会談(4月は電話、9月は対面)及び9月の外相会談に加え、9月の日・バーレーン外務省間政策協議、外交・公用旅券所持者の査証免除措置の早期導入に向けた調整などを通じて、政治、経済・ビジネス分野での協力が進展した。オマーンとの間でも、外務大臣レベルでの電話会談や、9月の故安倍晋三国葬儀へのマアシャニー・オマーン宮内省顧問の参列などの機会を活用し、二国間関係の更なる強化を確認した(160ページ コラム参照)。
カタールとは、岸田総理大臣がタミーム・カタール首長と4月及び9月の2回にわたって電話会談を行い、世界最大級の産ガス国であるカタールと国際エネルギー市場の安定化に向けて緊密に連携することを確認した。また、11月から12月にかけて、中東初となるFIFAワールドカップがカタールで開催され、日本代表チームも参加した。
クウェートとは、8月に本田外務大臣政務官が同国を訪問したほか、林外務大臣とアフマド・クウェート外相が2回の会談(4月は電話、9月は対面)を行った。また、12月には岸田総理大臣がミシュアル・クウェート皇太子との間で電話会談を行い、国際原油市場の安定化に向けて緊密に連携することを確認した。
イエメンの安定は、中東地域全体の平和と安定のみならず、日本のエネルギー安全保障に直結するシーレーンの安全確保の観点からも重要である。イエメンでは、イエメン正統政府及びアラブ連合軍と、ホーシー派との間での衝突が継続していたが、グランドバーグ国連事務総長特使を始めとした国際社会による仲介により、4月に6年ぶりに全土での停戦が実現した。10月に停戦が失効したものの、ホーシー派による越境攻撃は2022年末まで発生していない。一方、紛争長期化により、イエメンは「世界最悪の人道危機」とされる深刻な状況に直面し、ウクライナ情勢を受けた穀物価格の高騰及び原油価格上昇に起因する輸送費用の高騰などにより飢餓発生リスクが一層増大している。日本は2015年以降、主要ドナー国として国際機関などと連携し、イエメンに対し、合計約4億ドルの人道支援を実施してきているほか、5月には停戦を支えるため、国連世界食糧計画(WFP)を通じた1,000万ドルの緊急無償資金協力(食料支援)を決定し実施した。
(10)シリア
ア 情勢の推移
2011年3月に始まったシリア危機は、発生から11年が経過するも、なお情勢の安定化及び危機の政治的解決に向けた見通しは立っておらず、2019年に国連の仲介により設立され政権側及び反体制派側が一堂に会する「憲法委員会」の下での議論も平行線をたどっている。シリア政府は4月には大規模な恩赦令を発出し、国民和解に向けた措置を見せるものの、具体的な成果は未知数のままである。一方、シリア国内で人道支援を必要とする人々の規模は2022年末時点で1,460万人(前年比120万増)に上り、国内避難民の数も690万人(同20万人増)に達するなど、危機発生以降、人道支援ニーズが最も高い状況にあるとされている。なおシリア周辺国に退避した難民の本国帰還の進展も低調なままとされている。
対外関係では、アサド政権を支持するロシアやイランとの協力関係は維持されている一方、2021年に見られたアラブ諸国との関係改善の動きは2022年においては低調となり、11月に開催されたアラブ連盟首脳サミットではシリアの復帰は協議対象とならなかった。なお、欧米諸国は、アサド政権による化学兵器使用や人権蹂躙(じゅうりん)行為などを理由に、シリア政府との関係再開には依然として慎重な姿勢を維持している。
軍事・治安面では、首都ダマスカスの治安は総じて維持されている一方、シリア国内の刑務所へのISILによる襲撃事案(1月)やISIL指導者などの死亡が複数回発表されるなど、テロ勢力の活動と掃討作戦が継続している。特に北部においては、11月にイスタンブールで発生した爆発事案の報復措置として、トルコがクルド人武装組織拠点への空爆を強化し、大規模な地上作戦の実施を示唆している。また、シリアにおける親イラン勢力などの活動を警戒するイスラエルは、ダマスカス空港を始めとするシリア国内への空爆を断続的に行っている。
2022年はアラブ首長国連邦(UAE)、オマーン、バーレーンと、それぞれ外交関係樹立50周年の節目を迎えたことを記念し、日本及び各国で様々な取組、交流活動が行われました。

日本とUAEの関係は、公式な外交関係を樹立する1972年5月以前(UAEは1971年12月に建国)に遡ります。1960年代後半からの日本企業によるアブダビでの石油開発への参入、1970年の大阪万博へのアブダビ首長国の参加など、UAE建国以前から活発な交流が行われていました。それから50年が経(た)ち、現在では、エネルギー分野にとどまらず、様々な分野で両国の協力が進んでいます。また、UAEには、4,000人以上の在留邦人と300社以上の日系企業が進出しており、中東・アフリカ地域で最大の邦人コミュニティが形成されています。
2021年10月から2022年3月まで、ドバイにおいて中東地域初となる国際博覧会が開催されました。来場者数は2,400万人を超え、日本パビリオンにも多数の来場者がありました。閉幕式には、若宮健嗣国際博覧会担当大臣が出席し、次回の大阪・関西万博に向けて万博旗を引き継ぎ、UAEから日本へバトンが渡されました。
両国間では、2018年4月に発表した「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)」に基づき協力を進めてきましたが、2022年9月、林外務大臣とジャーベル産業・先端技術相兼日本担当特使の間で、「CSPIの実施に関する共同宣言(CSPI枠組文書)」への署名が行われました。これによって今後、エネルギー分野にとどまらず、再生可能エネルギー、インフラ、環境、科学技術、教育、宇宙、防衛などの幅広い分野で両国の協力関係が一層強化されることが期待されています。このほかにも、9月の故安倍晋三国葬儀へのハーリド・アブダビ執行評議会委員兼執行事務局長(ムハンマド大統領長男)の参列など、両国間の活発な要人往来や会談を通じ、外交関係樹立50周年の機会を捉え、二国間関係強化のため引き続き緊密に連携していくことを確認しました。
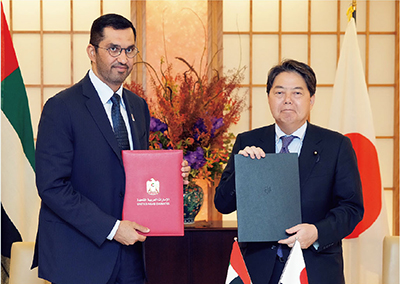
また、11月1日から、UAEの一般旅券所持者を対象として、事前の登録を不要とする新たな査証免除措置が開始されました。これにより、UAEから日本への観光客の更なる増加、ビジネス面での利便性の向上などにつながることが期待されています。

オマーンは、アラビア海とオマーン海に挟まれ、ペルシャ湾に通じるホルムズ海峡を自国の領海内に擁し、古くから海洋国家として発展してきました。アデン湾やインド洋にもアクセスできる地政学的にも優れた要衝であり、石油・天然ガスの輸入のみならず、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」というビジョンを実現する上で重要な国です。
日本とオマーンは、1972年に公式な外交関係を樹立しました。その後の50年間、日本企業によるオマーンの石油・液化天然ガス(LNG)権益への参画を始めとして、両国はエネルギー分野を中心に、様々な分野で関係を強化してきました。2014年に安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてオマーンを訪問した際には、「日本国とオマーン国との間の安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップの強化に関する共同声明」を発出するなど、両国の関係は一層深化しています。
節目の年となった2022年は、4月の林外務大臣とバドル外相の電話会談のほか、5月には旭日大綬章叙勲に伴う親授式出席のためアラウィ元外相が、9月には故安倍晋三国葬儀へ参列するためにマアシャニー宮内省顧問一行がそれぞれ訪日するなど、両国の絆(きずな)を確認する1年ともなりました。


バーレーンは、ペルシャ湾・アラビア湾に浮かぶ日本の佐渡島ほどの小さな島国です。紀元前三千年紀にはディルムン文明の中心地として、また、古代より真珠の産地として栄えてきました。
日本とバーレーンの関係は、公式な外交関係を樹立する1972年以前に遡ります。1932年に湾岸諸国で初めての油田がバーレーンで発見されると、1934年にはバーレーン産原油が初めての輸出先として日本に輸出されました。このように日本とバーレーンは古くから強い結び付きがあり、エネルギー、政治、経済、ビジネス、安全保障などの幅広い分野で良好な関係を築いてきました。
加えて、2月には、バーレーンとUAEが共同開発した人工衛星「ライト1号」が、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力により、国際宇宙ステーションの実験棟「きぼう」から放出され、地球軌道への投入に成功するなど、新たな分野での二国間協力も進んでいます。また、バーレーンでは日本車を筆頭に日本の技術や製品に対する日本のプレゼンスが高く、近年では、若年層に日本のアニメやマンガの人気が高まっているほか、富裕層においては、新婚旅行先として日本の人気も広がっています。
2022年は両国の要人往来も活発に行われ、4月には、岸田総理大臣がサルマン皇太子兼首相と電話会談を行い、9月には、6年ぶりとなる日・バーレーン外務省間政策協議が東京で開催され、バーレーンからアブドッラー政務担当外務次官が訪日しました。また、同月末の故安倍晋三国葬儀に際しては、サルマン皇太子兼首相及びザヤーニ外相が参列し、その後の会談では、外交関係樹立50周年の機会も捉え、両国関係をより一層強化していくことで一致しました。

(9月28日、東京 写真提供:内閣広報室)
外交関係樹立50周年を祝し、本田外務大臣政務官が6月にオマーン及びバーレーンを訪問しました。
オマーンでは、バドル外相、ウーフィー・エネルギー・鉱物資源相らオマーン側閣僚と会談を実施し、クリーン・エネルギーなどを含む次の50年に向けた二国間協力について意見交換を行い、引き続き協力深化に向けて連携していくことで一致しました。
バーレーンでも、ザヤーニ外相やサルマン財務・国家経済相と会談を行ったほか、同財務・国家経済相の立ち会いの下、日・バーレーン投資協定への署名を行いました。バーレーンとは、2008年に「日・バーレーン・ビジネス友好協会」、2012年に「日本・バーレーン経済交流協会」が設置されるなど、様々なレベルでの経済交流が続いており、今後、同協定の発効により、投資環境の整備が一層促進され、両国の経済関係が更に緊密化することが期待されます。
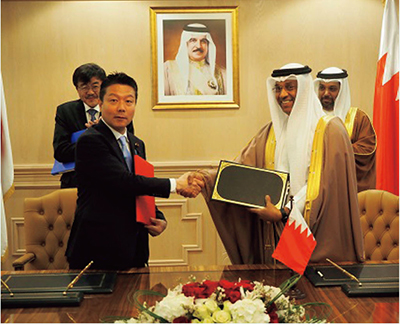
UAEでは伝統工芸品「尾張七宝(おわりしっぽう)」に関するセミナー、バーレーンでは日本の和太鼓の講演が開催され、オマーンでも、11月に陸上自衛隊西部方面音楽隊などによる自衛隊音楽隊初の中東公演(オマーン軍楽祭に参加)が、首都マスカットのロイヤル・オペラハウスで実施されました。

日本においても、UAEとの記念事業としてアラブ地域の伝統楽器である「ウード」によるコンサートが開催されました。また、駐日オマーン大使館が主催したオマーン・山梨宝飾展が承子女王殿下のご臨席の下で開催されたほか、同大使館におけるナショナルデー・レセプションに山田賢司外務副大臣及び髙木啓外務大臣政務官を始め、多くのゲストが参加するなど、官民問わず、活発な交流が実施されました。加えて、考古学分野における日・バーレーン両国の協力関係を発信するシンポジウムが開催されるなど、文化・学術分野での交流も更に盛り上げる機会となりました。
イ 日本の取組
日本は、一貫して、シリア危機の軍事的解決はあり得ず、政治的解決が不可欠であると同時に、人道状況の改善に向けて継続的な支援を行うことが重要との立場をとっている。5月に開催された「シリア及び地域の将来の支援に関する第6回ブリュッセル会合」には本田外務大臣政務官が出席し、対シリア人道支援における日本の揺るぎない決意を表明した。日本は、シリア情勢が悪化した2012年以降、総額約33億ドルの人道支援をシリア及び周辺国に対して実施してきている。
(11)レバノン
レバノンは、引き続き経済危機など様々な課題に直面する中、議会選挙が5月15日に大きな混乱なく予定どおり実施され、また10月にはイスラエルとの間の海洋境界が画定され国連事務局に登録されるなど前向きな進展も見られた。
一方、政治勢力間の対立などにより議会選挙後の新内閣が成立していないことに加え、10月末で任期切れとなったアウン大統領の後任を選出する議会での協議も妥結に至らず、大統領不在という政治空白が生まれている。この政治的混乱は、レバノンにおける経済や人道状況の更なる悪化に拍車をかけている(10月には30年ぶりにコレラの国内感染が確認された。)。通貨価値の下落とそれに伴う物価高騰、また停電や燃料不足の継続に市民の不満は蓄積しており、銀行への襲撃事案などが度々発生する事態に発展した。
日本は、人道状況が悪化するレバノンを支援するため、2012年以降、合計2億5,680万ドル以上の支援を行っている。また3月には両国間で技術協力協定の署名が行われた。
2 エルトゥールル号事件の詳細については、外務省ホームページ参照:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page22_001052.html

