3 国際機関における取組
(1)WTO
ア WTOが直面する課題
天然資源に乏しい日本が、戦後、目覚ましい経済成長を遂げることができたのは、自由貿易体制の恩恵をいかしてきたためである。WTOは貿易自由化のルール作り、WTO加盟国間の紛争解決、WTO協定の履行監視などを通じて自由貿易の推進を後押ししてきた。しかし、現在のWTOは、新興国の台頭やデジタル経済といった変化に十分対応できておらず、さらに新型コロナも自由貿易体制における新たな課題を生んでいる。
WTOの機能不全が端的に現れているのが、ドーハ・ラウンド11の停滞に見られるルール形成機能の弱体化であり、上級委員会の機能停止に代表される紛争解決制度の停滞である。また、各国の貿易政策の透明性と予見可能性を高めるため、通報など協定履行監視を行っているものの、義務履行状況は芳しくない。
WTOの統計によれば、新型コロナの感染拡大により、2020年の世界全体の貿易量は前年比9.2%減の見通しとなり、多くの国がマスクなどの医療品や食品の輸出規制を導入した。これら輸出規制については、現行のWTO協定での対応では限界があり、新型コロナ、そして将来のパンデミックに備える観点から、新しいルール作りの必要性が加盟国間で議論されている。
イ 高まるWTO改革の機運
上記の様々な課題に直面し、WTOは、オコンジョ=イウェアラ新事務局長(2021年3月に就任)の下、その改革(157ページ 特集参照)を進めていく必要性が国際社会において強く認識され、その機運が高まっている。
デジタル経済については、2017年の第11回WTO閣僚会議(MC11)で有志国による共同声明イニシアティブが発出され、現在86か国が参画するWTO電子商取引交渉が活発化している。日本も「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」12を実現させるために「大阪トラック」13の下で、WTO電子商取引交渉をオーストラリア及びシンガポールと共に共同議長国として主導している。また、WTOでは加盟国の3分の2が自己宣言のみで「途上国」として協定上の義務が免除されている(「特別のかつ異なる待遇(S&DT)」14)。先進国は、新興国が台頭する中で各国が応分の責任を果たすべきとの立場であり、近年、台湾、ブラジル、シンガポール及び韓国が現在及び将来の交渉におけるS&DTを放棄した。S&DTは真に必要な国に、真に必要な範囲で認められるべきであるとの立場の下、日本も建設的に議論に参加している。
紛争解決制度については、上級委員会機能停止を受けて、一部の国は暫定的な代替措置として、多国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)15と呼ばれる制度を立ち上げた。一方、日本は、上級委員会が明確かつ迅速に案件を解決するという本来の役割を果たせていないとの問題に対応した形での恒久的な紛争解決制度改革を重視しており、同改革を主導している。
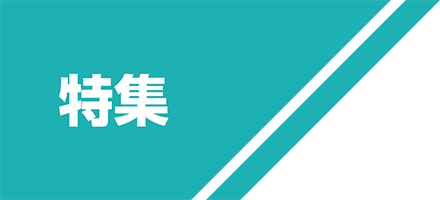
自由貿易を止めない─。菅総理大臣が国連総会で発信し、その後のG20サミットやAPEC閣僚会議でも国際社会が目的を共有した世界貿易機関(WTO)の改革。WTO改革で日本がリードする国際協調の一端を紹介します。
WTOは1995年の創設以降、世界の自由貿易を支えてきました。しかし、25年を迎えたこの国際機関が、時代の趨勢(すうせい)に対応できなくなっています。例えば、新興国の台頭やデジタル化の進展は、ここ数年で国際貿易やビジネスの現場の様相を一変させましたが、それを律するルールは追いついていません。また、WTOの紛争解決手続は1年以上機能停止の状態にあります。さらに、一方的な関税措置の応酬や新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)に伴う輸出制限の増加など、世界全体が内向き・縮み志向を強めています。2020年はこれまで以上に、WTOの制度疲労と大胆な改革の必要性を痛感した1年でした。
WTO加盟164か国は、制度立て直しの真っただ中にあるのかもしれません。日本は、戦後のGATT※・WTO体制の恩恵を受けて平和と繁栄を享受してきました。最近は、保護主義が高まる中、TPP11協定、日EU・EPA、日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定、日英包括的経済連携協定及びRCEP協定の署名などを通じて、世界に自由貿易の血液を必死に循環させてきました。自由貿易の旗手たる日本のこうした実績には、WTO改革の主力打者としての期待が寄せられています。
日本は、WTOの山積する課題の中でも、特に以下の4点を重視し、各国とスクラムを組み改革に日々汗をかいています。
一つ目は、新型コロナ流行下で世界中でデジタル化が進む中、信頼性のある自由なデータ流通(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト:DFFT)の原則に基づき新しいルールを作ること。日本は2019年のG20大阪サミットの際、デジタル経済に関する国際的ルール作りを進めるための「大阪トラック」を立ち上げました。この傘の下、日本はWTOで、現在90近い加盟国が参加する電子商取引交渉の共同議長をオーストラリアとシンガポールと共に務めています。デジタル技術の普及や利用状況の異なる各国の利害調整は大変です。
二つ目は、新興国の台頭で国際経済の実態が変わる中、各国が応分の責任を果たす環境を作ること。ここでは、例えば、企業活動に対する非市場経済国家の過剰な介入を抑えるための「市場志向条件」を米国などと示してきました。
三つ目は、新型コロナ流行下で一時的にはやむを得ないものの、自由貿易を制限しかねない措置に条件を付すこと。10余りの有志国と練り上げた提案を、WTO全体のルールとするよう議論しています。
最後は、恒久的な紛争解決制度への改革です。オーストラリアやチリと共に、上級委員会が長年積み重ねてきた諸問題への処方箋を提案しました。
WTO改革は待ったなしです。日本は国際社会で果たすべき責任を担うためにも、2021年2月に任命されたオコンジョ=イウェアラ事務局長を盛り立て、他の加盟国と協力しながら、多角的自由貿易体制の維持・強化に引き続き貢献していきます。
WTO改革及び日本の取組については、連載企画「なぜ、今、WTO改革なのか」も是非御覧ください(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_002061.html)。


(10月27日、東京)
※GATT:General Agreement on Tariffs and Trade
ウ 新型コロナに係るWTO及びその他国際場裡での動き
2020年は、新型コロナの感染拡大により露呈した自由貿易体制の限界や脆弱(ぜいじゃく)性を踏まえ、切迫感をもって取り組むべき行動について、様々な場で合意が見られた。3月及び5月にはG20貿易・投資担当大臣臨時テレビ会議が行われ、貿易円滑化や透明性確保、グローバルサプライチェーンの強靭化について「新型コロナウイルスに対して世界貿易・投資を支えるためのG20行動」が発出された。WTOでは、通常の会合が延期となる中、新型コロナに関連した貿易関連措置のモニタリングや、貿易への影響分析などをWTO事務局が行ってきた。また、日本も共同提案国となり、「新型コロナウイルスと多角的貿易体制に関する閣僚声明」が発出され、WTO通報の重要性や、紛争解決制度改革の恒久的な解決を含むWTO改革が強調された。6月には、WTO改革を推進する少数有志国の集まりであり、日本も参加するオタワ・グループ閣僚会議で「新型コロナウイルスに焦点を当てた行動」が発出され、新型コロナに係る貿易措置が「的を絞り、目的に照らし相応で透明かつ一時的なもので、WTOルールと整合的」であるべきとの原則が再確認されるとともに、医療用品や電子商取引などの分野でも合意が見られ、また、11月にも同閣僚会合が開催され日本は積極的に議論に貢献した。

エ 第12回WTO閣僚会議(MC12)に向けた議論
新型コロナの感染拡大により2020年6月の開催が延期となったMC12に向けた議論は続いており、以下のような点が特に注目されている。
漁業補助金交渉については、「国連持続可能な開発のための目標(SDGs)」で定められた「違法・無報告・無規制(IUU)16漁業や過剰漁獲につながる補助金の禁止」の達成に向け、MC11での決定を踏まえ、全WTO加盟国が参加する漁業補助金交渉が進んでいる。日本は、真に過剰漁獲能力・過剰漁獲につながる補助金を規制すべきとの立場で、早期の交渉妥結を目指して、積極的に交渉に参加している。
また、デジタル分野のルール作りについては、新型コロナの世界的感染拡大も受け、インターネットを介した貿易やデジタル経済の果たす役割が大きくなっている中、交渉の重要性が一層高まっている。前述のWTO電子商取引交渉は新型コロナの流行により一時中断を余儀なくされたものの、その後は、バーチャル形式での会合を活用し、継続的に協議されている。日本は共同議長国として交渉を主導し、12月、共同議長報告を発表し、高い水準のルール作成を目指して、交渉を加速させることを確認した。日本は、MC12に向けて、国境を越えるデータの移転、個人情報の保護などの論点を含め、実質的な進展を図るべく、引き続き主導的な役割を果たしていく。
オ 個別の紛争処理案件
WTO紛争解決制度は、加盟国間のWTO協定上の紛争を手続に従い解決するための制度である。同制度は、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられる。日本が当事国である最近の主な案件は以下である(2020年12月現在)。
・韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置(DS504)17:2016年6月にパネルが設置され、2018年4月に韓国の措置がWTO協定違反であると認定された。2019年9月に、上級委員会もパネルと同様の判断を行い、韓国に対する措置の是正勧告が確定した。2020年8月に韓国は措置を撤廃した。
・インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置(DS518):2017年4月にパネルが設置され、2018年11月にインドの措置がWTO協定違反と認定された。同年12月に上級委員会に付託されたが、上級委員会の機能停止を受け手続が停止している。
・韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置(DS553):2018年10月にパネルが設置され、2020年11月、韓国の措置がWTO協定違反と認定され、措置の是正が勧告された。
・韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571・DS594):2018年11月、日本は韓国に対し二国間協議を要請し、同年12月協議を実施した。2020年1月、韓国における新たな支援措置も対象として改めて協議を要請し、3月に協議を実施した。
・インドによる情報通信技術(ICT)製品の関税上の取扱い(DS584):2019年5月、日本はインドによるICT製品を対象とした関税引上げ措置のWTO協定整合性につき、二国間協議を要請した。2020年7月にパネルが設置された。
・日本による対韓国輸出管理運用の見直し(DS590):2019年7月、日本は、韓国への半導体材料3品目(フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素)の輸出に係る措置の運用を見直し、個別に輸出許可を求める制度とした。同年9月、韓国は日本の措置がWTO協定に違反するとして二国間協議を要請し、2度の協議を実施した。同年11月、韓国は日韓当局間の輸出管理政策対話が正常に行われる間、本件WTO紛争解決手続を中断すると発表し、2回にわたり輸出管理政策対話が行われたが、韓国は2020年6月にWTO紛争解決手続を再開し、7月にパネルが設置された。
(2)経済協力開発機構(OECD)
ア 特徴
OECD18は、政治・軍事を除く経済・社会の極めて広範な分野(マクロ経済、貿易・投資、農業、産業、環境、科学技術など)を扱う「世界最大のシンクタンク」として政策提言を行っているほか、各種委員会などで行われる議論を通じて、国際的な規範を形成している。日本は、1964年に非欧米諸国として初めてOECDに加盟して以降、各種委員会などでの議論や、財政・人的な貢献を通じて、OECDの取組に積極的に関わってきている。
イ 2020年閣僚理事会
当初5月に予定されていた閣僚理事会は新型コロナの影響により延期となり、6月から9月にかけて、分野別の閣僚理事会ラウンドテーブルが3回開催され、新型コロナ対策や回復に向けた政策に係る各国の知見が共有された。「コロナ危機からの回復への道」をテーマに開催された10月の閣僚理事会では、菅総理大臣がビデオメッセージを発出し、国際連携の重要性を強調するとともに、感染拡大防止と社会経済活動の回復の両立に向けOECDが政策協調の場として果たす役割に期待すると述べた上で、デジタル化や人の往来の再開に向けた日本の取組を発信した。また、鷲尾英一郎外務副大臣から、政府全体でのデジタル化の取組、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)を踏まえたルール作りを後押しするOECDの活動の重要性、中長期的な医療・保健システム強化を含む日本の国際協力の取組を強調するとともに、アジア地域へのアウトリーチ(関係強化・政策対話)を牽引(けんいん)していくと発信した。

(10月29日、東京)
ウ OECD条約署名60周年記念式典
12月のOECD条約署名60周年記念式典では、菅総理大臣がビデオメッセージで参加し、これまでのOECDの優れた経済分析や質の高いルール作りなどの活動を高く評価し、グローバル化や新型コロナ危機におけるOECDの役割の重要性を強調したほか、「デジタル化の推進」や「グリーン社会の実現」といった課題への日本の取組を発信し、OECDと東南アジアを含むアジア地域への関係強化を後押ししていくと述べた。
エ 各分野での取組
鉄鋼の過剰生産能力問題について、2016年のG20杭州サミット(中国)を受けて、鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム(GFSEC)が設立された。2020年10月の閣僚会合には、30の主要鉄鋼生産国・地域及びOECD事務局などが参加し、新型コロナの鉄鋼需要への影響や構造的な過剰生産能力問題の解消に向けた多国間の協力について議論を行った。引き続き、日本はこの課題の解決に向け強いリーダーシップを発揮し、積極的な役割を果たしていく。
また、OECDはG20との連携を強化しており、経済の電子化に伴う国際課税原則の見直し、質の高いインフラ投資やコーポレート・ガバナンスに関する原則策定などの分野で協力している。
オ アジアとの関係強化
OECDは、世界経済の成長センターとしての東南アジアの重要性の高まりを受け、同地域との関係強化を重視している。2020年は、東南アジア諸国とOECD加盟国との間でオンライン形式による様々な政策対話などが行われた。新型コロナへの対応としてOECDが東南アジアで優先的に取り組むべき分野などについても議論が行われ、協力の重要性が確認された。今後も、東南アジア地域プログラムを効果的に活用しながら、同地域からの将来的な加盟も見据えつつ、引き続き、同地域の経済統合や国内改革を後押ししていくことが重要である。
カ 財政的・人的貢献
日本は、OECDのⅠ部予算(義務的拠出金)の9.4%(2020年、米国に次ぎ全加盟国中第2位)を負担しており、OECD事務局のナンバー2のポストである事務次長(現在は河野正道次長)も歴代輩出している。また、日本はOECD開発センターへの分担金最大負担国(2020年)であるほか、開発センター次長(湯浅あゆ美次長(2020年9月着任))を輩出するなど、財政的・人的貢献を通じてOECDを支えている。
11 「ラウンド」とは、全ての加盟国が参加して行われる貿易自由化交渉を意味する。GATT(関税及び貿易に関する一般協定)の時代には、1947年にジュネーブにおいて第1回目の交渉が行われたのを皮切りに、その時々の世界経済の要請に応える形で、1994年に終了したウルグアイ・ラウンドに至るまで、合計8回のラウンド交渉が行われた。ウルグアイ・ラウンドでは、サービス貿易や知的財産権など、いわゆる新分野へのルールの適用や、WTOという国際機関の設立を始めとする機構面の強化などが決定され、その後、WTO体制の下で初めて開始されたのがドーハ・ラウンドである。
12 信頼性のある自由なデータ流通(DFFT):Data Free Flow with Trust。2019年1月のダボス会議でのスピーチにおいて安倍総理大臣が提唱した、デジタル経済の国際的なルール作りを進めていく上でのコンセプト。具体的には、データを特定の国が独占するのではなく、プライバシーやセキュリティ、知的財産などの安全を確保した上で、原則として国内外において自由に流通させることを目指す考え方
13 2019年のG20大阪サミットの際に安倍総理大臣が主催した「デジタル経済に関する首脳特別イベント」において立ち上げられた、デジタル経済、特にデータ流通や電子商取引に関する国際的なルール作りを進めていくプロセス
14 特別かつ異なる待遇(S&DT):「Special and Differential Treatment」を指し、WTO協定の文言上、開発途上国やLDC(後発開発途上国)諸国に対して「特別」又は「(先進国とは)異なる」扱いを認めているもの。具体的には、義務の免除や緩和、技術協力を開発途上国に与える条項などが各協定にS&DT条項として存在している。
15 多国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA):Multi-party Interim Appeal Arbitration。上級委員会が機能回復するまでの当面の代替策としてEUが提案し、上級委員会に類似した仲裁手続を活用する内容。2020年4月に有志国・地域により同制度設立がWTO事務局に正式通報された。
16 IUU:Illegal, Unreported and Unregulated
17 「DS○○○」の番号は、協議要請がなされた時点でWTO事務局により紛争案件に付される整理番号で、1995年のWTO紛争解決(Dispute Settlement)制度開始以来の整理番号
18 OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development
