6 中東・北アフリカ各国
(1)ヨルダン・レバノン
2014年は日・ヨルダン外交関係樹立60周年であった。11月にはアブドッラー2世国王陛下を実務訪問賓客として日本に迎えるなど活発な要人の往来が行われ、伝統的に良好な両国の関係が更に深まった1年であった。特に、アブドッラー2世国王陛下の訪日では、安倍総理大臣との首脳会談が行われたほか、両国では初めてとなる共同声明を発出し、二国間関係の更なる強化と地域の平和と安定に向けた協力を確認した。混乱が続く中東地域において、ヨルダンは安定を維持しており、多数のシリア難民の受け入れやISILに対する取組、中東和平への積極的な関与など、ヨルダンが地域の平和と安定のために果たしている役割は、国際的にも高く評価されている。日本もこうしたヨルダンの役割を高く評価し、ヨルダンの安定の維持と産業基盤の育成のために継続的に支援してきている。2014年も有償資金協力「財政強化型開発政策借款」(120億円)や、一般文化無償資金協力「ペトラ博物館建設計画」(6億8,620万円)などの支援を行った。また、2015年1月、安倍総理大臣がヨルダンを訪問し、アブドッラー2世国王陛下との首脳会談において、上述の120億円の円借款を含む新規支援を表明したほか、両国の戦略的関係を更に発展させ、中東の平和と安定を促進するための協力を継続することを改めて確認した。
レバノンは、キリスト教やイスラム教などの18の宗教・宗派が混在する文化的に多様な国である。2013年3月のミーカーティー首相辞任から1年近くを経て、2014年2月にサラーム新内閣が発足した。一方、5月に任期が終了したスレイマン大統領の後任は未だ選出されておらず(2015年1月現在)、2013年6月に延期された国会議員選挙も実施の目処が立っていない。レバノンは、隣国シリア情勢の悪化やISILの勢力拡大など、地域を揺るがしかねない重大な諸課題に直面している。しかし、レバノンの安定は地域の安定と繁栄の鍵であり、日本はレバノンに対し、シリア難民支援など総額7,470万米ドルの人道支援を行っている。
(2)トルコ
トルコは、欧州、中東、中央アジア、コーカサス地域の結節点に位置する地政学上重要な地域大国としてだけでなく、国際社会においてもその存在感を高めており、2014年12月からG20議長国を務めている。また、1890年のエルトゥールル号事件、1985年の在テヘラン邦人救出事件などのエピソードに代表されるように歴史を通じた親日国であり、近年は、両国首脳間の強固な信頼関係に基づき、特に経済分野を中心として、協力関係が深化している。
2014年は、日・トルコ外交関係樹立90周年にあたり、2013年5月に首脳間で合意された「日本国とトルコ共和国の戦略的パートナーシップの構築に関する共同宣言」に基づき、様々な分野で協力関係に進展が見られた。1月、エルドアン首相が10年ぶりに日本を公式訪問し、安倍総理大臣と2013年以来通算3度目となる首脳会談が実現した。4月には、広島での軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)外相会合の機会にダーヴトオール外相が訪日し、岸田外務大臣との外相会談が実現したほか、彬子女王殿下がトルコを御旅行になるなど、ハイレベルの要人往来が活発に行われた。また、経済・文化面でも官民連携の下で両国の協力関係を促進するため、12月、外務省を事務局として、「日トルコ経済・文化交流促進官民連絡協議会」が設立された。
日本とトルコは、2015年がエルトゥールル号事件125周年となることを見据え、二国間関係の更なる強化を目指すこととしている。
(3)エジプト
アフリカ大陸の北東に位置し、地中海を隔てて欧州に接するエジプトは、中東・北アフリカ地域の安定に重要な役割を有する大国である。
同国では、2014年1月に修正憲法案の国民投票が実施され、98.1%の賛成を得て承認された。また、5月26日から28日にかけて大統領選挙が実施され、エルシーシ前国防相が当選し、6月8日に新大統領に就任した。今後、議会選挙が実施され、一連の政治プロセスが完了する予定である。
日本との関係では、7月に岸外務副大臣がエジプトを訪問し、エルシーシ大統領を表敬、シュクリ外相と会談を行った。9月には、国連総会出席の際、安倍総理大臣とエルシーシ大統領との首脳会談が行われた。2015年1月には、安倍総理大臣がエジプトを訪問し、エルシーシ大統領、マハラブ首相と会談を行ったほか、今後の二国間関係を深化させる包括的な共同声明に合意した。また、日エジプト経済合同委員会の場で「中庸が最善:活力に満ち安定した中東へ-新たなページめくる日本とエジプト-」と題する政策スピーチを行い、25億米ドル相当の新たな中東支援を含め、中東地域の安定に向けた日本の貢献を表明した。さらには、エルシーシ大統領と日本の経済ミッションとの会合などを通じて、スエズ運河開発計画や電力エネルギー分野などの国家的プロジェクトに日本企業が参画し、両国経済関係の更なる拡大につなげる機会となった。
(4)リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコ
欧州・アフリカ・中東の結節点に位置するマグレブ地域は、歴史的、文化的、言語的共通性を有しており、近年、経済分野を始め地域としての潜在性に注目が集まっている。3月には岸外務副大臣がモロッコ、アルジェリア、チュニジアを訪問した。
「アラブの春」と呼ばれる中東・北アフリカの政変により長期政権が崩壊したチュニジアとリビアでは、民主化の定着が最優先課題である。1月に新憲法が制定されたチュニジアでは、10月に議会選挙が行われた。同国の民主化を一貫して支持する日本は、中根外務大臣政務官率いる選挙監視団を派遣した。その後に行われた大統領選挙を経て、まもなく新政権が成立し、民主化プロセスが完了する予定である。一方、リビアでは、部族社会に根ざす勢力間の対立と治安の悪化が深刻である。6月には代表議会選挙が行われたが、未だ制憲議会から代表議会への正式な権限委譲はなされておらず、国連や近隣諸国による仲介努力が続いている。なお、治安の著しい悪化を受け、在リビア日本大使館は7月から一時閉館している。
アルジェリアやモロッコでは、安定した政権運営が続いている。アルジェリアでは、4月の大統領選挙でブーテフリカ大統領が4選を果たした。16年目に入った同政権は、憲法改正を始めとする諸改革に着手すると同時に、周辺国の情勢悪化などを受け、国内での治安・テロ対策を強化している。モロッコでは、質の高いインフラや地政学的利点から外国企業の進出が顕著である。日本企業の進出も拡大しており、2015年にJETRO事務所が活動を開始した。
(5)湾岸諸国(イエメンを含む。)
(ア)湾岸6か国(アラブ首長国連邦(UAE)、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーン)
湾岸諸国は引き続き堅調な経済を維持しており、エネルギー安全保障の観点やインフラや医療システム輸出などを展開する上でも重要な市場である。2013年から2014年1月にかけて、安倍総理大臣はこれら湾岸諸国を全て訪問し、エネルギーのみならず幅広い分野において重層的な関係(「包括的パートナーシップ」)を築いていくことを確認した。また、湾岸諸国からも2014年2月のサウジアラビアのサルマン皇太子及びアラブ首長国連邦(UAE)のムハンマド・アブダビ首長国皇太子のそれぞれの公式訪問を始めとして、各国要人による訪日が活発に行われた。
一方、2014年は、湾岸諸国も少なからずISILの活動の活発化の影響を受けた。これらの国々の若者が外国人戦闘員としてISILに参加する問題が顕在化したほか、サウジアラビア、UAE、カタール及びバーレーンが米国主導の対ISIL空爆に参加した。
(イ)イエメン
イエメンでは、国内紛争の激化のため、2014年6月以降不安定な治安情勢が続いているが、9月に各政治勢力間で和平合意が署名され、11月に新内閣が発足した。
1月には、牧野外務大臣政務官がイエメンを訪問し、日本が新国家建設を目指す同国の取組を支持することをバシンドワ首相及びカルビー外相に伝達した。4月のイエメン・フレンズ会合では、計3,000万米ドル(政権移行プロセス支援として100万米ドル、人道支援として2,900万米ドル)の新規支援を表明し、9月の同会合でも100万米ドルの政権移行プロセス支援を表明するなど、日本は、イエメンの安定のための支援を継続している。
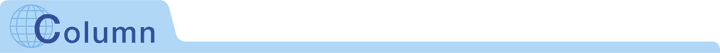
SJAHI(Saudi Japanese Automobile High Institute;サウジアラビア・日本自動車高等研修所)は、1998年のアブダッラー皇太子(現国王)の訪日時に両国政府間で交わされた「自動車整備の技能向上のための学校設立に関する覚書」により、官民の連携協力の下に2001年にスタートした支援事業です。
日本の支援形態は様々に変遷しましたが、研修所創設13年目を迎え、これまでに2,238名の卒業生が輩出され、サウジアラビア国内の日本自動車メーカーの販売店各社のサービスショップに配属されて活躍中です。中にはサービス部長に昇進した例もあります。
当事業はサウジアラビアの自国民化政策の推進に大きく貢献しており、さらに、両国間の友好を促進するシンボリックな事業として高く評価されています。
SJAHIは、サウジアラビア人高卒者を受け入れる自動車整備分野の2年制技術専門学校です。学生定員500人、教職員数80人、施設は、一般教室、技術教室、実習棟、コンピュータ室、理科実験室、300人収容の学生寮のほか、モスクを含めて充実した機能を誇っています。

カリキュラムは英語の集中教育に始まり、英語による自動車整備の座学と実習、さらに企業内実習を経て、日本の3級自動車整備士資格に準ずる技能を身につけることを目標としています。
SJAHI2年生のある優秀な学生は「入学する前はSJAHIが一般の学校のように就職の架け橋であると思っていました。しかし、入学してみると、技術教育訓練プログラムの修得のみならず、自己啓発の基本、時間の考え方と活用方法、目標達成の本当の意味とその方法、創造的な考え方の大切さ、個性の活かし方、仕事の誇り、等々も学ぶ貴重な経験ができました。」と語ってくれました。

SJAHIは卒業生の就職先である日系自動車会社(JADIK)からは毎年定員数を上回る入学生の受入れを要望されるほどにサウジアラビア国内の他の工科大学などからも高い評価を得ています。将来はJADIKとの連携が一層強化され、更に発展することが期待されています。
SJAHIシニア専門家 水谷 千谷
