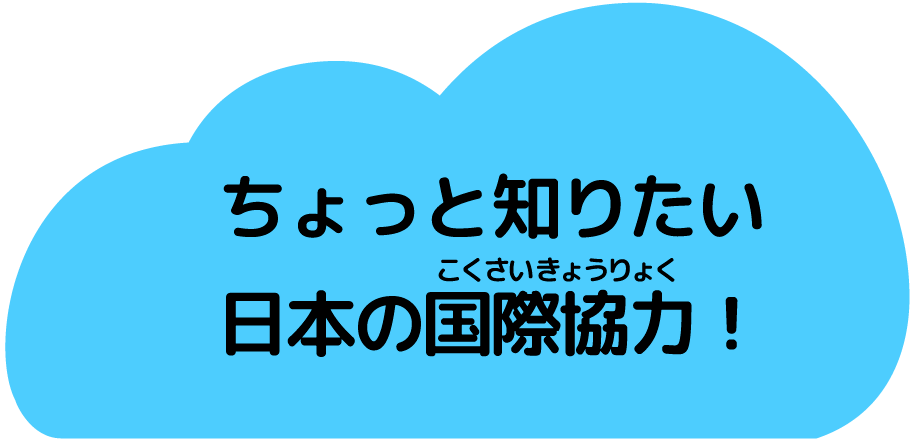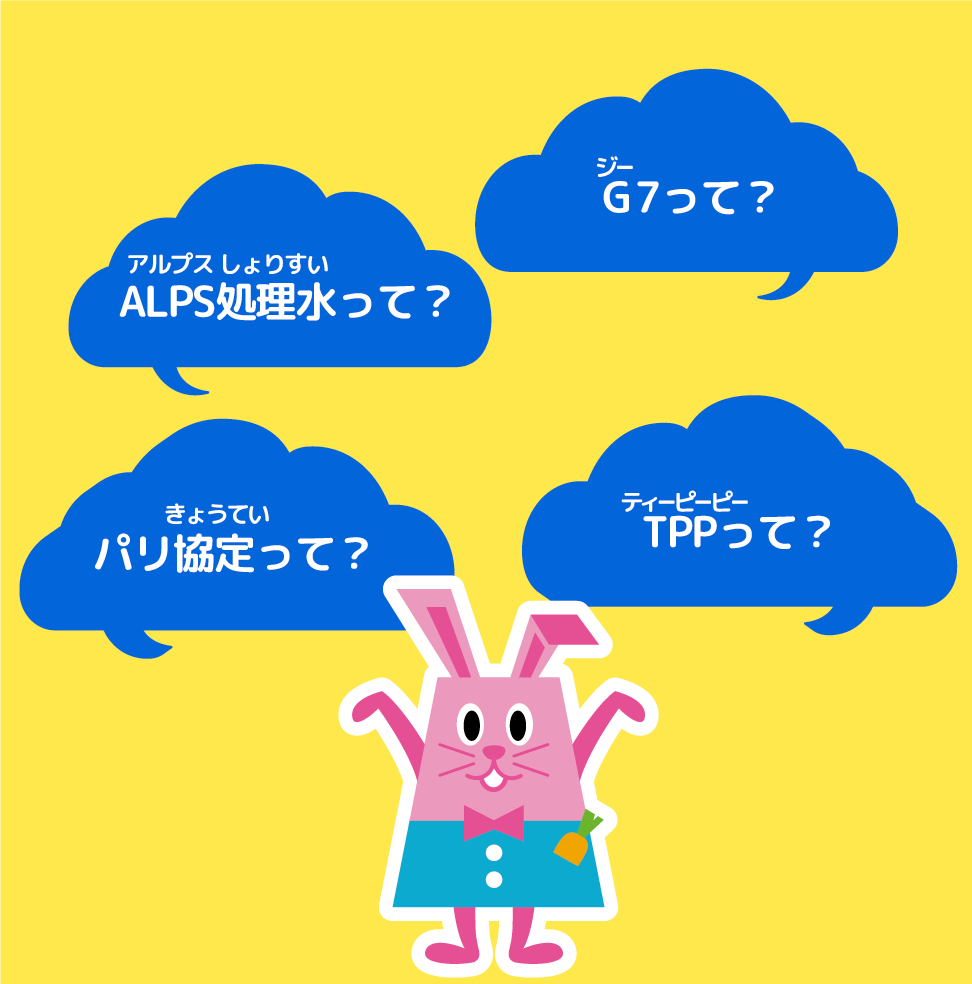日本は世界の国(開発途上国)にどんな協力をしているのですか?
生活水準が低く経済成長の途上にある国々(開発途上国)に対して行っている協力を、開発協力といいます。その重要な手段がODA(政府開発援助)です。
ODAのしくみは、大きく分けて2つあります。
1つは、日本が相手の国に直接支援をする二国間協力です。
二国間協力には、いろいろなやり方があります。
- (1)お金を貸す・・・・円借款といいます。
- 発電所の建設や、下水道の整備などといったお金のかかる事業について、開発途上国が必要だと思うことがあれば、とても低い利子でお金を貸します。貸したお金は長い時間をかけて少しずつ返してもらいます。 開発途上国にとって毎年の負担が軽くなりますし、計画的にお金を返すことはその国の自立にも役立ちます。
- (2)お金を贈る・・・・無償資金協力といいます。
- 開発途上国に対して、学校や病院等を建てる時に、そのためのお金を出して支援します。
- (3)技術を教える・・・・技術協力といいます。
- 開発途上国では、人々の知識や技術が十分でないために、産業、農業、教育等が必ずしも発達していないところもあります。そこで日本の技術を教えてその国の自立と発展を助けます。
もう1つは、国連などの国際機関を通じて世界の国々と一緒に開発協力を行う多国間協力です。多国間協力では、特定の分野についての知識や経験を持ち、どの国にも属さないという特徴がある国際機関の利点も生かして、日本が直接的な支援を行いにくい国・地域や分野への協力を行うことで、「誰ひとり取り残さない」国際社会の実現を目指しています。
日本は、開発途上国の状態や発展状況に合わせて必要なものを考え、このようにさまざまな方法を用いた支援を行っています。
1954年から70年にわたり行っている日本のODAは、1989年及び90年代(90年を除く)を通して世界第1位の援助国になり、今も3位という高い順位にあります。また、これまで日本がODAで支援をしてきた国や地域は、190の国と地域です。この国々の中には、日本がその国にとって最大の援助国になっている国がたくさんあります。
日本は、1954年10月6日、開発途上国に対するODAを開始しました。政府は、この10月6日を「国際協力の日」と定め、国際協力への国民の理解と参加を呼びかけています。また2024年は、日本がODAを開始してから70年の節目にあたります。

国際協力70周年のロゴ
なぜ日本は協力するのですか?
世界には、飲み水や食べ物が十分になかったり、教育を受けられなかったり、病気になったり怪我をしたりしても病院に行くことができない人々がたくさんいます。1日に200円くらいのお金で生活しなければいけない人たちもたくさんいます。このような人々が住んでいる国を開発途上国と呼んでいます。
日本が開発途上国に協力を行うのは、豊かな国が貧しい国を助けるという理由だけではありません。日本での食料やエネルギーの安定的な確保、日本企業が海外でビジネスをしやすくなるなどのメリットもあります。また、私たち日本国民の生活を守り、日本の平和と安定にもつながっているのです。だからこそ、積極的に協力をしていく必要があるのです。
協力する理由は?
-
日本の平和と繁栄は、世界の平和と繁栄があって初めて可能!
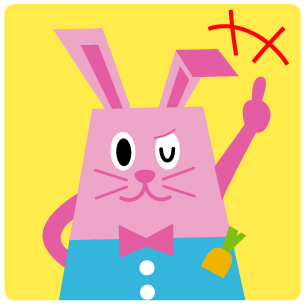 日本が平和でも、他の国で争いがあれば、日本の平和も脅かされてしまう可能性があるね。日本が開発協力を通じて、平和で安定し、繁栄した国際社会の構築に取り組んできたことは、私たち日本国民の生活を守り、繁栄を実現することにもつながってきたんだね。
日本が平和でも、他の国で争いがあれば、日本の平和も脅かされてしまう可能性があるね。日本が開発協力を通じて、平和で安定し、繁栄した国際社会の構築に取り組んできたことは、私たち日本国民の生活を守り、繁栄を実現することにもつながってきたんだね。
-
日本の経済成長につながる!
-
開発途上国が豊かになれば、その経済成長を日本の経済成長につなげることができます。
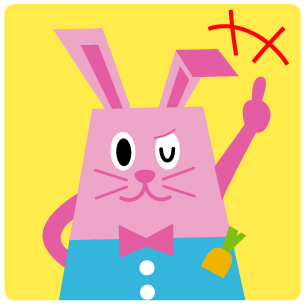 開発途上国が豊かになれば、日本企業の海外進出が活発になったり、日本からの輸出促進になったりなどのメリットにつながるね!
開発途上国が豊かになれば、日本企業の海外進出が活発になったり、日本からの輸出促進になったりなどのメリットにつながるね!
-
私たちが食べているものや石油などの資源といった身の回りの多くのものが、開発途上国から運ばれています。開発途上国が安定し発展すれば、食料や資源の輸入の安定につながります。
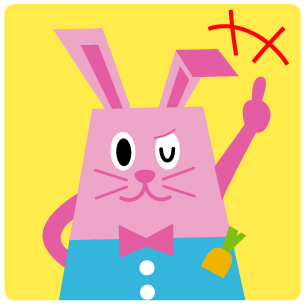 つまり、世界の安定したものの流れを維持することは、日本経済にもプラスになるね。
つまり、世界の安定したものの流れを維持することは、日本経済にもプラスになるね。
-
-
かつては日本も援助される側
東海道新幹線や東名・名神高速道路などのインフラは、第二次世界大戦後に世界銀行から資金支援を受けて整備されたものです。
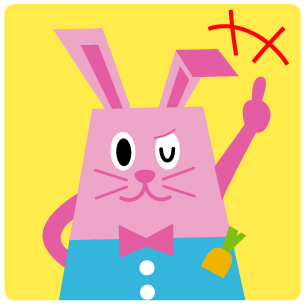 戦後の日本が貧しさから立ち直り、経済発展を遂げたのは、実はこうした多くの支援があったからだということを決して忘れてはいけないね。
戦後の日本が貧しさから立ち直り、経済発展を遂げたのは、実はこうした多くの支援があったからだということを決して忘れてはいけないね。
また、飢えや貧しさは、テロや紛争などの原因になります。さらに地球の環境が悪くなることや、新型コロナウイルス・エイズ・鳥インフルエンザなどの病気の問題は、国境をこえて地球全体で広がっています。これらを防ぐためには、世界の国々が力を合わせなくてはいけません。こうした問題に日本が国際社会の一員として積極的に取り組むことで、地球の未来や世界の平和を守るとともに、日本の存在感を高めることにもなるのです。
さらにくわしい情報はこちら!
● ウェブサイトで見る
● PDFで見る
● 動画で見る
日本の開発協力はどのように行われているのですか?
政府開発援助(ODA)を使って開発協力を行う際には、多くの人たちが関わっています。外務省を含む日本政府、国際協力機構(JICA)、国連などの国際機関、非政府組織(NGO)や企業などです。JICAは、日本政府が作った方針に基づいて、開発途上国で実際に開発協力を行っています。
途上国の人たちが本当に必要としている支援をするには、その国の様子を知り、その国の政府と話し合い、どのように協力をするか決めなければいけません。
現地の大使館、JICAなどがばらばらに動くのではなく、それぞれの情報や技術を持ちよって、アイデアを出し合うことが大事です。そのため、現地の大使館、JICAなどが「現地ODAタスクフォース」をつくり、組織をこえて協力し合ったり、NGOと政府が協力し合ったりする取組が行われています。また、開発協力をしている他の国々や国際機関などと協調することも必要です。日本は他国とも協調しながら効果的な開発協力を実施しています。
世界にはどのくらい貧しい人たちがいますか?
いま世界では、約10人に1人が1日200円くらいで生活をしています。また、約10人に1人が栄養不足に苦しんでいます。年間約490万人の子どもが5歳まで生きられず命を失い、およそ6,400万人の子どもたちが小学校にも通えないでいます。こうして、貧困が原因で、人々の生きる権利や才能をいかす機会が奪われています。
国際社会は世界の困っている人たちにどのようなことをしているのですか?
国連に加盟するすべての国は、どんな国や環境に生まれて育っても、みんなが元気に活躍できる社会をつくるため、2016年から2030年までの目標を17個決めました。これはSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)と呼ばれており、2030年までに持続可能でよりよい世界を実現することを目指しています。SDGsは開発途上国のみならず、すべての国が取り組むものであり、日本も積極的に取り組んでいます。
世界の困っている人たちに協力をしたいけれど、どうしたらいいですか?
世界の困っている人たちに協力するなら、まず、身近に取り組めることからはじめてください。世界はつながっています。食料や水を大切にする、ゴミを拾う、そういうひとつひとつの行動が世界をよりよくします。そして世界には学べない子供たちがたくさんいます。みんなが勉強に一生懸命取り組んで、将来大きくなったときに、困っている人たちに何かをできるようになるといいと思います。
いますぐ、誰にでも協力できる方法として、募金があります。世界各地で募金を行っている国際機関の中には、国連児童基金(ユニセフ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連世界食糧計画(WFP)のように、それぞれの活動に対する募金を日本でも受け付けている機関があります。また、私たちがインターネットのサイトのボタンをクリックするだけで募金が出来るシステムもあります。これは、企業がスポンサーとなって成り立つもので、私たちはお金を払うことなく、簡単に募金をすることが出来ます。
もっと直接的な活動がしたいという人には、夏休みなどを利用してNGO(非政府組織)のボランティア活動に参加したり、長期ではJICA海外協力隊に参加したり、と様々な方法があります。
NGOの国際協力活動についてくわしく知りたい場合は、「NGO相談員」がいますので、問い合わせることができます。
難民とはどんな人たちのことですか?
難民とは、「人種や宗教、政治の考え方などの違いが理由で、自分の国にいると命を狙われたり、ひどい目にあうおそれがあるので、外国にのがれた人」のこと。難民を守るためにできた難民条約では、このように定められています。難民となった事情はさまざまですが、戦争が起こったり、政治が混乱したことなどが大きな理由となっています。難民が増えることは、住みにくい国が増えているということです。世界には、現在も多くの難民が存在しています。それはまだまだ世界には、人が安心して暮らせる環境が整っていない地域がたくさんあるということなのです。
世界には何人くらいの難民がいますか?
世界には、約3,530万人の難民がいます(UNHCR 「グローバル・トレンズ・レポート 2022」)。
特に難民が多い国・地域はシリア(約650万人)、ウクライナ(570万人)、アフガニスタン(約570万人)などとなっています。また、自分の国の中で生まれ育った土地にいることができなくなって国内の別の場所に避難している人たちの問題も深刻で、その数は難民の数を上回っています(難民数:約3,530万人、国内避難民数:約6,250万人)。
日本は、1970年代後半にインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)から逃げ出した大勢の難民(インドシナ難民)が日本にたどり着いたことがきっかけとなり、1981年に「難民の地位に関する条約(難民条約)」に加入しました。インドシナ難民の受け入れ事業は、2005年度をもって終わりましたが、受け入れたインドシナ難民の数は11,319人になりました。また、難民条約に加入したことから日本国内では難民認定制度が整えられ、1982年から2023年末までの間に、1,420人が難民条約に基づく難民(条約難民)として認められています。さらに、2010年からは、難民を受け入れる制度が始まり、この枠組みによって、2023年までに101家族275人を受け入れています。
国内に受け入れたこれらの難民に対しては、日本での生活がしやすいように、日本語を教えたり、就職のお手伝いをしたりしています。
世界で大きな自然災害が起きた時、日本はどんな協力をしているのですか?
外国で地震や洪水、津波などの自然災害が起きて大きな被害を受けた国が、支援を求めてきた時には、日本は出来るだけ早く支援の手をさしのべます。
たとえば、地震などが起こった地域では、壊れたビルの下で生き埋めになっている人やけがをしている人がたくさんいます。日本は、このような人びとを助けるために、国際緊急援助隊としてレスキュー隊員やは救助犬、医師や看護師らのチームを直ちに現地に送っています。
また、災害により家をなくした人びとは、しばらくは避難所で生活しなければならないので、テント、毛布、浄水器など避難生活に必要なものを送ります。災害にあった人びとに配る食べ物や薬を買ったり、仮設住宅を建てるためのお金を送ったりすることもあります。
このように、日本は海外の災害に対して人を派遣したり、物やお金を送ったりするなどして支援しています。
また、日本はただ災害発生前の状態に戻すのではなく、より災害に強い状態に復興することを目指す、”Build Back Better(ビルド・バック・ベター:より良い復興)”という考えを重視しています。
日本はこれまでに多くの被災経験があるので、その分、防災に関する豊富な知見を有しています。災害を防ぐために、国際機関などと協力しながら、海外の人に災害に備えるための研修を行う、災害に強い施設を造るなど、日本自身の経験をいかした知識や技術を外国に伝えています。
世界遺産を守るために日本はどのような事をしているのですか?
2024年5月現在、全世界で合計1,199件の世界遺産がありますが、世界遺産になっても自然災害や紛争、開発などで遺産が傷ついたり、崩壊したりする危険があります。
例えば、2006年に起きたインドネシア・ジャワでの地震により「ブランバナン寺院群」が被害を受けました。また2001年3月にはイスラム原理主義勢力によりアフガニスタンの「バーミヤン遺跡」の大仏像が破壊されました。さらに、2012年以降、内戦状態にあったシリアで「古代都市アレッポ」、「パルミラ遺跡 」が破壊され、2015年にはイラクの「ハトラ遺跡」がイスラム過激派組織により破壊されました。
このように世界遺産が危機にさらされると、ユネスコを中心に、日本を含む多くの国々が、知恵を出し合い、自分たちの国にできる支援をしながら、被害を食い止め、壊れた部分を直し、元に戻す努力をしています。支援の方法は、壊れた部分を直すためのお金や機材をあげたり、どれくらい被害があったか調べる調査団を送ったり、現地の人に修復する技術を教えるなど、多くの分野にわたっています。
例えば、アンコール・ワットに代表されるカンボジアのアンコール遺跡群は、「危険にさらされている世界遺産(危機遺産)」に指定されていましたが、日本やフランスをはじめ世界各国が壊れた部分を直すなど、この貴重な遺産を守る協力を行ったので、2004年に指定が解除されました。現在も日本はカンボジア政府と協力し、ユネスコを通してさまざまな側面から遺産を守る協力を行っています。
世界全体で気候変動を食い止めるために、日本はどのような協力をしているのですか?
気候変動は、人間のさまざまな活動から排出される二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に増え、地球の平均気温が上昇すること(地球温暖化)によって引き起こされます。気候変動を食い止めるためには、人間の活動から排出される温室効果ガスをできる限り減らすとともに、森林の保護や新しい技術によって大気中の温室効果ガスを取り除くことが必要です。今、世界各国は、排出される温室効果ガスと、取り除かれる温室効果ガスの量を同じにし、差し引きした時に温室効果ガスの排出量をゼロにすること(これを「ネット・ゼロ」や「カーボンニュートラル」と呼びます)を目指しており、これが実現した世の中のことを「脱炭素社会」といいます。
日本は、日本の国内だけではなく、世界全体で脱炭素社会を作っていくため、各国に対してさまざまな協力を行なっています
例えば、政府開発援助(ODA)を通じて、太陽光・風力・地熱など、温室効果ガスを発生させないエネルギー(再生可能エネルギー)を使った発電所の建設や、気候変動に強いまちづくりをお手伝いするなど、脱炭素社会を目指す世界中の多くの国への協力を行っています。
途上国が気候変動対策に取り組むためには、お金の面での協力も重要です。日本は、政府や企業などを合わせた途上国への支援として、2021年から2025年までの5年間で最大700億ドルの支援を行う方針です。また、「緑の気候基金(GCF)」という途上国の気候変動対策を支援するための国際機関に、これまで30億ドル(約3,190億円)を提供し、さらに今後4年間で最大1,650億円を提供することにしています。加えて、気候変動によって起こる損失や損害(ロス&ダメージ)に対応するため、特に大きな影響を受ける途上国の支援を行う基金に対し、1,000万ドルを提供しました。
途上国が自分で温室効果ガスを減らすためには、技術を普及することも重要です。日本は、「二国間クレジット制度(JCM)」という制度を通じて、アジア・太平洋、中東、アフリカ、中南米の29か国で、温室効果ガスの排出を減らすための優れた技術、製品、サービスなどを使って、これまでに250件以上の温室効果ガスの排出を減らすプロジェクトを実施しています。