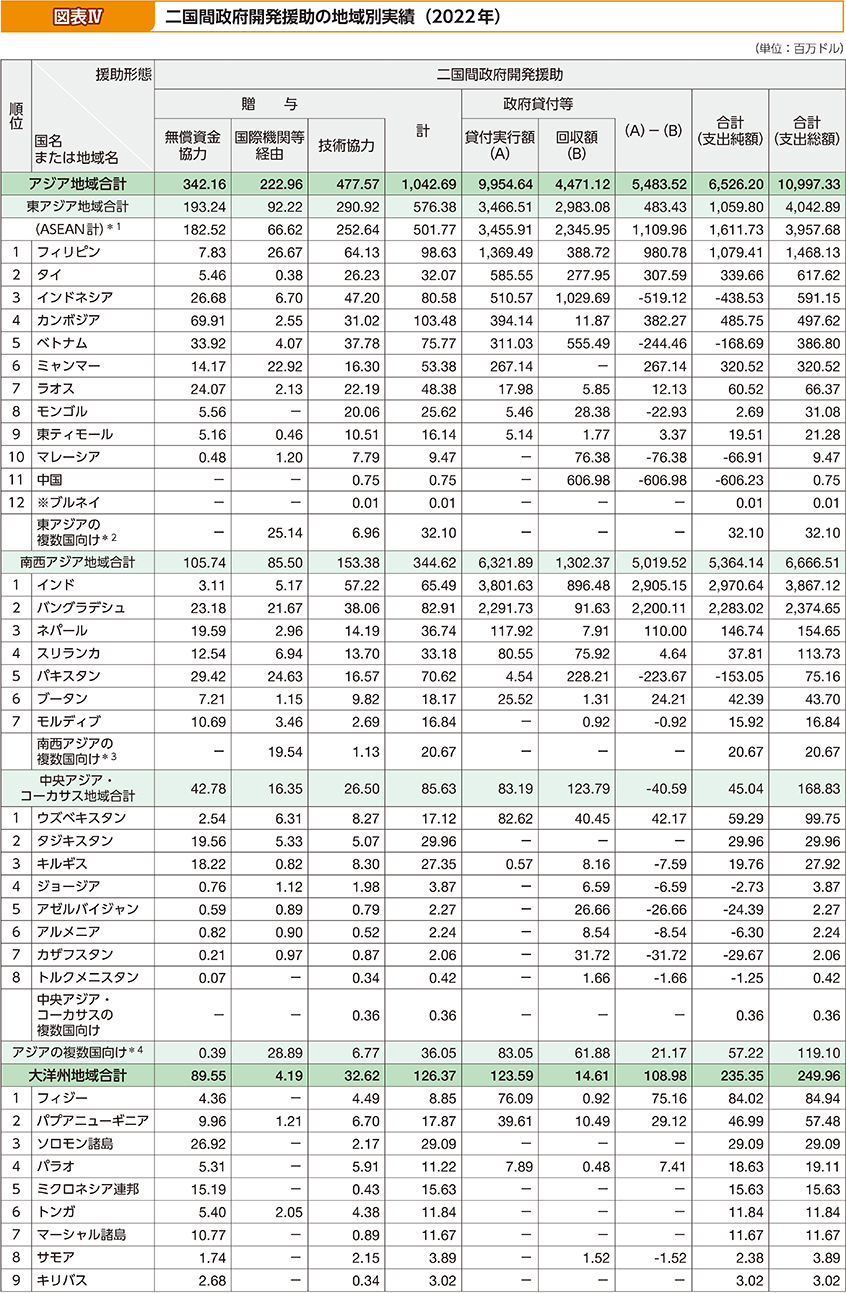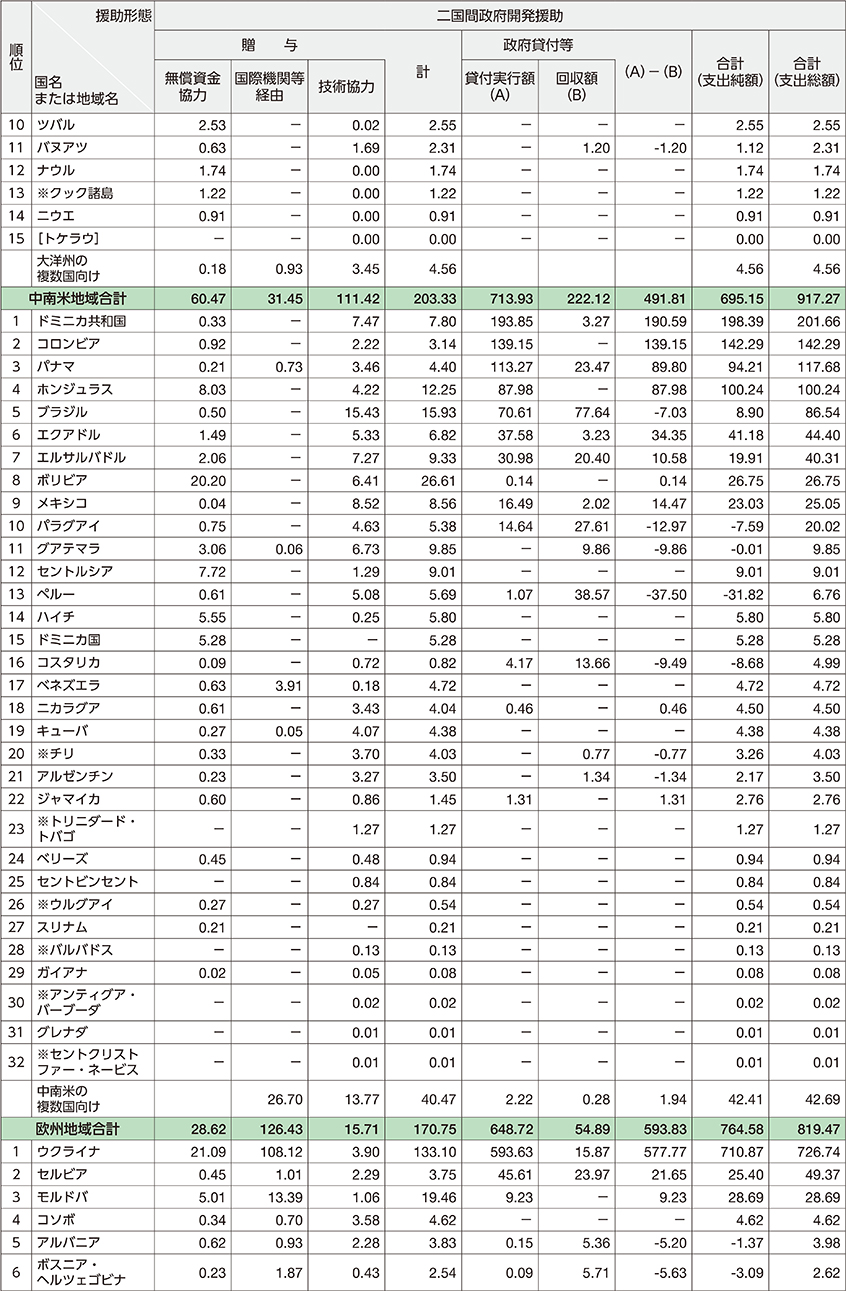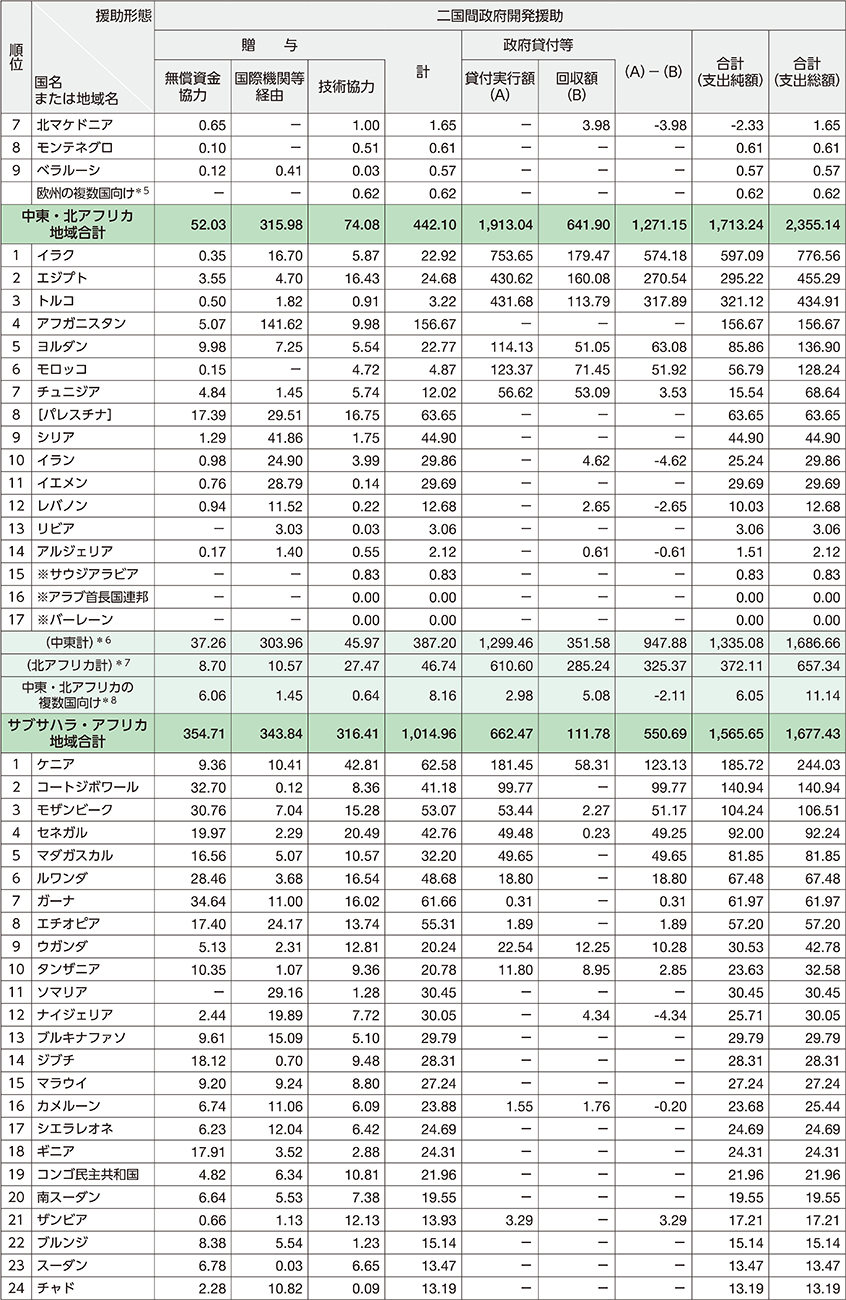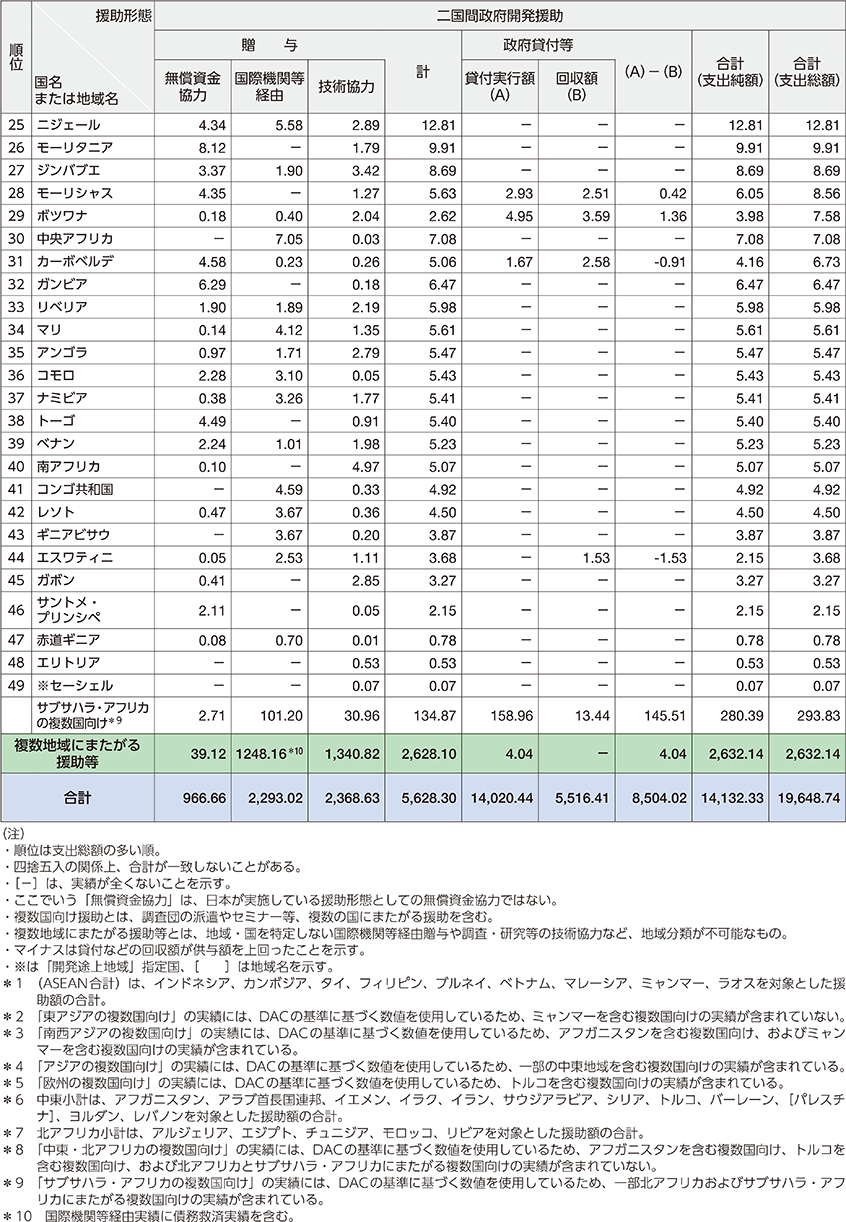8 アフリカ地域
2050年には世界の人口の4分の1を占めると言われるアフリカは、若く、希望にあふれる大陸です。豊富な資源と経済市場としての高い潜在性を有しており、ダイナミックな成長が期待されています。一方、貧困、脆(ぜい)弱な保健システム、テロ・暴力的過激主義の台頭など、様々な課題にも直面しています。
こうした課題に対応するため、アフリカ諸国は、アフリカ自身の開発アジェンダである「アジェンダ2063」注21に基づき、持続可能な開発に取り組んでいます。ロシアによるウクライナ侵略など国際社会の根幹を揺るがす動きが続き、これまで以上に国際社会が一致して対応することが重要になる中で、国際社会におけるアフリカの位置付けも大きく変化し、アフリカは国際社会における主要なプレーヤーとして、その重要性と発言力はますます高まっています。このため、アフリカ諸国との協力を一層推進していく必要があります。
●日本の取組

2023年8月にTICAD 30周年を記念して行われた「TICAD 30年の歩みと展望」のパネルディスカッション3「TICADの将来」の様子
日本はアフリカ開発会議(TICAD)解説などを通じて、長年にわたり、アフリカの持続可能な開発に貢献しています。2022年8月にチュニジアで開催されたTICAD 8において、日本は、「人への投資」、「成長の質」を重視し、グリーン投資、投資促進、開発金融、保健・公衆衛生、人材育成、地域の安定化、食料安全保障に取り組むこと、また、産業、保健・医療、教育、農業、司法・行政等の幅広い分野での人材育成を行っていくことを表明し、着実に実施しています。
日本は、アフリカの「声」を直接聞くことを重視しています。G7広島サミットの直前となる2023年4月29日から5月3日にかけて、岸田総理大臣はアフリカの東西南北の主要国であるエジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークを訪問し、各国が直面する様々な課題に耳を傾けました。G7広島サミットでは、アフリカ連合(AU)議長国のコモロを招待した上で、アフリカ歴訪での成果をサミットでの真剣な議論につなげました。7月31日から8月3日には、林外務大臣(当時)が、南アフリカ、ウガンダおよびエチオピアを訪問し、日本による長年の支援やさらなる連携強化について意見交換しました。
8月26日には、TICADが立ち上げられてから30年になることを記念して、TICAD 30周年行事「TICAD 30年の歩みと展望」を東京で開催し、TICADのこれまでの歩みと今後の展望について活発な意見交換が行われました。
2024年には東京でTICAD閣僚会合が、2025年には横浜でTICAD 9が開催されることが決定しています。日本は、アフリカと「共に成長するパートナー」として、「人」に注目した日本らしいアプローチで取組を推進し、アフリカ自身が目指す強靭(じん)なアフリカを実現していきます。
■経済
TICAD 8において、日本は新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢等による食料・エネルギー分野等における影響からのより良い回復を実現し、人々の生活を守るため、自由で開かれた国際経済システムを強化するとともに、各国のグリーン成長を支援し、強靭で持続可能なアフリカの実現を目指していくこと、また、活力ある若者に焦点を当て、民間企業・スタートアップの進出を後押ししていくことを表明し、その実現に取り組んでいます。
質の高い成長の実現に向けた「人への投資」として、日本はこれまでビジネスの推進に貢献する産業人材の育成を行ってきており、ABEイニシアティブでは、これまでに6,700人を超えるアフリカの若者に対し、研修の機会を提供しています(ABEイニシアティブについては、第Ⅴ部1(6)および第Ⅴ部2(2)アを参照)。産業人材のほかにも、技術協力を通じたICT人材の育成や、「Project NINJA」注22によるスタートアップ・起業家支援なども行っています(ルワンダにおけるABEイニシアティブ修了生の活躍については「国際協力の現場から1」、タンザニアにおける養蜂分野での取組については「匠の技術、世界へ」を参照)。
また、連結性の強化に向け、3重点地域注23を中心に、「質の高いインフラ」投資の推進にも取り組んでいます。デジタル・トランスフォーメーション(DX)を活用し、インフラ整備やワンストップ・ボーダーポスト(OSBP)等を通じた物流の改善や、世界税関機構(WCO)と協力して国境管理や関税等徴収の分野での能力構築支援などを実施しています。
ロシアによるウクライナ侵略の長期化により、食料・肥料・エネルギー価格が高騰し、アフリカにおける食料危機が深刻化していることを受け、2022年7月、アフリカ諸国に対して約1.3億ドルの食料支援を決定しました。また、中長期的な食料生産能力の強化のため、コメの生産量の倍増に向けた支援やアフリカ開発銀行(AfDB)の緊急食糧生産ファシリティへの約3億ドルの協調融資、今後3年間で20万人の農業人材育成を目指した能力強化支援などを行っています。日本は、食糧援助等の短期的支援と、農業生産能力向上等の中長期的支援の双方を通じて、引き続きアフリカの食料安全保障強化に貢献していきます。
■社会

日本の無償資金協力で建設されたベナンのコトヌ漁港の環境改善に向け、ごみ箱の設置を現地NGOスタッフと検討するJICA海外協力隊員(写真:JICA)

アフリカ10か国からの参加者が、チュニジアで廃棄物管理・都市衛生に関する第三国研修に参加し、回収した木材を堆肥にする施設を視察する様子(写真:JICA)

アンゴラ「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」において豊田通商株式会社現地法人CFAO Motors Angola, S.A.から提供された母子健康手帳寄贈式の様子(写真:JICA)
TICAD 8では、人間の安全保障、SDGs、「アジェンダ2063」を踏まえ、顕在化した格差の是正と質の高い生活環境の実現を目指していくことを表明しました。
感染症対策は引き続きアフリカの大きな課題です。日本は、COVAXファシリティ注24への財政的貢献や、コールド・チェーン注25整備等のラスト・ワン・マイル支援、ワクチン接種に対する忌避感情改善のための取組、ワクチンの域内製造・供給・調達支援など、包括的かつきめ細かい日本らしい取組を進めています。また、感染症を含む公衆衛生上の脅威に対応するため、アフリカ7か国注26に対し、国連児童基金(UNICEF)を通じてデジタルを活用した予防接種情報管理体制を整備するための支援も実施しています。さらに、感染症対策の拠点となる現場への支援を強化すべく、アフリカ疾病対策センター(CDC)などとも連携しながら、医療人材の育成にも取り組んでいます。
TICAD 8の機会に発表したグローバルファンドに対する最大10.8億ドルのプレッジ(供与の約束)を始めとする国際機関等を通じた支援や二国間支援を通じ、日本は、引き続きアフリカにおける保健システムの強化に取り組んでいます。また、将来の公衆衛生危機に対する予防・備え・対応(PPR)も念頭に、「誰の健康も取り残さない」という信念の下、アフリカにおけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向け貢献しています。
経済成長には、成長の担い手となる「人づくり」が重要であり、若者や女性を含め、質の高い教育へのアクセス向上に取り組んでいます。日本は、TICAD 8でSTEM教育注27を含む質の高い教育を900万人に提供すること、400万人の女子の教育アクセスを改善することを表明し、技術協力等を通じて就学促進、包摂性の向上、給食の提供等に取り組んできています。例えば、学校、保護者、地域社会と協働してこどもの学習環境を改善する「みんなの学校プロジェクト」注28は、2004年の開始以降、アフリカ9か国の約7万校の小中学校に広がっています(ケニアにおける障害児支援については「案件紹介」を参照)。
アフリカでは、急速に進む都市化に伴う様々な課題への対応も急務となっています。日本は、「アフリカのきれいな街プラットフォーム」注29の下、廃棄物管理を通じた公衆衛生の改善を推進するとともに、JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム(JJ-FAST)による森林の定期監視を行うなど、気候変動対策を含む環境問題にも取り組んでいます(エチオピアでの廃棄物管理における支援については、「匠の技術、世界へ」、ウガンダにおける緑化を通した強靱なコミュニティづくりへの取組については「案件紹介」を参照)。
■平和と安定
TICAD 8において、日本は、人間の安全保障および平和と安定を阻害する根本原因にアプローチする「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」解説の下、経済成長・投資や生活向上の前提となる平和と安定の実現に向けて、アフリカ自身の取組を後押ししていくことを表明し、その実現に着実に取り組んでいます。
平和で安定した社会や持続可能な成長は、法の支配があって初めて成し遂げることができます。日本は、法の支配に関連してアフリカ自身の取組を後押しする具体的協力として、警察官への研修や国境管理支援等を行っています。加えて、司法・行政分野の制度構築、ガバナンス強化のための人材育成、公正で透明な選挙の実施や、治安確保に向けた支援などを行っています。平和と安定の礎となる行政と住民の間の相互理解・協力関係を促進するため、コミュニティ・レベルで行政と住民が協働する取組支援も行っています。
また、日本は、アフリカ自身の仲介・紛争予防努力を、アフリカのPKO訓練センターにおけるPKO要員の能力強化やアフリカ連合(AU)等の地域機関への支援を通じて後押ししています。2008年以降、アフリカ15か国内のPKO訓練センター等が裨(ひ)益するプロジェクトに対し1.1億ドル以上の支援を行い、60人以上の日本人講師を派遣し、施設の訓練能力強化や研修の実施などを支援しています。また、PKO要員への支援枠組みである「国連三角パートナーシップ・プログラム(TPP)」を拡充し、AUが主導する平和支援活動に派遣される要員への訓練を実施するために、約850万ドルを拠出することを決定しました。2023年9月、岸田総理大臣は、国連総会での一般討論演説において平和の担い手への支援を拡充する旨を述べました。
サヘル地域においては、NAPSAの下、サヘル諸国の行政制度の脆(ぜい)弱性に焦点を当てながら、治安維持能力強化につながる機材の提供、制度構築に携わる人材育成、若者の職業訓練・教育機会の提供、PKO人材の育成強化などを通じて、同地域の平和と安定に貢献しています。例えば、サヘル地域の安定のため、国連開発計画(UNDP)を通じてリプタコ・グルマ地域注30住民に対する支援を行うなど行政サービスの改善に向けた取組を実施しており、コミュニティの基盤強化に貢献しています。
南スーダンにおいて日本は、2011年の独立以来、同国の国造りを支援しています。現在は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO法)に基づき、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、司令部要員として自衛官を派遣しています。日本は、東アフリカの地域機構である政府間開発機構(IGAD)などを通じて、南スーダン自身のイニシアティブである和平プロセスへの支援も行っており、インフラ整備や人材育成支援、食糧援助などの支援と並んで、南スーダンにおける平和の定着と経済の安定化に大きな役割を果たしています(南スーダンにおける水分野への支援については「案件紹介」を参照)。
また、国民の融和、友好と結束を促進するため、南スーダンの青年・スポーツ省による国民体育大会「国民結束の日」の開催への支援を第1回大会(2016年)から毎年行っています。2023年は3月から4月にかけて第7回大会が開催され、全国を代表する17歳未満の336人が参加しました。また、7月には「スポーツを通じた平和促進プロジェクト」の一環で、南スーダンの青年・スポーツ省、一般教育・指導省などから計13人を日本に招聘(へい)し、競技の視察や教育機関への訪問を含む研修を実施しました。参加者は視察先での体験や意見交換などを通じて、人々の融和、人材育成等に対するスポーツの力を再認識しました。今後も平和の定着を同国の国民が実感し、再び衝突が繰り返されないように、国際社会が協力して南スーダンの平和の定着を支援していくことが重要です。
案件紹介12
ウガンダ
住民と共に行う地域の強靱性強化
ウガンダ北部における道路インフラ整備・地域の緑化を通した強靭なコミュニティづくり
日本NGO連携無償資金協力(2023年3月~2024年3月)
東アフリカ、ウガンダの北部では1980年代から約20年間続いた紛争により、インフラ開発が著しく立ち遅れ、他地域との格差が課題となっています。また、寛容な難民受入れ政策の下、南スーダンなど周辺国から大量の難民を受け入れる中、難民が燃料として周辺の森林を伐採するなどして、環境への負荷も懸念されています。
そこで、特定非営利活動法人道普請人(みちぶしんびと)は、北部2県(グル県、キトゥグム県)を対象に、住民の生計向上と地域の強靱(じん)性強化を通してコミュニティの活性化を支援しています。「自分たちでできるインフラ整備・環境保全」を目標に掲げ、(1)土のう工法を用いた農村道路整備活動、(2)住民主体の育苗場の設置と植林を通した緑地面積の回復、(3)薪燃料の使用量を70%減少できる「省エネ型かまど」の作成を実施しています。併せて、小学生への環境教育、生理用品作成などの女子学生支援にも取り組んでいます。
土のう工法については、年間150人の訓練生に技術移転を行い、若者の雇用につなげるとともに、団体として地元政府に登録することによって活動を継続できるシステム作りも支援しています。グル県では、これまで560メートルの農道補修が行われました。住民主体の苗木生産も進んでおり、住民全体を巻き込んだ植林イベントを通し、今後、年間10ヘクタールの緑化を目指しています。また、331基のかまど作成が完了し、世帯での実用化が始まっています。

土のう工法を用いた農道補修訓練(写真:特定非営利活動法人道普請人)

訓練生と今後の活動の継続性について話し合う日本人職員(写真:特定非営利活動法人道普請人)
用語解説
- アフリカ開発会議(TICAD:Tokyo International Conference on African Development)
- 1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議。国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)との共催により、アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を具現化するもの。2022年8月には、チュニジアでTICAD 8が開催され、20名の首脳級を含むアフリカ48か国が参加。
- アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA:New Approach for Peace and Stability in Africa)
- 2019年8月に横浜で開催されたTICAD 7において、日本が提唱した新たなアプローチ。アフリカのオーナーシップの尊重および紛争やテロなどの根本原因に対処するとの考えの下、アフリカ連合(AU)や地域経済共同体(RECs)などによる紛争の予防、調停、仲介といったアフリカ主導の取組、制度構築・ガバナンス強化、若者の過激化防止対策や地域社会の強靱化に向けた支援を行うもの。2022年8月のTICAD 8でも、日本はNAPSAの下、経済成長・投資や生活向上の前提となる平和と安定の実現に向けたアフリカ自身の取組を後押ししていくことを示した。