6 大洋州
(1)オーストラリア
ア 概要・総論
オーストラリア政府は2017年11月に発表した外交白書において、今後10年のオーストラリア外交の指針として、開かれた、包摂的で、繁栄したインド太平洋地域の推進、保護主義への対抗、国際ルールの推進・保護等を掲げるとともに、日本を始めとするパートナーとの協力強化を打ち出した。2018年8月に、ターンブル首相からモリソン首相に交代した後も、この外交方針は引き継がれている。
地域が様々な課題に直面する中、基本的価値と戦略的利益を共有する日本とオーストラリアの「特別な戦略的パートナーシップ」の重要性はこれまで以上に高まっている。インド太平洋地域における、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた両国の戦略的ビジョンは広い範囲で一致しており、首脳の年次相互訪問や外相間の緊密な関係を基盤とし、国際社会の安定と繁栄に向けて、政治・安全保障面での協力・連携を一層深化させている。さらに、日米豪、日豪印、日米豪印といった多国間での連携及びパートナーシップも着実に強化されている。
両国は、経済面において、TPP協定を始めとする自由貿易の推進に関してリーダーシップを発揮している。日本にとってオーストラリアは第5の貿易相手国、オーストラリアにとって日本は第2の貿易相手国であり、両国は、日豪経済連携協定(EPA)に基づき、相互補完的な経済関係を更に発展させている。2018年1月のターンブル首相の訪日及び11月の安倍総理大臣の訪豪では、安全保障・防衛協力の深化、経済分野や人的交流など幅広い分野での「特別な戦略的パートナーシップ」の深化が確認された。安倍総理大臣のオーストラリア訪問は、第二次世界大戦において旧日本軍が空爆したダーウィンを訪問するものであり、モリソン首相と共に、戦没者慰霊碑を訪問し、日豪間の戦後和解成功のメッセージを発信した。また、ダーウィンを基地とするイクシスLNGプロジェクトの生産開始を高く評価し、更なるエネルギー協力の推進で一致した。
ダーウィンにおいて、安倍総理大臣はモリソン首相と初の首脳会談を行ったほか、両首脳と通訳のみの会談や少人数の夕食会等も行い、個人的な信頼関係を構築した。両首脳は自由で開かれたインド太平洋地域の維持・強化のため、海洋安全保障の能力構築支援や連結性強化等で具体的協力を進めることで一致した。さらに、両首脳は、北朝鮮問題について協力することで一致するとともに、東南アジアや太平洋島嶼国地域等の地域情勢について認識を共有した。
外相間では、国連総会を含む様々な機会を捉え、頻繁に会談を実施した。10月には8回目となる日豪外務・防衛閣僚協議(「2+2」)がシドニーで開催され、厳しさを増す地域情勢に対する認識を共有するとともに、地域の平和と安定に向けて緊密に連携していくことを確認した。また、オーストラリアの各州との関係強化も進めており、堀井巌外務大臣政務官が2月にビクトリア州及びニューサウスウェールズ(NSW)州、6月に北部準州、南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ(NSW)州及びクイーンズランド州を訪問した。さらに、パラシェ・クイーンズランド州首相兼貿易相等が訪日した。
イ 安全保障分野での協力
インド太平洋地域の平和と繁栄の確保に向け、日本とオーストラリアは引き続き安全保障分野の協力を着実に強化・拡大させている。両首脳は、11月の日豪首脳会談において、日本の自衛隊とオーストラリア国防軍の間の共同運用と訓練を円滑にするために、行政的、政策的及び法的な手続を改善する相互訪問に関する協定にいて、これまでの交渉の大幅な進展を歓迎するとともに、関係する全ての閣僚に対し、望ましくは2019年の早い時期までに交渉を妥結させるため、交渉を加速するよう指示した。
第8回日豪「2+2」では、基本的価値と戦略的利益を共有する「特別な戦略的パートナー」である日豪両国の連携強化がかつてなく重要との認識を共有し、8月に就任したモリソン首相の政権下での日豪の揺るぎない連携を確認した。日本とオーストラリアの安全保障・防衛協力を一層強化することで一致するとともに、北朝鮮、南シナ海、東シナ海、東南アジアや太平洋島嶼国地域に関して連携を強化することを確認した。
また、米国の同盟国である両国は、日米豪の連携の更なる強化に引き続き取り組んでいる。8月には、第8回日米豪閣僚級戦略対話(TSD)を開催し、北朝鮮、南シナ海・東シナ海、インフラ投資、サイバーセキュリティ、テロ及び暴力的過激主義対策といった地域の諸課題に関して意見交換を行うとともに、これらの課題を含め、日米豪3か国で緊密に連携・協力していくことで一致した。
ウ 経済関係
日本とオーストラリアは、TPP協定及びRCEPを含む地域の自由貿易体制の推進について緊密に連携しリーダーシップを発揮している。日本とオーストラリアの間では、主に自動車などの工業品をオーストラリアに輸出し、また、主に石炭や天然ガスなどのエネルギー資源や牛肉などの農産物をオーストラリアから輸入するという相互補完的な経済関係が、長年にわたり着実に発展してきている。日本はオーストラリアへの世界第2の投資国であり、2015年1月の日豪EPA発効以降、日豪間のモノや資金、人の移動は活発化している。さらに、日豪交流促進会議の下、イノベーション主導の産業構造転換と地方主導の関係緊密化を二本柱として、日・オーストラリア間の経済関係を更に発展させるための取組が行われている。
エ 文化・人的交流
オーストラリアには約36万人に上る日本語学習者(人口比では世界第1位)や100件を超える姉妹都市など長年培われた親日的な土壌が存在する。青少年を含む人的交流事業であるJENESYS2018及び新コロンボ計画18による日本とオーストラリア間の相互理解の促進、若手政治家交流など、両国関係の基盤強化のための各種取組が行われた。
また、4月から11月まで、オーストラリア政府は、広報文化外交上の旗艦事業である「オーストラリア・ナウ」を日本国内で実施し、科学・研究・イノベーション、創造性・デザイン及びオーストラリアの生活様式をテーマとする公演や文化・スポーツ行事が行われた。
オ 国際社会における協力
両国は、国際社会の平和と安定に積極的に貢献するため、幅広い分野での協力を強化してきている。特に、海洋安全保障、北朝鮮の核・ミサイル開発といったインド太平洋地域が直面する諸課題に関して協力を深めてきている。2018年には、オーストラリアは、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮船籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、在日米軍嘉手納(かでな)飛行場を拠点とする警戒監視活動に航空機を三度派遣し、また、東シナ海を含む日本周辺海域における警戒監視活動にフリゲート艦「メルボルン」を派遣した。そのほか、オーストラリアとの関係が深い太平洋島嶼国地域に関しても緊密に連携している。11月、パプアニューギニアにおけるアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の機会に、「日米豪政府のインド太平洋におけるインフラ投資に関する三者間パートナーシップに関する共同声明」とパプアニューギニア、日本、オーストラリア、米国、ニュージーランドが署名した「パプアニューギニア電化パートナーシップ共同声明」を発出した。また、国連平和維持活動(PKO)、軍縮・不拡散、気候変動対策、国連安保理改革などの地球規模課題についても重要なパートナーとして協働している。
(2)ニュージーランド
ア 概要・総論
日本とニュージーランドは、民主主義、市場経済などの基本的価値を共有し、長年良好な関係を維持している。近年、「戦略的協力パートナーシップ」の下、経済、安全保障・防衛協力、人物交流を含む二国間協力の強化に加え、地域や国際社会の課題についても協力関係を強化している。2017年10月に約9年ぶりの政権交代により発足した労働党・NZファースト党連立政権は、対日関係重視を打ち出している。
イ 要人往来
日本からは、2月に中根外務副大臣がニュージーランドを訪問し、ピーターズ副首相兼外相と会談したほか、クライストチャーチ地震7周年追悼式典に出席した。10月には河野外務大臣が、日本の外務大臣として約5年ぶりにニュージーランドを訪問し、アーデーン首相を表敬するとともに、ピーターズ副首相兼外相等の要人と会談を行い、両国関係の強化と太平洋島嶼国地域における協力の促進や、北朝鮮問題を始めとする地域情勢に関する連携につき一致した。
ニュージーランドからは、5月にピーターズ副首相兼外相が第8回太平洋・島サミット(PALM8)に出席するため訪日し、河野外務大臣と外相会談を行い、特に太平洋島嶼国地域における協力の促進につき一致した。また、11月のASEAN関連首脳会議の機会に、安倍総理大臣はアーデーン首相との間で首脳会談を行い、引き続き緊密に連携し両国関係を強化することで一致した。
ウ 経済関係
両国は、相互補完的な経済関係を有しており、TPP協定の発効に向けて連携した。また、食料・農業分野においては、2014年から日本の酪農の収益性を向上させることを目的とした「ニュージーランド・北海道酪農協力プロジェクト」が実施されている。さらに、羊産業の活性化を目的に「ニュージーランド・北海道羊協力プロジェクト」が開始された。
エ 文化・人的交流
2018年度は、JENESYS2018の一環として、ニュージーランドから約20人の大学生が訪日した。日・ニュージーランド間の青少年等の人的交流は、累計で1,100人を超えた。
また、青少年間の相互理解促進を目的とした姉妹都市間のネットワーク化が進んでいる。さらに、ワールドカップ連覇のラグビーを通じて日本の学生の英語教育を支援するニュージーランド政府主催事業「Game on English」が行われており、2018年にはこの事業により日本から31人の学生がニュージーランドを訪問した。
オ 国際社会における協力
両国は、国連の場を含む国際場裏にて国際社会の平和と安定のために緊密に協力している。特に、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮船籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、ニュージーランドは、2018年9月に米国、オーストラリア及びカナダと共に在日米軍嘉手納飛行場を拠点として、航空機による警戒監視活動を実施した。また、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、APECなどの地域協力枠組みにおける協力を行っている。また、太平洋島嶼国地域については、太平洋・島サミット(PALM)などを通じて協力を行っており、日・ニュージーランド外相間で「太平洋地域における協力に関する共同プレスリリース」や日・ニュージーランド間で「太平洋気候変動センターに関する協力」についての共同プレスリリースを発出した。
(3)太平洋島嶼国(とうしょこく)
ア 概要・総論
太平洋島嶼国は、日本と太平洋によって結ばれ、歴史的なつながりも深く、国際場裏での協力や水産資源・天然資源の供給において重要なパートナーである。また、太平洋の中心に位置することから、地政学的な観点でもその重要性が高まっている。日本は、1997年から3年に一度、太平洋・島サミット(PALM)を開催しており、2018年5月には第8回太平洋・島サミット(PALM8)が開催された。ほかにも、1989年に太平洋諸島フォーラム(PIF)が域外国対話を開始して以降、日本から継続してハイレベルが出席している。こうした国際会議の機会も活用した各レベルでの要人往来やODA、活発な人的交流などを通じて、太平洋島嶼国との関係を一層強化してきている。
イ 太平洋・島サミット(PALM)
PALMは2017年に20周年の節目を迎えた。2018年5月には、PALM8が、安倍総理大臣とトゥイラエパ・サモア首相の共同議長の下、福島県いわき市において開催された。PALM8は、「繁栄し自由で開かれた太平洋に向けたパートナーシップ」というキャッチフレーズの下、日本、太平洋島嶼14か国、ニュージーランド、オーストラリアに加え、新規参加のニューカレドニア・仏領ポリネシアの2地域を含む19か国・地域の首脳等が参加し、安倍総理大臣は各国首脳と個別に首脳会談を行った。PALM8では、①法に基づく海洋秩序、持続可能な海洋、②強靭(きょうじん)かつ持続可能な発展、③人的往来・交流の活性化、④国際場裏における協力の四つの議題を中心に議論を行い、議論の成果として「PALM8首脳宣言」を採択した。各国からは、日本がPALM等を通じて行ってきた貢献に謝意が表された。
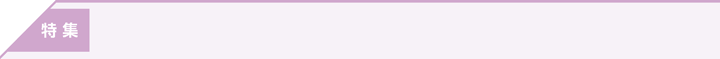
2018年5月18日から19日まで、福島県いわき市において、第8回太平洋・島サミット(PALM8)が開催されました。
太平洋・島サミットは、太平洋島嶼国地域が直面する様々な問題について首脳レベルで率直に意見交換を行い、地域の安定と繁栄に貢献するとともに、日本と太平洋島嶼国地域のパートナーシップを強化することを目的として、1997年から3年に一度開催されている首脳会議であり、これまで7回開催されています。PALM8は、「繁栄し自由で開かれた太平洋に向けたパートナーシップ」というキャッチフレーズの下、日本、島嶼14か国、ニュージーランド、オーストラリアに加え、新規参加のニューカレドニア・フランス領ポリネシアの2地域を含む19か国・地域の首脳等が参加しました。

首脳会合では、安倍総理大臣が基調講演を行い、2015年のPALM7で約束した協力は、目標を大幅に超える形で達成したと説明した上で、今後3年間で、①自由で開かれた持続可能な海洋、②持続可能な発展、③人的交流・往来の活性化の3分野を中心に協力を進めていくことを表明しました。また、日本政府として、太平洋島嶼国のニーズにしっかりと耳を傾けながら、島嶼国の人々と社会が真に裨益(ひえき)する、ソフトとハード両面でのきめ細かな質の高い支援を提供し、これらの分野を中心に今後3年間で5,000人以上の人材育成・交流を実施することを約束すると表明しました。太平洋島嶼国からは、PALMがこれまで果たしてきた役割を高く評価するとの発言があり、日本と太平洋島嶼国でPALMプロセスを一層強化することで一致しました。また、日本の長年にわたる貢献に対して謝意が表されるとともに、今後3年間の新たな協力・支援策に対する力強い支持が表明されました。

今回のPALMでは、①法の支配に基づく海洋秩序及び持続可能な海洋、②強靱かつ持続可能な発展、③人的往来・交流の活性化、④国際場裏における協力の四つの議題を中心に議論を行い、議論の成果として「PALM8首脳宣言」を採択しました。
閉会に際して、共同議長国サモアのトゥイラエパ首相からは、PALM8の成功における日本を始めとする各国への謝意が述べられるとともに、日本と太平洋島嶼国のパートナーシップを更に強化していきたいと述べられました。最後に安倍総理大臣は、PALM8首脳宣言を基礎に、日本と太平洋島嶼国で新時代のパートナーシップを共に築き、繁栄し、自由で開かれた太平洋を共に確保していく決意を新たにし、閉会を宣言しました。
ウ 要人往来
1月、堀井巌外務大臣政務官がナウル独立50周年記念式典に出席するためナウルを訪問し、ワンガ大統領等と会談を行った。薗浦総理大臣補佐官が3月にパプアニューギニア及びソロモンを訪問し、パト・パプアニューギニア外相及びホウエニプウェラ・ソロモン首相等と会談を行い、4月にパラオとミクロネシアを訪問し、レメンゲサウ・パラオ大統領及びクリスチャン・ミクロネシア大統領等と会談を行った。同月、堀井巌外務大臣政務官がサモア等を訪問し、トゥイラエパ首相等と会談を行った。8月、堀井巌外務大臣政務官はクック諸島第53回憲法記念式典に出席するためクック諸島を訪問するとともに、トンガ、キリバス、マーシャル等を訪問し、プナ・クック首相、ポヒヴァ・トンガ首相、マーマウ・キリバス大統領、ハイネ・マーシャル大統領等と会談を行った。11月、クリスチャン・ミクロネシア大統領とロバート・ミクロネシア外相が訪日し、安倍総理大臣と阿部外務副大臣とそれぞれ会談を行った。同月、安倍総理大臣と河野外務大臣はAPECに出席するためパプアニューギニアを訪問し、オニール首相とパト外相とそれぞれ会談を行った。12月、鈴木外務大臣政務官は、官民合同経済ミッションの団長としてパラオを訪問し、貿易・投資・観光セミナーへ出席したほか、レメンゲサウ大統領等と会談を行った。


エ 太平洋諸島フォーラム(PIF)などとの関係
9月、ナウルでPIF総会が開催され、総理特使として堀井巌外務大臣政務官が域外国対話に出席した。日本は、自由で開かれたルールに基づく海洋秩序の維持並びに海洋資源の持続可能な活用及び海洋環境の維持保全を地域における政策の優先事項として扱い、太平洋島嶼国と協力していくことを表明した。また、堀井外務大臣政務官は、ワンガ・ナウル大統領と会談したほか、出席した太平洋島嶼国各国要人と会談した。
オ 文化・人的交流
2015年のPALM7の「3年間で4,000人の人づくり」の強化の一環として、JENESYSを通じた大学生等との人的交流を実施した。また、2016年度から太平洋島嶼国の若手行政官を対象とした太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacific-LEADS)を開始し、2017年度は41人を受け入れた。
カ 在バヌアツ兼勤駐在官事務所の設立
バヌアツは南太平洋のメラネシア地域に位置する島国であり、これまでも国連安保理改革や国際機関選挙等において日本の立場を支持するなど日本にとって重要な国である。これを踏まえ、日本は2018年1月にバヌアツに兼勤駐在官事務所を設置した。
18 オーストラリアの大学生のアジアに対する知見を広めることを目的として、アジアへの海外留学を促進するオーストラリア政府の政策。
