ポーランド共和国
ポーランド共和国(Republic of Poland)
基礎データ
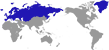
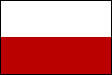
一般事情
1 面積
31.39万平方キロメートル(日本の約5分の4、日本から九州、四国を引いた程度)
2 人口
約3,768万人(2023年8月:ポーランド中央統計局)
3 首都
ワルシャワ(約179万人)
4 民族
ポーランド人(人口の約97%)
5 言語
ポーランド語
6 宗教
カトリック(人口の約88%)
7 国祭日
5月3日(憲法記念日)、11月11日(独立記念日)
8 略史
| 年月 | 略史 |
|---|---|
| 966年 | ピアスト朝、キリスト教を受容 |
| 1386年 | ヤギェウォ朝の成立 |
| 1573年 | 選挙王制 |
| 1795年 | 第3次分割によりポーランド国家消滅 |
| 1918年11月 | 独立回復 |
| 1945年7月 | 国民統一政府の樹立 |
| 1989年9月 | 非社会主義政権の成立 |
| 1999年3月 | NATO加盟 |
| 2004年5月 | EU加盟 |
- 10世紀に建国。15~17世紀には東欧の大国。18世紀末には3度にわたり、ロシア、プロイセン、オーストリアの隣接三国に分割され、第一次大戦終了までの123年間世界地図から姿を消す。
- 第二次大戦ではソ連とドイツに分割占領された。大戦での犠牲者は、総人口の5分の1を数え、世界最高の比率。
- 大戦後は、ソ連圏に組み込まれたが、「連帯」運動(1980年代)など自由化運動が活発で、東欧諸国の民主化運動をリードした。1989年9月、旧ソ連圏で最初の非社会主義政権が発足した。
- 「欧州への回帰」を目標に掲げ、1999年3月にNATO加盟、2004年5月にEU加盟を果たした。
政治体制・内政
1 政体
共和制
2 元首
アンジェイ・ドゥダ(Andrzej DUDA)大統領(2020年8月再任、任期5年)
3 議会
二院制(下院460議席、上院100議席、両院とも任期4年)
4 政府
- (1)首相名 ドナルド・トゥスク(Donald TUSK)(2023年12月就任)
- (2)外相名 ラドスワフ・シコルスキ(Radosław SIKORSKI)(2023年12月就任)
5 内政
- (1)1989年9月にマゾヴィエツキ首相の非社会主義政権が成立して以来、大統領及び議会の自由選挙が実施され、民主主義が定着。2007年10月に行われた総選挙までは、「連帯」の流れを汲む中道右派政党と旧共産党系の左派政党が交互に政権についた。
- (2)2007年10月21日に行われた総選挙では、与党であった「法と正義」(PiS)を破り、同じく「連帯」の流れを汲む最大野党「市民プラットフォーム」(PO)が勝利した。POは、同党のトゥスク党首を首班とする農民党(PSL)との連立政権を発足させた。
- (3)2010年4月10日、カティンの森70周年追悼式典に出席のため、カティンに向かっていた政府専用機がロシアのスモレンスク近郊で墜落、レフ・カチンスキ大統領夫妻等乗員乗客96名全員が死亡した。新大統領選出のために同年6月から7月にかけて行われた大統領選挙では、決選投票において、与党POのコモロフスキ下院議長が、死亡した前大統領の双子の兄であるヤロスワフ・カチンスキPiS党首を破って当選した。
- (4)2011年10月9日に行われた総選挙では、POが再び勝利し、PO及びPSLによる連立政権が2期8年にわたり継続した。他方、2014年8月にトゥスク首相が次期欧州理事会議長に選出されたことを受けて、同年9月からはコパチ首相が連立政権を率いた。
- (5)2015年5月、任期満了に伴う大統領選挙が行われ、決選投票で、最大野党PiSが擁立したドゥダ候補が現職のコモロフスキ大統領を破り、8月6日に大統領に就任した。
- (6)2015年10月25日、総選挙が実施され、PiSが上下両院で単独過半数の議席を獲得した。同年11月16日、PiSにより、1989年の民主化後初めての一党単独政権が発足し、シドゥウォPiS副党首が首相に就任した。
- (7)2017年12月7日、シドゥウォ首相が辞任を表明し、同月11日、モラヴィエツキ副首相兼財務・開発大臣が首相に就任した。
- (8)2019年10月13日に実施された総選挙では、与党PiSが下院で単独過半数の議席を維持したものの、上院では過半数を維持できず、上下両院の間で「ねじれ」が生じた。同年11月19日、再任されたモラヴィエツキ首相を首班とする新内閣が発足した。
- (9)2020年6月から7月にかけて実施された大統領選挙では、決選投票の結果、現職のドゥダ大統領が、野党候補であるチシャスコフスキ・ワルシャワ市長(PO所属)を僅差で破って再選し、同年8月6日に再任された。
- (10)2023年10月15日に実施された総選挙では、与党PiSが下院で第一党となったものの過半数には届かず、ドゥダ大統領が組閣を行うよう命じたモラヴィエツキ首相は下院の信任を得られなかった。12月13日、下院が選出したトゥスク首相を首班とし、「市民連立」(KO)、「ポーランド2050」、「農民党」(PSL)、「左派」による連立政権が発足し、8年ぶりに政権交代が起きた。
外交・国防
1 外交
- (1)1999年にNATO加盟、2004年にEU加盟を果たし、NATO及びEUとの協力強化を通じて国の安全と繁栄を確保していくとの姿勢。また、「連帯」運動の伝統から民主主義の推進に熱心。アジア諸国とは経済関係の強化に関心がある。
- (2)順調な経済、積極的な外交を背景としてEU内で重要なプレーヤーとなりつつあり、2014年8月のトゥスク首相の欧州理事会議長選出(2019年11月退任)及び欧州議会最大会派である欧州人民党(EPP)党首就任(同12月1日)はEUにおけるポーランドの存在感を示す一例と言える。近隣諸国ともヴィシェグラード・グループ(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、略称「V4」)、三海域イニシアティブ(経済協力が中心、略称「3SI」)、ブカレスト・ナイン(安全保障協力が中心、略称「B9」)等の地域フォーマットを通じて、EU及びNATO内における存在感を高めている。EUの施策の内、特にEUの東方近隣諸国政策にリーダーシップを発揮し、2009年に発足した東方諸国(ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン)のEUとの統合を推進する東方パートナーシップに積極的に取り組んできた。ロシアとの関係では、2010年に同国で墜落したポーランド政府専用機の機体返還等の問題が残されている。また、ウクライナ危機を受け、EUの対露制裁、ロシアによるEU農産品の禁輸措置など対立局面が続いている他、ポーランド国内の旧ソ連の記念碑の取り扱いに関する問題等も生じている。
- (3)安全保障面ではNATO、EU及び米国とのパートナーシップを3本柱として位置付け、集団安全保障機構としてのNATOの役割を重視。2016年7月にはNATOワルシャワ首脳会合を主催し、同会合はNATO東方地域の強化等の成果を出した。また、米国との関係ではNATOの計画でもある欧州ミサイル防衛システムの構築を一貫して支持。2024年から米SM-3ミサイルを装備するイージス・アショアの運用が開始される予定(同配備に対しロシアは常に強い懸念を表明)であり、2016年5月に設置作業が開始された。また、2020年8月に米国との間で強化防衛協力合意(EDCA)が締結され、在ポーランド米軍1,000名の増派が明示されるとともに、米軍用インフラ施設の整備が進められている。自国の軍備の近代化も進めており、ミサイル等の兵器の新規購入を積極的に実行している。更に、2014年3月以降のウクライナ情勢を受け、NATO及びウクライナも含めた隣国との合同部隊の本部をポーランド国内に設置するとともに、東欧地域の様々な枠組みを活用し自国及び他国との協力を強化する等、多層的な安全保障態勢の整備を推進している。2022年2月のロシアによるウクライナ侵略を受けた米軍のポーランド増派により、約10,000人の米兵が駐留し、米陸軍第5軍団の前方司令部が常設されることになった。
- (4)ポーランドは、安全保障における国際協力にも積極的であり、NATO及びEUの枠組で、イラク、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ等に人員を派遣、2019年11月から国連の枠組でレバノンに人員の派遣を行っている。現在、ポーランド軍は約1,400名の兵士を国外へ派遣している。
- (5)2022年2月のロシアによるウクライナ侵略を受け、ポーランドは、近隣諸国最大規模のウクライナからの避難民を積極的に受け入れ、人道支援を提供し、社会生活をサポートしている。また、ウクライナに対して戦車、榴弾砲、砲弾、弾薬、対空ミサイル、軽迫撃砲、偵察用ドローン等約30億ユーロ相当の軍事支援を行っている。侵略直後、一早くロシア航空機のポーランド領空通過禁止措置や露系放送局の放送免許取消等の独自措置を実施。さらに、ロシアに対しては、エネルギー資源(石油、石炭、ガス)の禁輸、ロシアの銀行のSWIFTからの排除、ロシア関係者の資産没収といった厳しい制裁を課すよう主張し、各国に積極的な働きかけを実施している。
2 軍事力
- (1)予算 約230億ドル(対前年GDP比4%)(2023年:ポーランド国防省予算資料)
- (2)兵力 総兵力約16.4万人(2023年)
- (3)徴兵制は2009年末で廃止
経済
1 主要産業
食品・飲料、金属・金属品、自動車・自動車部品、コンピュータ・電子・電子機器、ゴム・プラスチック
2 GDP
約6,546億ユーロ(2022年、欧州委員会)
3 一人当たりGDP
約17,300ユーロ(2022年:欧州委員会)
4 経済成長率
5.3%(2022年:中央統計局)
5 物価上昇率(前年同月比)
+6.2%(2023年12月:ポーランド中央統計局)
6 失業率
5.1%(2023年12月:ポーランド中央統計局)
7 総貿易額
- (1)輸出 3,438億ユーロ(2022年:ポーランド中央統計局)
- (2)輸入 3,637億ユーロ(2022年:ポーランド中央統計局)
8 主要貿易品目
- (1)輸出 機械機器類、農産品・食料品、金属製品等
- (2)輸入 機械機器類、金属製品、化学製品等
9 主要貿易相手国
- (1)輸出 ドイツ、チェコ、フランス、英国(EUが約75.8%)
- (2)輸入 ドイツ、中国、イタリア、米国(EUが約51.4%)
10 通貨
ズロチ(ZŁ)
11 為替レート
1ZŁ=約36円(2023年12月現在)
12 経済概況
(1)堅調なマクロ経済
2004年のEU加盟以降、2022年までにGDPは3倍以上となり、2008年のリーマンショック直後もEU内で唯一プラス成長を維持した。
2011年に再び欧州が信用危機に見舞われた際、堅調な輸出や個人消費に牽引され5.0%の成長率を達成。2012年には欧州債務危機の影響による個人消費の落ち込みから1.6%の成長となったが、2013年第2四半期から順調に回復し、2019年には4.7%の成長を達成した(ポーランド中央統計局)。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響があったが、他のEU諸国よりも限定的であり、その後の2021年の成長率は6.9%に回復。2022年の成長率は新型コロナウイルス感染症後であったがウクライナ侵略の影響で5.3%となった。
金融政策委員会は、2015年3月に政策金利を当時史上最低の1.5%に利下げして以降、同金利を維持していたが、新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案し、2020年4月に0.5%に、また、同年5月には0.1%に再度引き下げるなど金融政策を緩和した。しかし、インフレ(2022年6月の対前年同月比消費者物価指数は+15.5%)が進んだことを踏まえ、2021年10月以降、政策金利を2022年10月までに政策金利を順次6.75%まで引き上げたが、インフレ鈍化により2023年11月から5.75%に引き下げた。
(2)財政状況
2009年から政府の単年度財政が悪化し、財政赤字が対GDP比7.3%とEUの過剰財政赤字手続適用値(同3.0%)を大きく超えた。欧州委員会から是正勧告を受け、財政赤字削減に取り組んだ結果、2014年は同3.6%へと改善し、それ以降は3.0%以下を維持してきた。しかし、2020年は新型コロナウイルス感染症、2022年はウクライナ侵略の影響を受け、大規模な経済対策やウクライナ支援を打ち出す等した結果、財政赤字の対GDP比はそれぞれ6.9%、3.7%に増加した。
(3)経済政策上の課題
2023年12月に8年ぶりの政権交代が行われ、トゥスク政権は、ウクライナ支援、脱炭素路線の継続と強化、EUとの関係修復と強化、国営企業の非政治化を主な政策として掲げている。
特にグリーンエネルギー分野では、風力・太陽光・バイオガスといった再生可能エネルギーの財政的・技術的支援システムを構築し、DXを推進する法整備を加速させていくことを表明している。また前政権で滞っていた欧州復興基金の一部を早々に解除させるなど、EU基金等を活用した政策を押し進めている。
(4)エネルギー
ロシアのエネルギー資源からの独立と、脱炭素化が課題。政府は、ロシアによるウクライナ侵略前から北欧、中東、米などからガス等を輸入し多様化を図り、LNGターミナル建設・拡張やパイプライン網の構築等に取り組んでいる。ロシアからの輸入依存度について、天然ガスは2021年の60%から2023年第1四半期にゼロになり、原油は2021年の62%から2022年には43%に低下。電力の約7割を石炭火力に依存しているが、発電所の老朽化、電力需要の増加、気候変動対策を踏まえ、原子力発電の導入や再エネ導入の加速を計画。2021年に2040年までのエネルギー戦略を制定したが、ロシアによるウクライナ侵略や政権交代が起きたことにより改定案を検討中。
(5)EU基金
順調な経済成長を下支えしてきたのがEUの基金。ポーランドは2007~2013年の多年度財政枠組み(MFF)において673億ユーロ、2014~2020年に825億ユーロと、共に加盟国中最大の受給枠を確保した。2021-2027年のMFF及び欧州復興基金から総額約1,700億ユーロを獲得見込み。
経済協力
1 日本の援助実績(1989~2008年、2022年~)
(1)概略
日本は、1989年の民主化以降2008年まで、市場経済及び民主主義への円滑な移行に資するため、技術協力を中心に産業、経済、貿易振興等の諸政策の立案支援をはじめ、生産性向上、品質管理等の企業育成支援や、環境保全、技術革新等、多岐にわたる支援を実施(ポーランドのEU加盟等を踏まえ終了)。
また、日本は、2004年から3年間、ODAで設立・発展したポーランド日本情報工科大学によるウクライナのキーウ工科大学、リヴィウ工科大学に対する遠隔教育(遠隔教育センターはUNDPにより整備)を行うなど、ポーランドとの開発援助協力(三角協力)を実施した。
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略により多くの避難民を受け入れているポーランドを含む周辺国に対し、日本は緊急人道支援を実施。さらに、侵略の長期化により増加するポーランドを含む周辺国の負担や脆弱性を軽減し、ウクライナへの人道、復旧・復興支援を効果的に行う観点から、2023年2月、ポーランドに、直接ODAを供与することを決定した。これを受けて同年3月、草の根・人間の安全保障無償資金協力による避難民児童のための移動用バスの供与や、日本NGO連携無償資金協力によるウクライナ避難民支援の実施を決定した。また、同年7月から1か月間、ポーランドに滞在するウクライナ避難民の雇用促進・生活安定のため、ITビジネススキル研修を80名以上に対して実施した。
(2)日本の対ポーランド経済協力実績
(実施年度1989~2008年度)
- (ア)有償資金協力 213.92億円
- (イ)無償資金協力 40.36億円
- (ウ)技術協力 89.71億円
(実施年度2022年~)
- 2022年 緊急人道支援 約794万ドル
- 2023年 緊急人道支援 約723万ドル
- 2023年 日本NGO連携無償資金協力 2.8億円
- 2023年 草の根・人間の安全保障無償資金協力 855万円
二国間関係
1 政治関係
両国関係は伝統的に良好。1919年3月に日本はポーランド共和国及び同国政府を承認し、国交を樹立(2019年は国交樹立100周年)。1920年8月に在京ポーランド公使館開設。1921年5月に在ポーランド日本公使館開設。第二次大戦後は1957年に国交を回復。1990年に海部総理、2002年に天皇皇后両陛下、2003年に小泉総理がポーランドを訪問し、ポーランドからは1991年にビエレツキ首相、1994年にワレサ大統領、1998年にクファシニエフスキ大統領、1999年にブゼク首相、2005年にベルカ首相、2008年にカチンスキ大統領が訪日した。また、2012年にはコモロフスカ大統領夫人が訪日し、東日本大震災被災地を訪問した。
2013年6月、安倍総理が日本の首相としては10年ぶりにポーランドを訪問した。安倍総理は、日・ポーランド首脳会談に続き、ヴィシェグラード4諸国(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー)と第1回「V4+日本」首脳会合を行った。
2015年2月、コモロフスキ大統領夫妻が訪日し、安倍総理と日・ポーランド首脳会談を実施し、共同記者発表において、「日本国とポーランド共和国との間の共同声明「自由、成長、連帯への戦略的パートナーシップ構築」(PDF) を発出した。また、安倍総理夫人がコモロフスカ大統領夫人と懇談を行った。
を発出した。また、安倍総理夫人がコモロフスカ大統領夫人と懇談を行った。
2015年10月、高円宮妃殿下がポーランドをご旅行され、ドゥダ大統領夫妻と懇談された。
2017年5月、ヴァシチコフスキ外相が訪日し、岸田外務大臣と会談を行った。両外相は「日・ポーランド戦略的パートナーシップに関する行動計画」に署名した。
2018年7月、河野外務大臣がポーランドを訪問し、チャプトヴィチ外相と会談を行った。
同年10月、第12回アジア欧州会合(ASEM)首脳会合に際し、ブリュッセルにて第2回「V4+日本」首脳会合が開催された。
2019年4月、安倍総理のスロバキア訪問に際し、日・ポーランド首脳会談及び第3回「V4+日本」首脳会合が行われた。安倍総理は、モラヴィエツキ首相との間で戦略的パートナーシップ関係の発展を歓迎し、引き続き連携していくことを確認した。
2019年6月27日~7月2日、秋篠宮皇嗣同妃両殿下が国交樹立100周年の機会にポーランドを御訪問し、ドゥダ大統領夫妻と懇談されたほか、周年記念行事に出席された。
2019年10月の即位礼正殿の儀には、コルンハウゼル=ドゥダ大統領夫人が出席した。
2020年1月、モラヴィエツキ首相が訪日し、日・ポーランド首脳会談を実施した。戦略的パートナーとして政治・安全保障、経済、文化・人的交流など様々な分野でのさらなる関係深化について合意した。
2021年5月、茂木外務大臣がポーランドを訪問し、ドゥダ大統領表敬及びラウ外相との会談を実施した。また、第7回「V4+日本」外相会合を開催した。
2021年7月、東京オリンピック競技大会開会式に出席するため、ドゥダ大統領が訪日し、菅総理と首脳会談を実施した。両首脳は、両国の戦略的パートナーシップを一層深化させていくことで一致した。
2022年3月、G7首脳会合に出席するためにブリュッセルを訪問していた岸田総理は、モラヴィエツキ首相と首脳会談を実施し、ロシアによるウクライナ侵略を受けた意見交換を行った。
2022年4月、ロシアによるウクライナ侵略を受け、総理特使として林外務大臣がポーランドを訪問し、ドゥダ大統領及びモラヴィエツキ首相を表敬訪問するとともに、ラウ外相との会談を実施した。両外相は、自由で開かれた国際秩序を守るため、戦略的パートナーとして、引き続き緊密に連携していくことで一致した。
2023年3月、岸田総理が、日本の首相としては10年ぶりにポーランドを訪問し、ドゥダ大統領及びモラヴィエツキ首相とそれぞれ首脳会談を実施した。岸田総理からは、ポーランド訪問前に行った自身のウクライナ訪問にあたってのポーランドの協力に謝意を表明の上、ウクライナ情勢や二国間関係について意見交換を行った。同年4月、NATO外相会合に参加するためベルギーを訪問中の林外務大臣は、ラウ外相と会談を実施した。3月の岸田総理によるポーランド訪問時のドゥダ大統領及びモラヴィエツキ首相による歓迎に感謝の意を表しつつ、ロシアによるウクライナ侵略への対応や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて引き続き緊密に連携していくことで一致した。同年5月、ラウ外相が訪日し、林外務大臣との間で会談等を実施した(6年ぶりの外相訪日)。二国間関係やウクライナ、インド太平洋の地域情勢について意見交換を実施した。また、岸田総理はラウ外相からの表敬を受けた。同年7月、岸田総理はポーランドを訪問し、モラヴィエツキ首相と首脳会談を実施した。両首脳は、3月の岸田総理によるポーランド訪問以降も、二国間関係は急速に緊密化しており、経済関係をさらに強化していくこと、大阪関西万博をその機会にしていくことで一致した。さらに、同年9月、林外務大臣がポーランドを訪問し、ラウ外相との間で同年3度目となる会談を実施した。両外相は、数え切れない分野における政府間での協力のみならず、両国の戦略的パートナーシップ関係が順調に発展していることを改めて確認した。
2024年1月、上川外務大臣がポーランドを訪問し、ドゥダ大統領を表敬するとともに、シコルスキ外相との間で会談を行った。2023年12月に政権交代が起きてトゥスク政権が発足した直後の訪問を通じて両国関係の変わらぬ強化の方向性について確認した。
2 経済関係
(1)日本の対ポーランド貿易(2023年:財務省貿易統計)
(ア)総貿易額 7,436億円
- 輸出 5,912億円
- 輸入 1,524億円
(イ)主要品目
- 輸出 自動車及び自動車部品、機械機器
- 輸入 機械機器、自動車及び自動車部品、食料品
(2)進出日系企業数
367社(2023年10月現在:外務省海外在留邦人数調査統計)
3 文化関係
(1)概略
- 両国民の互いの文化に対する高い関心を背景として、国内各地で武道や伝統文化、ポップカルチャーを中心とした文化交流や、日本語教育が活発。健康志向の高まりとともに、日本食も大きなブームとなっている。2013年にワルシャワで開始された総合日本文化交流事業「日本祭り」も2023年に約25,000人の参加者を得るまでに成長した。
- 1994年11月、ワイダ監督夫妻のイニシアティブと尽力により日本美術技術センター(現在は「日本美術技術博物館」、通称Manggha館)がクラクフ市に設立。ポーランドのみならず中・東欧地域の一大日本文化発信拠点となっている。これまでに、天皇皇后両陛下(2002年)、高円宮妃殿下(2015年)、安倍総理夫人(2013、2014年)、秋篠宮皇嗣同妃両殿下(2019年)など、多くの要人も訪問している。創立20周年となる2014年には、「ポーランドの日本美術傑作展」をはじめ様々な記念行事が実施され、同年11月に開催された20周年式典にはコモロフスキ大統領夫妻、安倍総理夫人、ワレサ元大統領等が出席した。
- 2015年秋に開催された第17回ショパン国際ピアノ・コンクールに際しては、12名の日本人ピアニストが出場、高円宮妃殿下のご臨席も得て、両国の音楽交流が一層活発化した。2021年10月、新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期となった第18回同コンクールでは、14名の日本人ピアニストが出場、2位と4位に入賞し、話題となった。日本人の2位入賞は過去最高位で51年ぶりの快挙。
- 2022年5月、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)と駐日ポーランド共和国大使館によって創設された、国際的に活躍が期待される日本の若手女性研究者を表彰する「羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)」の第1回授賞式が駐日ポーランド共和国大使館にて開催。式典には高円宮妃殿下も御臨席された。
- 2023年、シベリアに残されたポーランド人孤児が日本の協力によって救済され、ポーランドに帰国した1923年から100周年を迎え、ワルシャワにて関連行事が行われた。
(2)日本語
国立5大学に在籍する約630名の日本学科学生に加え、約50の学校・機関で合計約5,300名が日本語を学習している(学生・学習者数は2024年推計)。各大学の日本語学科への入学試験競争率は20倍前後の難関である。40年以上の伝統を誇る日本語弁論大会も毎回多数の参加者を得て実施されている。
(3)スポーツ
空手、柔道、相撲、合気道、剣道等の日本の武道が盛んであり、国内各地に道場がある。特に、空手(伝統空手含む)の競技人口は57,000人超(2022年統計)で、競技人口別第5位の人気スポーツとなっている。また、相撲をきっかけとした地方自治体間(島根県隠岐の島町とクロトシン市)の交流が行われており、2016年6月に友好都市提携の調印式が行われた。
(4)文化無償協力・草の根文化無償協力
1991年から2004年まで、大学など学術機関や文化施設を中心にほぼ毎年機材供与の実績あり。2000年から2007年までは3件の草の根文化無償協力を実施。
4 在留邦人数
2,136名(2023年10月1日現在:外務省海外在留邦人数調査統計)
5 在日ポーランド人数
1,762人(2023年6月末現在:法務省在留外国人統計)
6 日本人訪問者数
20,006人(2023年ポーランド中央統計局)
7 要人往来
| 年月 | 要人名 |
|---|---|
| 1990年 | 海部総理大臣、中山外務大臣 |
| 1992年 | 村山衆議院副議長(下院公式招待) |
| 1994年 | 高円宮同妃両殿下 |
| 1996年 | 塚原通商産業大臣 |
| 1997年 | 池田外務大臣、白川自治大臣 |
| 2000年 | 斎藤参議院議長(上院公式招待) |
| 2001年 | 丸谷外務大臣政務官 |
| 2002年 | 天皇皇后両陛下、松浪外務大臣政務官 |
| 2003年 | 小泉総理大臣、参議院公式議員団(上院公式招待) |
| 2004年 | 田中外務大臣政務官(「拡散に対する安全保障構想」(PSI)総会) |
| 2005年 | 衆議院日本ポーランド友好議員連盟代表団(下院公式招待) |
| 2007年 | 麻生外務大臣、高木経済産業大臣政務官 |
| 2008年 | 斎藤環境大臣、江渡防衛副大臣、小野寺外務副大臣、横路衆議院副議長、谷合経済産業大臣政務官、三ツ矢財務大臣政務官 |
| 2009年 | 石原東京都知事 |
| 2011年 | 伴野外務副大臣、園田内閣府大臣政務官 |
| 2012年 | 浜田外務大臣政務官 |
| 2013年 | 安倍総理大臣、左藤防衛大臣政務官、石原環境大臣 |
| 2014年 | 松島経済産業副大臣、愛知財務副大臣、西村内閣府副大臣、安倍総理夫人 |
| 2015年 | 高木経済産業副大臣、城内外務副大臣、高円宮妃殿下 |
| 2017年 | 田野瀬文部科学大臣政務官、郡司参議院副議長 |
| 2018年 | 河野外務大臣、原田環境大臣、滝波経済産業大臣政務官 |
| 2019年 | 秋篠宮皇嗣同妃両殿下、衆議院日本ポーランド友好議員連盟代表団(下院公式招待) |
| 2021年 | 茂木外務大臣 |
| 2022年 | 林外務大臣(総理特使)、中谷総理補佐官、津島法務副大臣、武部農林水産副大臣、武井外務副大臣(OSCE外相会合) |
| 2023年 | 岸田総理大臣(3月及び7月)、西村経済産業大臣、小野田防衛大臣政務官、林外務大臣、辻󠄀外務副大臣、岩田経済産業副大臣 |
| 2024年 | 上川外務大臣 |
| 年月 | 要人名 |
|---|---|
| 1990年 | コザキエヴィチ下院議長(即位の礼) |
| 1991年 | ビエレツキ首相(非公式訪問) |
| 1992年 | スクビシェフスキ外相(外務省賓客) |
| 1994年 | ワレサ大統領(国賓)、オレクスィ下院議長(衆議院議長招待) |
| 1996年、1997年 | ストゥルジク上院議長(参議院議長招待) |
| 1998年 | クファシニエフスキ大統領(IOC賓客) |
| 1999年 | ブゼク首相(非公式訪問) |
| 2000年 | ゲレメク外相(外務省賓客) |
| 2001年 | グジェシコヴィアック上院議長(参議院議長招待)、ジェリンスキ文化相 |
| 2004年 | クライベル科学相、ラチュコ財務相 |
| 2005年 | ベルカ首相、カリシュ内務・行政相(国連防災会議)、グロニツキ財務相 |
| 2006年 | メレル外相(外務省賓客) |
| 2007年 | ウヤズドフスキ文化相、セヴェリンスキ科学・高等教育相 |
| 2008年 | カチンスキ大統領(公式実務訪問賓客)、シコルスキ外相(外務省賓客)、サヴィツキ農業・農村開発相、ノヴィツキ環境相 |
| 2009年 | サヴィツキ農業・農村開発相、グラド国有財産相、ノヴィツキ環境相 |
| 2010年 | ボルセヴィチ上院議長、クラシェフスキ環境相 |
| 2011年 | ズドロイェフスキ文化・国家遺産相 |
| 2012年 | コモロフスカ大統領夫人 |
| 2013年 | シェモニャク国防相、ズドロイェフスキ文化・国家遺産相、ピエホチンスキ副首相兼経済相 |
| 2015年 | コモロフスキ大統領(実務訪問賓客)、ヴァシャク・インフラ開発相(閣僚級招へい)、グラボフスキ環境相(国連防災世界会議)、下院ポーランド・日本友好議員連盟(衆議院公式招待) |
| 2017年 | ヴァシチコフスキ外相 |
| 2018年 | ジェジチャク外務副相 |
| 2019年 | バンカ・スポーツ・観光相、コルンハウゼル=ドゥダ大統領夫人(即位礼出席) |
| 2020年 | モラヴィエツキ首相、グロツキ上院議長(参議院議長招待) |
| 2021年 | ドゥダ大統領(東京オリンピック競技大会開会式出席) |
| 2022年 | ブダ開発・技術相、コヴァルチク副首相兼農業・農村開発大臣(故安倍晋三国葬儀) |
| 2023年 | ブダ開発・技術相、ラウ外相 |
| 2025年 | シコルスキ外相 |
8 二国間条約・取極
| 年月 | 略史 |
|---|---|
| 1957年 | 国交回復に関する協定(同年発効) |
| 1978年 | 通商航海条約(1980年発効) |
| 1978年 | 科学技術協力協定(同年発効) |
| 1978年 | 文化、教育交流取極(同年発効) |
| 1980年 | 二重課税防止条約(1982年発効) |
| 1994年 | 航空協定(1996年発効) |
| 1994年 | 外交・公用旅券保有者の相互査証免除取極(1995年発効) |
| 1998年 | 一般旅券保持者の相互査証免除取極(1999年発効) |
| 2004年 | 運転免許試験の相互免除に関する二国間取極(同年発効) |
| 2015年 | 日・ポーランド・ワーキング・ホリデー協定(同年発効) |
9 外交使節
- (1)河野章 駐ポーランド日本国特命全権大使
- (2)パヴェウ・ミレフスキ 駐日ポーランド共和国特命全権大使

