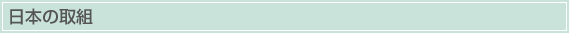| >>ICT分野における政策方針 >>ICT分野における事例 |
Last Updated: 2007. 07. 24 |
近年、ICTを活用可能な人々とそうでない人々との格差の解消を図ることが極めて重要な課題となっている。日本は、ODA大綱において、ICT分野における協力を重点課題の一つである持続的成長のための支援の一環として位置づけている。また、2000年7月の九州・沖縄サミットにおいて「国際的な情報格差問題に対する日本の包括的協力策について」を発表する等、産学官の連携のもとに、アジア各国の政府や国際機関とも連携体制をとりつつ、ICT分野の取組を積極的に行っている。

写真提供:JICA、ガーナの高校での授業で説明を聞きながら、コンピューター画面に見入る生徒たち
情報通信技術(ICT)はその普及に応じて便益が拡大する反面、情報格差(デジタル・デバイド)が存在し、先進国と開発途上国間の経済的格差を増幅させ、国際社会の将来的な安定を揺るがしかねません。また、ICTの普及は、経済効率の上昇を通じて持続可能な経済成長の実現に寄与するという経済的な側面のみではなく、情報発信伝達の手段として、政府の情報公開の促進や市民の政治参加を推進し、民主主義の強化や透明性の確保、人権の促進といった政治面でも、極めて重要な役割を果たしえます。ICT分野では、機材等のハード面の協力と、ハードを使いこなす人材育成等のソフトの協力に加え、例えばガーナの母子保健医療サービス向上のために職員の研修情報を記録し情報管理をするなど、他分野の協力の中でもICTが用いられています。
日本はODA大綱において、情報通信技術(ICT)の分野における協力を、重点課題の一つである持続的成長のための支援の一環として位置付けています。また、2005年2月に発表した新ODA中期政策においては、持続的成長のための経済社会基盤整備の一環としての通信インフラの整備が、基礎社会サービスへのアクセス改善や、地域間格差が存在する都市部と村落地域を結ぶことにつながり、貧困削減に寄与することを指摘しています。
・政府開発援助(ODA)大綱・中期政策での扱い(抜粋)
ODA大綱(2003年8月)
3. 重点課題
(2)持続的成長
開発途上国の貿易、投資及び人の交流を活性化し、持続的成長を支援するため、経済活動上重要となる経済社会基盤の整備とともに、政策立案、制度整備や人づくりへの協力も重視する。このような協力には、知的財産権の適切な保護や標準化を含む貿易・投資分野の協力、情報通信技術(ICT)の分野における協力、留学生の受入れ、研究協力なども含まれる。
ODA中期政策(2005年2月)
3.重点課題について
(1)貧困削減
(ロ)貧困削減のためのアプローチ及び具体的取組
(b)貧困層を対象とした直接的な支援
(i)基礎社会サービスの拡充
貧困層の生活の質の向上を図るため、教育、保健、安全な水、居住の場の確保、電化等の基礎社会サービスの拡充を当該国のガバナンス改善も慫慂しながら積極的に支援する。例えば、貧しい地域で建設された学校で井戸、トイレの設置により衛生状態の改善及び意識の向上を図るほか、給食を通じて児童の栄養改善を図る。基礎社会サービス供給の強化の観点から、中央政府及び地方政府の能力強化や保健医療システム等の強化を支援すると同時に病院や学校へのアクセス改善を目的とした運輸・通信・電力インフラの整備を行う。また、サービスの質の向上を目的として、人材養成・研修、教材の普及を支援する。さらに、女性と子供の健康、リプロダクティブ・ヘルス、感染症対策、女性の能力構築に資する支援を行う。
(2)持続的成長
(ロ)持続的成長のアプローチ及び具体的取組
(a)経済社会基盤の整備
途上国の制度政策環境や債務管理能力などに留意しつつ、道路、港湾等の運輸インフラ、発電・送電施設、石油・天然ガス関連施設等のエネルギー関連インフラ、情報通信インフラ、生活環境インフラといった貿易・投資環境整備等に資する経済社会基盤の整備を支援する。また、インフラの維持管理と持続性の確保のため、インフラ整備への支援と併せて、分野ごとの課題に関する政策策定・対話の推進、人材育成等、インフラのソフト面での支援も行う。
(b)政策立案・制度整備
経済社会基盤の整備に加え、マクロ経済の安定化、貿易や投資に関する政策・制度の構築、情報通信社会に関する政策・制度整備といったソフト分野の支援は、民間セクターが牽引する持続的な成長を促進する上で不可欠である。
(c)人づくり支援
専門家の派遣や研修制度等を活用し、我が国の技術、知見、人材を活用して我が国の経験を伝えつつ、中小企業振興や情報通信を含む産業発展を始めとする様々な分野における人材育成を支援する。
(d)経済連携強化のための支援
地域レベルの貿易・投資の促進は、各国の経済成長に直接貢献するとともに、開発に必要な資金の動員や民間セクターの技術水準向上等に寄与する。このため、国や地域に跨る広域インフラの整備を行うほか、貿易・投資に関連する諸制度の整備や人材の育成を積極的に支援する。我が国が経済連携を推進している各国・地域に対しては、知的財産保護や競争政策等の分野における国内法制度構築支援や、税関、入国管理関連の執行改善・能力強化支援、情報通信技術(ICT)、科学技術、中小企業、エネルギー、農業、観光等の分野における協力を行う。
・イニシアティブ・資金コミットメント
「国際的な情報格差問題に対する我が国の包括的協力策について」(2000年7月)
2000年の九州・沖縄サミットにおいて、日本は、情報格差の問題に対して(1)制度・政策づくりへの知的貢献、(2)人づくり、(3)情報通信基盤の整備・ネットワーク支援、④援助におけるIT利用の促進を4つの柱とする協力策を発表しました。ICTは基本的に民間主導で発展する分野であることから、開発途上国の状況を踏まえ、様々な関係者との連携の下で、開発途上国におけるインフラ構築や人材育成など民間活動になじまない分野に対してODAを充てることとしています。
(情報通信技術)

マイクロ波システム中継局
(写真提供:JBIC)
日本は、1992年に、パキスタンにおける「電気通信網拡充計画」に対し、円借款を供与しました。本計画では、通信サービスの量的拡充、質的改善を図り、商業・産業活動の活性化に寄与することを目的に、パキスタン政府にて実施予定であった電話回線の増設に合わせて国内伝送路(光ケーブル)及び国際通信施設の整備・拡充を支援しました。その結果、電話普及率が倍増したほか、受益者調査(住民40世帯、企業89社対象)では、回答者ほぼ全員から、本事業により通信状況が改善し、家族とのコミュニケーションやビジネスにプラスの効果があったとの意見が寄せられました。
・国際機関・他ドナーとの連携
日本・ポーランド・ウクライナの協力
~ポーランド日本情報工科大学(二国間支援)ウクライナへの情報技術移転(UNDPプロジェクト)~

日本は1989年以降、ポーランドへ市場経済及び民主主義への円滑な移行に資するような支援を行ってきました。その一環として、情報化に対応できる人材を育成するため、ポーランド政府からの要請を受けて1994年にポーランド日本情報工科大学(PJICT)を設立し、1996年から5年間技術協力を通じた人材育成を行ってきました。現在、PJICTは修士課程、博士課程が設置され、ポーランドのトップクラスの情報系大学となっています。
ポーランドは中・東欧地域でIT分野における中核的役割を担うべく、1999年度から2003年度まで、PJICTで第三国研修として周辺国の人々を集めた「東欧情報工学セミナー」が行われ、2004年度より「中東欧情報工学セミナー」が実施されてきました。
さらに、日本からの二国間支援を受けて発展してきたポーランド日本情報工科大学は、日本がUNDPに設置しているICT基金を活用して、地理的にも言語的にも近いウクライナに対し得てインターネットを利用した遠隔教育の指導法・運営手法を支援しています。
このように、持続可能な発展に資する技術や知識、経験を近隣諸国と共有することは、地域間協力・南南協力を促進させ、日本の協力を開発途上国が自立性をもって広めることにつながります。
南太平洋大学遠隔教育・情報通信技術強化(フィジー)

南太平洋地域の島嶼国12カ国により設立された国際機関である南太平洋大学(USP)では、1969年の設立以来遠隔教育が実施されており、現在約9千人の在校生のうち、45%が遠隔教育によって受講しています。日本は、オーストラリア及びニュージーランドと協調して1998年より「南太平洋大学通信体系改善計画」を無償資金協力によって実施し、フィジー本校と加盟各国にある分校との間に衛星イントラネット(USP-Net)を構築した結果、同時双方向の音声と画像による遠隔教育が可能となりました。さらに、日本は2002年より3年間、遠隔教育・情報通信技術強化プロジェクトとして、遠隔教材の開発・設備や域内出身講師の育成などを行ってきました。
島嶼国のように地理的に離れていても、ICTによって教育を受ける機会を向上することが可能となります。
写真出典:外務省「ミレニアム開発目標MDGs」ハンドブック
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()