1 朝鮮半島
(1)北朝鮮(拉致問題を含む。)
日本は、「対話と圧力」の方針の下、2002年の日朝平壌宣言に基づき、拉致問題、核・ミサイル問題といった北朝鮮との諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算し、日朝国交正常化を図ることを基本方針として、米国、韓国、中国、ロシアを始めとする関係国と緊密に連携しながら、引き続き様々な努力を行っている。
ア 内政・経済
(ア)内政
北朝鮮では、2011年の金正日(キムジョンイル)国防委員会委員長の死去から3年が経ち、人事(特に軍)には若干の変動があるが、金正恩国防委員会第一委員長を中心とした体制が続いている。
2014年は、金永南(キムヨンナム)最高人民会議常任委員長や朴奉珠(パクポンジュ)内閣総理の再任、李洙墉(リスヨン)元スイス「大使」の外相就任、姜錫柱(カンソクチュ)の党書記就任などの主要人事が発表されたほか、軍総政治局長が崔龍海(チェリョンヘ)から黄炳瑞(ファンビョンソ)に交代したことが明らかになった。
2013年の朝鮮労働党中央委員会全体会議(総会)で、経済建設と核武力建設を並進させていく「並進路線」が決定され、2014年1月1日の金正恩国防委員会第一委員長による「新年の辞」でも同路線の貫徹に言及している。
(イ)経済
厳しい経済難にあるといわれている北朝鮮にとって、経済の立て直しは極めて重大な課題とされている。2013年には経済開発区法を制定し、全国各道に経済開発区を設けることなどが決定された。2014年6月には新たに「対外経済省」が発足し、外資誘致に乗り出している。また、金正恩国防委員会第一委員長は朝鮮人民軍を動員して馬息嶺(マシンニョン)スキー場を始めとする大規模な建設プロジェクトを推進している。
2013年の経済成長率は、1.1%(韓国銀行推計値)であり、資金やエネルギーの不足、生産設備の老朽化、技術水準の後れなどの構造的な問題が依然として産業全体に存在しているものと見られる。穀物生産量は増加傾向とされるものの、依然として低い水準にとどまっていると考えられ、食糧事情についても、厳しい状況が続いていると見られる。
北朝鮮は、中国との経済関係を引き続き拡大させており、経済的に中国に依存する傾向が顕著になっている。2013年の北朝鮮の対中貿易額は、総額で約65.4億米ドルに上り(大韓貿易投資振興公社推計値)、北朝鮮の対外貿易の約75%近くを占めている。
イ 安全保障上の問題
(ア)近年の経緯
日本を含む国際社会が強く自制を求めたにもかかわらず、北朝鮮は2012年4月と12月の2度にわたって「人工衛星」と称するミサイル発射を強行し、2013年2月には3回目の核実験を実施するなど((イ)参照)、依然として核・ミサイル開発を継続している。また、北朝鮮は、定例の米韓合同軍事演習に反発し、挑発的な言動を繰り返している。2014年3月には、北方限界線(NLL)北方海域にて海上射撃訓練を実施した。一部の砲弾がNLL以南の韓国側海上に落下し、韓国側も対応射撃を行った。
(イ)核・ミサイル開発の現状
2014年に入り、北朝鮮は3月に新たな核実験の可能性を示唆する声明(1)を発表するなど、繰り返し核実験実施の可能性を表明した。また、北朝鮮は3月、6月、7月に累次にわたり弾道ミサイルを発射し、3月と7月には国連安全保障理事会(国連安保理)がこれらのミサイル発射を累次の国連安保理決議違反として非難する旨の安保理議長によるプレス向け発言が行われた。
北朝鮮の核・ミサイル開発の継続は、地域のみならず国際社会全体にとっての重大な脅威である。日本は、引き続き、米国、韓国、中国、ロシアを始めとする関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、いかなる挑発行為も行わず、六者会合共同声明や累次の国連安保理決議に従って非核化などに向けた具体的行動をとるよう強く求め続けていく。
ウ 日朝関係
(ア)日朝協議
2014年には、3月に開かれた2度の日朝赤十字会談の機会を利用して、日朝政府間で課長級の意見交換が行われ、政府間協議の再開を調整することで一致した。その後、3月30日と31日に、約1年4か月ぶりとなる日朝政府間協議が開催され、双方が関心を有する幅広い諸懸案について真摯かつ率直に議論し、協議を継続することで一致した。
5月26日から28日には、ストックホルム(スウェーデン)において日朝政府間協議が開催され、3月の議論を踏まえつつ、双方が関心を有する幅広い諸懸案について、集中的に、真剣かつ率直な議論を行った。この協議の結果、北朝鮮側は拉致被害者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を約束し、日本側は北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始する時点で、日本独自の対北朝鮮措置の一部を解除することとした。また、日本側からは、北朝鮮による核・ミサイル開発や地域・朝鮮半島の緊張を高めるような挑発行動について、北朝鮮の自制を求め、日朝平壌宣言や関連国連安保理決議、六者会合共同声明などを遵守するよう求めた。
その後、7月1日の日朝政府間協議(於:北京(中国))において、北朝鮮側から、特別調査委員会の組織・構成・責任者などに関する説明があり、日本側からは、この委員会に、全ての機関を対象とした調査を行うことのできる権限が適切に付与されているかという観点から、集中的に質疑などを行った。また、ミサイル問題につき、北朝鮮が国際社会の要求に真剣に対応するよう強く要請した。7月4日には、北朝鮮は拉致被害者を含む全ての日本人に関する調査の開始を発表し、日本は独自の対北朝鮮措置の一部を解除した(2)。
9月29日には、北朝鮮側から調査の現状について説明を受けるため、日朝外交当局間会合(於:瀋陽(中国))を開催した。北朝鮮側から、5月の日朝政府間協議における合意事項の履行や特別調査委員会による調査について説明があり、質疑などを行った。日本側から、北朝鮮側が調査を迅速に行い、その結果を速やかに通報することを強く求めた。核・ミサイル問題についても、日本側の強い懸念を伝えた。
10月28日から29日には、拉致問題が最重要課題であるとの日本政府の立場を直接、調査委員会の責任者に明確に伝え、特別調査委員会から調査の現状について直接説明を受けるため、日本政府担当者を平壌に派遣した。特別調査委員会との協議では、北朝鮮から、過去の調査結果にこだわることなく、新しい角度から調査を深めていくなどの説明があり、日本側から、拉致問題が最重要課題であることを繰り返し強調するとともに、迅速な調査と速やかな回答を強く求めた。
(イ)拉致問題に関する取組
現在、日本政府が認定している日本人拉致事案は、12件17人であり、そのうち12人がいまだ帰国していない。北朝鮮は、12人のうち、8人は死亡し、4人は入境を確認できないと主張しているが、そのような主張について納得のいく説明がなされていない以上、日本としては、安否不明の拉致被害者は全て生存しているとの前提で、問題解決に向けて取り組んでいる。北朝鮮による拉致は、日本の主権や国民の生命と安全に関わる重大な問題であると同時に、基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的問題である。日本としては、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの基本認識の下、その解決を最重要の外交課題の1つと位置付け、全ての拉致被害者の安全の確保と即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引渡しを北朝鮮側に対し強く要求している(日朝協議については(ア)参照。)。
(ウ)拉致問題等の解決に向けた国際社会との連携強化
日本は、首脳・外相会談、国際会議などの外交上のあらゆる機会を捉え、拉致問題を含む北朝鮮問題を提起し、諸外国からの理解と協力を得ている。
米国との間では、2014年4月のオバマ米国大統領訪日時の首脳会談において、北朝鮮の核問題について日米韓で引き続き緊密に連携していくことを確認し、拉致問題に関してオバマ米国大統領から日本への支持が表明された。
また、日米韓3か国は、3月にハーグにおいて首脳会談を、8月にネーピードー(ミャンマー)にて外相会合を開催し、北朝鮮問題に関して3か国が一層緊密に協力していくことの重要性を確認した。
それ以外の国についても、5月の日英首脳会談、7月の日豪首脳会談の機会に発出された共同声明などにおいて、北朝鮮に対して拉致問題を含む人道上の懸念への速やかな対応を求めることを確認している。
さらに、6月のブリュッセル(ベルギー)でのG7首脳会合では、北朝鮮の核・ミサイル開発の継続を強く非難し、北朝鮮に拉致を含む人権侵害への対処を促す首脳宣言が発出されたほか、10月に開催されたアジア欧州会合では、議長声明に初めて拉致問題が明記され、11月に開催された東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN+3首脳会議の議長声明にも拉致問題が明記された。国連の場では、2月に、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(COI)(3)が、北朝鮮における深刻な人権侵害を、拉致問題を含む複数の分野にわたり包括的に詳述した最終報告書を公表し(4)、3月の人権理事会では、日本とEUが提出した、この報告書の内容を反映したこれまで以上に強い内容の北朝鮮人権状況決議が採択された(同決議の採択は7年連続7回目)。続く12月には、国連総会本会議で北朝鮮人権状況決議が、過去最多となる62か国の共同提案国を得た上で、賛成多数で採択された(決議の採択は10年連続10回目)(5)。これを受け、12月22日(ニューヨーク時間)、国連安保理において、「北朝鮮の状況」が初めて議題として採択され、人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論された。
日本は、関係国と緊密に連携・協力しつつ、国連安保理決議に基づく対北朝鮮措置(6)を引き続き実施しており、北朝鮮に対して関連する安保理決議の全面的な履行を求めていく(国連における取組については第3章第1節8.ア「国連における取組」参照)。
エ 各国の取組
米国と北朝鮮との関係については、北朝鮮は、定例の米韓合同軍事演習に反発しており、8月に行われたウルチ・フリーダム・ガーディアン(7)の際も外務省スポークスマン談話(8月18日付)を通じ、「核戦争演習が継続する限り、それに対処した我が方の自衛的対応も年次化、定例化するであろう」と強調した。一方で、2014年に北朝鮮は、抑留していた米国人3人を解放した。
12月には、金正恩国防委員会第一委員長の暗殺を題材にした映画を制作したソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントに対するサイバー攻撃(8)について、米国は、北朝鮮当局に責任があると結論を下す十分な情報を有していることを発表し、北朝鮮を非難した(9)。続く2015年1月、米国は対北朝鮮措置に関する大統領令を発出し、制裁対象を拡大した。
韓国の朴槿恵(パククネ)大統領は2014年3月にドレスデン(ドイツ)において、南北関係について、北朝鮮の核放棄を求めるとともに、人道支援、インフラ支援、交流拡大を柱とする構想を発表した(10)。一方の北朝鮮は、国防委員会が1月16日に「南朝鮮当局に送る重大提案」などの発表を通じて、韓国に対し、南北関係改善のため、お互いに誹謗・中傷や米韓合同軍事演習を含む軍事的敵対行為を全面中止することなどを提案した(11)。10月には、仁川(インチョン)アジア大会に選手団を派遣するとともに、黄炳瑞軍総政治局長を始め高官3人が閉幕式参加に合わせ電撃訪韓した。しかし、その後、北朝鮮は韓国民間団体による北朝鮮体制を批判するビラ散布行為などに反発し、合意していた南北対話は実施されなかった。
中国と北朝鮮との間では、金正日時代に比べ政府や党レベルの交流は減少している一方、経済面での中朝貿易は増加している。8月には中朝外相会談が行われ、双方が関心を持つ事項について協議した。
ロシアと北朝鮮の間では、政府高官などの往来が増加しており、11月には、崔龍海党政治局常務委員・書記が金正恩国防委員会第一委員長の特使としてロシアを訪問し、プーチン大統領に同委員長の親書を渡した。経済面では2014年の貿易額が約9,234万米ドルと、前年比で11.4%減少した。
オ その他
北朝鮮から逃れた脱北者は、滞在国当局の取締りや北朝鮮への強制送還などを逃れるため、潜伏生活を送っている。日本政府としては、こうした脱北者の保護や支援について、北朝鮮人権侵害対処法の趣旨を踏まえ、人道上の配慮、関係者の安全、脱北者の滞在国との関係などを総合的に勘案しつつ対応している。なお、日本国内に受け入れた脱北者については、関係省庁間の緊密な連携の下、定着支援のための施策を推進している。
(2)韓国
ア 韓国情勢
(ア)内政
2014年、就任2年目を迎えた朴槿恵大統領は、新年の記者会見において、「経済革新3か年計画」を発表し、国政ビジョンである「国民幸福時代」を開いていくと表明した。また、「国民幸福時代」のための必須条件として、朝鮮半島統一時代を開くための基盤を構築していくと発表した。
2014年の年初も、朴槿恵大統領は、前年に引き続き安定した支持率を維持していたが、4月に旅客船(セウォル号)沈没事故が発生し、支持率は下落した。同事故の後、朴槿恵政権は、事故対応への責任問題から内閣や青瓦台の人事改革(12)を行った。
6月と7月には、統一地方選挙と再・補欠選挙が行われた。与党セヌリ党は旅客船沈没事故による逆風で厳しい選挙戦を強いられる中、野党の新政治民主連合(13)に対し優勢を維持(14)した。
しかし、11月以降は青瓦台内部文書流出事件(15)もあり、朴槿恵大統領への支持率は再び下落した。
(イ)外交
朴槿恵大統領は、「信頼と原則」の外交を謳い、「北東アジア平和協力構想(16)」や「朝鮮半島信頼醸成プロセス(17)」に対する支持を得ることを重視している。2014年度の外交テーマは、「新しい朝鮮半島時代」を開く平和統一信頼外交であり、2014年も積極的な首脳外交を展開した(18)。
朴槿恵政権の外交は、前年に引き続き、米中重視の傾向がみられた。対米関係では、2014年4月のオバマ米国大統領訪韓時に、就任後2回目の米韓首脳会談を実施した。同会談では、米韓共同でファクトシートを発出し、北朝鮮問題に対して米韓両国がしっかり対応するとのコミットメントを共有するとともに、強固な米韓同盟をアピールした。
また、対中関係においては、2013年11月の中国国防部による「東シナ海防空識別区」の認定により、一時緊張した時期もあったが、2013年6月の朴槿恵大統領の中国訪問以降、6回の首脳会談を行っており、総じて良好な関係を維持している。2014年7月には習近平(しゅうきんぺい)主席が韓国を国賓として訪問し、中韓共同声明を発出した。また、11月のAPECの際の中韓首脳会談では、中韓FTAの実質的な妥結を宣言するなど、経済面においても関係を強化している。
(ウ)経済
2014年、韓国の実質GDP成長率は3.3%を記録し、前年の3.0%よりも上昇した。総輸出額は、前年比2.3%増の約5,727億米ドルであり、総輸入額は、前年比1.9%増の約5,256億米ドルとなったため、貿易黒字は約472億米ドルとなった。
国内的な経済政策としては、朴槿恵大統領は、新年の記者会見において「経済革新3か年計画」を発表し、潜在成長率の4%台への引き上げ、雇用率70%の達成、一人当たりの年間国民所得の3万米ドル超の達成を目標に掲げた。通商分野では、引き続きFTAを積極的に推進しており、9月にカナダとの間でFTA締結に正式署名し、11月にはニュージーランド、中国、12月にはベトナムとの間でFTA締結交渉の実質的妥結を発表した(19)。
イ 日韓関係
(ア)二国間関係一般
韓国は、日本にとって最も重要な隣国であり、良好な日韓関係はアジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠である。両国は、日韓国交正常化50周年である2015年に向けた協力の重要性を確認しつつ、北朝鮮問題を始め、平和構築、核軍縮や不拡散、貧困などの地域や地球規模の様々な課題について連携して協力してきた。日韓間には、困難な問題も存在するが、大局的な観点から、未来志向で重層的な関係を、双方の努力により構築していくことが重要である。
2014年3月25日、核セキュリティ・サミット(於:ハーグ(オランダ))の際に、安倍総理大臣と朴槿恵大統領との初の直接の会談となった日米韓首脳会談が行われ、北朝鮮問題を中心とする東アジアの安全保障について、日米韓の3か国が一層緊密に連携していくことの重要性が確認された。
また、8月9日、ASEAN関連外相会合(於:ネーピードー(ミャンマー))の際の日韓外相会談において、岸田外務大臣と尹炳世(ユンビョンセ)外交部長官は、日韓関係の前進に向け前向きな意見交換を行い、引き続き様々なレベルで緊密に意思疎通を図っていくことで一致した。さらに、9月26日の国連総会(於:ニューヨーク(米国))の機会にも日韓外相会談を行い、日韓間の高い政治レベルの意思疎通を継続し、深化させる重要性を再確認するとともに、2015年の日韓国交正常化50周年を良い雰囲気で迎えるべく互いに努力していくことを改めて確認した。
この他にも、10月1日には第13回日韓次官戦略対話を東京で開催したほか、日韓間の諸課題を幅広く議論する日韓局長協議を数回にわたり開催するなど、日韓関係の前進に向け、様々なレベルで積極的に意思疎通を積み重ねてきている。

(イ)交流
日韓両国民の相互理解と交流の流れは着実に深化し、拡大してきている。近年、日韓両政府が両国民の交流環境の整備のための施策を講じていることもあって(20)、国交正常化当時には年間約1万人であった両国間の人の往来は、2014年には約504万人に達した(21)。日本では「K-POP」や韓国ドラマなどが世代を問わず幅広く受け入れられ、また、韓国において日本の漫画・アニメや小説を始めとする日本文化が人気を集めている。
日韓両国で毎年開催されている文化交流事業「日韓交流おまつり」は、2014年に第10回を迎えた(22)。ソウルでは9月14日に「おまつり10年、夢のせて」をテーマに、東京では9月27日、28日に「心がひとつになる二日間」をテーマに開催され、それぞれ約5万人、約6万人が参加するなど前年以上の盛況ぶりとなった。
また、アジア・大洋州諸国・地域との青少年交流事業である「JENESYS2.0」では、2013年3月末から、4,400人規模で日韓の青少年交流を実施している。
2015年は日韓国交正常化50周年であり、これを契機に、青少年・世代別交流や文化・スポーツ交流などの実施を始めとして、日韓間の交流の更なる深化・拡大に向けた取組を推進していく。
(ウ)竹島問題
日韓間には竹島の領有権をめぐる問題があるが、竹島は歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本固有の領土であるという日本の立場は一貫している。日本は、竹島問題に関し、様々な媒体で日本の立場を対外的に周知するとともに(23)、韓国国会議員などの竹島上陸、韓国による竹島やその周辺での軍事訓練や建造物の構築などについては、韓国に対して累次にわたり抗議を行ってきている。日本は、竹島問題に関し、国際法に則り、平和的に紛争を解決するため、今後も粘り強い外交努力を行っていく方針である。
(エ)その他の問題
慰安婦問題について、日本は誠意をもって取り組んできた。この問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は法的に解決済み(24)であるが、元慰安婦の方々の現実的な救済を図るとの観点から、国民と政府が協力して「アジア女性基金」を設立し、医療・福祉支援事業、「償い金」の支給などを行うとともに、歴代総理大臣から、元慰安婦の方々に対し「おわびと反省の気持ち」を伝える手紙を送ってきた。しかし、韓国は、この問題は解決していないとして、日本による更なる対処を求め続けている。日本としては、この問題を政治問題、外交問題化させるべきではないと考えており、引き続き日本の立場やこれまでの真摯な取組に理解が得られるよう、最大限努力していく。
朝鮮半島出身の「旧民間人徴用工」をめぐる裁判(25)については、日韓間の財産・請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済み(26)であり、今後とも適切に対応していく。
韓国検察当局による産経新聞前ソウル支局長の起訴は、報道・表現の自由及び日韓関係の観点から極めて遺憾であり、韓国政府に対し、引き続き適切な対応を求めていく。
そのほか、朝鮮半島出身者の遺骨問題(27)、在サハリン「韓国人」支援(28)、在韓被爆者問題への対応(29)、在韓ハンセン病療養所入所者への対応(30)など、多岐にわたる分野で、人道的観点から、日本は可能な限りの支援を進めてきている。
また、排他的経済水域(EEZ)境界画定交渉などについては、日韓間で協議を重ねてきている。
ウ 日韓経済関係
日韓の経済関係は、緊密に推移している。2014年の日韓間の貿易総額は、約8.99兆円であり、韓国にとって日本は第3位、日本にとって韓国は第3位の貿易相手国である。なお、韓国の対日貿易赤字は、前年比約4.7%減の約1.92兆円となった(財務省貿易統計)。また、日韓間の投資額は、日本からの対韓直接投資額が約24.9億米ドル(前年比7.5%減)(韓国産業通商資源部統計)で、日本は韓国への第2位の投資国であり、韓国からの対日直接投資は約4.1億米ドル(前年比40.6%減)(韓国輸出入銀行統計)であった。
このように、日韓両国は相互に重要な貿易・投資相手国であり、製造業におけるサプライチェーンの一体化の進展とともに、日韓企業の第三国への共同進出など、両国間では新たな協力関係が進んできている。
こうした緊密な日韓経済関係を一層強固にし、また日韓両国としてアジア地域の経済統合に主導的な役割を果たすためにも、日韓両国の経済連携が重要である。こうした認識の下、日本は日中韓自由貿易協定(FTA)や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)交渉などに取り組み、進展に向け努力を続けている。
また、日韓経済関係の更なる強化を図る観点から、2015年1月に行われた第13回日韓ハイレベル経済協議では、日韓の経済情勢や日韓経済関係に加え、世界経済情勢、マルチ・地域レベルの枠組みにおける協力など、広範なテーマについて意見交換を行った。
韓国政府による日本産水産物の輸入規制(31)の問題に関しては、日本は、様々な機会を捉えて、韓国側が科学的な根拠に基づいて規制を早期に撤廃するよう求めた。この関連で、2014年12月と2015年1月、韓国専門家委員会による訪日調査が行われた。
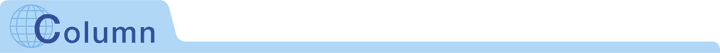
現在の日本では、頻繁に報道などで耳にする領土問題などを原因に、韓国に対してあまり良くない印象を抱いている人が多いのが現状です。事実、私もこの訪韓研修に参加する以前は心のどこかで韓国への偏見を持っていました。
しかし、実際に韓国の学校を訪れ、言語の壁がある中でも簡単な互いの母国語やジェスチャーを駆使し、現地の学生と一緒に授業を受けたりスポーツに汗を流すことで交流出来ました。特に驚いたことは、韓国の学生が親切で積極的であったことです。また、そこには世間の考えとは関係なく、一人の人として、互いの国の文化、歴史、価値観を認め合う姿がありました。
今回の訪韓を通して、私の韓国に対する印象は良い方向へと変わりました。今なお当時の友人との交流が続き、体験したことをより多くの人へ広めているところです。だからこそ、若い世代からこのような視野を広げる経験を重ねるべきだと思います。そして、そうして育った人々が、やがて地球人として本当の国際社会を築いていけると信じています。


幼い頃から日本に関心を持ち、高校で日本語を学んでいる私は、一年生の時、香港での世界の高校生の貿易企画コンテストに参加し、日本チームの高校生と出会った。私は嬉しくて自分から声をかけたが、彼らは韓国人が日本人を嫌いだと思っているようで、緊張した雰囲気だった。しかし、互いに相手国の文化を話題に話をするうちに、打ち解けて親しく交流することが出来た。その後、彼らとはメールをやり取りしており、今や日本というと真っ先に彼らのことが思い浮かぶ。
両国には、過去の歴史や外交問題のために、相手に反感を持っている人々が多い。政治と外交は、切れやすくもつれやすい細い糸のようだ。もつれた糸は、解きほぐすのも大変だ。だが、糸にはつなぎ直すことができるという長所もある。
国同士の関係も同様に、安定した関係が危うくなることもあり、その関係を解きほぐすのに多くの労力が必要だ。韓日関係の安定は、政府の努力だけでは難しいかもしれない。何よりも民間交流を拡大し、両国の国民の意識を変えていくことが大切だと思う。
1 外務省声明(2014年3月30日)。米韓合同軍事演習を非難し、「核抑止力を一層強化するための新たな形態の核実験も排除されない」とした。
2 ①人的往来の規制措置の解除(ア. 北朝鮮籍者の入国の原則禁止措置、在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止措置、日本人に対する北朝鮮への渡航自粛要請措置等を解除。イ. 北朝鮮籍者の入国については、入国申請があった場合に、個別具体的に適切に審査(安保理決議指定個人の入国は、引き続き認めない。))
②支払報告及び支払手段等の携帯輸出届出の下限金額の引下げ措置の解除(ア. 北朝鮮に住所若しくは居所を有する自然人又は主たる事務所を有する法人その他の団体に対する支払について、報告を要する金額(下限額)を現行の300万円超から3,000万円超に戻す。イ. 北朝鮮を仕向地とする支払手段などの携帯輸出について、届出を要する金額(下限額)を現行の10万円超から100万円超に戻す。)
③人道目的の北朝鮮籍船舶の入港(ア. 人道物資輸送のために北朝鮮籍船舶が我が国に入港する場合を、特定船舶入港禁止特別措置法第6条第1項に規定する入港禁止の例外となる「特別の事情」に該当する場合であると閣議決定。イ. 入港する船舶への積込みが許されるのは、北朝鮮内にある者が個人で使用する人道物資のみ(食料、医療品、衣料等)。(輸出全面禁止措置は維持。)ウ. 入港が認められる場合も、原則として、事前に認められた人道物資の積込み以外の活動(乗員の乗下船、物資の取卸し等)は認めない。貨物検査法や船舶の入港に関する関係法令及び手続は通常どおり適用される。)
なお、北朝鮮への全ての品目の輸出禁止、北朝鮮からの全ての品目の輸入禁止、日本・北朝鮮間の航空チャーター便の日本への乗り入れ禁止などは引き続き講じており、国連安保理決議に基づく様々な措置についても、関係各国と連携しながら引き続き着実に実施している。
3 拉致問題を含む北朝鮮の人権状況全般に関する人権侵害を調査するため、2013年3月の国連人権理事会における決議で設置が決定。活動期間は1年
4 同報告書は、北朝鮮による人権侵害が、「人道に対する犯罪」に該当するとし、北朝鮮に具体的な取組を勧告するとともに、国際社会や国連にもさらなる行動を求めている。拉致問題についても、その事実を記載するとともに、拉致及び拉致被害者の置かれた状況は、現在も進行中の人道に対する犯罪であると認め、北朝鮮に対し、拉致被害者に関する情報提供と被害者本人及びその子孫を帰国させるよう勧告している。
5 北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難するとともに、具体的な人権侵害に言及し、北朝鮮で「人道に対する犯罪」が行われているとのCOI報告書の内容を認識した上で、北朝鮮に対して、拉致を含む人権侵害を終わらせることを強く要求している。また、安保理がCOIの勧告を検討し、適切な行動をとるよう促しており、この中には北朝鮮の事態の国際刑事裁判所(ICC)への付託の検討及びCOIが人道に対する犯罪を構成し得るとした行為について、最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲に関する検討が含まれている。
6 2012年12月のミサイル発射を受けて採択された安保理決議第2087号に基づき、2013年2月6日から、同決議で指定された4個人・6団体に対する資産凍結などの措置を講じている。また、4月5日からは、2月の核実験を受けて採択された安保理決議第2094号に基づき、①3個人・2団体に対する資産凍結、②日本の金融機関などに対する北朝鮮の金融機関とのコルレス関係の確立などの差し控え要請、③北朝鮮金融機関の本邦における支店の設置などの不認可、本邦の金融機関の北朝鮮における支店の設置の不認可、④禁制品を積載している疑いのある航空機の離着陸・上空通過の不許可などの措置を新たに講じている。2014年7月には、国連安保理が新たに1団体を資産凍結などの措置の対象に指定したことを受け、日本も同団体に対して資産凍結などの措置を行った。
7 米韓両国軍の即応体制を向上させるための年次合同軍事演習
8 2014年11月24日、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントがサイバー攻撃を受け、各種の内部情報が流出。12月16日には、サイバー攻撃に関与したとみられる集団が、金正恩国防委員会第一委員長の暗殺を題材にした米国映画「ザ・インタビュー」を上映する映画館へのテロを予告した。
9 北朝鮮は、サイバー攻撃は、(北朝鮮の)支持者・同情者らによるものであるとしつつ、国防委員会政策局声明(2014年12月21日)を通じ「我らは彼らの住所も居場所も知らないが、彼らの正義の行動を高く評価する」と主張。
10 核問題については、北朝鮮が核放棄の決断をすれば、必要な国際金融機関への加入、国際的な投資の誘致を積極的に支援すると述べ、また、「北東アジア開発銀行」を作り、北朝鮮の経済開発と周辺地域の経済開発を図ることができるとした。4月に北朝鮮(祖国平和統一委員会)は、一方が他方を従わせる形での統一は受け入れられないなどと批判。
11 6月30日にも、国防委員会は、「南朝鮮当局に送る特別提案」を発表、誹謗中傷や軍事的敵対行為の中止を要求。
12 鄭烘原(チョンホンウォン)国務総理が旅客船沈没事故への対応の責任をとって辞任を表明したが、その後複数の公認内定者が指名を辞退し、同総理が留任することになった。また、同事故の収拾に対する責任及び「経済革新3か年計画」推進のため、国家安保室長、青瓦台秘書官(5ポスト)及び長官(8ポスト)を交代。また海洋警察庁及び消防防災庁の廃止、国家安全処、人事革新処及び教育・社会・文化副総理の新設(教育部長官が兼任)など、内閣組織の改編(17部3処18庁→17部5処16庁)が行われた。
13 安哲秀(アンチョルス)無所属議員が立ち上げた新党「新政治連合」と民主党が、2017年の次回大統領選挙での政権交代を目標に、2014年3月、統合新党「新政治民主連合」を結成。安哲秀(アンチョルス)議員と金漢吉(キムハンギル)民主党代表が共同代表に就任したが、7月の再・補欠選挙の責任を取って辞任している。
14 統一地方選では17主要自治体首長のうち、与党セヌリ党が京畿道、釜山、仁川などの8ポストを獲得、再・補欠選挙においても15選挙区のうち11議席を獲得し、国会で過半数の議席を獲得した。
15 朴槿恵大統領の国会議員時代の秘書である鄭允会(チョンユンフェ)氏が、青瓦台の人事などの国政に介入したとする青瓦台の内部報告書が報じられた事件。同報道に対し青瓦台関係者があわせて文書流出に関する捜査も指示したことから検察が捜査を開始した。
16 北東アジアにおいて多者間対話の枠組みをつくり、可能な分野から対話と協力を始め、信頼を築いていき、安全保障などの他の分野へと協力の範囲を広げていくという構想
17 堅固な安全保障をもとに南北間の信頼を築くことで、南北関係を発展させ、朝鮮半島に平和を定着させるとともに、統一基盤の構築を目指すという構想
18 2014年も1月にスイス、インド、3月にオランダ、ドイツを訪問し首脳会談を行うなど、積極的な首脳外交を展開。その後も、米国、アラブ首長国連邦(UAE)、中央アジア諸国、カナダなどを訪問し、首脳会談を行った。
19 この他に、2014年12月にオーストラリアとの間のFTAが発効している。
20 2006年から短期滞在査証免除措置の無制限延長を実施。また、2011年には、日韓ワーキング・ホリデー制度における双方の査証発給枠を年間7,200件から1万件に拡大。
21 2014年の渡航者数 訪日韓国人数:276万人(日本政府観光局(JNTO)発表)、訪韓日本人数:228万人(韓国観光公社(KTO)発表)
22 「日韓交流おまつり」は、2005年から2008年まではソウルで開催され、2009年からソウルと東京で開催されている。
23 2013年10月以降、外務省ホームページにおいて、竹島に関する動画やフライヤー、パンフレットを公開し、現在は11言語(日本語、英語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ロシア語、中国語、イタリア語)での閲覧が可能になっている。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html)
24 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条1により、日韓両国は、「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」が「完全かつ最終的に解決されたこととなること」を確認している。
25 第二次世界大戦中、日本統治下の朝鮮半島において、新日鉄住金株式会社及び三菱重工業株式会社の前身企業に「強制徴用」されたとされる韓国人が、それぞれの企業に損害賠償と未払賃金の支払を請求した件に関し、2013年7月10日に韓国ソウル高等裁判所が新日鉄住金に対して、同月30日には韓国釜山高等裁判所が三菱重工業に対して、それぞれ原告側の訴えを認め、損害賠償などの支払を命じた。この他にも、同様の訴訟が韓国で複数提起されている。
26 脚注25に同じ
27 第二次世界大戦終戦後、日本に残された朝鮮半島出身者の遺骨返還問題。韓国政府から返還要請があった遺骨について、可能なものから順次返還を進めている。
28 第二次世界大戦終戦前、様々な経緯で旧南樺太(サハリン)に渡り、終戦後、ソ連による事実上の支配の下、韓国への引揚げの機会が与えられないまま、長期間にわたり、サハリンに残留を余儀なくされた朝鮮半島出身者に対し、日本政府は、一時帰国支援、永住帰国支援、サハリン再訪問支援などを行ってきている。
29 第二次世界大戦時に広島又は長崎に在住して原爆に被爆した後、日本国外に居住している方々に対する支援の問題。これまで日本は、被爆者援護法に基づく手当や被爆者健康手帳などに関連する支援を行ってきている。
30 第二次世界大戦終戦前に日本が設置した日本国外のハンセン病療養所入所者が、「ハンセン病療養所などに対する補償金の支給などに関する法律」に基づく補償金の支払を求めていたが、2006年2月に法律が改正され、新たに国外療養所の元入所者も補償金の支給対象となった。
31 (1)福島を含む8県の水産物50種に対する輸入禁止措置を、これら8県の全ての水産物に拡大(2)8県以外の水産物について、セシウムとヨードが微量でも検出された場合には、他の放射性物質の証明書を追加で要求
