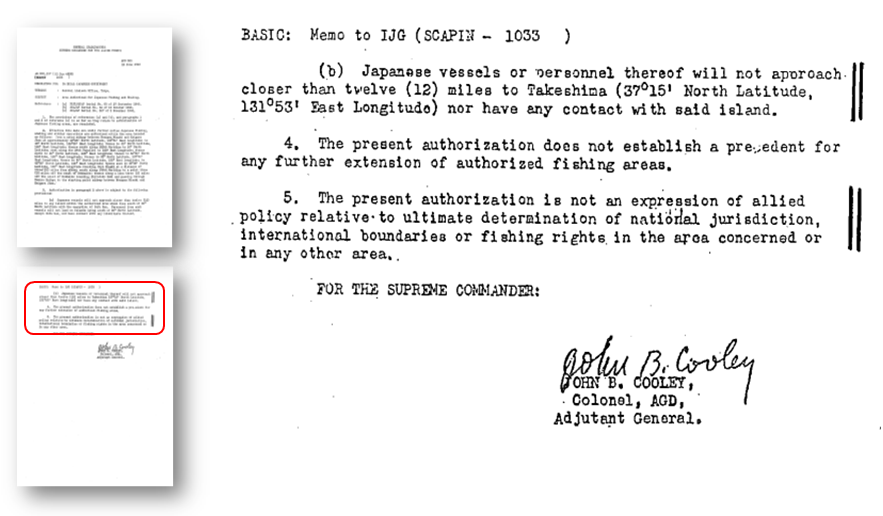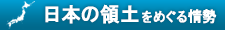日本の領土をめぐる情勢

竹島問題に関するQ&A
- Q1国際法上,ある島が自国の領土に距離的に近いことは,その島の領有権に関係があるのですか?
- Q2韓国側の古文献・古地図には竹島のことは記載されているのですか?
- Q3「安龍福」とは,どのような人物だったのですか?
- Q41905年の日本政府による竹島編入以前に,韓国側が竹島を領有していた証拠はあるのですか?
- Q5竹島は,カイロ宣言にいう「暴力と貪欲により奪取した」地域に該当するのですか?
- Q6第二次世界大戦後,竹島は,連合国総司令部によって日本の領域から除外されたのですか?
Q1国際法上,ある島が自国の領土に距離的に近いことは,その島の領有権に関係があるのですか?
- A1韓国側は,鬱陵島と竹島とが地理的に近いことを理由に「竹島は地理的に鬱陵島の一部」であると主張していますが,国際法上,地理的に距離が近いことのみを理由に領有権が認められることはありません。このことは,国際判例においても示されています。
例えば古くは1920年代に米国とオランダが争ったパルマス島事件において,「領域主権の根拠とされる近接性に基づく権原は,国際法上,根拠がない(no foundation)」と判示されました。また最近では,2007年のホンジュラスとニカラグアが争ったカリブ海における領土・海洋紛争事件の判決において,国際司法裁判所(ICJ)は,紛争当事国が主張した地理的近接性を領有権の根拠として認めませんでした。加えて,2002年のインドネシアとマレーシアが争ったリギタン島・シパダン島事件では,帰属の決まっている島から40カイリ離れている両島を付属島嶼だとする主張を退けました。
Q2韓国側の古文献・古地図には竹島のことは記載されているのですか?
- A2いいえ,韓国側は,韓国の古文献・古地図に記載されている「于山島」を,現在の竹島であると主張していますが,この主張は根拠に欠けるものです。
【韓国側が「根拠」とする古文献について】
韓国側は,朝鮮の古文献の記述をもとに,「鬱陵島」と「于山島」という2つの島を古くから認知していたのであり,その「于山島」こそ,現在の竹島であると主張しています。しかし,朝鮮の古文献で,于山島が現在の竹島であるという韓国の主張の証拠は見つかっていません。
例えば,韓国側は,『世宗実録地理誌』(1454年)や『新増東国輿地勝覧』(1531年)に于山・鬱陵の2島が(蔚珍)県の東の海にあると記されており,この于山島が竹島だと主張しています。しかし,『世宗実録地理誌』は「新羅の時代には于山国と称した。欝陵島とも云う。その地は方百里」(新羅時称于山国 一云欝陵島 地方百里),『新増東国輿地勝覧』は「一説に,于山・鬱陵は本来1つの島である。その地は方百里」(一説于山欝陵本一島 地方百里)としており,これらの文献には,「于山島」に関しては何ら具体的に記述されておらず,鬱陵島のことしか書かれていません。于山島が現在の竹島でないことを明確に示す朝鮮の古文献もあります。例えば『太宗実録』巻33の太宗17年2月条(1417年)には,「按撫使金麟雨が于山島から還り,産物である大竹…を献上し,住民3名を連れてきた,その島の人口はおよそ15戸で男女あわせて86人」(按撫使金麟雨還自于山島 獻土産大竹水牛皮生苧綿子撿撲木等物 且率居人三名以来 其島戸凡十五口男女并八十六)と記述されています。しかし,竹島には竹は生えず86人も居住できません。
韓国側は,『東国文献備考』(1770年)などに「欝陵と于山は全て于山国の領土であり,于山は日本でいう松島である」と書いてあると主張していますが,こうした18世紀以降の文献の記述は,1696年に日本に密航した安龍福という人物の信憑性のない供述に基づくものです(Q&A3参照)。また,18世紀,19世紀の書物の編者が「于山は日本のいう松島である」と記したとしても,そのことから『世宗実録地理志』(15世紀),『新増東国輿地勝覧』(16世紀)の于山が竹島であることにはなりません。
【韓国側が「根拠」(注)とする古地図について】
韓国側には,16世紀以来の朝鮮の地図に竹島が于山島として描かれているとの議論もありますが,これまでの朝鮮地図に見られる于山島は,いずれも竹島ではありません。
(注)なお,国際法上,地図は,条約の付属のものでもない限り領有権の根拠にはならないものとされていますが,たとえ条約の付図であっても,条約当事者の意図はあくまで条約の文言によって証明され,地図は補強証拠程度の意味しか持たないとされています。
例えば,『新増東国輿地勝覧』(1531年)に添付されている「八道総図」には鬱陵島と「于山島」の2島が描かれています。仮に,韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば,この島は,鬱陵島の東方に,鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。しかし,この地図における「于山島」は,朝鮮半島と鬱陵島の間に位置し,また,鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれています。したがって,この「八道総図」の于山島は,鬱陵島を2島に描いたものか,または架空の島であって,鬱陵島のはるか東方に位置する竹島ではありません。
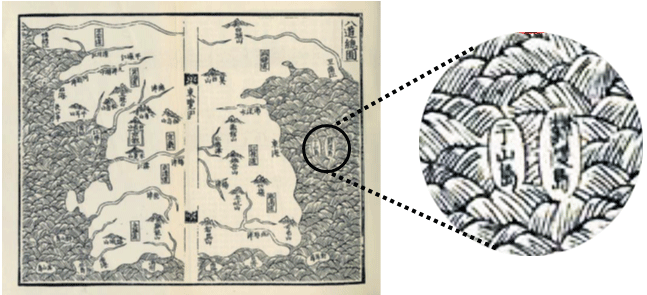
▲「新増東国輿地勝覧 八道総図」(写し)
18世紀以降の朝鮮地図では鬱陵島の東側に于山島を描くものも現れます。しかし,その于山島も現在の竹島ではありません。
例えば,1711年に行われた朴錫昌(パク・ソクチャン)による鬱陵島巡視に関連する「欝陵島図形」には鬱陵島の東側に「于山島」が描かれていますが,そこには「所謂(いわゆる)于山島 海長竹田」と記されています。この「海長竹」とは女竹(笹の一種)のことですが,岩礁島である竹島には一切そのような植物が生えないことから,この于山島は竹島ではありません。なお,鬱陵島の東約2kmに位置する竹嶼(ちくしょ)(注)には女竹が群生しています。このことから,「欝陵島図形」における「于山島」は竹嶼のことだと考えられます。
(注)竹嶼(ちくしょ):鬱陵島の東約2kmに位置する小島。
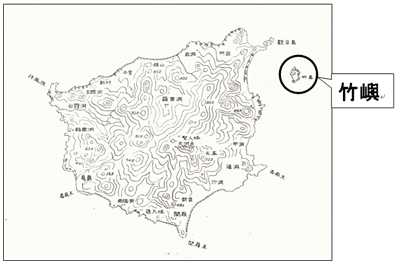
▲海軍水路部による欝陵島実測図
韓国の著名な地図作成者である金正浩(キム・ジョンホ)によるとされる「靑邱圖」(せいきゅうず)(1834年)中の「欝陵島図」にも,鬱陵島の東に「于山」と記した縦長の島が描かれています。
この地図には図の上下左右に目盛(一目盛10朝鮮里,約4km)が付いていることから,距離が分かりますが,鬱陵島と于山が約2~3kmの距離で描かれていること及び島の形状から,この于山は,明らかに鬱陵島の東約2kmに位置する竹嶼を指しています(竹島は鬱陵島から約90km離れています)。
つまり,18世紀以降の朝鮮の地図に描かれる于山は,「竹嶼(ちくしょ)」のことと考えられます
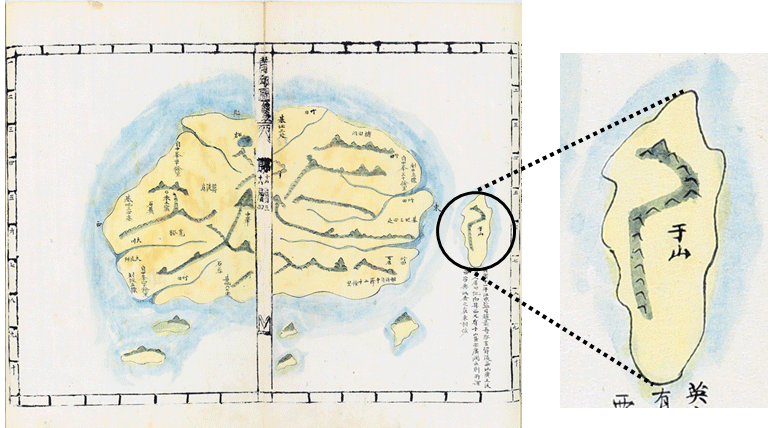
▲「靑邱圖」(1834年)の「鬱陵島図」(天理大学附属天理図書館蔵) 転載厳禁
鬱陵島の東約2kmにある竹嶼を于山とする地図は,近代になっても作成されています。大韓帝国の学部編輯局が1899年に出した「大韓全図」は,経度緯度の線が入った近代的な地図ですが,鬱陵島の直近の位置に「于山」を描いています。この于山も竹嶼であって,現在の竹島ではありません。
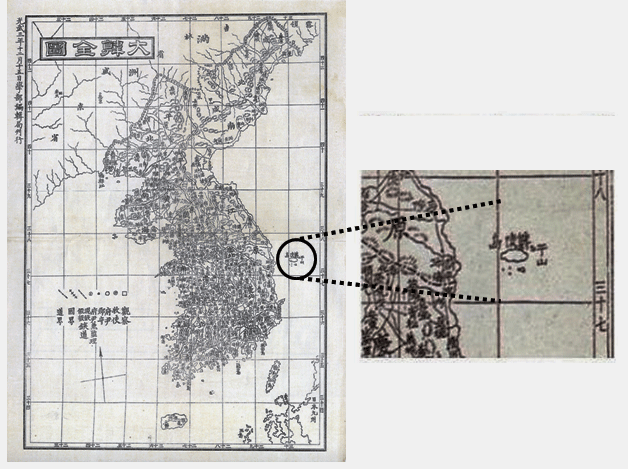
▲「大韓全図」(東洋文庫 所蔵)
Q3「安龍福」とは,どのような人物だったのですか?
- A3安龍福は,1693年に鬱陵島(当時の日本名「竹島」)へ出漁し大谷家の手代によって日本に連れ帰られ,1696年に鳥取藩に訴えごとがあるとして今度は自らの意思で日本に来た人物です。しかし,その後,安龍福は,みだりに国外に渡航したとして朝鮮で取調べを受けています。取調べの際,安龍福は,鬱陵島で日本人の越境を咎めた,日本人が松島に住んでいるというので,松島は「子山島」である,これもまた我が国の地だと言ったなどと供述しました。このため,その後の朝鮮の文献で于山島と今日の竹島を結び付ける記述が生まれました。
韓国側はこの安龍福の取調べの際の供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。
この安龍福の供述は『粛宗実録』の粛宗22年(1696年)9月戊寅条に記録されています。しかし、同文献(粛宗23年丁丑2月乙未条)からは、当時の朝鮮が安龍福の行動を関知しておらず、その行動は朝鮮を代表するものではないと認識していたことが確認できます(補足その1参照)。また、安龍福の供述そのものについても、事実と合致しない描写が数多くあり、信憑性に欠けます(補足その2参照)。
◎補足その1:安龍福は朝鮮を代表していない
『以下の点から,安龍福が朝鮮を代表していなかったことは明らかです。
- 『肅宗実録』には安龍福の渡日について,次のように記されています。
「東萊府使李世載が王に言うには,対馬の使者(注)が 『昨年貴国人が訴え出ようとしたが朝命によるものか(去秋貴国人有呈単事出於朝令耶)』と問うた,これに対し,李世載が『もし弁ずべきことがあれば訳官を江戸へ送る,何をはばかって愚昧な漁民を送ることがあろうか(若有可弁送一訳於江戸 顧何所憚而乃送狂蠢浦民耶)』と述べた。…備辺司は『…風に漂う愚民がたとえ何かしても朝家の知るところではない(…至於漂風愚民 設有所作為 亦非朝家所知)』と述べた,そのように対馬の使者に言うことが諮られ王がこれを許した(請以此言及館倭允之)」(粛宗23年丁丑二月乙未条)。 - このことは、朝鮮国禮曹参議李善博から対馬藩主宛ての書簡の中で、次のとおり日本に伝えられています。
「昨年漂着した者のことですが、海浜の人は舟を操ることを稼業とし、大風に遭えばたちまち波浪に洗われ越境して貴国に至ります(昨年漂氓事濱海之人率以舟楫為業颿風焱忽易及飄盪以至冒越重溟轉入貴国)。…もし訴え出たのなら、誠にそれは妄作の罪にあたります(…若其呈書誠有妄作之罪)。そのためすでに法に基づいて流刑に処しました(故已施幽殛之典以為懲戢之地)。」
(注)対馬藩は,江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口でした。 - なお,安龍福が乗っていた船には「朝鬱両島監税将臣安同知騎」の旗印が立てられており,また安龍福は「鬱陵于山両島監税将」と名乗ったとされますが,この官名は架空のものであり,安龍福自身が詐称であったことを認めています。安龍福が「監税」や「監税将」と称したのは、鬱陵島や于山島の徴税官ということのようです。安龍福は于山島を大きな島で人が住んでいると思い込んでいたようです。
◎補足その2:安龍福の供述の信憑性
安龍福の供述には多くの矛盾があり,信憑性に欠けます。
- 安龍福は2度,日本に渡っています。最初は1693年,鬱陵島(当時の日本名「竹島」)で漁ができなかったことの証拠として日本に連れて来られ,2度目は1696年、鳥取藩に訴えごとがあるとして密航し,鳥取藩によって追放されました。『粛宗実録』に記録されている安龍福の証言は,追放された安龍福が帰還後,備辺司での取調べに対して供述した調書の抄録です。それによると,安龍福は最初に日本に渡った際,鬱陵島及び于山島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たが、それを対馬藩に奪われたとしています。しかし,安龍福が日本に連れ帰られ,対馬藩経由で朝鮮に送還されたことを契機として鬱陵島への出漁をめぐる日本と朝鮮の交渉が始まったので,そうした交渉が始まる前の1693年の渡日時に,江戸幕府が鬱陵島と于山島を朝鮮領とする書契を与えることはありません。
- また,1696年5月に渡日した際,鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。しかし,同年1月には既に,幕府は鬱陵島への渡海を禁じる決定を行い,その指示が鳥取藩に伝えられており,大谷・村川両家に与えられていた「渡海免許」は返納されています。韓国側には,この安龍福の供述を基に,あたかも1696年の安龍福の渡日によって幕府が日本人の鬱陵島への渡海禁制を決定したかのように主張する議論もありますが,安龍福が来たのは幕府が鬱陵島への渡海を禁じた4か月後です。
- 安龍福は,帰国後の取調べで,日本人に向かって「松島は即ち子山島(于山島)である,これもまた我が国の地だ。お前はどうしてここに住むのか(松島即子山島、此亦我国地、汝敢住此耶)」と詰問したと供述しています。この年,日本人は鬱陵島に渡海していないので,この話も事実ではありません。なお,安龍福は,于山島には人が住めると思い込んでいたふしがあります。安龍福は1693年に鬱陵島で漁をしていた際,仲間から鬱陵島の東北にある島を于山島と教えられ(『竹島紀事』)、日本に連れて来られる時には、「鬱陵島よりすこぶる大きな島」を目撃したとしています(『辺例集要』)。安龍福が「松島は子山島である」としたのは,1693年に日本に連れて来られた間に知った松島(今日の竹島)の名前を朝鮮が伝統的な知識として有していた于山島に当てはめた結果であると考えられますが,「松島は子山島である」というのも名称上のことで,今日の竹島を指していたわけではありません。
Q41905年の日本政府による竹島編入以前に,韓国側が竹島を領有していた証拠はあるのですか?
- A4いいえ,韓国側からは竹島を領有していた具体的な証拠は示されていません。
例えば,韓国側は,『世宗実録地理志』(1454年),『新増東国輿地勝覧』(1531年)など朝鮮古文献に名前が出てくる「于山(島)」が竹島のことであるとし,古くから自国の領土であったとしています。
しかし,朝鮮の古文献や古地図にある于山(島)は,鬱陵島の別名であるか,18世紀以降の地図に描かれた于山(島)のように鬱陵島の脇にある別の小島(竹嶼)であって,竹島ではありません。
また,韓国側は,「大韓帝国勅令41号」(1900年)(注)によって鬱陵島に郡を設置し,「欝島郡」が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定した,この「石島」が「独島」(竹島の韓国名)を指すと主張しています。
しかし,韓国側からは「石島」が竹島であるという明確な根拠は示されていません。また,仮に勅令の石島が竹島を指すとしても,勅令の公布前後に大韓帝国が竹島を実効的に支配した事実はなく,韓国による領有権が確立していたということはできません。
(注)1882年,朝鮮政府は,鬱陵島について470年間にわたって続いていた「空島政策」を廃止して,鬱陵島を開拓することにしました。その後,1900年6月,鬱陵島に多くの日本人が居住していたことから,日本と共同調査を実施しています。大韓帝国(朝鮮は1897年10月に国号を大韓帝国と改称)は,その共同調査の報告(禹用鼎の『欝島記』)を参考に,1900年10月,「外国人が往来交易し,交際上」必要であるとして,勅令41号「欝陵島を欝島と改称し島監を郡守と改正する件」を制定しました。この,勅令の第2条において「欝島郡」の管轄区域が「欝陵全島と竹島石島」と規定されました。しかし,突然出てきたこの石島がどこであるかは特定されていません。
一方,この勅令の制定に先立って行われた上記共同調査の報告では,鬱陵島を長さ70里(※約28km),広さ40里(※約16km),周回145里(…全島長可為七十里 廣可為四十里 周廻亦可為一百四十五里)とし,議政府賛政内部大臣李乾夏による「欝陵島を欝島と改称して島監を郡守と改正に関する請議書」(1900年)では,「該島地方は縦可八十里(※約32km)で横為五十里(※約20km)」としています。これらのことから,鬱陵島から約90km離れた竹島はこの範囲外にあり,石島が竹島ではないことが明確にわかります。なお,鬱陵島近傍(数km以内)には,竹嶼と観音島という比較的大きな島がありこうした島を意図していた可能性もあります。
1里(日本)=約10里(朝鮮)=約4Km
Q5竹島は,カイロ宣言にいう「暴力と貪欲により奪取した」地域に該当するのですか?
- A5いいえ,該当しません。
韓国側は,第二次世界大戦中に米英中3国首脳が出した「カイロ宣言」(1943年)にいう「暴力と貪欲により奪取した」地域に竹島が該当すると主張しています。しかし,竹島は一度も韓国の領土であったことはなく,日本が遅くとも17世紀半ばまでには領有権を確立し,1905年の閣議決定による竹島の島根県への編入によりその領有意思を再確認した上で,その後も平穏かつ継続的に支配していました。こうしたことからも,竹島は,日本が韓国から奪取した地域ではないことは明らかです。
なお,そもそも,戦後の領土の処理は,最終的には平和条約を始めとする国際約束に基づいて行われます。第二次世界大戦の場合,同大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり,カイロ宣言は日本の領土処理について,最終的な法的効果を持ち得るものではありません。サンフランシスコ平和条約では,竹島が我が国の領土であることが肯定されています。
Q6第二次世界大戦後,竹島は,連合国総司令部によって日本の領域から除外されたのですか?
- A6いいえ,違います。連合国総司令部には領土を処分する権限はありませんでした。
韓国側は連合国総司令部覚書(SCAPIN)第677号(補足その1参照)及び同第1033号(補足その2参照)において竹島は日本の領域から除外されていると主張しています。しかし,韓国側の説明の中では触れられていませんが,韓国側が主張の根拠とするいずれの指令においても「領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」ことが明示的に規定されており,韓国側の主張は全く成り立ちません。
戦後,我が国の領土を法的に確定したのは,サンフランシスコ平和条約(1952年発効)です。したがって,同条約が発効する以前に連合国総司令部が竹島をどう扱っていたのかによって,竹島の領有権が影響を受けないことは,事実に照らしても,国際法上も明らかです。
◎補足その1:SCAPIN第677号について
1946(昭和21)年1月,連合国総司令部は,SCAPIN第677号によって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令した際,その第3項に,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」として,鬱陵島や済州島, 伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙されました。
しかし,同第6項は,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明示的に規定しています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。韓国側の説明ではこの点に全く触れていません。
◎補足その2:SCAPIN第1033号について
1946(昭和21)年6月,連合国総司令部がSCAPIN第1033号をもって日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大した際,その第3項に,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。
しかし,同第5項は,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明示的に規定しています。これに関しても韓国側の説明では全く触れていません。
「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。


 竹島の認知【韓国における竹島の認知】
竹島の認知【韓国における竹島の認知】