第4節 日本への理解と信頼の促進に向けた取組
1 戦略的な対外発信
(1)偽情報対策を含む情報戦への対応
地政学的な競争が激化する中で、偽情報などの拡散を含む情報操作などを通じた、認知領域における国際的な情報戦が恒常的に生起しており、特にウクライナやイスラエル・パレスチナ情勢などをめぐりこうした傾向が顕著に見られる。外国による情報操作は、国家及び非国家主体が、日本の政策決定に対する信頼を損なわせ、民主的プロセスや国際協力を阻害するような偽情報やナラティブ(解説)を意図的に流布するものであり、対応の重要性が高まっている。
外務省としても、そうした認識の下、国家安全保障戦略も踏まえ、情報・政策・発信部門が連携し、情報戦に対応する情報収集・分析・発信能力を着実に強化してきている。外国による情報操作への対応に当たっては、メディア、シンクタンク、NGOなどを含めた社会全体のレジリエンス(強靱(じん)性)が極めて重要であり、政府としての対応は自由な情報空間を前提としたものとなる。ALPS処理水(226ページ 第3章第1節4(3)ウ参照)をめぐっては、事実とは異なる偽情報を拡散する試みが見られたことから、問題となった偽情報を否定する報道発表を発出するなどの対応をとった。
また、情報操作への対応に対しては同様の懸念を共有する諸国が一致して対処していくべきものとの認識に基づき、12月6日には日米間で情報操作に係る協力文書に署名を行った。そのほか、G7即応メカニズム(RRM)1や二国間協議などにおいて情報操作に関する協議を行い、価値観を共有する各国・地域との協力を進めている。

(12月6日、東京)
(2)戦略的対外発信の取組
情報戦が恒常的に生起する中で、日本の政策や取組に対する理解や日本への関心を高めるための戦略的対外発信(Strategic Communication)はこれまで以上に重要になってきている。外務省では、(ア)日本の政策や取組、立場の発信及び(イ)日本の多様な魅力の発信を行うことで(ウ)日本への関心・理解・支持を拡大する、という3本柱に基づき、様々な角度から情報収集し分析を行った上で、国家安全保障戦略も踏まえながら、戦略的対外発信を実施している。
(ア)日本の政策や取組、立場の発信に関し、2023年は、ロシアによるウクライナ侵略の長期化に加え、中東で新たな危機が生じるなど、国際社会は分断と対立の様相を一層深める状況となったことを受け、外務省は様々な外交機会や取組を通じ、国際社会の平和と安定及び繁栄、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化や地球規模課題への日本の基本的考えや取組について、様々なソーシャルメディアも活用しつつ、重点的に発信した。さらに、歴史認識や領土・主権の問題への理解の促進に取り組んだ。
具体的には、総理大臣や外務大臣を始め政府関係者が、記者会見やインタビュー、寄稿、外国訪問先及び国際会議でのスピーチなどで発信し、在外公館においても、任国政府・国民及びメディアに対する発信を積極的に行っている。また、事実誤認に基づく報道が海外メディアによって行われた場合には、速やかに在外公館や本省から客観的な事実に基づく申入れや反論投稿を実施し、正確な事実関係と理解に基づく報道がなされるよう努めている。加えて、政策広報動画などの広報資料を作成し様々な形で活用している。また、日本の基本的立場や考え方への理解を得る上で、有識者やシンクタンクなどとの連携を強化していくことも重要である。こうした認識の下、外務省は海外から発信力のある有識者やメディア関係者を日本に招へいし、政府関係者などとの意見交換や各地の視察、取材支援などを実施している。さらに、日本人有識者の海外への派遣を実施しているほか、海外の研究機関などによる日本関連のセミナー開催の支援を強化している。
さらに、いわゆる慰安婦問題を始めとする歴史認識、日本の領土・主権をめぐる諸問題などについても、様々な機会・ツールを活用した戦略的な発信に努めている。また、一部で旭日(きょくじつ)旗について事実に基づかない批判が見られることから、外務省ホームページに旭日旗に関する説明資料や動画を多言語で掲載するなど、旭日旗に関する正しい情報について、国際社会の理解が得られるよう様々な形で説明している。2
これらの発信を一層効果的なものにするためには各種ソーシャルメディアや外務省HPの活用が不可欠であり、これらによる発信の強化に努めている。
(イ)日本の多様な魅力の発信に関し、海外における対日理解を促進し、日本と国民が好意的に受け入れられる国際環境を醸成するとの観点から、在外公館や独立行政法人国際交流基金を通じ、様々な文化交流・発信事業を実施している。具体的には、世界各地の在外公館や国際交流基金の海外拠点を活用した文化交流事業や日本国際漫画賞などの事業を通じ、伝統文化からポップカルチャーを含む幅広い日本文化の魅力をソーシャルメディアなども活用して積極的に発信した。またその際、国内外の関係者と協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護への取組と、日本の文化・自然遺産の「世界遺産一覧表」及び「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への記載を推進した。さらに、より深い対日理解の促進のため、国際交流基金などを通じ、人的・知的交流や日本語の普及に努め、「対日理解促進交流プログラム」などによる日本と諸外国・地域間の青年交流、世界の主要国の大学・研究機関での日本研究支援を進めている。


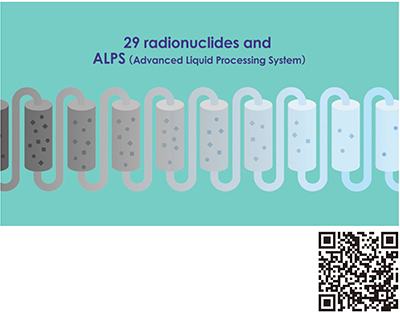
https://www.youtube.com/watch?v=hGnbpLbjw4w
これらの取組を通じ、今後も、外務省は日本への関心・理解・支持を拡大することを目指し、一層の努力を行っていく。
(3)ジャパン・ハウス
外務省は、日本の多様な魅力や様々な政策・取組・立場の発信を通じ、これまで必ずしも日本に関心がなかった人々を含む幅広い層を惹(ひ)き付け、日本への関心・理解・支持を一層拡大することを目的に、サンパウロ(ブラジル)、ロンドン(英国)及びロサンゼルス(米国)の3都市に戦略的対外発信拠点「ジャパン・ハウス」を設置している。
本活動を行うに当たっては、(ア)政府、民間企業、地方公共団体などが連携してオールジャパンで発信すること、(イ)現地のニーズを踏まえること、及び(ウ)日本に関する様々な情報がまとめて入手できるワンストップ・サービスを提供することで、効果的な発信に努めている。
ジャパン・ハウスは、「日本を知る衝撃を世界へ」を標語として、各拠点が独自に企画する「現地企画展」に加え、日本で広く公募し、専門家による選定を経て3拠点を巡回する「巡回企画展」を開催し、現地・日本双方の専門家の知見をいかした質の高い企画を実施している。また、展示のみならず、講演、セミナー、ワークショップ、ウェビナー、図書スペース、ホームページ・SNS、物販、飲食、カフェなどを活用し、伝統文化・芸術、ハイテクノロジー、自然、建築、食、デザインを含む日本の多様な魅力や様々な政策・取組・立場を発信している。現在、一部展示の他都市や近隣国での開催や、ポスト・コロナ時代に対応した対面とオンラインのハイブリッド方式での発信など、新たな訴求対象の獲得に向けても積極的に取り組んでいる。2023年末には、3拠点の累計来館者数が597万人を超え、各都市の主要文化施設として定着しつつある。
(4)諸外国における日本についての論調と海外メディアへの発信
2023年の海外メディアによる日本に関する報道については、G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催、岸田総理大臣のNATO首脳会合出席、日米韓首脳会合、日本ASEAN友好協力50周年、イスラエル・パレスチナ情勢、ウクライナ情勢、日中関係、日韓関係、北朝鮮への対応などの外交面に加え、ALPS処理水の海洋放出、防衛力強化、エネルギー政策などに関心が集まった。
外務省は、日本の政策・取組・立場について国際社会からの理解と支持を得るため、海外メディアに対して迅速かつ積極的に情報提供や取材協力を行っている。海外メディアを通じた対外発信としては、総理大臣・外務大臣へのインタビュー、外務大臣による定例の記者会見(オンラインでも日本語・英語のライブ配信を実施)、ブリーフィング、プレスリリース、プレスツアーなどを実施し、外交日程を踏まえて、時宜を得た戦略的かつ効果的な対外発信を行うよう努めている。また、看過できない事実誤認、 日本の立場とは相容(い)れない報道がなされた場合には、速やかに当該メディアへの申入れや反論投稿を行うことにより、正確な事実関係と理解に基づく報道がなされるよう努めている。
2023年はG7議長国としてG7広島サミットを主催するなど、国際社会から注目を集める年となった。総理大臣や外務大臣は寄稿・インタビューを通じて海外メディアに積極的に発信した。例えば、G7広島サミットの主催に際し、岸田総理大臣は複数の海外メディアへの寄稿を通じて、国際社会が歴史的な転換期を迎えている中、基本的価値を共有するG7は、国際社会の重要な課題に効果的に対応し、世界をリードしていかなければならないこと、また、協調の国際社会の実現に向けたG7の結束の確認と役割の強化のための積極的かつ具体的な貢献を、G7として明確に打ち出したいこと、さらに、国際社会が直面する諸課題の解決に向けたG7の断固たる決意を、広島の地から共に強く発信していきたいと訴えた。また、林外務大臣は5月にCNNによる対面インタビューに応じ、厳しさを増す安全保障環境に対する日本の姿勢の発信に努めた。このほか、10月の上川外務大臣によるブルネイ、ベトナム、ラオス及びタイ訪問時や11月の岸田総理大臣によるフィリピン及びマレーシア訪問の際には、現地メディアへの寄稿を通じて日本ASEAN友好協力50周年に伴う一層の関係・協力強化への姿勢などの発信も行った。総理大臣は、12月の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議の際にも、加盟各国現地メディアへの寄稿を実施した。
このような形で、2023年には、総理大臣の寄稿・インタビューを計34件、外務大臣の寄稿・インタビューを計36件実施し、外務報道官などによる海外メディアに対する発信、総理大臣及び外務大臣の外国訪問に際する、現地外国メディアへの記者ブリーフィングを随時実施した。海外メディアの招へい事業については、2023年は、20件の招へい案件を実施し(うち、訪日を伴う招へいは13件、オンライン形式での取材は7件)、延べ87か国から153人の記者の参加を得た。
(5)インターネットを通じた情報発信
外務省は、日本の外交政策に関する国内外の理解と支持を一層増進するため、2023年には公式インスタグラムアカウントを開設するなど、外務省ホームページや各種ソーシャルメディアなどインターネットを通じた情報発信に積極的に取り組んでいる。外務大臣の定例記者会見のライブ配信(日本語・英語)を行っているほか、G7広島サミット及び関連会合、ウクライナ情勢、ガザ情勢、ALPS処理水などに関する情報発信を迅速かつ積極的に行った。
また、外務省ホームページ(英語)を、広報文化外交の重要なツールと位置付け、領土・主権、歴史認識、安全保障などを含む日本の外交政策や国際情勢に関する日本の立場、さらには日本の多様な魅力などについて英語での情報発信の強化に努めてきている。さらに、海外の日本国大使館、総領事館及び政府代表部のホームページやソーシャルメディアを通じ、現地語での情報発信を行っている。
1 RRM:Rapid Response Mechanism
2 旭日旗に関する説明資料の外務省ホームページ掲載箇所はこちら:
(1)https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_003194.html

(2)動画リンク:https://www.youtube.com/watch?v=Oaehixu4Iuk『伝統文化としての旭日旗』(2021年10月8日からYouTube外務省チャンネルで公開)

