4 西部アフリカ地域

(1)ガーナ
西アフリカ最多の進出日本企業数を誇るガーナでは、1月、アクフォ=アド大統領が平和裏な選挙を経て就任し、財政健全化や産業化などの改革を進めている。
2017年は日・ガーナ外交関係樹立60周年、野口英世博士のガーナ来訪90周年、青年海外協力隊派遣40周年に当たり、和太鼓やファッションショーなどのイベント、外交や野口英世博士に関するシンポジウム、柔道、空手などのスポーツ大会等を通じて二国間関係が促進された。また、アジマン=メーヌ保健相が7月に訪日した際、安倍総理大臣を表敬し、日本の保健分野での貢献に謝意が表明された。

(2)ギニア
2014年から2015年までのエボラ出血熱流行による危機を乗り越えたギニアは、農業や水産業の高い潜在力と豊富な鉱物資源を軸とした経済発展を模索している。
6月、コンデ大統領(2017年AU議長)がギニア国家元首として初の二国間公式訪問を行い、安倍総理大臣との会談で、開発協力や国際場裏での協力について議論を行った。コンデ大統領は、国際協力機構(JICA)拠点の首都コナクリへの設置を始めとした日本の協力に謝意を表明し、TICADプロセスへの貢献を約束した。訪日の機会に開催された日・ギニア・ビジネスフォーラムでは、両国の官民の関係者の間で交流が行われた。

(3)コートジボワール
コートジボワールは、アフリカ開発銀行の本部のほか、西アフリカ最大のコンテナ取扱量を誇るアビジャン港を擁し、西アフリカの物流の拠点の一つとなっている。内戦が終結した2012年以降安定した経済成長を続けている。6月に2018年から2019年までの国連安保理非常任理事国に選出され、国連コートジボワール活動(UNOCI)の完全撤退が実現するなど、地域の中核国としての復権を印象付けた。一方、国軍兵士や元戦闘員による騒動が頻発するなど、内政上の課題も残る。
日本との関係では、円借款再開第1号となる「アビジャン港穀物バース建設計画」が3月に署名されたほか、11月に同国を訪問した佐藤外務副大臣がウワタラ大統領及びアモン=タノー外相を表敬し、二国間関係の強化が確認された。
(4)セネガル
西アフリカの安定勢力として経済成長を遂げているセネガルは、近年、沖合いで石油・天然ガスが発見されたこともあり、日本企業の関心が高まっている。2016年1月から2年間、日本と共に国連安保理非常任理事国を務めた。
11月、佐藤外務副大臣は「第4回アフリカの平和と安全に関するダカール国際フォーラム」出席のためセネガルを訪問し、開会式でのスピーチでアフリカの平和と安定への日本の貢献について説明した。
12月、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)フォーラム2017出席のためサル大統領が訪日し、UHC推進のモデル国の一つとしての取組を紹介した。安倍総理大臣との会談ではインフラ整備や人材育成等の協力について議論し、電力、食料安全保障、保健分野での無償資金協力に関する書簡交換が行われた。

※セネガルは2018年ワールドカップで日本と同一グループリーグ
(5)ナイジェリア
人口、経済規模共にアフリカ最大のナイジェリアは、資源国として高い潜在性を有する。一方、原油価格下落に伴う財政状況の悪化や、イスラム過激組織「ボコ・ハラム」の北東部を中心としたテロ行為や周辺諸国侵攻が問題となっている。ブハリ大統領は、産業多角化や治安改善に力を入れ、これら諸課題に取り組んでいる。
日本は5月に武井外務大臣政務官を団長とした貿易・投資促進官民合同ミッションを派遣し、複数の関係閣僚等と意見交換を行った。
(6)ブルキナファソ
農業を経済の中心とする内陸国のブルキナファソは、2014年の政変以降、内政が流動化していたが、2015年のカボレ大統領の就任以降、政治情勢は比較的安定している。一方、隣国マリの情勢悪化の影響を受けて同国からのイスラム過激派の流入が問題となっており、8月、首都ワガドゥグで市内レストランへの襲撃事件が発生した。
9月の第72回国連総会の機会に河野外務大臣とバリー外相との間で会談が行われ、二国間関係や国際場裏での協力が確認された。なお、ブルキナファソは、台湾と外交関係を有するアフリカ2か国のうちの一つである。

(7)ベナン
ベナンは、1990年代以降、大統領の交代が平和裏に行われており、西アフリカの民主主義の模範ともいわれる。実業家出身で汚職対策を政権の最重要課題とするタロン大統領は、2016年就任以降安定した政権運営を行っている。
7月にはワダニ経済・財務相が訪日し、麻生副首相兼財務大臣及び松村経済産業副大臣と会談した。8月のTICAD閣僚会合に出席したアベノンシ外務・協力相は河野外務大臣と会談し、経済協力や国際場裏での協力について議論した。

(8)マリ
独立以降、北部のトゥアレグ族勢力との対立に直面してきたマリでは、2015年にマリ政府と北部武装勢力との間で結ばれた和平・和解合意の実施が引き続き課題となっている。また、北部からのイスラム過激派の流入と中部以南及び周辺国へのテロの拡散が深刻な問題となっており、これに対応するため、2月にはマリを含むサヘル地域諸国による合同部隊の設立が決定された。
日本はマリの平和と安定を支援するため、マリの警察及び司法当局に対して治安維持機材を供与しているほか、国連機関と連携し、マリ平和維持学校の支援も実施している。
(9)リベリア
19世紀初頭より米国の解放奴隷の移住地として発展し、アフリカ最初の共和国として独立したリベリアは、2003年まで約14年間に及んだ内戦を克服し、アフリカにおける平和の定着のモデルケースともいわれる。サーリーフ前大統領は2011年にノーベル平和賞を受賞したアフリカ初の民選女性大統領である。12月、同大統領の後任を決める大統領選挙決選投票が平穏に行われ、元プロサッカー選手のウェア候補が当選した。
日本は同選挙に際し、国連開発計画(UNDP)を通じた治安維持体制の強化を支援するとともに、選挙監視員の派遣を行った。
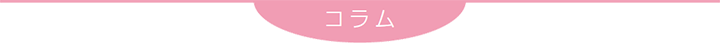
スーダンはアフリカ大陸では3番目、世界では16番目に広大な国でアフリカとアラブ地域の間に挟まれ、アジア、ヨーロッパ、湾岸地域、アフリカの玄関と呼ばれる紅海に面する戦略的に重要な国です。
世界最大の人道危機に直面したスーダン西部のダルフール、2011年の南スーダン独立に伴い現在でも続いている難民と受入先のコミュニティーの紛争予防が課題となっている南部、エリトリア、エチオピアからの移民の多い東部、そして気候変動の影響で砂漠化が続き、水の確保と紛争予防が課題になっている北部。スーダンはこうした「人道、開発、平和構築の連携」の課題を背負った国であり、私が最近まで勤務していたUNDP本部内でも最も注目されている国の一つです。
2017年6月国連安保理ではダルフール国連・AU合同ミッション(UNAMID:African Union- United Nations Mission in Darfur)の軍事と警察の30%の削減案が採択され、軍事人員は約1万1,000人、警察は3,000人弱に抑えられました。現地の治安と人権保護の状況を考慮した後、更なる削減が2018年に計画されていますが、平和構築に向けた法の整備、人権状況を踏まえた開発の必要性など問題はまだまだ残っています。UNDPのダルフール事務所のスタッフは国連ボランティア(UNV)を含め約80人(首都ハルツームにある国連事務所は約200人)。UNミッションと開発機関であるUNDPとの切れ目のない連携を実現させるためにも、UNDPのフィールドプレゼンスを強化する資金と支援を増加させることが現在の深刻な課題です。

スーダンでは数多くの日本人が国連で活躍しています。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の代表、国連人間居住計画(UN-HABITAT)の副代表も日本人です。UNDPスーダンでは私を含め4人の邦人職員が在籍しています。ダルフールでは天野裕美さんと備瀬千尋さんが、日本政府が支援する「青年ボランティア・ダルフール平和復興支援プロジェクト」で、紛争予防と復興支援に従事しています。これまで合計380人のスーダン人青年ボランティアと共に中小ビジネス企画の発案支援、マイクロファイナンス機関への橋渡しなどを通じ、環境の考慮も踏まえた貧困削減に向けてフィールドを毎日駆け回っています。開発と平和構築に役に立ちたいと夢を見る地元の若者と直接触れ合い、笑いや辛さを分かち合い、彼女たち自身が町と村の人々と一緒に汗を流し、コミュニティー間の協力体制を育んでいます。地元の人々との信頼関係を一生懸命、時には我慢強く育む姿勢は、まさしく日本の「顔」といえます。

ボランティアの活躍激励のスピーチ(筆者)
芹沢智一さんは、人道・開発・平和構築の連携支援の最先端で活躍しています。南部国境線近くの難民キャンプに自ら足を運び、難民そして受入先の村人が何を長期的に必要としているかに注意深く耳を傾け、同じ目線で理解する。現地の人たちは日本・UNDP協同の支援に感謝しており、こうした支援が更に他のコミュニティーまで拡充できるよう願っています。また、芹沢さんは過激主義の移動経路の調査に取り組んでいます。イラクやシリアでの「イラクとシリアのイスラム国」(ISIS)の軍事的敗北によりスーダン人ISISメンバーがスーダンに帰国しており、その対応を誤れば社会を不安定化させる危険性が増すと指摘されています。UNDPはテロ法の見直し、若者を主に対象とした雇用機会の増強やアドボカシー(政策提言)などを含めた技術支援を増強していく予定です。
スーダンから、人道・開発・平和構築の連携の成功例を日本の御支援と共に世界に発信していきたいと思います。

