第4節 日本への理解と信頼の促進に向けた取組
1 戦略的な対外発信
(1)戦略的対外発信の取組
自由で開かれた安定的な国際秩序が重大な挑戦に晒(さら)され、また、日本が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面していることを踏まえ、日本の外交政策・国際情勢認識の対外発信は一層重要性を増している。外務省では、対外発信の最前線である在外公館の体制強化を図りつつ、(1)日本の政策や取組、立場の発信に一層力を入れ、(2)日本の多様な魅力の発信及び(3)親日派・知日派の育成を推進するという3本柱に基づいて戦略的に対外発信を実施している。日本の政策や取組、立場の発信については、主に国際社会の平和と安定及び繁栄や法の支配に基づく国際秩序の維持・強化に対する日本の貢献への理解、歴史認識や領土・主権の問題に対する理解の促進などを念頭に取り組んでいる。具体的には、まず、総理大臣や外務大臣を始め政府関係者が、記者会見やインタビュー、寄稿、外国訪問先及び国際会議でのスピーチなどで積極的に日本の立場や考え方について発信に努めている。また、在外公館においても、歴史認識や領土・主権を始め幅広い分野で、日本の立場や考え方について各国政府・国民及びメディアに対する発信に努めている。また、事実誤認に基づく報道が海外メディアによって行われた場合には、速やかに在外公館や本省から客観的な事実に基づく申入れや反論投稿を実施し、正確な事実関係と理解に基づく報道がなされるよう努めている。加えて、政策広報動画などの広報資料を作成し様々な形で活用しているほか、外務省ホームページやソーシャルメディアを通じたオンラインでの情報発信にも積極的に取り組んでいる。また、日本の基本的立場や考え方への理解を得る上で、有識者やシンクタンクなどとの連携を強化していくことも重要である。こうした認識の下、外務省は海外から発信力のある有識者やメディア関係者を日本に招へいし、政府関係者などとの意見交換や各地の視察、取材支援などを実施している。さらに、日本人有識者の海外への派遣を実施しているほか、海外の研究機関などによる日本関連のセミナー開催の支援を強化している。
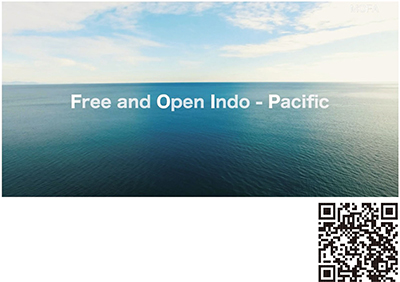
2022年は、ロシアによるウクライナ侵略によって国際秩序が大きな挑戦を受ける一方、気候変動を始めとする地球規模課題への対応として国際社会の協力が強く求められる複雑な状況となった。そうした中、外務省は様々な外交機会や取組を通じ、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化や地球規模課題への日本の基本的考えや取組について重点的に発信した。また、偽情報などの拡散を含め、認知領域における情報戦に対応するため情報部門と広報・政策部門の連携を行うなど、体制の強化を図った。12月に閣議決定された国家安全保障戦略においても偽情報などへの対応の重要性が強調された。
そのほか、海外の研究機関などとの連携事業や招へい・派遣事業を中心に、オンライン形式のセミナー(ウェビナー)や交流事業など、人の往来を伴わずに実施可能な取組を継続した。また国際的な人の往来を伴う事業が再開される中で、対面とオンライン双方の形式を活用し事業を実施した。
さらに、いわゆる慰安婦問題を始めとする歴史認識、日本の領土・主権をめぐる諸問題などについても、様々な機会・ツールを活用した戦略的な発信に努めている。また、一部で旭日(きょくじつ)旗について事実に基づかない批判が見られることから、外務省ホームページに旭日旗に関する説明資料や動画を多言語で掲載するなど、旭日旗に関する正しい情報について、国際社会の理解が得られるよう様々な形で説明している1。
日本の多様な魅力の発信については、対日理解を促進し親日感を醸成するという観点から、また、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)収束後の訪日観光促進にもつなげるため、在外公館を中心に様々な広報文化事業を実施している。世界各地の在外公館や国際交流基金による文化事業及び第15回日本国際漫画賞を実施し、日本各地の魅力をソーシャルメディアなども通じて積極的に発信した。国際的な人の往来を伴う事業が徐々に再開される中、世界各地の状況に合わせて、文化を通じた日本と世界のつながりを維持し、更に発展させていくため、対面とオンライン双方の形式を活用して事業を実施した。また、国内外の関係者と協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護への取組と、日本の文化・自然遺産の「世界遺産一覧表」及び「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への記載を推進した。親日派・知日派の育成については、人的・知的交流や日本語の普及に努め、「対日理解促進交流プログラム」を通じた日本と諸外国・地域間の青年交流、世界の主要国の大学・研究機関での日本研究支援を進めている。外交政策や国益の実現に資するため、前述の3本の柱に基づく取組を引き続き戦略的かつ効果的に実施していく。
(2)ジャパン・ハウス
外務省は、日本の多様な魅力や政策・取組・立場の発信を通じ、これまで必ずしも日本に関心がなかった人々を含む幅広い層をひき付け、親日派・知日派の裾野を一層拡大することを目的に、サンパウロ(ブラジル)、ロンドン(英国)及びロサンゼルス(米国)の3都市に戦略的対外発信拠点「ジャパン・ハウス」を設置している。
本活動を行うに当たっては、(1)政府、民間企業、地方公共団体などが連携してオールジャパンで発信すること、(2)現地のニーズを踏まえること及び(3)日本に関する様々な情報がまとめて入手できるワンストップ・サービスを提供することで、効果的な発信に努めている。
ジャパン・ハウスは、「日本を知る衝撃を世界へ」を標語として、各拠点が独自に企画する「現地企画展」に加え、日本で広く公募し、専門家による選定を経て3拠点を巡回する「巡回企画展」を開催し、現地・日本双方の専門家の知見をいかした質の高い企画を実施している。また、展示のみならず、講演、セミナー、ワークショップ、ウェビナー、図書スペース、ホームページ・SNS、物販、飲食、カフェなどを活用し、伝統文化・芸術、ハイテクノロジー、自然、建築、食、デザインを含む日本の多様な魅力や政策・取組・立場を発信している。現在、一部展示の他都市や近隣国での開催も進めているほか、新型コロナの感染拡大以降は、オンライン発信を一層強化し、対面とオンラインを駆使したハイブリッド方式での発信も展開するなど、新たな訴求対象の獲得にも積極的に取り組んでいる。2022年末には、3拠点の累計来館者数が470万人を超え、各都市の主要文化施設として定着しつつある。
(3)諸外国における日本についての論調と海外メディアへの発信
2022年の海外メディアによる日本に関する報道については、ウクライナ情勢への対応、バイデン大統領の訪日及び日米豪印首脳会合、第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)、日中関係、日韓関係、北朝鮮への対応などの外交面に加え、故安倍晋三国葬儀、新型コロナに係る水際対策、防衛力強化、エネルギー政策、為替変動などに関心が集まった。
外務省は、日本の政策・取組・立場について国際社会からの理解と支持を得るため、海外メディアに対して迅速かつ積極的に情報提供や取材協力を行っている。海外メディアを通じた対外発信としては、総理大臣・外務大臣へのインタビュー、外務大臣による定例の記者会見(オンラインでも日本語・英語のライブ配信を実施)、ブリーフィング、プレスリリース、プレスツアーなどによる在京特派員への取材機会・情報提供を行っており、外交日程を踏まえて、時宜を得た発信を行うことにより、戦略的かつ効果的な対外発信となるよう努めている。
2022年は対面外交の再開に伴い、岸田総理大臣や林外務大臣は積極的に外国を訪問し、寄稿・インタビューを通じて海外メディアに発信した。例えば、8月のTICAD 8の開催に際しては、岸田総理大臣及び林外務大臣は開催国であるチュニジアの主要メディアを始めとする複数紙に寄稿し、今後もアフリカ自らが主導する持続可能な開発のために貢献していくと発信した。また、10月には岸田総理大臣がフィナンシャル・タイムズ紙のインタビューに応じ、防衛力強化の必要性を訴えるなど、外遊などの機会以外にも適時をとらえ積極的な発信に努めた。
このような形で、2022年には、総理大臣の寄稿・インタビューを計15件、外務大臣の寄稿・インタビューを計17件実施し、外務報道官などによる海外メディアに対する発信、総理大臣及び外務大臣の外国訪問に際する、現地外国メディアへの記者ブリーフィングを随時実施した。海外メディアの招へい事業については、水際措置の状況に応じて、訪日を伴う招へい及びオンライン形式での取材を並行して実施した。2022年は、26件の招へい案件を実施し(うち、訪日を伴う招へいは6件、オンライン形式での取材は20件)、延べ137か国から231人以上の記者の参加を得た。
(4)インターネットを通じた情報発信
インターネット上のメディアが活発に利用されるようになってきていることも踏まえ、外務省は、日本の外交政策に関する国内外の理解と支持を一層増進するため、外務省ホームページやソーシャルメディアなどインターネットを通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。2022年は、ウクライナ情勢に関する情報発信のほか、外務大臣の定例記者会見のライブ配信(日本語・英語)、国際会議におけるビデオメッセージの掲載など、オンラインでの情報発信を積極的に行った。
また、外務省ホームページ(英語)を、広報文化外交の重要なツールと位置付け、領土・主権、歴史認識、安全保障などを含む日本の外交政策や国際情勢に関する日本の立場、さらには日本の多様な魅力などについて英語での情報発信の強化に努めてしている。さらに、海外の日本国大使館、総領事館及び政府代表部のホームページやソーシャルメディアを通じ、現地語での情報発信を行っている(301ページ コラム参照)。
外交活動におけるソフト・パワーについて、ソーシャルメディアの活用が効果的であるといわれて久しく、外務省でもインターネット上で文化、スポーツ、観光などの情報発信に積極的に取り組んでいます。
私がソーシャルメディアの世界に足を踏み入れたのは、2015年に駐イラク日本大使として首都バグダッドに赴任した時に、当時の治安状況などの止(や)むを得ぬ事情によりフェイスブックのアカウントを開設したことがきっかけでした。その経験を踏まえて、2021年2月にサウジアラビアに赴任した時には、サウジアラビアではツイッターのユーザーが多いことから、首都リヤドに着いた翌日にツイッターのアカウントを開設して「呟(つぶや)き」始め、これまでにおよそ9万7,000人(注)のフォロワーを集めるに至りました。
日本とサウジアラビアの二国間関係は、サウジアラビアからの石油輸入に対して日本の自動車などの製品輸出といった経済分野での結び付きが深く、昨今の世界的な日本アニメ・マンガ人気の中で日本ファンも多いのですが、そのほかの日本の文化や社会についてはあまり知られていないのが実情です。したがって、私のツイートでは、大使としての外交活動に加えて、日本の気候や文化、時に自分の家族のことなどを交えて、様々なテーマで「呟く」ことにしています。
そして、私がツイートする時に心がけていることは、現地語であるアラビア語で発信すること、発信後に寄せられるコメントを一つ一つ読み、必要な時には返信し、フォロワーと理解し合うことです。外交官は、ともすれば特別な存在と思われがちですが、こうした交流を通して彼らと共にあることを目指しているのです。コメントの中で、私のツイートで日本のことを知った、日本に親しみを覚えるようになったというメッセージや、ひいては日本に行ってみたいと言ってくれる方もあり、サウジの人々の日本への親近感が高まっていることを実感しています。
また、丹念にコメントを読む中で、サウジアラビアの人々の関心の在りどころや価値観に触れることは、赴任国の社会を知る上で重要でもあります。家族関係やサッカーのツイートには多くの温かいコメントをいただくことから、サウジアラビアの人々が家族を大切にしていてサッカーが好きということがよく分かります。また、ある時には、個人的な素朴な疑問をツイートで投げかけたところ、それに対する反論コメントや、さらにそのコメントに対する反論が重なり、ツイッター上で一大議論が巻き起こったことがありました。思わずサウジアラビア社会の虎の尾を踏んでしまったというところでしょうか。
このように、ツイッターを通じた発信に加えて、コメント上で市民と対話をしていくことで相互理解が深まり、日本の認知度向上や親日感情の醸成に寄与していると実感できることは、大使として嬉(うれ)しく思います。ソフト・パワーの目的を、「人々の意識の根底に、いざという時に日本に賛同してくれる思いを根付かせるもの」と捉えると、ソーシャルメディアを活用した外交活動の可能性はまだまだ広く、追求しがいがあるのではないでしょうか。

(筆者右端)(8月)

動画発信。34万回再生
(5月、サウジアラビア・ナジュラーン)
(注)2022年12月末時点
1 旭日旗に関する説明資料については外務省ホームページ参照:
(1)https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_003194.html
(2)動画リンク:https://www.youtube.com/watch?v=Oaehixu4Iuk
『伝統文化としての旭日旗』(2021年10月8日からYouTube外務省チャンネルで公開)


