3 科学技術外交
岸輝雄(きしてるお)外務省参与(外務大臣科学技術顧問)は、外務大臣の活動を科学技術面でサポートし、各種外交政策の企画・立案での科学技術の活用について外務大臣及び関係部局に助言を行う役割を担っている。また、内外の科学技術分野の関係者との連携強化を図りながら、日本の科学技術外交についての対外発信にも取り組んでいる。
2017年には、外務大臣科学技術顧問を座長とする「科学技術外交推進会議」及びスタディ・グループ会合を開催し、SDGsの実施や北極外交に資する科学技術の活用に関する討議を行った。


その結果、5月には、科学技術外交推進会議の下でSDGs実施に向けた「未来への提言」を取りまとめ、岸外務大臣科学技術顧問から岸田外務大臣に提出した。この提言は、日本外交が①イノベーションを通じて「変える、変わる」未来像を提示し、②地球規模の科学的データを用いながら課題を「捉えて、解き」、③そのために異なるセクターや国・地域を「結び、つなげ」、④取組を支える人材を「育てる」という四つのアクションを柱として、SDGs実施を積極的に先導する役割を果たすべきであるとしている。
8月には、白石隆(しらいしたかし)科学技術外交推進会議委員を座長とする作業部会により、「外務大臣科学技術顧問のこれまでの活動と今後の方向性について」と題する報告書が作成・公表された。この報告書では、顧問を通じた外交への科学的助言体制の構築は、日本外交に新たな特色を創出しており、今後も顧問制度を継続し、科学技術外交の取組を推進していくべきとの結論が示された。
また、同顧問は、日本の優れた科学技術力について発信力を高めるべく、内閣府と外務省の連携による科学技術イノベーションの対外発信事業5を諸外国6で実施し、今後の連携可能性等について相手国の関係機関・研究者らと議論した。
さらに、同顧問は米国、英国、ニュージーランド等の各政府の科学技術顧問と共に各種国際会議に出席し意見交換を行う等してネットワーク構築・強化に努めるとともに、各国顧問と共著論文を発表した。このほか、国内外での各種フォーラム等で、日本の科学技術外交の取組について広く発信している。また、外務省内の知見向上のため、科学技術外交セミナーも定期的に開催している。
日本は32の科学技術協力協定を締結しており、これらは現在、46か国及びEUとの間で適用され7、協定に基づき定期的に合同委員会を開催して政府間対話を行っている。2017年は、インド、フランス、イタリア、スロベニア、EU、南アフリカ及びブルガリアとの間でそれぞれ合同委員会を開催し、関係省庁等も出席の下、多様な分野における協力の現状、今後の方向性などを協議し、科学技術交流の促進に寄与した。ブルガリアとは19年ぶりの開催となった。
多国間協力では、旧ソ連の大量破壊兵器研究者の平和目的研究を支援する国際科学技術センター(ISTC)の理事国として、米国及びEUと協力し、中央アジア諸国を中心に支援を行っているほか、国際熱核融合実験炉(ITER)計画に参画している。
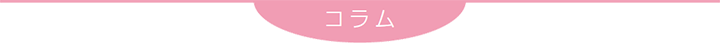
私は長年、日本の製造業に身を置き、研究開発の立場から科学技術イノベーション(STI)に関わってきました。ものづくりの役割は、科学的な発見を実社会のニーズに合わせて製品という形にし、世の中をより良くするのに役立てるものといえます。
2030年に向けた国連の持続可能な開発目標(SDGs)は、 その実現のためにSTIの活用に期待を寄せ、国際協力を進めるためのメカニズムを設けています。科学技術立国を自認してきた日本はこのために何をなすべきでしょう。この点につき科学技術外交推進会議で提言を行うため、そのまとめ役を引き受けることとなりました。
提言づくりに向け、SDGsは人類が抱える様々な課題を包括的、かつ包摂的に解決しようとしていることから、海洋、宇宙、基礎科学、アカデミア、産業界と幅広い分野で活動する方々と、「STI for SDGs」のあり方を討議しました。特に、Society5.0に向けた日本の取組や、地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)等の国際協力の拡大と深化によって、地球社会の持続的な発展に貢献できることを確認しました。また、科学技術が、日本外交にとって重要な役割を果たすことを、改めて認識しました。こうして2017年5月に完成した「未来への提言」は、「STI for SDGs」の方向性について四つの具体的アクションを提示しました。未来社会のビジョン提示(Society5.0)、データ活用による課題解決、国やセクターを超えるパートナーシップ、担い手となる人材の育成です。
その後、提言の作成に関わったメンバーと共に、ニューヨークの国連本部で開催された第2回STIフォーラムに出席しました。100か国の行政、大学、企業、NGO等から700人が集まり、2日間の議論を通じて強調されたことは、人材育成、ステークホルダーとの連携、そしてビジネスの参画の重要性など、提言の内容とも重なりました。各国からは、日本がSDGsに向けた取組で先行し、モデルケースを示して欲しいとの期待が寄せられました。

「未来への提言」では、STIには「橋を架ける力」があると述べました。人工知能やロボットなど急速に進展する新技術に対する期待と不安が交錯する今日、技術が伸びゆくままに任せるのではなく、50年後、100年後の人類社会はどうあるべきかという視点でSTIの発展を先導し、人間中心の未来社会への橋渡しをしていく重要性が高まっていることを痛感しました。
STIにより解決すべき課題を見出す手がかりを与えてくれるものがSDGsとも言えます。そして、研究成果が実社会に根を下ろし広がるための「社会実装」を、将来にわたり地球規模で進めていくことでSDGs実現に近づくことができるのです。
5 将来の国際協力や日本の研究開発成果の国際展開の布石とするため、内閣府(総合科学技術・イノベーション会議)が司令塔機能を発揮し、省庁・分野横断的な11の課題において産学連携により基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を促進する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」について、外務省(在外公館)との連携により、諸外国に向けて紹介する事業(通称「SIPキャラバン」)
6 2017年3月にインドネシア、同6月にフィリピン及びタイ、同9月にオランダで実施
7 日ソ科学技術協力協定をカザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、アルメニア、ジョージア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、トルクメニスタン及びタジキスタンが各々異なる年月日に承継。日チェコスロバキア科学技術協力取極を1993年にチェコ及びスロバキアが各々承継。日ユーゴスラビア科学技術協力協定をクロアチア、スロベニア、マケドニア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロが各々異なる年月日に承継
