1 ロシア
(1)ロシア情勢
ア ロシア内政
プーチン大統領は、2014年3月のクリミア「併合」後に獲得した国民世論の圧倒的支持を背景に、2017年も年間を通じて高い支持率を維持した。一方、3月にはメドヴェージェフ首相の蓄財疑惑に対する大規模な抗議活動が発生し、6月及び10月には、野党派が主導する大規模な反政府抗議活動が発生した。
イ ロシア経済
国際的な原油価格の下落や欧米諸国による経済制裁によって2014年後半から低迷していたロシア経済は、油価の安定に伴い、2016年に下げ止まりが見られ、GDP成長率はマイナス0.2%になった。2017年は、消費や投資の更なる改善やインフレの低下、賃金の上昇が見られ、GDP成長率もプラス1.5%(速報値)を記録するなど回復傾向にある。一方、実質所得は依然マイナス傾向にあるなど、不安要素も多い。
ウ ロシア外交
ロシアと欧米諸国との間では、ウクライナ情勢、ロシアによる選挙介入疑惑等をめぐり、対立関係が続いた。米露間では、様々な対抗措置の応酬を始め、依然として関係改善の兆しは見えていない。
中国とは、ユーラシア経済同盟と「一帯一路」の接合を進めるとともに、2度の合同軍事演習を実施するなど、緊密な関係を維持している。
中東では、ロシアは地域内の様々な国と対話ができる独自の立場をいかす外交を展開した。特にシリアについては、12月にプーチン大統領が同地に派遣されていたロシア軍の撤退開始を指示するとともに、イラン・トルコと協力しつつ政治対話プロセスの促進に取り組んでいる。
そのほか、ロシアは独立国家共同体(CIS)との伝統的な協力関係も維持し、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)や上海協力機構等の多国間枠組みを活用した外交を展開している。
(2)日露関係
ア アジア太平洋地域における日露関係
近年、ロシアは、極東・東シベリア地域の開発を重視し、世界経済の成長センターであるアジア太平洋地域諸国との関係強化を積極的に推進している。日露両国がアジア太平洋地域のパートナーとしての関係を発展させていくことは、日本の国益のみならず、地域の平和と繁栄にも資するものである。日本とロシアは、政治、安全保障、経済、文化・人的交流など様々な分野で協力関係の進展に努めている。
一方、日露間の最大の懸案となっているのが北方領土問題である。政府としては、首脳間及び外相間で緊密な対話を重ねつつ、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結すべく、ロシアとの交渉に精力的に取り組んでいる。
イ 北方領土と平和条約締結交渉
北方領土問題は日露間の最大の懸案であり、北方四島は日本に帰属するというのが日本の立場である。政府は、1956年の日ソ共同宣言、1993年の東京宣言、2001年のイルクーツク声明などこれまでの諸合意及び諸文書並びに法と正義の原則に基づき、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの一貫した基本方針の下、ロシアとの間で精力的に交渉を行っている3。
2017年には、4回の首脳会談及び5回の外相会談を始め政治対話が活発に行われる中で、2016年末のプーチン大統領訪日の際に首脳間で合意した事項4の具体化が進められた。北方四島における共同経済活動については、2月及び3月の日露外相会談を経て4月末にモスクワで行われた日露首脳会談の結果、北方四島への官民現地調査団の派遣で一致し、6月に最初の現地調査が行われた。7月のG20ハンブルク・サミット(ドイツ)の際の日露首脳会談、8月の河野外務大臣就任後初となる日露外相会談(フィリピン・マニラ)を経て、9月のウラジオストクでの日露首脳会談の結果、早期に取り組む5件のプロジェクト候補5を特定するとともに、双方の立場を害さない法的枠組みを検討し、できるものから実施していくことで一致した。その後、9月の国連総会の際の日露外相会談を経て、これらのプロジェクト候補の具体化に向けて、10月に北方四島における2回目の現地調査が行われた。11月のベトナムアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の際の日露首脳会談では、2018年春に向けてプロジェクト候補を具体化するための検討を加速させることで一致した。また、11月末、河野外務大臣がロシアを訪問した際の日露外相会談で、今後の作業の具体的な進め方を確認した。
また、北方領土の元島民の方々のための人道的措置として、8月に、アクセスが制限されていた国後(くなしり)島瀬石周辺への墓参と、歯舞(はぼまい)群島墓参の際の追加的な出入域地点の設置が実現した。さらに、9月には航空機を利用した特別墓参が初めて実施され、元島民の方々の身体的負担の軽減に向けた新たな方途が切り拓かれた。日露双方は、2018年以降も元島民の方々がより自由に往来できるよう、更なる改善策を採っていくことで一致している。

日露が共に北方四島の未来像を描き、その中から、双方が受け入れ可能な解決策を見いだしていくという未来志向の発想により、平和条約の締結を実現するため、政府としては、日露両首脳の強いリーダーシップの下、今後も、首脳間で合意した事項の具体化に向けて取り組んでいく。
政府は、四島交流、自由訪問及び北方墓参並びに隣接地域における防災分野での協力などの北方領土問題解決のための環境整備に資する事業にも積極的に取り組んでいる。また、北方四島周辺水域における日本漁船の安全な操業の確保や、禁止された流し網漁に代わる漁法でのさけ・ます類の漁獲の継続のため、ロシア側に対する働きかけや調整を行っている。一方で、北方四島でのロシアの軍備強化に向けた動きは、北方領土問題に関する日本の立場と相いれないものであり、ロシア側に対して申入れを行っている。
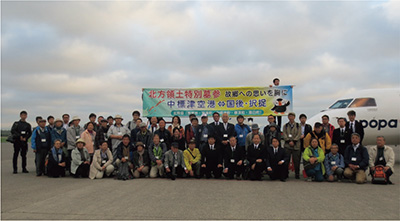
ウ 日露経済関係
2017年の日露間の貿易額は、ロシアから日本への主要な輸入品目である石油・天然ガスの価格安定や、日本からロシアへの自動車部品の輸出増加を受け、2013年以来4年ぶりに増加した(約2兆2,224億円、前年比約25%増(出典:財務省貿易統計))。
一方、日本の対露直接投資残高は2,176億円(2015年)から、1,757億円(2016年)へと減少した(日本銀行国際収支統計)。
2016年5月に安倍総理大臣が提案した経済分野における8項目から成る「ロシアの生活環境大国、経済・産業の革新のための協力プラン」6については、2017年4月に安倍総理がモスクワを訪問し、プーチン大統領に「協力プラン」のメリットを映像を用いて提示し、具体化を更に進めることで一致した。6月のサンクトペテルブルク国際経済フォーラム及び7月の産業総合博覧会「イノプロム」(エカテリンブルク)には世耕弘成経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣が出席したほか、日露の企業間でも活発な意見交換が行われた。このような取組を通じて迎えた9月の第3回東方経済フォーラム(ウラジオストク)では、改正日露租税条約の署名、国際協力銀行(JBIC)とロシア直接投資基金(RDIF)による共同投資枠組みの設立、デジタル経済の実現に向けた協力覚書の署名等の幅広い成果が生まれ、2016年12月のプーチン大統領の訪日以来、両国の民間企業間の文書は100件に達した。

11月のベトナムAPEC首脳会議の際の日露首脳会談では、両首脳は、「協力プラン」が具体化していることを歓迎し、協議の継続を確認した。同月の貿易経済に関する日露政府間委員会第13回会合(モスクワ)では、河野外務大臣とシュヴァロフ第一副首相との間で、日露租税条約の早期発効に向けた国内手続を両国で迅速に進めることで一致したほか、極東地域の協力について、日本側から、①農林水産業の発展、②輸出基地化のためのインフラ整備、③エネルギー開発及び④投資促進の基盤整備を中心に協力を進めることを提案した。12月の日本投資家デー(ウラジオストク)には日本の企業関係者と共に世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣が参加し、極東における協力を更に活発化させるための意見交換が行われた。
また、ロシア国内6都市で活動している日本センターは、両国企業間のビジネスマッチングや経営関連講座を実施しており、これまでに約8万2,000人が講座を受講し、そのうち約5,100人が訪日研修に参加している。
エ 様々な分野における日露間の協力
(ア)防衛交流・安全保障・海上保安
2017年も、日露戦略対話を始め、軍縮・不拡散、領事など幅広い分野で外交当局間の協議を行った。また、日露の専門家により、アフガニスタンや中央アジアの麻薬対策官に対し実践的訓練を実施したほか、テロ、麻薬、マネーロンダリング、腐敗対策での新たな協力を進めることで一致し、国連薬物犯罪事務所(UNODC)に外務省職員を派遣した。
安全保障分野では、3月に東京で3年4か月ぶりに日露外務・防衛閣僚協議(「2+2」)が開催されたほか、8月に外交当局間で日露安保協議を実施し、9月及び12月には谷内正太郎国家安全保障局長とパトルシェフ安全保障会議書記の会談が行われた。また、防衛交流については、11月にサリュコフ・ロシア地上軍総司令官が、12月にゲラシモフ・ロシア参謀総長が訪日した。実務レベルでは、引き続き各種協議や日露捜索・救難共同訓練等を実施し、相互理解の促進及び偶発事故の防止に努めた。さらに、海上保安庁巡視船とロシア警備艇との合同訓練も実施し、海上交通の安全についても連携を確認した。7月には中島敏海上保安庁長官がロシアを訪問し、約4年ぶりに日露海上警備機関長官級会合が実施された。
(イ)文化・人的交流
2016年12月の日露首脳会談で青年交流の倍増が確認されたことを受け、2017年には1,121人(前年比約2.3倍)が日露青年交流事業に参加し、幅広い分野で交流が実施された。
また、ロシア各地で様々な日本文化行事が行われ、日本では世界初の「ロシアの季節」が開催される等文化交流も活性化した。さらに、2017年9月の日露首脳会談(ウラジオストク)において、2018年5月26日に「ロシアにおける日本年」・「日本におけるロシア年」の開会式をモスクワで開催することを決定した。

3 かつて、ソビエト連邦(ソ連)が領土問題の存在自体を否定し続けるという状況の下で、1972年10月に大平正芳外務大臣から国際司法裁判所への北方領土問題の付託を提案したが、ソ連のグロムイコ外相がこれを拒絶した。現在は、ロシア側は日本との間で二国間の交渉を通じて平和条約を締結する必要性を認めており、日本として交渉を通じた問題解決に取り組んでいる。
6 ロシア・ソチでの日露首脳会談において、安倍総理大臣から提示し、プーチン大統領から高い評価と賛意が表明された。8項目とは、(1)健康寿命の伸長、(2)快適・清潔で住みやすく、活動しやすい都市作り、(3)中小企業交流・協力の抜本的拡大、(4)エネルギー、(5)ロシアの産業多様化・生産性向上、(6)極東の産業振興・輸出基地化、(7)先端技術協力及び(8)人的交流の抜本的拡大
