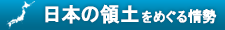Q1北方領土問題に関する政府の基本的立場は、どのようなものですか?
- A1我が国政府は、我が国固有の領土である北方四島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)の帰属に関する問題を解決して平和条約を早期に締結するという一貫した方針を堅持しています。また、北方四島の我が国への帰属が確認されるのであれば、実際の返還の時期、態様については柔軟に対応する考えです。
Q2北方四島が我が国の「固有の領土」であることの根拠は何ですか?
- A2北方四島はいまだかつて一度も外国の領土となったことがない我が国の領土です。
日露両国は、1855年2月7日に調印した日魯通好条約により、両国の国境を択捉島とウルップ島との間に定めました。その後1875年の樺太千島交換条約において、我が国は千島列島(シュムシュ島からウルップ島までの18島。)をロシアから譲り受けるかわりに、ロシアに対して樺太全島に対する権原、権利を譲り渡しています。
ソ連は、第二次世界大戦末期の1945年8月9日、当時有効であった日ソ中立条約を無視して、我が国に対し宣戦布告し、我が国のポツダム宣言受諾後の8月18日には千島列島に侵攻し、その後28日から9月5日までの間に北方四島のすべてを占領し、一方的に自国に編入しました。なお、1951年のサンフランシスコ平和条約で我が国が千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しましたが、そもそも北方四島は千島列島には含まれていません。また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約への署名を拒否しました。
Q3終戦当時北方四島にいた日本人はどうなったのですか?
- A3戦前、北方四島には、約1万7千人の日本人が住んでいましたが、その全員が、1948年までに強制的に日本本土に引き揚げさせられました。
Q41956年の日ソ共同宣言とはどのようなものですか?
- A4ソ連がサン・フランシスコ平和条約への署名を拒否したため、我が国はソ連との間で平和条約交渉を別途行うこととなり、1956年、日ソ両国は日ソ共同宣言を締結して、戦争状態を終了させ、外交関係を再開しました。日ソ共同宣言は、日ソ両国の立法府での承認を受けて批准された法的拘束力を有する条約です。
同宣言において、両国は、正常な外交関係が回復された後、平和条約の交渉を継続することとなっており、またソ連は、平和条約の締結後に歯舞群島及び色丹島を我が国に引き渡すこととなっています。
Q51956年当時、なぜ平和条約が締結されずに、「日ソ共同宣言」という名称の条約が締結されたのですか?
- A51956年当時、日ソ両国は平和条約を締結すべく交渉を行っていましたが、我が国が一貫して返還を主張した北方四島のうち国後島及び択捉島の帰属の問題について合意が達成できなかったため、とりあえず共同宣言を締結して外交関係を回復し、平和条約交渉を継続することとして、領土問題の解決を将来にゆだねたからです。
Q6日ソ共同宣言は今も有効ですか?
- A6もちろん1956年から現在まで一貫して法的に有効です。1960年の日米安全保障条約の締結に際して、ソ連は、日ソ共同宣言で合意された歯舞群島及び色丹島の引渡しに、我が国領土からの全外国軍隊の撤退という新たな条件を一方的に課してきました。また、ソ連はその後長らく、領土問題は既に解決済みであるとの立場をとっていました。
しかし、冷戦の終焉に伴い、ロシア側は、領土問題の存在を認めるとともに、改めて日ソ共同宣言が日露両国間で有効であることを確認するようになりました。2000年9月、プーチン大統領は日本を訪問した際、首脳会談において、「56年の日ソ共同宣言は有効と考える」と発言しました。2001年3月のイルクーツク声明においては、日ソ共同宣言が両国間の平和条約締結交渉の出発点となった基本的な法的文書であることが確認されています。また、2004年11月、ラヴロフ外相及びプーチン大統領は、相次いで、ロシアにはソ連と同一の国として、1956年の日ソ共同宣言を履行する義務がある旨の発言を行いました。
Q71993年の東京宣言とはどのようなものですか?
- A7ソ連崩壊後の1993年10月、ロシアのエリツィン大統領が訪日した際に、日露両首脳間で署名された文書のことです。この宣言は、北方四島の島名を列挙して、北方領土問題をその帰属に関する問題であると位置付けるとともに、この問題を歴史的、法的事実に立脚し、両国間で合意の上作成された諸文書、「法と正義の原則」を基礎として解決するという明確な交渉指針を示しました。その後、日露間においては、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという東京宣言の方針が繰り返し確認されてきています。
Q8北方四島に居住しているロシア人は、北方四島が我が国に返還された場合、どうなるのですか?
- A8現在、北方四島には約1万8千人のロシア人が居住しており、主に水産業・水産加工業に従事しています。我が国は、領土問題の解決に当たっては、現在北方四島に居住しているロシア人の人権、利益及び希望を十分に尊重していく考えです。この点については、日露両国の外務省が共同で作成した日露間領土問題の歴史に関する資料集(Q10参照)の前文においても、「日本政府も、領土問題の解決にあたり、現在これらの島々に居住しているロシア国民の人権、利益及び希望を十分に尊重していく意向である旨明らかにしている。」と明記されているところです。
Q9現在、北方四島への訪問、北方四島に住んでいる人達との交流等は行われているのですか?
- A9政府は、我が国国民がロシア側の出入域手続に従うことを始め、ロシアの不法占拠の下で北方四島に入域しないよう要請していますが、特例的に日露両国間で設定された以下の四つの枠組みによる訪問、交流等が行われてきています。
- (1)北方墓参
1964年から、元島民及びその親族による北方四島の墓地への墓参が行われ、2020年末までにのべ4,851人が訪問しました。
- (2)四島交流
1992年4月から、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として、我が国国民と北方四島の住民との間で相互訪問が開始され、2020年末までにのべ24,488人が参加しました。
- (3)自由訪問
1999年9月から、元島民及びその家族による北方四島にある元居住地等への訪問が行われ、2020年末までにのべ5,231人が参加しました。
- (4)人道支援
北方四島の患者の受入れ等、北方四島在住のロシア人にとって真に人道的に必要な支援が行われてきています。
Q10北方領土問題に関する資料として日露両国間でまとめられているものはありますか?
- A101992年9月に日露両国外務省により、北方領土問題に関する客観的な事実を集めた「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」が作成され、日露両国において領土問題に関する正確な認識の普及のための努力に利用されています。また、2001年1月には、新版が作成されています。