チャレンジ41か国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
2011年1月
ヒンディー語の専門家 大工原さん
![]() (ナマステー)=こんにちは!
(ナマステー)=こんにちは!
大工原さんは,大学院で専攻した国際政治学を生かせる仕事に就きたいと考え,外務省に入省しました。でも,専門語が「ヒンディー語」になるとは思ってもみなかったということで,まさに青天の霹靂でした。

デリーのモスク,ジャマーマスジットにて。
ヒンドゥー教徒が多数派ですが,憲法上世俗主義が国是となっており,
イスラム教徒人口もインドネシアに続き世界第2位です。
まさかのヒンディー語!?
外務省を受験する時,専門語については第5希望まで出すことができますが,実はヒンディー語は,大工原さんが受験した年には募集言語にもありませんでした。にもかかわらず,ヒンディー語を専門語とするよう告げられ,「正直言って不安でした。」
インドって大変そう…
「インドに行った人は,好きになるか嫌いになるか,そのどちらかだと言われますが,私はたぶん嫌いになると漠然と思っていたくらい,インドとは関わりを持ったことがなく,インドのことを好きになれるのか,関心を持てるのか,不安でした。しかし,知らないことを知ることができるチャンスと考えて,怖かったけれども思い切って飛び込んでみました!」

タージマハル(やっぱりインドと言えば)
ヒンディー語を母語とする人は約4割
10億人超の人口を抱えるインドですが,公用語であるヒンディー語を母語とするのは4億人程度。中国語,英語に次いで世界で3番目に多く話されている言葉ですが,インドの残りの6割の人々は,インドで話されている約600(方言を除くと約260とも言われています)の言語のいずれかを母語としていることになります。連邦レベルの公用語であるヒンディー語の他に,州レベルの公用語として認められている言語が21あり,英語も政府の公用語として使われています。「ロシアを除いたヨーロッパとほぼ同じ面積なので,1つの国ですが実に様々な言葉が話されているのも当然かもしれません。」
デーヴァナーガリー文字
ヒンディー語の文字は「デーヴァナーガリー文字」と言われていて,8世紀に形成,9世紀にインドに普及したと言われています。ヒンディー語の他,マラーティー語,ネパール語やインドの古典語のサンスクリット語の文字として使用されています。文字の上に,シローレーカー(頭線)と言われる横線が引かれているのが特徴です。日本語の音韻もサンスクリット語の音韻学に基づいているため,ヒンディー語も日本語の「あいうえお」に似ていますので,見た目よりも覚えるのは簡単かもしれません。
ヒンディー語を習得する意外な難しさ
「ヒンディー語は文法も発音も日本語と似ているので,言葉としてはそれほど難しくはありません。しかし,インド人の6割はヒンディー語以外の言葉を母語としているので,インドに行けば皆がヒンディー語をしゃべっているというわけではありません。大学の授業は英語でしたし,職場でもほとんど英語を使うことが多いので,意識的にヒンディー語を使おう,使おう,としないと,ヒンディー語を使わなくても生活できてしまうんです。」
「ボリウッド」がおすすめ!
そのような環境でどのようにヒンディー語を習得したのでしょうか?「ボリウッド(映画制作の中心地ムンバイの旧名ボンベイとハリウッドに由来)とも言われるヒンディー映画をオススメします。インドは案外映画大国で,毎週金曜日に新作が1~2本封切られます。映画館に観に行くのもいいですし,DVDも多く出ているので,ヒンディー語の勉強になりますよ。」
「明日」と「昨日」が一緒
ヒンディー語では,「明日」という単語と「昨日」という単語が同じなんです。動詞の活用法で見分けます。「インドでヨガに通っていたんですが,先生から,『今という瞬間に集中しなさい』とよく言われました。もしかしたら,インド人の世界観は,『今』と『その周り』から成り立っているのかもしれません。特にインドの田舎の方に行くと,デリーも日本も「ここ」の外として同じ感覚で話している人が多いです。」

パンジャーブ州の農村にて
(インドの穀倉地帯パンジャーブ州の農村の様子。
インドのおじさんのお腹にはいつも何がはいっているだろう、と思うくらい立派!)
感情が私にくっつく?
感情を表す表現を日本語では例えば「私は嬉しい。」とか「私は怒っている。」とか言いますが,ヒンディー語では,好き,怒り,お腹がすいたなどの感情や状態が私にくっつくという言い方をします。「私は~~。」という言い回しをする日本語とは違い,感情がどこからかふっと私のところに降りてくるというような感じです。
とにかく暑い
「インドでの研修の最初の半年くらいは,暑いと眠いしか覚えていません…。」学生寮はとにかく暑く,一日3回の給水後タンクの水が終われば水がなくなってしまう環境でした。食事は三食カレーだったということですが,友人たちと一緒に食べたり,楽しく過ごしました,と笑顔で話す大工原さん。特に地方出身者には真面目な学生が多く,高価な教科書を手書きで写して節約する姿には,自分が育ってきた環境の有り難さも感じたそうです。「水の有り難さもインドで実感しましたし,また,インド各地から来ている学生が,外国人である自分と同じ位にデリーの言葉,気候,食べ物に慣れるのに悪戦苦闘している姿を見て,インドの多様性を感じました。」

ヒマーチャル・プラデーシュ州のお祭りローリーにて
大学の友人と(右から3番目が大工原さん)
学生の選挙の様子。夕方に開票が始まってからそれぞれの政党
(学生政党ですが,実際の政党の下部組織になっています)
支持者が,歌ったりしながら翌朝の選挙結果を待ちます。
太鼓ひとつあれば、歌って踊れるインド人です。
大使館での勤務
2年間の研修後,大工原さんは,在インド日本国大使館![]() に3年間勤務し,儀典,経済,広報文化を担当しました。「業務では英語を主に使用するので,ヒンディー語を使う機会はあまりありませんでした。」専門語の第一希望が英語であった大工原さん。実は,英語/ヒンディー語というちょっと珍しい採用でした。「ヒンディー語を学ぶ必要が本当にあるのかと思った時期もありましたが,インド人は感情や本当に思っていることはヒンディー語で表現することが多いですし,ヒンディー語を話すと相手が喜んでくれて,相手との距離がぐっと縮まります。そのような時は,ヒンディー語を学んでいてよかったと心から思います。」
に3年間勤務し,儀典,経済,広報文化を担当しました。「業務では英語を主に使用するので,ヒンディー語を使う機会はあまりありませんでした。」専門語の第一希望が英語であった大工原さん。実は,英語/ヒンディー語というちょっと珍しい採用でした。「ヒンディー語を学ぶ必要が本当にあるのかと思った時期もありましたが,インド人は感情や本当に思っていることはヒンディー語で表現することが多いですし,ヒンディー語を話すと相手が喜んでくれて,相手との距離がぐっと縮まります。そのような時は,ヒンディー語を学んでいてよかったと心から思います。」
日本とインドの共通点
インドにいる間は,違いばかりに目が行っていました。共通点を考えるようになったのは,日本に帰国してからでしょうか。家族や年長者を大事にする点はインドと日本の共通点だと思います。また,ヒンドゥー教は多神教で,水の神様や風の神様がいたりします。日本と似ているかもしれませんね。また,ヒンドゥー教の神様や女神が日本でも毘沙門天,弁財天,吉祥天等として日本でも信仰されています。
日印関係の強化
大工原さんが入省した2003年にちょうどBRICsレポートが出され,インドへ注目が集まるようになりました。「2005年から毎年首脳往来があり,その全てに関わることができています。日印関係が良好なこの時期にインドを担当させて頂けたのはすごく有り難いことだと思っています。」現在,南西アジア課でインドを担当している大工原さん。これからもご活躍を期待しています!

ダージリンから見たヒマラヤカンチェンジュンガ山
印象に残っている言葉
 (カバーブ・メーン・ハッディー)
(カバーブ・メーン・ハッディー)
「カバーブ(串焼き肉)の中に骨=蛇足」
ベジタリアンの多いインドなので,時々お肉が食べたくなるとイスラム教徒の多く居住する地区にカバーブを食べに行きました。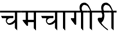 (チャムチャーギーリー)
(チャムチャーギーリー)
「おべっか,ごますり」
チャムチャーはスプーンの意味で,一つのスプーンの腹にもう一つのスプーンを合わせることから,相手にあわせる,ゴマをするという意味になります。ごまをする人は,チャムチャーワーラーと呼んだりします。 (ムスカーン)
(ムスカーン)
「微笑み」
クラスメートからつけられたヒンディー語のニックネーム。大好きな単語の一つです。
便利なフレーズ
 (ティーク・ヘ!)
(ティーク・ヘ!)
「結構です,承知しました」
インド人は,同意する時に首を縦ではなく横に振るので,首を横に振りながら使用してください。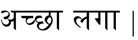 (アッチャー・ラガー)
(アッチャー・ラガー)
「気に入りました,良かったです」
アッチャーは,「良い」を意味し,文字通りには「良いことが自分にくっついた状態」を表します。食べた料理,見た映画,会った人など,自分がいいな~と思った物に対して使用可能。 (マザー・アーヤー)
(マザー・アーヤー)
「楽しかった,面白かった」
文字通りには,マザー(楽しい)という状態が自分のところにやってきたことを意味します。

