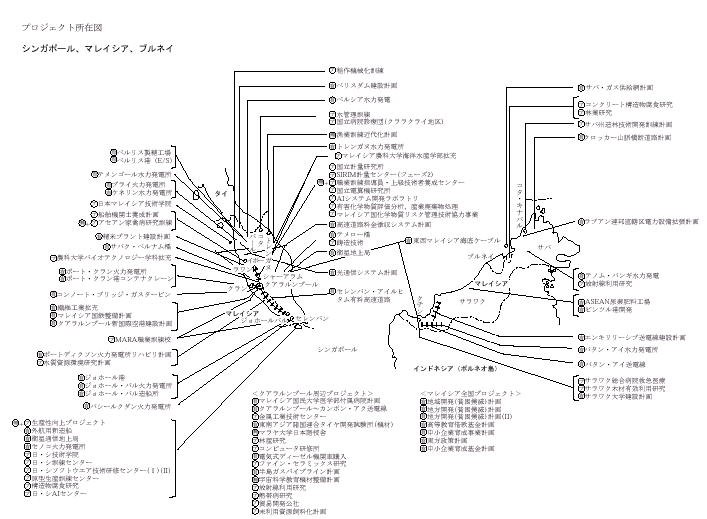国別援助実績
1991年~1998年の実績
[10]マレイシア
(1) マレイシアは、連邦制立憲君主国であり、国民は大別してマレイ系(61%)、中国系(30%)、インド系(8%)に分けられる複合民族国家である。マレイ系と非マレイ系民族の対立を回避することが建国以来の最大の課題であり、また、各民族の調和を国是とし、相対的に貧困なマレイ系の経済的地位を引き上げることを目的とした「ブミプトラ政策」と呼ばれるマレイ系優先政策を進めている。現在、マハディール首相(81年就任)は、調和がとれ安定した複合民族国家の構築のために人造りを重視し、労働倫理・経営哲学を我が国及び韓国に学ぶ「東方政策」を推進している。
内政は、95年4月の総選挙にてマハディール首相率いる連合与党「国民戦線」が圧勝し、同首相の確固たる指導力の下、安定的に推移してきたが、98年9月以降、アンワール副首相兼蔵相の更迭、治安維持法に基づく同氏の逮捕・拘留及び起訴・裁判といった展開があり、次期総選挙(2000年6月に下院議員の任期満了)を控えての政治・経済動向が注目されている。99年1月、アブドゥラ副首相兼内相が指名される等の内閣改造が実施され、同年3年のサバ州議会選挙では、連合与党は州政権を維持している。
外交面では、ASEAN諸国との協力、イスラム諸国との協力、非同盟及び大国との等距離外交、自由主義諸国との協力及び南南協力、対外経済関係の強化を基本としており、マハディール首相就任以降は、「東方政策」に基づき、我が国及び韓国との関係が緊密化している。同国は、小国・途上国の立場・権利の擁護を主張するなど、途上国のスポークスマン的役割を果たしており、99年~2000年の国連安保理非常任理事国となっている。
(参考1)主要経済指標等
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口(千人) | 17,752 | 20,140 | 20,565 | 21,667 | |
| 名目GNP | 総額(百万ドル) | 41,524 | 78,321 | 89,800 | 98,195 |
| 一人当たり(ドル) | 2,340 | 3,890 | 4,370 | 4,530 | |
| 経常収支(百万ドル) | -870 | -7,362 | - | - | |
| 財政収支(百万リンギット) | -3,437 | 1,861 | 1,815 | 6,627 | |
| 消費者物価指数(90年=100) | 100.0 | 124.7 | 131.1 | 134.9 | |
| DSR(%) | 12.6 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | |
| 対外債務残高(百万ドル) | 15,328 | 34,343 | 39,673 | 47,228 | |
| 為替レート(年平均、1USドル=リンギット) | 2.7049 | 2.5044 | 2.5159 | 2.8132 | |
| 分類(DAC/国連) | 高中所得国/- | ||||
| 面積(千平方キロメートル) | 328.6 | ||||
(参考2)主要社会開発指標
| - | 90年 | 最新年 | - | 96年 | 最新年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生児の平均余命(年) | 70 | 72(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
22 | 11(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下の人口割合(%) | - | 4.3(95年) | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
29 | 14(97年) | |
| 下位20%の所得又は消費割合(%) | 4.6(89年) | 4.6(89年) | 妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
59(80-90年平均) | 34(90-97年平均) | |
| 成人非識字率(%) | 22 | 16(95年) | 避妊法普及率 (15~49歳女性/%) |
51(80-90年平均) | - | |
| 初等教育純就学率(%) | - | 102(96年) | 安全な水を享受しうる人口割合(%) | 79(88-90年平均) | 89(96年) | |
| 女子生徒比率(%) | 初等教育 | 49 | 49(96年) | 森林面積 (1000平方キロメートル) |
176 | 155(95年) |
| 中等教育 | 51 | - | ||||
(2) かつてはゴムと錫中心の典型的なモノカルチャー型経済であったが、外資系企業の積極的な誘致による輸出志向型工業化政策の推進により、85年以降急速な工業化を通じて著しい経済成長を達成し、経済成長率は88年以来9年連続8%を超える成長を遂げた。一方、インフレ率は、3.5%に抑えられており、政府の目指す「インフレなき持続的経済成長」はほぼ達成されていた。
このように、80年代後半からマレイシア経済は極めて順調に推移してきたが、97年のアジア経済危機の影響を大きく受け98年にはマイナス成長を記録した。マレイシア政府は当初よりIMFによる支援を仰がず、独自に緊縮型の経済政策をとってきたが、経済の悪化に歯止めをかけるべく景気刺激策に転換し、不良債権処理や金融機関のリストラにも取り組み、また98年9月、為替管理措置、固定相場(1米ドル=3.8リンギ)を内容とした政策を導入した。現在、流動性増加が見られ、外貨準備高、貿易収支において効果を上げてきている一方、これらの政策を実施するための海外からの資金調達・社会的弱者対策などの対策が不可欠となっている。なお、マレイシア政府は99年の成長見通しを1%としている。99年予算案では、積極財政による内需拡大を優先している。
(3) マレイシア政府は91年、それまでの新経済政策(NEP)が終了したのに伴い、2000年までの10年間の社会・経済政策の基本となる「国家開発計画(NDP)」及び同計画を具体的に表現した「第2次長期総合計画(OPP2)」を策定した。NDPは、NEP同様、国家の統合を究極の目標としNEPの貧困撲滅及び社会の再編成という二大目標を踏襲し、経済の持続的成長の障害とならないように「ブミプトラ政策」(マレイ人優先政策)を柔軟に運用していくこととしている。また、NDPでは、2020年までに先進工業国への仲間入りを目指し(「ビジョン2020」)、年平均7%の経済成長の達成を目標としていえる。これらを踏まえ、より具体的な経済社会計画である第7次マレイシア計画(96~2000年)が策定されている。この計画では、1)マクロ経済の強化、2)知識・熟練労働者の供給、3)貧困撲滅と社会変革、4)金融セクター強化、5)民間債務やコーポレート・ガバナンスの改善、6)農業・地方開発の活性化、7)製造業の成長の回復、8)サービス部門の向上、9)情報技術の強化、10)科学技術の強化、11)環境保全や社会サービス等生活の質の向上等を重点課題としている。
(4) 我が国との関係は、「東方政策」に象徴されるように全般的に極めて良好である。政府間交流も活発に行われており、98年10月には第2回東京アフリカ開発会議に参加するためマハディール首相が来日し、98年11月のAPECに際しては、小渕総理、高村外務大臣が往訪した。また、我が国は、マレイシアにとって最大の貿易相手国であり、97年の我が国への輸入は木材やLNGなど1兆3,751億円、我が国からの輸出は電気機械(含む半導体)や一般機械を中心に1兆7,555億円となっている。対マレイシア投資は、円高などを背景に87年以降飛躍的に増大し、95年度555億円、96年度644億円、97年度971億円と増加している。日系進出企業の主要投資業種は製造業、商業・サービス及び金融関係で、地域的にも首都に近いセランゴール州のみにとどまらず、ジョホール、マラッカ、ケダ州など地方への進出が見られる。
(1) 我が国は、1)マレイシアが我が国と貿易、投資等の面で密接な相互依存関係を有するなど、我が国にとって政治・経済面において重要な存在であること、2)また、調和のとれた安定した複合民族国家構築のため人造りを重視しており、労働倫理、経営哲学を日本等に学ぶ「東方政策」を推進しており、我が国との関係が全般的に極めて良好であること、3)更に、80年代以降の急速な経済発展に伴い、環境、貧富の格差等様々な問題が顕在化していること、4)97年のアジア経済危機による経済困難を経験しているマレイシアは、為替管理措置・固定相場制を導入しつつ、積極財政による景気刺激策、不良債権処理を含む金融セクター改革等の実施により困難の克服を図っているが、マレイシアの経済回復努力を支援する必要があること等を踏まえ、援助を実施する。
なお、最近マレイシアから、経済構造の一層の高度化のために、我が国からの技術移転を求める声が強まっていること、マレイシアが情報産業に力を入れており、クアラルンプール近郊に新たな情報都市「サイバージャヤ」を建設し、「マルチ・メディア・スーパー・コリドー計画(MSC)」を推進している点に留意する。
(2) 我が国は、マレイシアの社会・経済開発努力を積極的に支援するため、98年10月発表の新宮澤構想を踏まえ、99年3月及び4月にはほぼ5年ぶりに円借款(総額1,140億7,300万円)を供与した。円借款のほか、援助以外の公的資金協力として輸銀保証の活用及び9億ドル相当円程度の輸銀融資を表明している。
(3) 我が国は、マレイシアにおける開発の現状と課題、開発計画等に関する調査・研究及び93年3月に派遣した経済協力総合調査団及びその後の政策協議等におけるマレイシア側との政策対話を踏まえ、以下の分野を援助の重点分野としている。
(イ) 環境保全
マレイシアの持続的な発展のためには、環境と開発の両立が必要。開発にあたっては環境面に最大限の注意が払われるべきであり、(a)森林等の自然資源の保全及び持続可能な利用、(b)都市環境の改善・整備、(c)産業公害対策等に留意しつつ協力を行う。
(ロ) 貧困撲滅と地域振興
マレイシアでは急速な経済発展によりセクター間や地域間での所得格差が拡大した。絶対貧困層は劇的に減少したものの、相対的な貧困の問題が顕在化しているため、この問題に対しては、(a)地方振興(経済・社会基盤の整備)、(b)農業振興、(c)農村工業振興を最優先に対処する。
(ハ) 人材及び中小企業の育成
今後のマレイシアの発展に必要な、(a)人材育成、(b)中小企業・サポーティング・インダストリーの育成を重点的に支援する。
人材育成としては、熟練工・技術者への職業訓練や高等教育への支援を中心としつつ、高付加価値産業、金融セクター、福祉・安全・衛生における人材育成に加え、東方政策、女性のエンパワーメントへの協力について、また、中小企業育成としては、中小企業が国際競争力を備え、経済成長を支える輸出産業と連携するサポーティング・インダストリーとして育成されるよう、産業の研究開発能力の向上及び生産性・付加価値向上、情報処理技術の向上及び利用普及、サービス部門の育成、試験・標準にかかる能力向上及び調和化等への協力について、同国の優先度を考慮し、具体的な協力を検討する。
(4) 97年6月の対マレイシア援助技術協力政策協議において、マレイシア側より、重点分野については、(イ)科学技術、(ロ)情報技術(IT)、(ハ)人材育成、(ニ)環境の4分野の提示があったが、我が方からは、科学技術・情報技術については、人材育成・中小企業育成といった観点からの協力を行うなど、再検討を要する旨回答している。
(5) 我が国はマレイシアに、98年支出純額で1.79億ドルを供与しており(我が国二国間ODAの第10位)、69~98年までの支出純額累計で16.44億ドルを供与している(第12位)。
有償資金協力については、これまで経済インフラ整備(エネルギー開発等)を中心に行ってきている。但し、マレイシア国民の一人当たりGNPが我が国円借款基準を上回る(中進国)ようになったことに鑑み、94年度を最後に通常の円借款を「卒業」し、その後は例外的に検討を行うこととしていたが(97年度までは特に要請はなかった)、アジア経済危機による困難を背景に留学生支援やプロジェクト案件の要請を受け、98年10月に政府調査団を派遣した。これを踏まえ、99年3月、東方政策(留学プログラム)や高等教育借款基金計画等、総額1,076億9,500万円の円借款を供与する旨の支援会合の署名が行われた。例外的に検討を行う趣旨としては、「急速な経済成長に伴って生じた歪みの是正」への協力が挙げられており、対象分野としては、「環境改善」、「貧困撲滅・所得間格差是正」に加え、「中小企業育成」及び「人材育成」についてもこれに資する案件であれば取り上げることとされている。
無償資金協力は原則として文化無償及び草の根無償のみ実施しているが、アジア経済危機に対する支援として、マレイシアの政府派遣留学事業を継続させるための緊急無償援助(約4億5,000万円)を97年度に実施している。
技術協力は、同国の経済開発が進んだ結果、農林水産、鉱工業、医療等の分野の人造り支援に加え、環境や産業育成支援等の分野での比較的高度な協力の割合が高い。また、アジア地域の通貨・経済危機による経済困難の影響を踏まえ、「日・ASEAN総合人材育成プログラム」に基づき、人材育成への協力を実施している。開発調査は、従来エネルギー、都市整備、治水計画、工業化計画等の社会・経済インフラの分野を中心に実施していたが、近年は、従来のシステムを改善する案件や地域格差是正に資する公共性の高い案件も積極的に実施している。
我が国は、急速なマレイシアの経済成長を受けて、マレイシアの「援助国化」に向けた南南協力支援を推進している。
(6) 急激な経済発展を進めてきたマレイシアは、種々の環境問題に直面しており、今後も持続的な発展を実現するためには、都市、農村を問わず環境の保全に十分注意を払うべき旨が国家開発計画(UNDP:1991~2000年)の基本方針にも盛り込まれている。
(1)我が国のODA実績
| 暦年 | 贈与 | 政府貸付 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 | 1.61(-) | 78.01(-) | 79.62(-) | 84.98 | -74.30(-) | 5.32(100) |
| 95 | 1.46(-) | 84.68(-) | 86.13(-) | 169.38 | -21.30(-) | 64.83(100) |
| 96 | 0.69(-) | 69.91(-) | 70.60(-) | 205.82 | -553.11(-) | -482.51(100) |
| 97 | 1.20(-) | 62.77(-) | 63.97(-) | 386.48 | -322.84(-) | -258.88(100) |
| 98 | 3.92(2) | 59.53(33) | 63.45(35) | 183.72 | 115.65(65) | 179.10(100) |
| 累計 | 75.77(5) | 954.61(58) | 1,030.35(63) | 3,505.71 | 613.16(37) | 1,643.51(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
(2) DAC諸国・国際機関のODA実績(97年、支出純額、単位:百万ドル)
DAC諸国、ODA NET
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 日本 | 64.8 | 豪州 | 22.8 | フランス | 13.0 | ドイツ | 7.7 | カナダ | 4.5 | 64.8 | 106.9 |
| 96 | デンマーク | 8.4 | ドイツ | 7.5 | 豪州 | 5.9 | フランス | 3.5 | カナダ | 3.4 | -482.5 | -455.2 |
| 97 | デンマーク | 9.9 | ドイツ | 6.4 | 豪州 | 2.9 | カナダ | 2.2 | オランダ | 2.0 | -258.9 | -243.7 |
国際機関、ODA NET
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | UNDP | 7.3 | UNTA | 2.4 | ADB | 1.5 | UNICEF | 0.8 | CEC | 0.7 | 1.7 | 14.4 |
| 96 | UNDP | 3.9 | UNTA | 1.2 | UNHCR | 1.0 | UNICEF | 0.8 | CEC | 0.5 | 0.5 | 7.8 |
| 97 | UNDP | 5.2 | UNTA | 1.6 | UNHCR | 0.8 | UNICEF | 0.6 | CEC | 0.5 | 0.2 | 8.9 |
(3) 年度別・形態別実績
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 |
|---|---|---|---|
| 90年度までの累計 | 4,680.18億円 (内訳は、1997年度版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ gaiko/oda/ shiryo/jisseki/kuni/ j_90sbefore/901-10.htm)) |
101.10億円 (内訳は、1997年度版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ gaiko/oda/ shiryo/jisseki/kuni/ j_90sbefore/901-10.htm)) |
485.28億円 研修員受入 5,665人専門家派遣 989人 調査団派遣 3,466人 協力隊派遣 826人 機材供与 6,656百万円 プロジェクト技協 25件 開発調査 86件 |
| 91 | なし | 5.77億円 漁業訓練所近代化計画 (4.87)トレンガヌ州博物館に対する視聴覚車 (0.47) マレイシア国民大学に対する視聴覚機材供与 (0.41) 草の根無償(1件) (0.02) |
43.00億円 研修員受入 522人専門家派遣 107人 調査団派遣 249人 協力隊派遣 27人 機材供与 265百万円 プロジェクト技協 6件 開発調査 11件 |
| 92 | 629.31億円 第14次円借款 (629.31)高等教育借款基金計画 (54.93) テノム・パンギ水力発電所修復計画 (5.43) 中小企業育成事業計画 (139.80) ポートクラン火力発電所計画(第3期) (319.66) 地方開発(貧困撲滅)(II) (109.49) |
0.78億円 国立博物館に対する視聴覚機材 (0.40)ケダ州立図書館に対する視聴覚・展示機材供与 (0.36) 草の根無償(1件) (0.02) |
43.56億円 研修員受入 513人専門家派遣 108人 調査団派遣 267人 協力隊派遣 27人 機材供与 516百万円 プロジェクト技協 8件 開発調査 13件 |
| 93 | 538.70億円 第15次円借款 (538.70)ポートクラン火力発電所計画(第3期第2段階) (399.55) ラブアン連邦直轄区設備拡張計画 (37.00) マレイシア国民大学医学部付属病院計画 (102.15) |
1.30億円 災害緊急援助(豪雨及び洪水災害) (40万ドル=0.49)マレイシア工科大学日本高等予備教育センターに対する理科学実験機材 (0.48) 全寮制中高等学校に対する語学教育機材供与 (0.27) 草の根無償(1件) (0.06) |
45.40億円 研修員受入 541人専門家派遣 146人 調査団派遣 254人 協力隊派遣 42人 機材供与 804百万円 プロジェクト技協 9件 開発調査 11件 |
| 94 | 615.18億円 第16次円借款 (615.18)クアラルンプール新国際空港建設計画 (615.18) |
1.03億円 パハン州立博物館に対する視聴覚機材供与 (0.49)マラヤ大学日本文化センターに対する視聴覚機材供与 (0.50) 草の根無償(1件) (0.04) |
49.11億円 研修員受入 517人専門家派遣 111人 調査団派遣 246人 協力隊派遣 32人 機材供与 629百万円 プロジェクト技協 8件 開発調査 10件 |
| 95 | なし | 1.04億円 国立公文図書館への記録映画保存機材供与 (0.50)TV3への番組ソフト供与 (0.36) 草の根無償(4件) (0.18) |
41.73億円 研修員受入 494人専門家派遣 106人 調査団派遣 188人 協力隊派遣 27人 機材供与 512.1百万円 プロジェクト技協 8件 開発調査 8件 |
| 96 | なし | 1.26億円 サラワク大学機材供与 (0.49)マレイシア国立交響楽団機材供与 (0.49) 緊急無償洪水災害 (0.10) 草の根無償(6件) (0.18) |
37.89億円 研修員受入 513人専門家派遣 124人 調査団派遣 194人 協力隊派遣 31人 機材供与 505.5百万円 プロジェクト技協 7件 開発調査 10件 |
| 97 | なし | 5.70億円 緊急無償経済困難(対日留学生派遣支援) (4.54)マレイシア・プトラ大学日本語学習機材供与 (0.36) マレイシア国立図書館(マラッカ州立図書館、ペラ州立図書館)視聴覚機材供与 (0.46) 草の根無償(7件) (0.34) |
40.05億円 研修員受入 488人専門家派遣 111人 調査団派遣 163人 協力隊派遣 16人 機材供与 454.0百万円 プロジェクト技協 7件 開発調査 7件 |
| 98 | 1,076.95億円 対マレイシア円借款 (1,076.95)東方政策計画 (140.26) ベリスダム建設計画 (97.37) ポートディクソン火力発電所リハビリ計画 (490.87) サラワク大学建設計画 (185.49) 中小企業育成基金計画 (162.96) |
0.84億円 草の根無償(16件) (0.39)ケダ州文化施設音響・照明機材 (0.45) |
46.57億円 研修員受入 730人専門家派遣 117人 調査団派遣 167人 協力隊派遣 23人 機材供与 891.0百万円 プロジェクト技協 6件 開発調査 12件 |
| 98年度までの累計 | 7,540.32億円 | 118.82億円 | 832.57億円 研修員受入 9,983人専門家派遣 1,919人 調査団派遣 5,194人 協力隊派遣 1,051人 機材供与 11,231.9百万円 プロジェクト技協 28件 開発調査 103件 |
- 「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
- 「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
- 68年度から90年度までの有償資金協力及び無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-10.htm)
(参考1)98年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件
| 案件名 | 協力期間 |
|---|---|
| 診療団 | 66.4~68.3 |
| 稲作機械化訓練 | 70.12~75.12 |
| MARAクアラルンプール職訓校 | 73.6~76.1 |
| 船舶機関士養成計画 | 73.12~82.6 |
| MARAジョホールバル職訓校 | 76.9~81.9 |
| 水管理訓練 | 77.9~86.3 |
| 金属工業技術センター | 78.8~84.8 |
| 国立計量研究所 | 81.12~85.12 |
| 職業訓練指導員・上級技能者養成センター(ASEAN人造り) | 82.8~91.3 |
| マレイシア農科大学海洋水産学部 | 84.10~89.9 |
| 林産研究 | 85.4~90.3 |
| 国立電算機研修所 | 85.11~90.11 |
| アセアン家禽病研究訓練 | 86.4~93.4 |
| サバ州造林技術開発訓練 | 87.3~94.3 |
| ファインセラミックス研究 | 87.11~92.11 |
| 鋳造技術 | 88.10~93.10 |
| 放射線利用研究 | 89.7~94.7 |
| マレイシア農科大学バイオテクノロジー学科拡充 | 90.6~95.5 |
| サラワク総合病院救急医療 | 92.8~97.7 |
| 熱帯病研究 | 93.1~95.12 |
| サラワク木材有効利用研究計画 | 93.4~98.3 |
| 有害化学物質評価分析・産業廃棄物処理 | 93.9~97.9 |
| 貿易開発公社 | 94.7~99.6 |
| AIシステム開発ラボラトリ | 95.3~00.2 |
| 標準工業研究所・計量センター(II) | 96.3~00.2 |
| 未利用資源飼料化計画 | 97.3~02.3 |
| 日本マレイシア技術学院 | 98.1~02.1 |
| 化学物質リスク管理技術協力事業 | 98.4~02.3 |
| 水産資源・環境研究計画 | 98.5~03.5 |
(参考2)98年度実施開発調査案件
| 案件名 |
|---|
| サバ州石炭探査・評価調査(フェーズ2)(第1年次) |
| 総合都市排水改善計画調査(第1年次) |
| クアラルンプール都市交通環境改善計画調査(第3年次) |
| 省エネルギー促進計画調査(第2年次) |
| 交通官制データ整備調査(在外開発調査)(第1年次) |
| 交通官制データ整備調査(在外開発調査)(通信システム計画) |
| 半島マレイシア穀倉地域農業用水管理システム近代化計画調査(第3年次) |
| 総合都市排水改善計画事前調査(S/W協議)(都市排水施設) |
| 総合都市排水改善計画事前調査(S/W協議)(水文・水理/環境配慮) |
| 交通官制データ整備調査(在外開発調査)(交通管理計画)(第1年次) |
| クアラルンプール歩行者空間整備計画調査(在外開発調査)(第1年次) |
| 交通官制データ整備調査(在外開発調査)(通信システム計画) |
(参考3)98年度実施草の根無償資金協力案件
| 案件名 |
|---|
| サバ州洪水被害支援計画 |
| 起業家育成国際セミナープロジェクト |
| 音楽療法リハビリテーション計画 |
| ホスピスデイケアセンター整備計画 |
| 医療機器整備計画 |
| エイズ患者送迎車両購入計画 |
| 障害児用教材整備計画 |
| 障害児教育用教材拡充計画 |
| 障害児通学用車両導入計画 |
| マラッカ家族計画教育向上計画 |
| 環境教育機材制作計画 |
| 婦人援助協会視聴覚機器購入計画 |
| 障害者施設備品購入計画 |
| 自閉症児職業訓練計画 |
| セランゴール家族計画教育向上計画 |
| ペラ家族計画教育向上計画 |
(参考4)第7次マレイシア計画(1996年~2000年)
(イ) 目標
(1)経済を投資牽引型から生産性牽引型に転換
(2)労働節約型・技術・資本集約型産業への転換
(3)物価と対外バランスを安定させる持続的成長の堅持
(4)産業間の連関の強化と資本財・中間財の国内生産化による輸入削減と輸出拡大
(5)競争力のある産業の育成
(6)サービス産業等の新しい成長産業の育成
(7)科学技術、研究開発の振興(特に情報技術)
(8)民営化の推進
(9)環境や子光度保全にも配慮し持続的開発を目指す
(10)社会経済の安定、社会の再編成を図る
(11)社会のモラルや倫理の維持
(ロ) 主要経済指標の目標値
- 実質GNP成長率(平均):8.0%
- 経常収支:黒字に転換
- 雇用:完全雇用