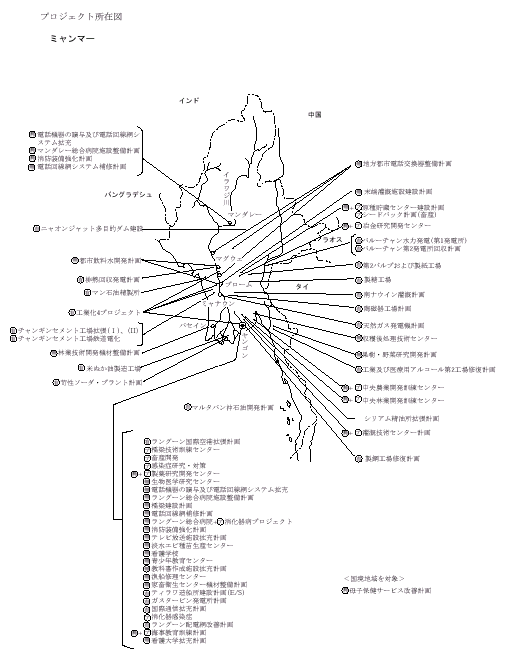国別援助実績
1991年~1998年の実績
[11]ミャンマー
(1) ミャンマーは48年に英連邦外の共和国として独立した。62年に国軍がクーデターで全権を掌握したが、88年ネ・ウィン体制下の一党支配による政治的閉鎖性及び経済困難に対する不満を背景とした全国規模での民主化要求デモが勃発した。国軍はこれを鎮圧するとともに、国家法律秩序回復評議会(SLORC)を設置し、自らを暫定政権と位置付け、総選挙実施後の政権委譲を公約した。90年5月に行われた総選挙の結果スー・チー女史率いる国民民主連盟(NLD)が8割以上の議席を獲得したが、SLORCは、選挙結果を無視して政権委譲を行わず、政権委譲までの手続きとして憲法の基本原則決定のための国民会議を断続的に開催している。
スー・チー女史は、89年に国家防御法違反で自宅軟禁措置となったが、95年の自宅軟禁解除後、支持者に対し政府批判の演説等を行ったため、政権側は96年9月以降、自宅敷地外での政治活動を制限した。NLDは95年11月国民会議をボイコットして以降、政府との対決的姿勢を次第に強め、98年8月にNLDが90年の選挙に基づく国会を独自で召集することを発表したことを受け、政権側は国会議員を含むNLD関係者を大量に拘束し、両者の対立が強まっている。その間、SLORCは97年11月、汚職閣僚の排除、国軍人事の若返り、対外イメージ改善等を狙い国家平和開発評議会(SPDC)に改組し大幅な国軍幹部の人事異動を実施した。
外交面では、ASEAN諸国、中国等、近隣諸国との関係緊密化に努めており、これら諸国との間で要人交流及び経済交流が活発化してきている。ASEAN等地域協力にも積極的であり、96年7月にはASEAN地域フォーラム(ARF)に新規参加したのに続き、97年7月には正式にASEANへの加盟を果たした。
ASEAN各国は、ミャンマーに対し、ミャンマーの人権状況改善や民主化を促すため、経済面を中心とした交流を進めていくとの「建設的関与政策」を推進している。また、中国とは経済援助等を通じての経済交流が盛んである。一方、88年以来欧米諸国との関係は冷却化しており、特に96年から97年にかけてのNLD党大会開催を巡り、ミャンマー政府が同党党員を一時的に大量拘束したことに対し、欧米諸国は強い懸念を表明したほか、米国は97年5月よりミャンマーに対する新規投資禁止措置を実施している。
国連は、98年秋以降、ミャンマー情勢の改善に向けた働きかけを強めており、10月にはデ・ソト事務次長補が国連事務総長の特使としてミャンマーを訪問し、キン・ニュン第一書記、スー・チー女史と会談している。
(参考1) 主要経済指標等
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
| 人口(千人) | 41,609 | 45,106 | 45,883 | 43,893 | |
| 名目GNP | 総額(百万ドル) | - | - | - | - |
| 一人当たり(ドル) | - | - | - | - | |
| 経常収支(百万ドル) | -431.3 | - | - | - | |
| 財政収支(百万チャット) | -7,789 | -24,924 | - | - | |
| 消費者物価指数 | 100.0 | 299.7 | 368.2 | 475.1 | |
| DSR(%) | 2.2 | 5.4 | 1.4 | 1.0 | |
| 対外債務残高(百万ドル) | 4,695 | 5,771 | 5,184 | 5,074 | |
| 為替レート(年平均、1米ドル=チャット) | 6.3386 | 5.6670 | 5.9176 | 6.2418 | |
| 分類(DAC/国連) | 後発開発途上国/LDC | ||||
| 面積(千平方キロメートル) | 657.6 | ||||
(参考2)主要社会開発指標
| - | 90年 | 最新年 | - | 90年 | 最新年 | |
|
出生時の平均余命(年) |
61 | 60(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
65 | 79(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下の人口割合(%) | - | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
88 | 131(97年) | ||
| 下位20%の所得又は消費割合(%) |
- |
- |
妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
460(80-90年平均) | 580(90-97年平均) | |
| 成人非識字率(%) | 19 | 17(95年) | 避妊法普及率 (15-49歳女性/%) |
5(80-90年平均) |
- |
|
| 初等教育純就学率(%) | - | - | 安全な水を享受しうる人口割合(%) | 33(80-90年平均) | 60(96年) | |
| 女子生徒比率(%) | 初等教育 | - | - | 森林面積 (1000平方キロメートル) |
289 | 272(95年) |
| 中等教育 | - | - | ||||
(2) 62年以降、農業を除く主要産業の国有化等社会主義経済政策を急速に進めたが、その閉鎖的経済政策等により外貨準備の枯渇、生産の停滞、対外債務の累積等経済困難が増大し、87年12月には国連より後発開発途上国(LLDC)の認定を受けるまでに至った。現政権はこのような経済困難に対し、88年9月の国軍による全権掌握後、四半世紀にわたる社会主義経済政策等を放棄し、外資法の制定、輸出入業務の自由化、タイや中国等との国境貿易の合法化などの市場経済開放政策を推進した。更に、様々な経済関連法や諸制度の整備に努めるとともに、経済インフラの整備、民間活力の導入、外国投資の誘致を図り、特に95年までの4年間のミャンマー経済は、順調な農業部門を背景に、年平均成長率7.5%を達成した。また、96年度からの新経済5か年計画においては年平均6%の成長を目標としている。
しかし、97年以降、主要輸出品である米の不作、インフラの未整備、外国投資の伸び悩み等により、外貨準備高の逼迫が表面化した。更に97年7月以降には、タイ・バーツの変動相場制移行と並行してチャットが短期間に急落したため、また、タイやマレイシアなどで働くミャンマー人労働者からの送金が減少したため、外貨証券(FEC)預金による外貨送金を月5万ドルに制限すると共に、不要不急の輸入に対する規制措置という緊急手段をとらざるを得ない状況にある。97年の経済成長率は4.6%に低下した。
(3) 我が国とミャンマーは、政府間のみならず国民各層における交流を通じ伝統的に友好関係にある。こうした伝統的な二国間関係を基本として、現政権に対し民主化及び人権状況の改善を促すべく粘り強く働きかけてきているが、最近では、97年8月に、高村外務政務次官(当時)が訪問したほか、同年12月のASEAN非公式首脳会議の機会には橋本総理大臣(当時)がタン・シュエ議長に民主化・人権状況の改善につき直接働きかけを実施している。
我が国との貿易額は、97年で、我が国からの輸出211百万ドル、我が国への輸入99百万ドルとなっている。96年7月の大阪・ヤンゴン直行便開設等により近年本邦企業関係者のミャンマー訪問は増加しているが、ミャンマーにおける我が国企業の投資は、諸外国と比較して低調で、98年8月末時点での対ミャンマー投資の累積認可額は、約2.2億ドルで第9位、全体の3.1%に過ぎない。
(1) ミャンマーは、我が国と緊密で良好な関係を有し、独立後一貫して親日国であること、及び同国の大きな開発ニーズを踏まえ、他の東南アジア諸国と並んで我が国援助の重点国の一つとして位置付けられていた。しかし、88年の政変以降は、一定の分野を除いてミャンマーへの経済協力は実質上停止されていた。
95年7月のスー・チー女史の自宅軟禁解除等に見られる事態の進展を受け、上記方針を一部見直し、同国の民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、既往継続案件や民衆に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心にケース・バイ・ケースで検討の上実施するとの方針に基づき協力が実施されている。
しかし、98年9月には、NLDによる独自の国会招集宣言に対し、ミャンマー政府がNLD関係者の大量拘束を行う等、膠着状態が続いている。国際社会は比較的冷静な反応を示している。現在、国連による仲介努力(「デ・ソト・アプローチ」:デ・ソト国連事務次長補によるミャンマー政府・NLD双方への働きかけ)が進んでいる。
(2) 98年度、我が国の対ミャンマー援助は、無償資金協力52.90億円(うち40億円は債務救済無償)、技術協力7.68億円の総額60.58億円である。
有償資金協力は、87年度以降は新規の供与を行っていない。但し、98年3月、既往案件である「ヤンゴン国際空港拡張計画」につき、その後の同空港の利用状況の急増及び施設の著しい老朽化から、同空港の安全維持のためには緊急な対応が必要と判断し、安全面に絞った必要最低限の応急措置を決定(約25億円の貸付の実行)している。
無償資金協力については、98年7月、国連薬物統制計画との連携も踏まえつつ、麻薬代替作物栽培支援のための食糧増産援助(8億円、肥料・農機供与)を行い、99年3月には乳幼児死亡率と妊産婦死亡率の低減を目的とする「母子保健サービス改善計画(子供の健康無償)」(3.30億円、ユニセフ経由)を実施したほか、保健医療や水供給分野を中心に草の根無償資金協力を27件実施した。
技術協力においては、BHN、民主化、経済開放化に資する協力を中心に実施している。ミャンマー山岳地におけるケシ栽培に従事する少数民族の生活改善と麻薬関係作物の転作のための「蕎麦栽培プロジェクト」として短期・長期専門家派遣、また、市場経済化及びBHN分野を中心とした本邦研修員受入、ポリオ等のワクチン供与の他、母子の健康対策特別機材の供与等を行ったほか、農業分野でのプロジェクg方式技術協力を実施している。
| (1) 我が国のODA実績 |
| (支出純額、単位:百万ドル) |
| 年 | 贈与 | 政府貸付 | 合計 | |||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 95 96 97 98 |
99.95(75) 139.27(-) 101.98(-) 55.14(-) 47.01(-) |
7.37(6) 12.16(-) 9.87(-) 9.28(-) 11.01(-) |
107.32(80) 151.42(-) 111.85(-) 64.42(-) 58.02(-) |
26.49 15.96 6.05 - 3.90 |
26.49(20) -37.19(-) -76.65(-) -49.59(-) -41.94(-) |
133.82(100) 114.23(100) 35.19(100) 14.83(100) 16.09(100) |
| 累計 | 1,177.54(45) | 155.51(6) | 1,333.00(51) | 1,669.07 | 1,296.59(49) | 2,629.58(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
(2) DAC諸国・国際機関のODA実績(97年支出純額、単位:百万ドル)
| DAC諸国、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
日本 114.2 日本 35.2 日本 14.8 |
フランス 4.3 フランス 2.1 フランス 1.9 |
オランダ 2.0 オランダ 1.8 豪州 1.7 |
豪州 1.9 ドイツ 1.5 ノールウェー 1.6 |
ドイツ 1.3 豪州 1.5 ドイツ 1.4 |
114.2 35.2 14.8 |
126.3 45.3 23.6 |
| 国際機関、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
UNDP 14.3 UNHCR 9.6 UNDP 14.0 |
UNDP 14.3 UNHCR 9.6 UNDP 14.0 |
UNTA
7.9 UNDP 5.8 UNHCR 7.9 |
UNICEF
6.9 UNTA 2.8 UNTA 4.2 |
CEC
2.3 UNFPA 1.0 CEC 2.7 |
-17.4 -16.3 -15.5 |
25.6 10.9 21.7 |
| (3) 年度別・形態別実績 |
| (単位:億円) |
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 | ||
| 90年度までの累計 |
4,029.72億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
975.94億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
150.97億円
|
||
| 91 |
なし |
50.00億円
債務救済 (30.00) |
3.87億円
|
||
| 92 | なし |
40.00億円
債務救済 (20.00) |
4.08億円
|
||
| 93 |
なし |
62.18億円
債務救済 (20.00) |
3.24億円
|
||
| 94 | なし |
130.42億円
食糧増産援助 (10.00) |
3.98億円
|
||
| 95 | なし |
158.99億円
看護大学拡充計画 (16.25) |
5.99億円
|
||
| 96 |
なし |
80.97億円
債務救済 (40.00) |
4.93億円
|
||
| 97 | なし |
41.22億円
債務救済 (20.00) |
6.33億円
|
||
| 98 |
なし |
52.92億円
債務救済 (20.00) |
7.68億円
|
||
| 98年度までの累計 |
4,054.72億円 |
1,592.60億円 |
191.09億円
|
(注)1.「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
2.「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
3.68年度から90年度までの有償資金協力及び無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-11.htm)
(参考1) 98年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件
| 案件名 | 協力期間 |
|
ウィルス研究所 |
67.7~73.3 |
(参考2)98年度実施草の根無償資金協力案件
| 案件名 |
|
小学校を対象とした巡回歯科診療サービス計画 ヤンゴン視覚障害者教育センター建設計画 パコック総合病院医療機材整備計画 メッティーラ病院母子保健促進計画 マンダレー伝統医療病院医療機材整備計画 ファラムタウン上水供給計画 全ての子どもたちに基礎教育の機会を提供するための学校支援プロジェクト インレー湖流域環境共生型農林業訓練センター建設計画 感染症病院医療機材整備計画 マンダレー看護大学教育機材整備計画 学校中退少女のための訓練センター改善計画 ライバン村小規模水力発電計画 ミャンマー外国語大学日本語教育機材整備計画 フラインタヤ第28小学校建設計画 ダゴンミョーティ南第8小学校建設計画 ダゴンミョーティ北第29小学校建設計画 シュエピータ・ミョーティ第14小学校建設計画 シュエピータ・ミョーティ第36小学校建設計画 フラインタヤ第21小学校建設計画 フラインタヤ第40小学校建設計画 タゴンミョーティ南第6小学校建設計画 タゴンミョーティ北第30小学校建設計画 トンガ村タゴンミョーティニュータウンシップ南小学校建設計画 遠隔地の学生のための寄宿舎建設計画 医薬機材及び医薬品援助プロジェクト シャン州におけるエイズ及び性病予防計画 視覚障害者学校施設改善計画 |
プロジェクト所在図