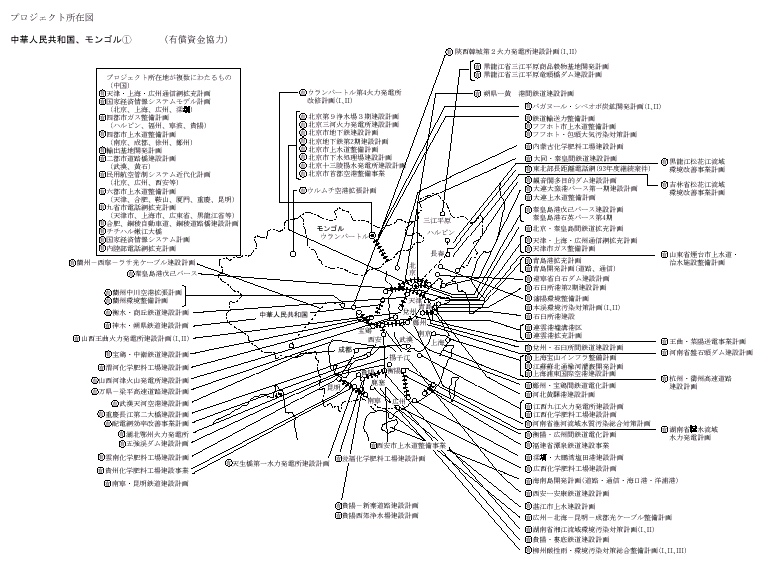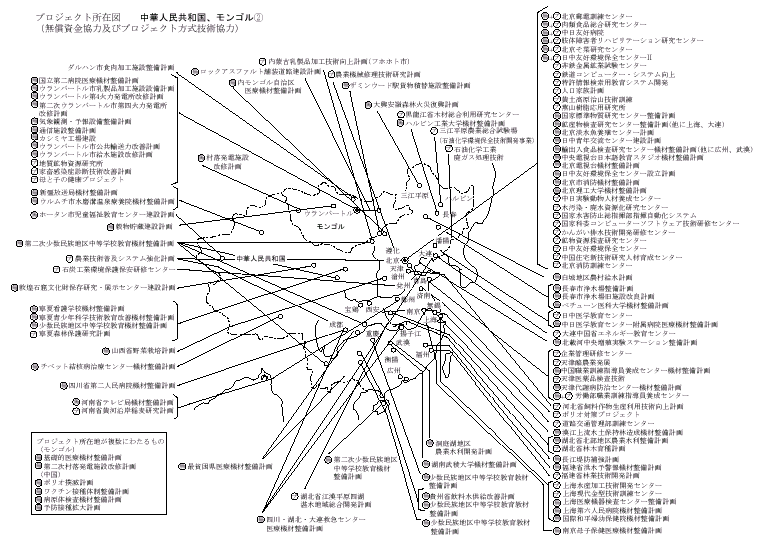国別援助実績
1991年~1998年の実績
[12]モンゴル
(1) モンゴルは、従来旧ソ連、東側諸国の支援の下に国家建設を進めていたが、90年以降は、市場経済体制への以降に努め、所有制の改革、価格の自由化等の経済改革を進め、西側諸国との関係を強めている。
(2) 政治体制は、長らく人民改革党による一党独裁であったが、90年以降、国家元首としての大統領制、複数政党制の採用、自由選挙の実施等民主化が急速に進展した。96年の総選挙では民主連合が過半数を占め、首相に選出されたエンフサイハン民主連合議長は、大胆な行政機関の統廃合、公共料金の大幅引き上げ、国有企業の民営化、自由貿易政策の徹底といった諸改革を実施した。97年5月の大統領選挙では、政府と大統領の関係にバランスを求める国民が、野党人民革命党のバガバンディ党首を選出した。
98年にはこれまで前例がない内閣総辞職が二度にわたって行われた。一度目は、議院内閣制の趣旨に沿って議員は閣僚になり得るとする1月の法改正によって、非議員から構成されていたエンフサイハン内閣が4月に総辞職したものである。二度目は、次のエルベグドルジ内閣が銀行政策の失敗から内閣不信任案を可決され、7月に総辞職したものである。
その後、新首相候補に対する議会の否決が続き、12月に、ナランツァツラルト・ウランバートル市長が首相に選出されたが、モンゴル・ロシア合弁鉱山企業のロシア側持ち株分の民営化問題で99年7月に総辞職するとアマルジャルガル元対外関係大臣が新首相に進出された。
(3) 経済面では、主要輸出産品である銅及びカシミアの国際市場の価格の下落のため96年のGDP成長率は2.6%、97年のGDP成長率は3.3%にとどまった。また、経済インフラの未整備、明確な産業振興策や経営管理ノウハウの不足、増大する対外債務、銀行の多額な不良債権、偏った産業構造など今後解決すべき問題は多い。98年の経済は、GDP成長率3.5%を記録し、インフレ率が96年の20.5%から6.0%に低下し、マクロ面での改善がみられた。
(参考1)主要経済指標等
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
| 人口(千人) | 2,124 | 2,461 | 2,516 | 2,542 | |
| 名目GNP | 総額(百万ドル) | - | 767 | 902 | 998 |
| 一人当たり(ドル) | - | 310 | 360 | 390 | |
| 経常収支(百万ドル) | -639.5 | 38.9 | - | - | |
| 財政収支(百万トゥグリク) | -1,449 | -14,921 | -353,379 | - | |
| 消費者物価指数(90年=100) | 100.0 | 4,733.6 | 5,725.0 | - | |
| DSR(%) | - | 9.1 | 9.9 | 11.7 | |
| 対外債務残高(百万ドル) | - | 512.4 | 524.4 | 717.9 | |
| 為替レート(年平均、IUSドル=トゥグリク) | - | 448.61 | 548.40 | 789.99 | |
| 分類(DAC/国連) | 低中所得国/- | ||||
| 面積(千平方キロメートル) | 1566.5 | ||||
(参考2)主要社会開発指標
| - | 90年 | 最新年 | - | 90年 | 最新年 | |
| 出生時の平均余命(年) | 63 | 66(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
64 | 52(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下の人口割合(%) | - | - | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
84 | 68(97年) | |
| 下位20%の所得又は消費割合(%) | 7.3(95年) | 7.3(95年) | 妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
140(80-90年平均) | 65(90-97年平均) | |
| 成人非識字率(%) | - | 17(95年) | 避妊法普及率 (15-49歳女性/%) |
- | - | |
| 初等教育純就学率(%) | - | 81(96年) | 安全な水を享受しうる人口割合(%) | 65(88-90年平均) | 54(96年) | |
| 女子生徒比率(%) | 初等教育 | - | 51(96年) | 森林面積 (1000平方キロメートル) |
139 | 94(95年) |
| 中等教育 | - | 57(96年) | ||||
(4) 民主化以降モンゴルと我が国との関係は急速に強まっている。98年5月には、モンゴル元首として始めて、バガバンディ大統領が公式訪日した。同大統領と橋本総理(当時)との会見後、日本、モンゴル両国政府は、1)総合的パートナーシップ確立の目標の再確認とモンゴルの民主化、改革への日本の継続支援、2)投資保護協定締結の必要性についての検討、3)文化ミッションの派遣、4)日本側による今後3年間で500名の青年受け入れ、5)環境調査団の派遣などの内容を盛り込んだ「友好と協力に関する共同声明」を発表した。99年には、3月にゴンチグドルジ国家大会議議長が、5月にはトヤー対外関係大臣が訪日している。7月には小渕総理大臣がモンゴルを訪問し、円借款及び無償ベースの協力により約160億円程度の支援を行う旨を表明した。
(5) 97年のモンゴルとの貿易は、モンゴルへの輸出が約61億円、モンゴルからの輸入が約81億円である。モンゴルからの主要輸入品は、金、銅、繊維材料(カシミア原毛他)である。モンゴルへの輸出品目は、機械・機器が大部分を占めている。ウランバートル市内に事務所を開設する邦人企業も増加傾向にあり、モンゴルの市場経済への移行を背景に、民間の経済活動も新たな段階を迎えている。
(1) 我が国は、以下の点を踏まえて、ODA大綱に則りモンゴルへの援助を実施することとしている。
(イ) 90年以降、モンゴルが民主化及び市場経済化に向けた改革を進めていること。
(ロ) モンゴルの安定と経済発展は、周辺地域における政治的・経済的安定にとって重要なものであること。
(ハ) 内陸国であるとともに、市場経済への経済体制の移行期にあり、経済基盤の未整備、貧富の差の拡大等の課題があることから、援助需要が大きいこと。
(2) モンゴルにおける開発の現状と課題等を踏まえ、我が国は97年3月に経済協力総合調査団をモンゴルに派遣し、モンゴルの経済・社会開発計画等を踏まえ、重点分野の選定及び各重点分野における我が国の中長期的な対モンゴル援助方針について協議を行った。
こうした、政策対話等を踏まえ、我が国は以下の分野を援助の重点分野としている。
(イ) 産業振興のための経済基盤及び条件整備(エネルギー、運輸、通信等のインフラの本格的リハビリ)
(a)エネルギー
現有施設のエネルギー供給の回復を図るためのリハビリテーションへの協力、発電所の安定操業、炭坑の生産性向上や経営改革、構造改善等に資する協力。
(b) 運輸
鉄道については鉄道路線、設備の充実等への協力、道路については幹線道路整備等既存施設の改修、主要都市の公共交通サービスの改善等への協力。その際には十分な大気汚染防止策を図る。
(c)通信
通信網整備への協力、通信網を支える人材育成のための専門家派遣・研修員受入等の協力。
(ロ) 市場経済移行のための知的支援、人材育成
経済政策及び法・行財政改革への知的支援に向けた、専門家派遣、研修員受入等の協力。
(ハ) 農業・牧畜業振興
長期的農業計画の策定、協同組合の運営体制・農畜産物流通体制の整備に関する協力及び農業技術の開発・普及等に関連する協力。
(ニ) 基礎生活支援(教育、保健・医療、水供給)
(a)教育
教育施設改善及び教員能力向上等の充実に向けた協力。高等教育の質の向上及び基礎的な職業教育への協力。
(b)保健・医療
基礎的医療機材整備、医師・看護婦の再訓練及び育成の実施に資する援助、母子保健への協力。将来的な医療体制の整備への協力。
(c)水供給
既存施設整備、拡充及び水質改善の推進による水供給の安定化への協力。
(3) 我が国は91年から7回にわたり、世銀との共同議長の下、「モンゴル支援国会合」を主催し、対モンゴル支援の国際的枠組み構築に努めている。
97年10月には、20ヶ国、6国際機関が参加して第6回会合が開催され、参加ドナーから計2億5,000万ドルの支援表明がなされた。99年6月には、25か国、12国際機関が参加して第7回会合が、初めてウランバートルで開催され、参加ドナーから計3億2,000万ドルの支援表明がなされた。
(4) 我が国の援助は、89年度までは、技術協力として研修員受入、専門家派遣、機材供与、また、資金協力として教育、広報用の機器を中心とした文化無償援助にとどまっていたが、モンゴルの民主化の進展を受けて、90年度以後両国の経済協力関係に大きな進展が見られた。一方でモンゴル側においても実施体制の強化等の援助吸収能力の一層の向上が重要である。
有償資金協力としては、91、92年度に商品借款を供与したのに引き続き、93年度以降プロジェクト借款を供与している。
無償資金協力は、90年度からの一般無償援助の再開、91年度からのノンプロジェクト無償の実施等、大幅に拡充された。
技術協力においては、研修員受入れ枠の拡大等全般的に拡充されるとともに、青年海外協力隊の派遣取極めが締結され(92年4月より派遣開始)、93年度からはプロジェクト方式技術協力が実施されている。また、99年7月小渕総理がモンゴルを訪問した際、シニア海外ボランティア派遣の文書に署名した。
開発調査は98年度は6件が実施された。
(5) モンゴルは、従来主要援助国であった旧ソ連、東欧諸国からの援助が、90年以後各国の経済情勢の悪化を反映して激減するのに対し、西側諸国との関係を緊密化させるとともに、91年にADB、IMF、世界銀行にそれぞれ加盟した。
| (1) 我が国のODA実績 |
| (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 贈与 | 政府貸与 | 合計 | |||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 95 96 97 98 |
45.71(64) 54.95(55) 48.91(47) 46.10(59) 38.22(41) |
23.04(32) 30.18(30) 24.78(24) 19.18(25) 21.30(23) |
68.75(97) 85.13(85) 73.70(71) 65.28(84) 59.51(63) |
2.33 14.80 30.05 12.70 34.48 |
2.33(3) 14.80(15) 30.05(29) 12.70(16) 34.48(37) |
71.08(100) 99.93(100) 103.75(100) 77.98(100) 93.99(100) |
| 累計 | 299.57(50) | 148.67(25) | 448.25(75) | 6,931.60 | 4,953.76(65) | 601.39(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
(2) DAC諸国・国際機関のODA実績(支出純額、単位:百万ドル)
| DAC諸国、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | 合計 |
| 95 96 97 |
日本 99.9 日本 103.8 日本 78.0 |
ドイツ 11.8 ドイツ 11.8 ドイツ 14.0 |
デンマーク 5.7 米国 6.0 米国 12.0 |
オランダ 3.9 デンマーク 3.5 デンマーク 6.6 |
英国 1.5 ノールウェー 3.0 オランダ 1.8 |
99.9 103.8 78.0 |
126.9 136.2 118.1 |
| 国際機関、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
ADB 55.8 ADB 34.8 ADB 67.4 |
IDA 8.4 IDA 11.0 IDA 33.8 |
CEC 5.0 IMF 8.1 IMF 7.7 |
UNDP 3.9 UNDP 3.2 UNDP 5.2 |
UNTA 3.9 CEC 3.0 CEC 3.2 |
4.0 4.5 11.3 |
80.9 64.6 128.6 |
(3) 年度別・形態別実績
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 |
| 90年度までの累計 | なし | 56.04億円
内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照 |
4.66億円
研修員受入 80人 |
| 91 | 48.36億円
商品借款 (48.36) |
33.08億円
社会福祉計画 (1.00) |
4.02億円
研修員受入 34人 |
| 92 | 24.59億円
商品借款 (24.59) |
39.08億円
通信施設整備計画(2/2期) (5.62) |
6.81億円
研修員受入 59人 |
| 93 | 33.21億円
鉄道輸送力整備計画 (33.21) |
45.35億円
災害援助(豪雪被害) (10万ドル=0.12) |
18.10億円
研修員受入 73人 |
| 94 | 47.53億円
鉄道輸送力整備計画(第2期) (47.53) |
59.05億円
食糧援助 (3.00) |
22.72億円
研修員受入 76人 |
| 95 | 44.93円
ウランバートル第4火力発電所改修 (44.93) |
58.25億円
ロックアスファルト舗装道路建設計画(国債1/3) (11.83) |
23.37億円
研修員受入 99人 |
| 96 | 58.27億円
バガヌール・シベオボ炭鉱開発計画 (58.27) |
48.03億円
食糧増産援助 (2.50) |
18.13億円
研修員受入 107人 |
| 97 | 42.98億円
モンゴル炭鉱総合開発計画2 (42.98) |
50.46億円
ロックアスファルト舗装道路建設計画(国債3/3期) (2.41) |
19.33億円
研修員受入 91人 |
| 98 | なし | 52.75億円
ウランバートル市給水施設改修計画(国債2/2) (10.80) |
24.65億円
研修員受入 112人 |
| 98年度までの累計 | 299.87億円 | 442.09億円 |
141.79億円
研修員受入 731人 |
| (注) | 1. | 「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。) |
| 2. | 「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。 | |
| 3. | 77年度から90年度までの無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-12.htm) |
|
(参考1)98年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件
| 案件名 | 協力期間 |
|
地質鉱物資源研究所 家畜感染症診断技術改善計画 母と子の健康 |
94.3~99.3 97.7~02.6 97.10~02.9 |
(参考2)98年度実施開発調査案件
| 案件名 |
|
市場経済化支援調査(第1年次) アルタイ市地下水開発計画調査(第3年次) 観光開発計画調査(第2年次) 工業開発計画調査 ウランバートル市道路整備計画調査(第2年次) 再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査(第1年次) 再生可能エネルギー利用地方電力供給計画予備調査 アルタイ市地下水開発計画調査 |
(参考3)98年度実施草の根無償資金協力案件
| 案件名 |
|
歴史・伝統文化教育強化計画 ウムヌゴビ県医療施設通信網改善計画 ウランバートル市第63特殊学校職業訓練強化計画 スフバータル県第一10年制学校改修計画 貧困家庭に対する農業指導強化計画 極貧層子女に対する個別教育計画 モンゴル・グローブ計画 中小企業研修センター強化計画 セレンゲ県職業訓練強化計画 ドルノゴビ県障害者向け職業訓練強化計画 医療器材輸送支援計画 バヤンウルギー県デルーン村水供給計画 ザブハン県水供給改善計画 |