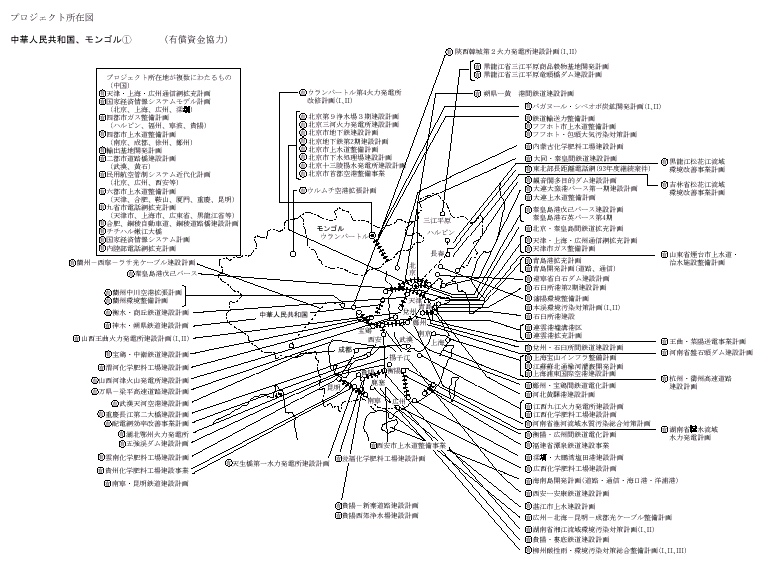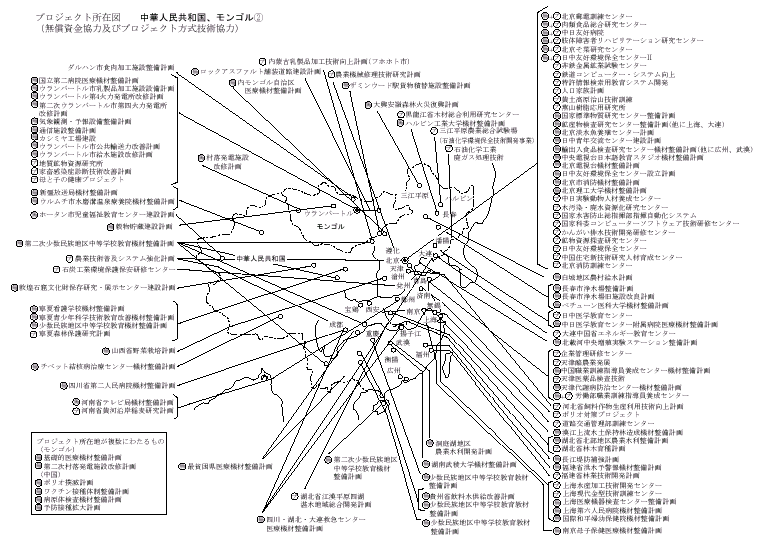国別援助実績
1991年~1998年の実績
[7]中国
(1) 中国は、世界一の人口、アジア第一の国土面積を擁し、56の民族(うち漢民族が92%を占める)を有する多民族国家である。
(2) 中国は、78年の中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議(11期三中全会)以降、近代化建設を最優先課題として位置付け、改革・開放政策を進めている。92年1~2月の鄧小平氏の南方視察における重要講話を契機として改革・開放政策が加速化され、同年10月の第14回党大会では「社会主義市場経済」という新たな概念が提起され、93年3月の全国人民代表大会ではこれが憲法に盛り込まれるなど、中国経済の「市場経済化」の方向が定着した。92年以降は経済の過熱傾向が生じ、急成長に伴う格差も拡大したため、94年から引き締め基調の経済運営が行われ、96年には、一定の経済成長を維持しつつ(GDP成長率は9.7%)、インフレ抑制で成果をあげた(小売物価上昇率は95年の14.5%から6.1%に低下)。一方、国民一人当りのGNPは約860ドル(97年世界銀行統計)と依然として低いレベルにあり、また、国有企業の不振、農村の停滞と地域間格差の拡大などは依然として問題となっている。
96年3月には、国民経済・社会発展のための第9次5カ年計画及び2010年までの長期計画が策定され、2000年までに国民一人当たりのGNPを80年の4倍とし、2010年にGNPを更に倍増させるという目標を掲げるとともに、経済の安定とバランスを重視し、量より質に重点を置き、持続可能な経済成長を提唱している。
98年3月には、江沢民国家主席が再選されるとともに、李鵬全人代常務委員長、朱鎔基総理らの指導部を選出、国有企業改革、金融体制改革、行政機構改革の三大改革に積極的に取り組んでいる。
97年に発生したアジア通貨危機の直接的な影響は、管理フロート制為替制度と資本取引の制限のために限られたものであったが、98年は、輸出及び海外直接投資の低迷、7~8月の洪水災害の影響等により、実質成長率は7.8%にとどまった。なお、中国側は、人民元の切り下げは行わないとの方針を累次言明している。中国政府によると、99年度の経済成長率の見通しは7%前後とされているが、デフレ傾向が顕在化しており、引き続き貿易収支の動向、国有企業改革、失業問題、不良債権問題等の帰趨が注目されている。
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
| 人口(千人) | 1,133,696 | 1,200,241 | 1,215,414 | 1,227,177 | |
|
名目GNP |
総額(百万ドル) | 415,884 | 744,890 | 906,079 | 1,055,372 |
| 一人当たり(ドル) | 370 | 620 | 750 | 860 | |
| 経常収支(百万ドル) | 11,997 | 1,618 | 7,243 | 29,718 | |
| 財政収支(十億元) | -14.65 | -58.15 | -54.78 | -57.00 | |
| 消費者物価指数(90年=100) | 100.0 | 183.9 | 196.0 | 197.6 | |
| DSR(%) | 11.7 | 9.9 | 8.7 | 8.6 | |
| 対外債務残高(百万ドル) | 55,301 | 118,090 | 128,817 | 146,697 | |
| 為替レート(年平均、164ドル=元) | 4.7832 | 8.3514 | 8.3142 | 8.2898 | |
| 分類(DAC/国連) | 低所得国/- | ||||
| 面積(千平方キロメートル) | 9326.4 | ||||
(参考2)主要社会開発指標
|
- |
90年 | 最新年 | 90年 | 最新年 | ||
| 出生時の平均余命 (年) |
70 | 70(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
30 | 32(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下の 人口割合(%) | 22.2(95年) | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
42 | 39(97年) | ||
| 下位20%の所得又は 消費割合(%) | 6.0(90年) | 5.5(95年) | 妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
95(80-90年平均) | 95(90-97年平均) | |
| 成人非識字率(%) | 27 | 18(95年) | 避妊法普及率 (15-49歳女性/%) |
49(80-90年平均) | 85(90-98年平均) | |
| 初等教育純就学率 (%) |
100 | 102(96年) | 安全な水を享受しうる 人口割合(%) | 74(88-90年平均) | 83(96年) | |
| 女子生徒比率 (%) |
初等教育 | 46 | 47(96年) | 森林面積 (1000平方キロメートル) |
1,247 | 1,333(95年) |
| 中等教育 | 42 | 44(96年) | ||||
(3)外交面では、最優先課題たる国内経済建設に邁進するため、良好な国際環境を希求し、「全方位外交」を展開してきている。特に98年から首脳レベルにおける近隣諸国との往来が活発化している。
我が国との関係では、72年の国交正常化以降、基本的に順調に発展しており、人的、経済的文化交流が飛躍的に増加している。日中国交正常化25周年であった97年に両国総理の相互訪問が実現したのに続き、日中平和友好条約締結20周年であった98年には江沢民国家主席が国家元首として初めて訪日した。その際に日中共同宣言が出され、平和と発展のための友好協力パートナーシップを確立し、日中間の33項目具体的協力項目につき共同プレス発表が発出された。99年7月には小渕総理が訪中し、2000年の朱鎔基総理の訪日、21世紀に向けた日中協力を着実に進めていくことで一致した。
(4)日中経済関係は72年の国交正常化以降着実に発展し、相互依存関係が一層進展している。例えば、72年に輸出入合計約11億ドルにすぎなかった日中貿易総額は、98年には約572億ドルと約51倍の伸びを示しており、我が国の貿易相手国として中国は米国に次いで第2位、中国にとって我が国は第1位となっている。日中間の貿易構造は、従来の主として我が国から製品を、中国から原料をそれぞれ輸出するという垂直的な関係から、我が国の対中投資の増加等に伴い、近年は中国からの製品輸入が増大することにより、水平的な関係へと変化している。また、我が国からの対中直接投資は、中国の投資環境の改善や円高の進行等に伴い84年頃から本格化し、従来は労働コストの低下を目的とする委託加工輸出型が多かったが、近年は中国国内市場の開拓を目的とするものにシフトしている。
(1)我が国は、79年の大平総理(当時)訪中の際、中国の近代化努力に対して我が国としてできる限りの協力をすることを表明して以来、積極的に経済協力を促進してきており、中国は我が国援助の最重点国の一つに位置付けられている。
現在、我が国は、以下の点を踏まえて、中国への援助を実施することを基本的立場としている。
(イ)中国は、我が国と地理的に隣接し、政治的、歴史的、文化的に密接な関係にある
(ロ)我が国と中国との安定した友好関係の維持・発展が、アジアひいては世界の平和と安定につながる
(ハ)経済関係において、二国間政府ベースの経済・技術協力、民間の投資・貿易、資源開発協力などを含む幅広い分野にわたってその深さと広がりを増して発展してきている
(ニ)経済の近代化を最優先課題として位置付け、経済改革及び対外開放政策を進めている
(ホ)広大な国土面積と多数の人口を有し、一人当たりGNPが860ドル(97年)と低く、援助需要が高い
(2)89年1月、JICA国際協力総合研修所に「中国国別援助研究会」(座長:大来外務省顧問(元外務大臣))を設置し、広く各界の専門家、研究者、その他有識者の参加を得て、対中国援助のあり方について検討を進めた。
この成果を踏まえて、92年3月に我が国は、大来外務省顧問を団長とする経済協力総合調査団を中国に派遣し、中長期的経済協力のあり方について意見交換を行った。一連の協議において、当方からは、対中経済協力国別援助方針(重点地域、重点分野等)についての基本的考え方を伝えるとともに、今後の協力実施上の課題として、中国側関係機関間の調整の強化、環境配慮の強化、我が国の経済協力の中国側における広報努力等の問題を提起し、基本的に中国側と意見の一致をみた。また、我が国のODA4指針(現在のODA大綱の「原則」第3、第4)についても言及し、中国側の理解を求めた。
(3)我が国は、中国における開発の現状と課題、開発計画等に関する調査・研究及び前述の経済協力総合調査団及びその後の中国側との政策対話を踏まえ、対中国援助方針として以下を重点項目としている。
(イ)重点地域
有償資金協力を中心に、経済インフラ整備に資する協力を行うとともに、中国のバランスのとれた発展を支援するとの観点から、相対的に開発余地の大きい内陸地域にこれまで以上に配慮し、農業・農村開発への協力、豊富な資源を活用した開発への協力を進める。また、無償資金協力及び技術協力については内陸部を重視することとし、主として貧困地域に対する基礎生活分野の充足のための協力を実施。
(ロ)重点分野
(a)環境
我が国の経験と技術を活かして、省エネルギー、廃棄物リサイクル、煤煙処理、排煙脱硫等の大気汚染防止、下水道等の水質汚濁防止対策について、中国側のニーズを踏まえつつ援助を進める。また、96年5月、無償資金協力により設立した日中友好環境保全センターを核に各種協力を展開。
(b)農業
農業生産、特に食糧の安定的供給の確保へ向けた一層の農業生産性の向上を図ることが必要である。肥料、農業用資材供与、試験研究機関の充実を通じた農業技術の水準向上及び農村への技術の普及への援助等を実施する。
(c)経済インフラ
中国の経済発展のボトルネックとなっている運輸、通信、電力等の経済インフラの整備の遅れの解消に向け援助を行う。
1)運輸・交通施設建設による輸送能力の増大、輸送の効率化のための維持・管理技術の向上に資する援助を行う。
2)エネルギー絶対的な供給不足に対応するための発電所建設に対する援助を行う。その際に、十分な大気汚染防止対策を図る。
3)通信通信基盤の整備に資する協力、維持・管理面を考慮した人材養成への援助を行う。
(d)保健・医療
農村地域等では、依然として保健・医療水準の底上げが必要である。地域格差是正の観点から、農村地域等におけるプライマリー・ヘルス・ケアや予防保健事業への波及を念頭に置いた地域保健・医療水準の向上に資する協力を行う。
(e)人造り
教育用機材の供与や学校施設の建設への協力等による基礎教育の普及・充実。機材供与、研修員受入、専門家派遣等による中堅技術者・管理者の養成等に資する人造りへの協力
(4)我が国の対中経済協力は、ODA大綱の「原則」を踏まえ実施されている。まず、市場指向型経済移行努力の観点からは、経済の改革・開放路線を積極的に進め、「社会主義市場経済」を確立するとの方針が憲法に明記される等、好ましい動きが継続している。他方、国防費の増加傾向、武器の輸出入の動向等については内外で懸念が示されている。我が国としてはこうした状況も踏まえ、我が国のODA大綱に関する考え方を、種々の機会を通じて中国側に伝え理解を促すとともに、軍事面での透明性を高める努力を求めてきている。こうした中で、中国も95年11月「中国の軍備管理・軍縮」と題する白書を発表するなど透明性を高めるための一定の措置をとっていることは注目される。
95年8月、我が国は中国の核実験停止が明らかにならない限り、新規の対中無償資金協力を原則として凍結するとの措置をとったが、96年7月より中国が核実験のモラトリアムを実施していること等を踏まえ、97年3月より無償資金協力を再開している。
(5)93年以降ほぼ毎年中国は我が国二国間ODAの最大の受取国となっている(支出純額ベース、96年は第2位)また、中国にとり我が国がDAC諸国中最大の援助国である(97年実績。シェアは47%)。
(6)有償資金協力については、98年12月に第4次円借款後2年(1999~2000年度)分の28案件に対する計3,900億円を目途とした供与につき合意した。そのうち、環境分野が16件、農業分野が4件を占めることに示されるように、これらの分野への協力を引き続き重視するとともに、民間資金導入の期待が薄い内陸部の案件(18件)に配慮している。
無償資金協力においては、農業、医療、環境、人造りを中心に協力を実施しており、80年度以降「日中友好病院建設計画」(160億円)、「日中青年交流センター建設計画」(101.1億円)「日中友好環境保全センター設立計画」(102.56億円)等を実施してきた。
技術協力においては、98年度も農業、工業、経営管理、保健医療等の広範な分野で研修員の受入れや専門家の派遣が行われている。また、プロジェクト方式技術協力も実施されている。更に、開発調査も78年度より実施されている。
(7)環境分野への協力では、我が国としては、政策対話を通じて中国側の一層の自助努力を促すとともに、その努力を支援するため、環境分野を協力の重点分野と位置付け、さらに案件実施の際の環境配慮を十分に行ってきている(98年度の対中円借款供与額2,066億円のうち金額ベースで約35%が環境案件)。
一方、中国の極めて広い国土と人口及び我が国協力の限界を考慮すると、我が国協力が中国全土の環境対策に直接関与していくことは、我が国としては、日中友好環境保全センターなどの拠点を中心とした協力を通じ、環境関連技術・施設の中国側努力による全国的な普及を側面的に支援していくこととしている。
日中友好環境保全センターは、環境保全に係る人材育成及び中国の環境改善に即効性のある公害防止技術の研究を目的とするもので、施設整備に対して無償資金協力を実施してきているほか、プロジェクト方式技術協力として、中国側が実施する同センターの研究活動、技術者の養成訓練に対して技術的側面からも協力している。
96年5月には日中友好環境保全センターの開所式が行われたほか、日中双方より中央政府、地方自治体、民間団体からの参加を得て「日中環境協力総合フォーラム」の第1回会合が行われ、特に早急な対応が必要と考えられる大気汚染・酸性雨及び水質汚濁の問題を含む広範囲にわたる問題を重点的に議論した。
更に、97年9月の橋本総理(当時)訪中時には、1)中国内に環境対策のモデル都市を定め、大気汚染・酸性雨対策、循環型産業・社会システムの形成、温暖化対策を実施する「日中環境開発モデル都市構想」、2)中国における環境情報の収集・把握を図るため中国国内100都市にコンピューターを整備する「環境情報ネットワーク整備」、という2つの柱からなる「21世紀に向けた日中環境協力」構想を提案し、中国側より基本的な合意を得た。
このうち、「日中環境開発モデル都市構想」については、具体的な検討のために日中双方に専門家委員会(日本側座長:渡辺利夫東京工業大学大学院教授、中国側座長:王揚祖元国家環境保護局副局長)を設立、大連、重慶、貴陽の3都市をモデル都市とすることとし、具体的な協力の在り方について検討を行い、99年4月に開催された専門家委員会第3回合同会合において、各都市における環境対策のあり方及び具体的なプロジェクトに関する提言がなされている。
(8)中国経済の急成長に伴い地域間格差が拡大しており、96年3月に策定された国民経済・社会発展のための第9次5か年計画及び2010年までの長期計画において、地域格差の是正が主要課題の一つとして取り上げられた。
我が国の対中援助の実施にあたっては、第4次円借款後2年分で内陸案件を18件とり上げる等地域配分にも留意しているが、今後とも地域格差是正に資する援助を一層重視する必要がある。
(1)我が国のODA実績
| 暦年 | 贈与 | 政府貸付 | 合計 | |||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 95 96 97 98 |
99.42(7) 83.12(6) 24.99(3) 15.42(3) 38.22(3) |
246.91(17) 304.75(22) 303.73(35) 251.77(44) 301.62(26) |
346.34(23) 387.87(28) 328.72(38) 267.19(46) 339.83(29) |
1,298.46 1,216.08 774.08 556.75 1,083.60 |
1,133.08(77) 992.28(72) 533.01(62) 309.66(54) 818.33(71) |
1,479.41(100) 1,380.15(100) 861.73(100) 576.86(100) 1,158.16(100) |
| 累計 | 756.13(6) | 2,596.12(20) | 3,352.26(25) | 11,312.30 | 9,900.48(75) | 13,252.72(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
(2)DAC諸国・国際機関のODA実績
| DAC諸国、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | 合計 |
| 95 96 97 |
日本 1,380.2 日本 861.7 日本 576.9 |
ドイツ 684.1 ドイツ 461.1 ドイツ 381.9 |
フランス 91.2 フランス 97.2 フランス 50.1 |
オーストリア 66.2 英国 57.1 英国 46.2 |
スペイン 56.0 カナダ 38.4 豪州 36.0 |
1,380.2 861.7 576.9 |
2,531.3 1,670.9 1,228.6 |
| 国際機関、ODANET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
IDA 798.2 IDA 790.7 IDA 687.1 |
UNDP 38.3 CEC 34.8 UNDP 43.2 |
CEC 32.7 UNDP 28.7 WFP 38.2 |
WFP 21.2 WFP 22.4 IFAD 26.5 |
UNICEF 20.0 UNICEF 18.3 UNICEF 20.5 |
54.5 32.1 25.7 |
964.9 927.0 841.0 |
(3)年度別・形態別実績
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 |
| 90年度までの累計 |
9,934.24億円
(内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
631.09億円
(内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
414.80億円
研修員受入 3,150人 |
| 91 |
1,296.07億円
91年度円借款 (1,296.07) |
66.52億円
湖南武陵大学機材整備計画 (9.31) |
68.55億円
研修員受入 578人 |
| 92 |
1,373.28億円
92年度円借款 (1,373.28) |
82.37億円
日中友好環境保全センター設立計画(国債2/4) (19.14) |
75.27億円
研修員受入 575人 |
| 93 |
1,387.43億円
93年度円借款 (1,387.43) |
98.23億円
日中友好環境保全センター設立計画(国債3/4) (42.21) |
76.51億円
研修員受入 589人 |
| 94 |
1,403.42億円
94年度円借款 (1,403.42) |
77.99億円
日中友好環境保全センター設立計画(4/4期) (38.19) |
79.57億円
研修員受入 681人 |
| 95 |
1,414.29億円
95年度円借款 (1,414.29) |
4.81億円
ポリオ撲滅計画(3/3期) (2.42) |
73.74億円
研修員受入 697人 |
| 96 |
1,705.11億円
96年度円借款 (1,705.11) |
20.67億円
南京母子保健医療機材整備計画 (17.28) |
98.90億円
研修員受入 755人 |
| 97 |
2,029.06億円
97年度円借款 (2,029.06) |
68.86億円
病原体検査機材整備計画 (1.04) |
103.82億円
研修員受入 790人 |
| 98 |
2,065.83億円
対中国第23次円借款 (2,065.83) |
62.30億円
漢江上流水土保持林造成機材整備計画 (12.47) |
98.30億円
研修員受入 804人 |
| 98年度までの累計 | 22,608.73億円 | 1,112.84億円 |
1,089.47億円
研修員受入 8,619人 |
(注)1.「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
2.「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
3.80年度から90年度までの有償資金協力及び無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-07.htm)
(参考1)98年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件
|
案件名 |
協力期間 |
中日友好病院 |
81.11~92.10 82.11~87.11 83.10~91.10 84.10~91.10 85.4~91.3 85.9~93.3 86.11~93.11 86.1~92.12 86.2~92.2 86.11~91.4 87.3~92.2 87.7~91.6 88.1~94.12 88.11~93.11 89.11~94.11 90.3~94.2 90.1~95.1 90.3~97.2 91.7~98.6 91.9~95.8 91.12~99.12 92.7~97.6 92.7~99.1 92.9~95.8 92.4~98.3 92.11~97.11 93.6~00.5 93.11~98.11 93.11~98.11 93.4~98.3 93.6~00.6 94.9~99.8 94.11~99.10 94.4~01.3 94.6~99.5 95.4~00.3 95.4~00.4 95.9~00.8 96.1~00.1 96.2~01.1 96.11~01.10 97.1~02.1 97.3~02.2 97.10~02.9 99.3~04.2 |
(参考2)98年度実施開発調査案件
|
案件名 |
貴州省猫跳河(紅楓・百花湖水域)流域環境総合対策計画調査(第2年次) |
(参考3)98年度実施草の根無償資金協力案件
|
案件名 |
大連市旅順口区人民医院救急医療機材整備計画 |
(参考4)経済開発計画
・「国民経済・社会発展のための第9次5か年計画及び2010年までの長期計画」の概要
(目標)
・社会主義市場経済体制の確立
・2000年には1人当たりGNPを1980年の4倍、2010年にはGNPを2000年の2倍にする
(主要事項)
・「量より質へ」経済成長方式を転換
・マクロコントロール強化と中央政府主導により「産業政策」を貫徹
・農業問題が重要な課題
・国有企業の改革
・人口・就業が大きな圧力
・地域格差の是正
・対外経済での輸出入と国際収支のバランスを協調