3 外交におけるシンクタンク・有識者などの役割
外交におけるシンクタンク及び民間有識者の役割には、政府の公式見解にとらわれない形での外交・安全保障問題に関する国民の理解促進、外交・安全保障政策のアイデアを生み出す知的貢献、国際的な知的ネットワークの構築や日本の視点からの対外発信などがある。シンクタンク及び有識者による一般市民向けのセミナーやニュース解説は、外交・安全保障問題や政府の立場のより深い理解に不可欠であり、国民の理解を得ることによって政府の外交活動は一層力を発揮できる。また、政府とは異なる立場や専門性をいかした情報収集・分析・政策提言は、政府内の外交政策議論を豊かなものにする。さらに、国際的な知的交流は各国・地域の対日理解促進や国際世論形成への寄与という意味でも重要である。国際社会が複雑化し不透明感が増す中で、外交におけるシンクタンク・民間有識者の役割はますます重要になってきている。
このような背景の下、外務省は、日本のシンクタンクの情報収集・分析・発信・政策提言能力を高め、日本の総合的外交力の強化を促進することを目的として、外交・安全保障調査研究事業費補助金制度を実施し、2024年度は7団体に対して、13事業を支援した。本事業を通じ、刻一刻と変化する外交・安全保障環境に即した政策関係者への提言、諸外国シンクタンクや有識者との意見交換や、有識者による論文・論説の発表やメディアにおける発信、国際的な議論を先導するシンポジウムの開催などを促進している。これに加え、外務省は、2017年度から、日本の調査研究機関による領土・主権・歴史に関する調査研究・対外発信活動を支援する領土・主権・歴史調査研究支援事業補助金制度を運用しており、公益財団法人日本国際問題研究所(6)が国内外での一次資料の収集・分析・公開、海外シンクタンクと協力した公開シンポジウムの開催、研究成果の国内外への発信などを実施している。同事業を通じ、2024年度には、領土問題に関する北海道と島根県の高校交流事業が実施され、若い世代への講演及び意見交換会が行われたほか、アジアの若手研究員が来日し、日本の領土・主権・歴史問題についての理解を深め、日本の研究者との相互交流・研究ネットワークの構築を行った。日本の領土・主権・歴史に係る史料及び知見の蓄積や、国内外への発信強化が期待される。
公邸料理人とは、調理師としての免許を有する者又は相当期間にわたって料理人としての職歴を有する者で、在外公館長(大使・総領事)の公邸などにおける公的会食業務に従事する資格があると外務大臣が認めた者をいいます。在外公館は任国政府などとの交渉・情報収集・人脈形成などの外交活動の拠点であり、在外公館長の公邸において任国政財官界などの有力者や各国外交団などを招待して会食の機会を設けることは、最も有効な外交手段の一つです。その際に質の高い料理を提供するため、在外公館長は通常、専任の料理人を公邸料理人として帯同しています。
2024年6月から在トロント日本国総領事館で公邸料理人を務めております杉山雄治です。トロントに赴任して以来、「公邸会食」の場を通じて、日本の食文化を広げるための異文化交流を担っています。多様性あふれるトロントでは、さまざまな食の嗜(し)好や食事制限などを考慮し、カナダ産の食材を取り入れながら「トロントならではの日本の味」を創り上げる日々です。
日本料理は「目で味わう」ともいわれます。トロントの紅葉など季節の変化も盛り付けに取り入れるよう工夫しています。公邸での会食後、ゲストの方へ挨拶した際に直接料理の感想やコメントを頂くことで、自分の料理が日本の食文化を伝えられているということを実感でき、公邸料理人という仕事に大きなやりがいを感じています。公邸料理人は、メニュー作成、買い出し、仕込み、盛り付けなどを全て一人で行いますが、総領事館のスタッフの皆さんのサポートもあり、恵まれた環境の中で一層精進しようと気が引き締まります。また、移民が多くを占めるトロントでは様々な国の食材が手に入ることも、公邸会食で提供する食事の幅や自身の知見を広げる経験となっています。


私は幼い頃から料理に興味があり、8歳の頃から包丁を握り始めていました。港町で育ったため魚やホヤなど小学生の頃からさばいていたので、料理は私にとって生活そのものであり、自分を表現するための手段となっています。
トロントには娘を連れて家族で赴任しており、育児と仕事を両立する大変さに加え、医療の違いや物価の高さなどもあり、楽なことばかりではないと実感しています。一方で、日々の食卓でも新たなアイデアが生まれたり、日常的に娘を英語に触れさせられたり、また休日にはナイアガラの滝を見に家族で旅行を楽しんだりと、私生活も充実させながら、料理人としての貴重な経験を積むことができる環境に感謝しています。
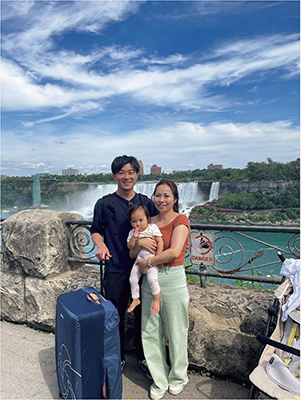
料理人という仕事に真摯に向き合い、地道に高みを目指していきたいという私の決意には、東日本大震災での経験も深く影響しています。私は石巻市の出身で、震災で実家が津波に流され、多くの友人を失いました。震災後、生き延びた自分に何ができるのかを考え抜き、料理で人々に希望や喜びを届けることこそ自分の使命だと感じました。震災の記憶は、私に料理人としての特別な使命感と、料理の力を信じる気持ちを与えてくれています。
料理は言葉を超えて人々の心に触れ、温かさを届けるものです。公邸料理人として、トロントの地で様々なゲストの方に提供する料理の一皿一皿に、日本の美しさや精神を込め、唯一無二の日本料理を提供するため、目の前のゲストに向き合うことを大切にしています。今後も技を磨き続け、どんな時も妥協せず真摯に料理に向き合い、コツコツと高みを目指すことで、私の料理が誰かの心を少しでも豊かにできればと思っています。
外務省では、公邸料理人として共に外交に携わってくださる方を随時募集しています。御関心のある方はぜひ以下ホームページからお問合せください。
【国際交流サービス協会】http://www.ihcsa.or.jp/zaigaikoukan/cook-1/

公邸料理人の活躍はSNSアカウント「外務省×公邸料理人(Facebook、X)」でも御覧いただけます。
Facebook:
https://www.facebook.com/MofaJapanChef

X:
https://twitter.com/mofa_japan_chef

─施設の大規模改修と維持管理─
外務省には、「在外営繕」という仕事があることをご存じですか。「日本の顔」として外交活動の拠点や舞台となり、非常時には邦人保護の最後の「砦(とりで)」となるのが、海外にある日本国大使館などの在外公館施設です。これら施設を設計・建設し、維持管理するのが「在外営繕」であり、外交活動を陰ながら支えつつ、日本国民の生命を守る重責の一端を担っているともいえます。ここでは、在ベトナム日本国大使館で大使館事務所施設の改修工事を担当した濁川(にごりかわ)営繕技官に在外営繕の仕事について語ってもらいました。
在ベトナム日本国大使館は1999年に完成しましたが、ベトナムの経済成長や二国間関係の進展に伴い、また、技能実習制度が始まったことを受け、日本へ渡航するための査証を求める申請者数が大幅に増加しました。一方で、急激な申請者数の増加に対して申請窓口をいきなり増やすことは困難であったため、一時期は建物の敷地の外にまで申請者の行列ができていました。また、査証申請者数の増加は領事班の業務増加を意味しており、領事班の執務室も併せて手狭になっていきました。
こうした状況を解決するため、領事班の申請窓口などの来客スペースと執務室の拡張を目的とした内装の大規模改修工事を実施することになりました。本改修工事は館内の一部の部屋で行う工事であるため、工事箇所以外の場所にいる大使館員はそのまま館内に残って執務しましたが、工事の騒音に加え、特に振動は扉を挟んでも館内に響くため、大使館の活動に支障が生じないよう工事の内容と時間に注意を払う必要がありました。
改修工事の規模は建て直しや新築工事と比べると小さいですが、日々の外交活動や来訪者、館内で勤務する大使館員に配慮する必要があると今回の工事で痛感しました。施設管理において、このような大規模改修は日常の小規模な修理のような維持管理とは異なり、大使館全体を巻き込んで内装や設備を一新する十数年に1度のいわば“動”の施設管理といえます。


時代の流れや要望に合わせて行う大規模改修も重要ですが、施設の日常的な保守も大切です。ベトナムは1年を通じて多湿なため、夏では湿度100%は当然ながら、冬であっても80%を超える日が多くあります。このため執務中は空調設備を常に使用しており、空調設備が故障すればたちまち大使館の活動に影響が出ます。このような不具合が発生しないようメンテナンスに気を配り、不具合が発生した際は迅速に修理できるように準備する必要があります。
上記は一例ですが、維持管理業務の本質は「当たり前の維持」にあります。大使館に限らず、施設内で活動する上で電気や水道などがなければ満足に活動することはできません。しかしながら、これらは誰かが管理しなければ、適切に供給することはできず大使館の業務は成り立ちません。日々の地道な“静”の業務ですが、大使館の活動を滞りなく進めるために必要不可欠の業務であり、感謝の言葉をもらうこともあるので、やりがいのある業務であると思います。
外務省では、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)技術系区分(試験区分:「建築」、「デジタル・電気・電子」、「機械」)の合格者の中から、営繕技官を採用しています。御関心のある方は以下外務省ホームページをご確認ください。
【外務省ホームページ「一般職採用試験(大卒・技術系):在外営繕業務」】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page23_003447.html

(6) 公益財団法人日本国際問題研究所ホームページ参照:
https://www.jiia.or.jp/jic/

